女の尻というのは、それ自体はクッションの役割を持つのだが、しかしこれが動いた時に初めてエロチックな景観を生み出す。
それは静止状態においても、それが動き出す可能性、また若しくは感触というのを期待しうるという点においても同じである。
しかしながら、実際、エロティックな女の尻というのは本当に稀なものでは無いかと思う。
それは夏のある時、駅に向かう一本道で、目の前をよたよたと歩いている女の尻を見たときに感じた感覚が、それ以降なかなか出会わないという事による。
また学生時代にもそのような事は稀にあったが、このような出来事には大概、
その人の品や、そして姿勢に秘密があるのだと思える。
勿論、女の尻をつい見てしまうのは男の性なのであるが、だがあるときに感じる強烈な感覚というのは、これが只の肉体機能的な問題では無い事だと気がつく。
ところで、世間ではちょっと前に「
エロ可愛い」といった具合の言葉が流れるようになった。
それはネットで発生し、某歌手の宣伝文句にも使われたものであったが、これが日本人の約半分を占める人達、若しくはその予備軍の品格の破壊に繋がったかどうかはハッキリという事はできない。
勿論、文化史的な観点から、やがて人々の性向というのは推測出来ようが、また最近では、「
ビッチ・ファッション」(※)なるものも登場したらしく、もういい加減辞めてもらいたいというのが本音である。
他に、
エキセントリックな美人芸人が俄かに注目を浴びているようだが、その芸風においては暗に日本の保守層を驚かせるものである。
ある意味、これらのような事柄というのは、その白雉な様から
エログロの極みと云っていいのだが、攻撃性を有したこの事態は自壊の方向へ進んで行くのが自然の道理である。
そして他の道理としては、それが
如何に軟着陸してゆくかが問題となろう。
---------------
※「ビッチ」に関して、これがファッションブランド名との造語なら理解できるが、侮蔑的表現との造語であるのなら、配信元の低脳さを疑っても良いのではと、ふと思った。
また「セレビッチ(=セレブ+ビッチ)」という用法があるそうだが、後者でその意味を捉えた場合、ソフトバンクのCMほどの衝撃を感じ、自分も相当なスイーツ脳なのだなと思ったり思わなかったり。











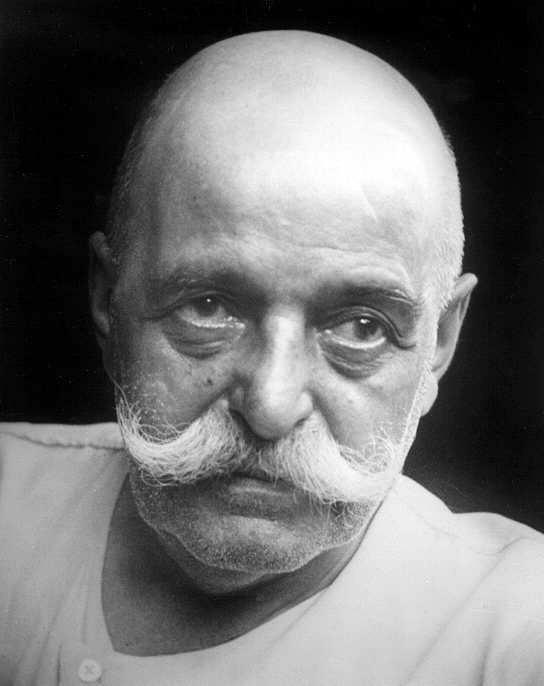

 (from Amazon)
(from Amazon)