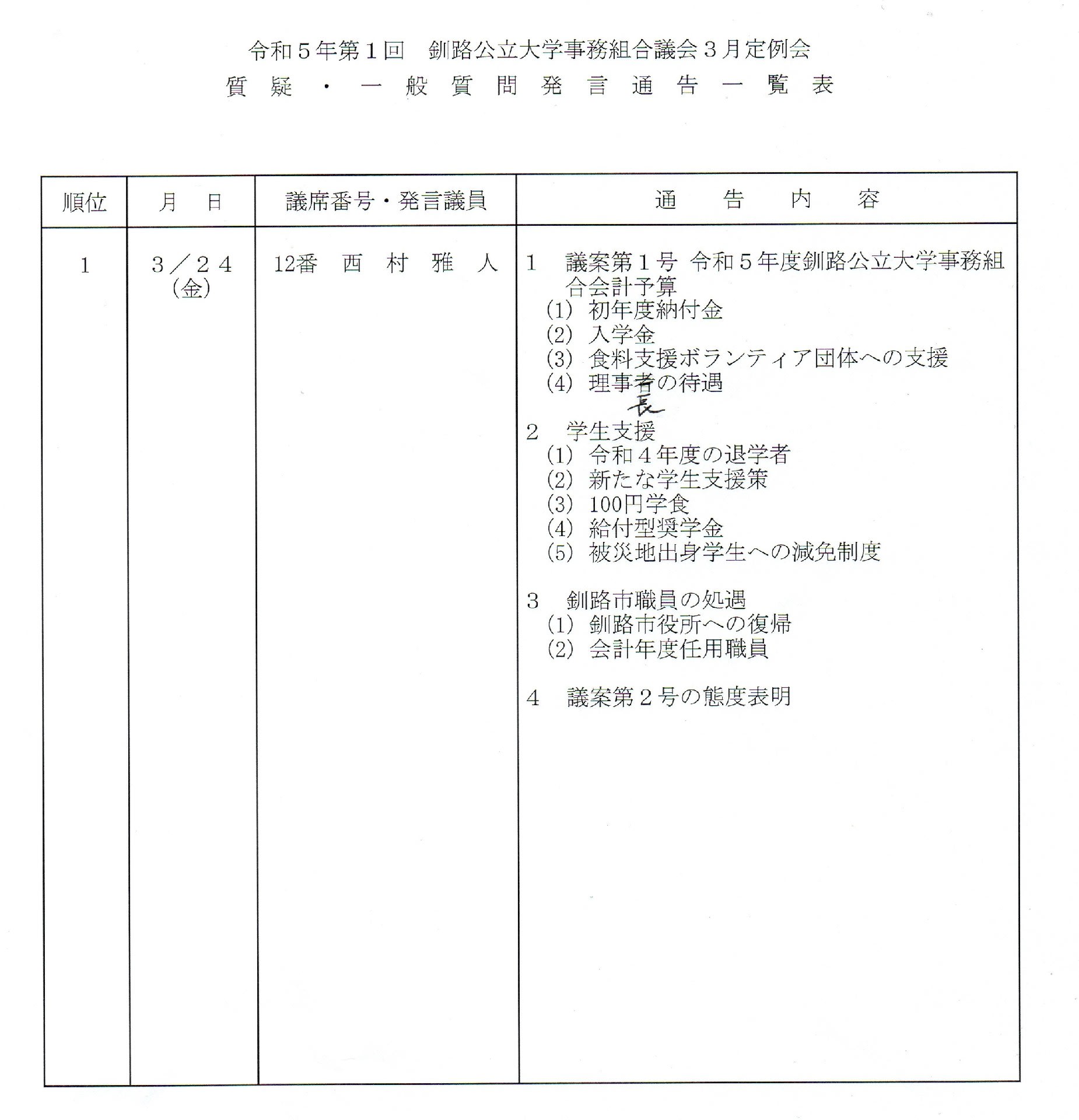釧路公立大学事務組合議会議事録シリーズ第2回目は、2022(令和4)年3月定例会のものを公開します。
2022年3月25日に開催されましたが、この時も質問は私1人でした。

1回目の質問
令和4年度予算案について
Q1 まず、議案第1号令和4年度釧路公立大学事務組合会計予算について質問致します。予算説明書11ページ、2款教育費の中の1番下に公立大学法人化事業費として、7840万円計上されています。これは前年よりも約5800万円も多く、事前に具体的な内容をお聞きした所、公立大学法人になるためのシステム導入費と移行支援に関わる業務委託費とのことでした。いよいよ、法人化に向けて具体的に動き出したことが予算の上からも見て取れます。また事前に頂いた「法人化移行までの業務スケジュール」によりますと、法人設立が令和5年4月とはっきりと明記されています。前回の議会で、管理者は教職員に対して十分な説明を行ったと答弁されました。担当課に伺ったところ説明会は今年度4回開催し、昨年度と併せると6回開いているそうです。前回の議会で私は丁寧な説明会の開催とともに、法人化について教員にアンケートとか投票をやって意思確認が必要ではないかと申し上げました。説明会の回数を増やしていることは最もなことですが、しかし投票まではやっていないとのことでした。
国立大学法人法は、2019年に法人の長と学長の分離を可能にし、複数の外部理事を義務付けるように改定されました。文科大臣が任命する法人の長が経営の最終決定を行い、学長は外部理事と同等の発言権しか持たないなど、大学の意思決定が経営優先で行われる危険があります。法改正されてからまだ3年しかたっていません。今は国立大学での法人化がもたらした現状と問題点を検証しなければならない期間です。釧路公立大学の法人化は国立大学法人の成り行きをみてからでも遅くはありません。今年6月にまた臨時の議会を開いてまで急ぐ必要性がないと思われます。市民にも周知されてはいません。今後1年の間に、評価委員会設置条例、職員引継条例、それに授業料上限設定など多くの手続きがあります。しかも市民や有識者そして何よりも教員の意見を聞きながら慎重に行う必要があります。よって、予算案にある公立大学法人化事業費はいったん凍結し、調査研究するための予算として昨年と同規模で執行すべきと考えますが、管理者のお考えをお聞きします。
〇管理者 蝦名大也
私の方から法人化についてご答弁させていただきます。
今、ご質問の中で大学の意思決定が経営目線で行われる危険性というお話だったと思いますが、今までもお話しさせていただいておりますけれど、「経営」という言葉のところが、私どもが考えている「経営」と、議員の言っている「経営」に大きな違いがあると感じてございます。
私どもは、経営力を高めるというのは、この大学の価値を高めていくと考えております。
先ほど小路学長からも「様々な可能性が考えられる」とあったように、これが経営力の強化になるものと認識しております。
本学の公立大学法人移行の目的は、「釧路公立大学の価値と魅力をさらに高め、将来にわたり道内外の学生に選ばれ、地域社会からも必要とされる大学を目指すことにある」と謳っているところでございます。
公立大学法人制度を活用いたしまして、これまでの「大学運営」から「大学経営」という理念を掲げて、経営力の強化及び教育環境の充実を図ることで、本学の継続した発展に結びつくよう、法人化への移行を予定どおり進めて参りたいと考えている次第でございます。
2回目の質問
予算案のうちの法人化に関わる点について、再質問させてもらいます。法人化すると、理事長というポストができ、その理事長は管理者が任命することになっています。学長は副理事長として理事長を補佐することになります。もし管理者が学外の人を理事長として任命するとしたら、大学はどうなのか心配です。企業経営とは異なる側面が多い大学経営です。学長が大学経営に責任をもち、リーダーシップを発揮することは、実行力ある大学運営に必要です。しかし、学長よりも上の理事長が独断専行の大学運営を行えば教職員の意欲をそぎ、大学の活力は低下します。公立大学法人制度には、それを防ぐ機能が欠けています。教員からの選挙で選ばれた学長が大学経営に全責任を持ち、教授会が学長の職務内容をチェックするというのが、民主的で、大学の自治の原則にも叶うものです。ある私立大学では膨大な権限をもった理事長が理事を側近で固め誰も物が言えなくなって不祥事につながり逮捕されるという事例も起きています。政治家でもある蝦名管理者が理事長を任命し、その理事長が学長よりも上のポストとなり、各理事は理事長が任命するという仕組みになると、自由な研究、真理の探求といいますが、それがやりにくくなることはないのでしょうか。本来なら教授会の権限が強いほど大学の自治の原則がいかせるはずですが、定款案には教授会は位置付けられていません。そこでお伺いしますが、私立のように理事長という学長よりも権限がある役職を設置することは、公立大学にはなじまず、大学の自治権を後退させる恐れもあり、民営化に近づきつつあるのではないかと思われますが、管理者の答弁を求めます。併せて、議案第1号、2号とも賛成はできかねるという意見を申し上げ、質問を終わります。
〇管理者 蝦名大也
まさにどのような制度、仕組みの中で物事を進めていくかでございますが、私どもは1つの制度がすべて万能だとは考えておりません。さまざまなプラスもあればマイナスもあると思っています。
議員の考えは、制度がすべてを決めるというお話しでのご質問になっていた訳でございますけれど、最終的にはやはり人というか、そういった中でいろいろなことをしっかり議論していくことが重要だと考えているところでございます。
その中で、私どもはこの理事長と学長については、公立大学法人制度の導入によりまして経営力の強化と価値を高めていくためや学生や社会のニーズを踏まえた教育研究を提供する観点から、経営の部門は理事長が行い、学長は教育部門の責任者として行うことで、経営と教育の役割分担の明確化と負担軽減を図って、それぞれに専念できる体制をつくるということであります。
その上で、法人内に理事長、副理事長となる学長及び学部有識者を含む理事で構成される理事会を設置することとしており、法人の運営に関する重要事項について適切な協議、運営がなされるものと考えておりますので、ご質問のご指摘には当たらないものと考えております。
2021(令和3)年10月29日の議会はこちらから
釧路公立大学事務組合議会 会議録 2021年10月 - 西村まさと