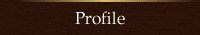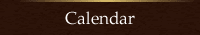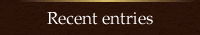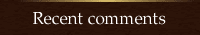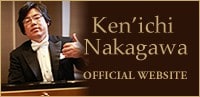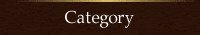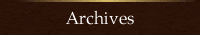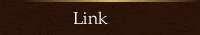お茶の水女子大学ドビュッシーゼミスタート。
ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲二台バージョンないし連弾バージョンの演奏、前奏曲集第一巻全曲の簡単な説明、アナリーゼ、学生の演奏、そしてその公開レッスン。
本日は第一日目3時間。(といいながらそれ以上かかりました・・)
ドビュッシーの音楽界の時代的背景、ドビュッシーの和音連結の自由度、その面白さ、ある程度の規則性の説明、牧神の午後への前奏曲のオーケストラ演奏を聴いて、二台ピアノでの演奏、指導、1894年あたりに作曲されたチャイコフスキー、ドボルザーク、マーラー、リヒャルト・シュトラウスなどの曲を聴き、また牧神の午後への前奏曲のスコアの簡単な読み方指導(指板の上でとか、弱音器をつけたりとったりとかのフランス語用語解説、ホルン、クラリネットの移調譜読み方指導など)をした後に前奏曲第一巻の音楽界の流れ、ドビュッシーの作曲背景説明、のちに第一巻の1〜4曲を各曲一人の学生が演奏、簡単なアナリーゼと演奏指導、最後に別のペアで牧神の午後への前奏曲を演奏、指導・・・ということでてんこ盛りになりました。
レッスン室のテレビモニター、オーディオを使い、音源を聴いたり、私がスキャンした楽譜を見ながら色々説明したりと、iPad、iPhone駆使という感じでした。
パワーポイントにもドビュッシーの自筆譜も入れて、基本的に使用しているデュラン=コスタラ版と、その注釈であり得た手稿譜、校正刷、校正書き込み、初版、初版書込み、重版、ドビュッシーの録音でのさらなる相違、ほかの版との比較などをしながら、様々な版を見ることの意味なども知ってもらいたいと色々な版を入れて比較して説明してみました。
このドビュッシーの前奏曲集はかなりさまざまな校正段階、ないし版で相当の違いがあったりもするので、その意味ではとても面白いです。
別の意味では、何が決定打かというのを特定するのも難しく、それを各々の自主的に考えるのがとても重要であること、またある版のみみてそれを盲信しないことなど理解してもらえたら・・・と願っております。
ドビュッシーの自作自演、全ての版には全く書いていない音を弾いていて、例えばある部分は全て2度違っているとか、細かい音のところを四分音符に思いっきり和音にして纏めてしまっている、などあると尚更何を本当に信じるか・・・というある意味とてもよいトレーニングになるかと思いました。
明日は同じく牧神の午後への前奏曲と前奏曲集
第一巻5〜8番です。
更に私も楽譜を読み込みます。
名古屋ライヒから帰って翌日から四日間ドビュッシー漬けでした。今までの資料確認、読み込み、資料再作成。
ライヒも全く違う世界。
ドビュッシーは本当に素晴らしいのですでにライヒとまた違った幸せの四日間です。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )