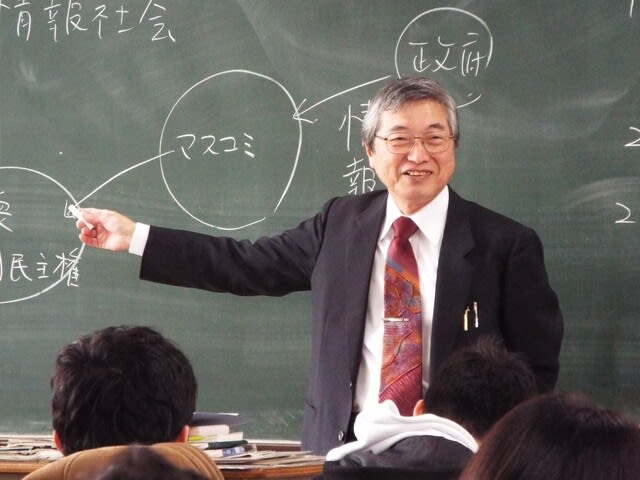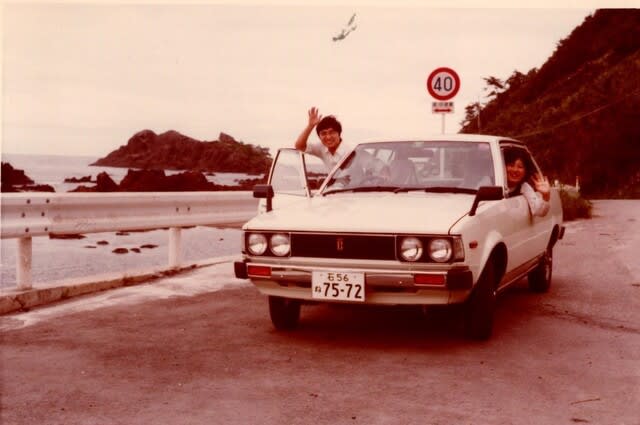58歳の時から家計管理を預かるようになりました。私のやり方は以下のとおりです。
【1】毎月の管理
(1)小袋に分ける
毎月17日に1か月分の生活費を銀行から降ろし、以下の項目に分けて小袋に入れます。
(A)毎月出費するもの
・日常の生活費
・私の小遣い
・妻の小遣い
・私の病院代
・妻の病院代
・新聞代
・クリーニング代
(B)1年に一度出費するもの(月割で積み立てる)
・固定資産税積み立て
・住民税積み立て
(C)突然の出費に備えて
・旅行積立、予備費
(2)家計簿
生活費の出費については家計簿に細かな記録はせず、いつ、どこで、いくら使ったか、また「生活費の残金」はいくらあるかを千円単位で記録します。例えば、スーパーで5800円の買い物をした場合
<5月2日 スーパーライフ 0,6 残金 ***円>
といった具合です。
家計簿は長く続けることが大切です。だから端数は記録しません。おつりが余ったら「ためため箱」に入れて端数の調整はそこで適当に相殺します。
家計簿をつけるのは生活費があといくら残っているかを把握するためです。細かな管理は必要ありません。大雑把に「1日いくらくらい」と決めておけば、1週間にだいたいこのくらい、半月でこのくらいという目安ができます。今月はちょっと使うペースが速すぎるとか、ちょっとゆとりがあるとかということで支出をコントロールできます。
また、普段から予備費として一定額を積み立てておくと、やれ洗濯機が壊れた、給湯器が壊れた、パソコンが壊れたなどの臨時出費があっても慌てずに済みます。
(3)自動引き落とし分
電気、ガス、水道、電話代、NHK受信料、国民健康保険料、生命保険料、マンション管理費など、銀行口座から自動引き落としされるものについてはエクセルで一覧表を作り、毎月記録しておきます。一か月でいくら引き落とされたかを過去のデータと比較すると面白いものです。私の場合、いつの間にか20年分くらいの記録がたまっています。
(4)クレジットカードの管理
最近はネットでいろんなものを購入することが多くなりました。クレジットカードを使った場合は
①クレジットカードの使用一覧表を作っておき、直ちに記入します。
②次に、使った金額を銀行口座に入れます。
③金額が大きくて②の処理ができない場合は、銀行口座の残高を減額しておきます。
(5)資産一覧表の作成
保有する資産の一覧表をエクセルで作成し、常に「今」「どこに」「いくら」の資産を保有しているかを把握しておくようにします。例えば次のような具合です。

それらの記録を時系列で眺めていると楽しいものです。ちなみに私の場合、数年先までの預金目標(資金計画)も記入しています。なお、銀行は「日常頻繁に出し入れする口座」と、「貯めることを目的とする口座」を分けておくことも大切です。
小さな金額は気にせず「誤差を誤差で打ち消して」、大雑把につけていくことが長続きさせるコツです。このような方法で家計管理をやるようになってもう10年余りになります。おかげで安心してお金を使うことができます。
普通に生活をして「残ったら貯蓄しよう」などと思っていては貯蓄などできるものではありません。年間の貯蓄目標を決め、それに合わせて家計管理をきちんとする必要があります。
株式投資に難しい経済理論は必要ありません。ただ一つの真実さえ知っていればいいのです。すなわち、株をたくさん所有している人の多くは金持ちであり、金持ちは政治を動かす力を持っています。だから、たとえ株が暴落しても必ず株式市場のテコ入れを図る政治力学が働きます。最近、株式市場にこうした政治力学が働いていることに気がついて、ようやく利益が出るようになりました。
ちなみに株式投資の買い場は10年に1回です。次のデータでわかるように、日本経済は約10年を周期に大きな不景気に見舞われています。
1965年 東京オリンピック終了直後
1974年 石油ショック直後
1986年 円高不況
1997年 山一証券・日本長期信用銀行などが倒産
2008年 リーマンショック
2020年 コロナショック
かつての私がそうだったように、短期売買をする人はこの周期的な不景気のたびに市場から振り落とされ、痛い目に会ってきました。しかし、たとえ不景気になっても先に述べたような政治力学が働いて、市場は必ず回復します。ですから、みんなが真っ青になってろうばい売りをしているときが、実は絶好の買い入れ時なのです。
株は暴落した時に買い、長期保有することが王道です。その意味で富裕層に非常に有利にできています。なぜなら、富裕層はお金にゆとりがあるから、短期的な目先の利益を追う必要がありません。また、お金にゆとりがあるから長期保有ができます。しかも受け取る配当に累進課税は適用されません。利子・配当にかかる税金は20パーセントと非常に優遇されています。ですから、金持ちはますます金持ちになっていく。これが私たちの生きる資本主義社会というものなのです。

【3】資産運用の5原則
|
1.一攫千金を狙わない。 2.他人に金儲けを説く人の話は信用しない。 3.自分が理解できないものには投資しない 4.卵は一つの籠に盛らない(分散投資) 5.契約を急がせるものは詐欺を疑え。 |
(参考)
興味のある方は次のサイトもご覧ください。
2馬力と1馬力