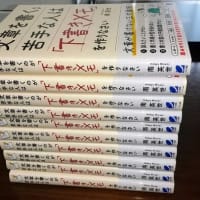今から140年前につくられたもっとも有名なこの彫刻。いったい何を考えているのだろう? 上の写真をレプリカだと思う人がいるかもしれないが、レプリカではない。ロダンが制作した型から鋳造されたもので、こうした本物は世界で20体以上存在すると言われる。日本では東京・上野の国立西洋美術館(写真上)、京都の国立近代美術館で本物が展示されている。
なぜ、ロダンを持ち出したか? 理由は「考える」ということについて考えてみたいからである。
高校で「政治・経済」を担当するようになってから40年になる。経済分野は一般にアダム・スミスの説明から始まる。「彼は、国家は国民の経済活動には干渉せず、国防・司法・公共事業といった必要最小限の活動に限るべきであると主張した(小さな政府)」と教科書には書いてある。しかし、そこには「なぜ小さな政府を主張したのか」ということは書かれていない。
(注)そのことは世界史の教科書の絶対王政の時代を学べば理解できるのだが、残念ながら世界史は世界史、政経は政経と別の勉強ととらえている生徒がほとんどである。中には世界史の近現代をまともに履修していない学校も少なくない。
今年から共通テストが始まり、考えることが重視されるようになった。確かに単純な暗記では解けない工夫がなされていた。しかし、考えるということの本質を突いた出題がどれほどあったかと問われれば、答えは否定的にならざるを得ない。
そもそも考えさせるということの目的は何か? 社会科学についていえば、それは当時の社会問題が何であったかを理解し、その問題を解決することによって多くの人々を幸せにするためであるといってよい。スミスの時代は国王と結びついた特権商人の存在が自由な経済活動を阻害していた。マルクスが生きた時代は労働者の貧困問題が最大の課題だった。また、ケインズは世界恐慌を背景にどうすれば不況を克服できるかを問い、新しい経済理論を打ち立てた。
もちろん、必ずしもすぐに役立つ必要はないのかもしれない。
・リンゴは木から落ちるのになぜ月は落ちてこないのか?
・大阪の環状線は1周何キロメートルあるのだろう?(過去に出題した定期考査問題)
・戦後日本の経済成長率をグラフに描き、そこからどんなことが読み取れるかを考えよう。
・コロナウィルスによって死亡した人は世界で200万人。そのうちアメリカが40万人と非常に多いのはなぜだろう?
・憲法ってなぜ存在するのだろう?
・日本の財政赤字はなぜここまで膨らんでしまったのだろう?
・お金で買ってはいけないものってあるのだろうか?
・貧富の差はどこまで許されるか?
・あなたは自分が賢いと思いますか?(ケンブリッジ大学入試問題)
・歴史は次の戦争を止めうるか?(ケンブリッジ大学入試問題)
・なぜ海の水はしょっぱいのか?(オックスフォード大学入試問題)
世間では「自分の頭で考えること」の大切さを説く人が多い。しかし、もっと大事なのは「まず疑問を持つこと」ではないか。小さいころ「なんで?」「どうして?」という疑問を頻繁に発していた子どもも、成長とともにそうした問いかけをしなくなる。そして正解を覚えることが勉強だと教えられる。もちろん、覚えるということの大切さを否定するつもりはない。しかし、覚えることが即学ぶことかと言われたら、「それは違うんじゃない」と言わざるを得ない。
以前、定期考査で「自分で問題を設定し、それについて説明せよ(字数制限なし、1問=100点)」という論述問題を出したことがある。いろんな答案が出てきて採点は面白かった。一番面白かったのは「私はこの1年間でいかに賢くなったか」という答案で、今でも印象に残っている。
本来、考えるということは時間がかかるものである。共通テストなどというスピードを競う試験で思考力を問うことには本質的な無理があるのではないか。
なぜ、ロダンを持ち出したか? 理由は「考える」ということについて考えてみたいからである。
高校で「政治・経済」を担当するようになってから40年になる。経済分野は一般にアダム・スミスの説明から始まる。「彼は、国家は国民の経済活動には干渉せず、国防・司法・公共事業といった必要最小限の活動に限るべきであると主張した(小さな政府)」と教科書には書いてある。しかし、そこには「なぜ小さな政府を主張したのか」ということは書かれていない。
(注)そのことは世界史の教科書の絶対王政の時代を学べば理解できるのだが、残念ながら世界史は世界史、政経は政経と別の勉強ととらえている生徒がほとんどである。中には世界史の近現代をまともに履修していない学校も少なくない。
今年から共通テストが始まり、考えることが重視されるようになった。確かに単純な暗記では解けない工夫がなされていた。しかし、考えるということの本質を突いた出題がどれほどあったかと問われれば、答えは否定的にならざるを得ない。
そもそも考えさせるということの目的は何か? 社会科学についていえば、それは当時の社会問題が何であったかを理解し、その問題を解決することによって多くの人々を幸せにするためであるといってよい。スミスの時代は国王と結びついた特権商人の存在が自由な経済活動を阻害していた。マルクスが生きた時代は労働者の貧困問題が最大の課題だった。また、ケインズは世界恐慌を背景にどうすれば不況を克服できるかを問い、新しい経済理論を打ち立てた。
もちろん、必ずしもすぐに役立つ必要はないのかもしれない。
・リンゴは木から落ちるのになぜ月は落ちてこないのか?
・大阪の環状線は1周何キロメートルあるのだろう?(過去に出題した定期考査問題)
・戦後日本の経済成長率をグラフに描き、そこからどんなことが読み取れるかを考えよう。
・コロナウィルスによって死亡した人は世界で200万人。そのうちアメリカが40万人と非常に多いのはなぜだろう?
・憲法ってなぜ存在するのだろう?
・日本の財政赤字はなぜここまで膨らんでしまったのだろう?
・お金で買ってはいけないものってあるのだろうか?
・貧富の差はどこまで許されるか?
・あなたは自分が賢いと思いますか?(ケンブリッジ大学入試問題)
・歴史は次の戦争を止めうるか?(ケンブリッジ大学入試問題)
・なぜ海の水はしょっぱいのか?(オックスフォード大学入試問題)
世間では「自分の頭で考えること」の大切さを説く人が多い。しかし、もっと大事なのは「まず疑問を持つこと」ではないか。小さいころ「なんで?」「どうして?」という疑問を頻繁に発していた子どもも、成長とともにそうした問いかけをしなくなる。そして正解を覚えることが勉強だと教えられる。もちろん、覚えるということの大切さを否定するつもりはない。しかし、覚えることが即学ぶことかと言われたら、「それは違うんじゃない」と言わざるを得ない。
以前、定期考査で「自分で問題を設定し、それについて説明せよ(字数制限なし、1問=100点)」という論述問題を出したことがある。いろんな答案が出てきて採点は面白かった。一番面白かったのは「私はこの1年間でいかに賢くなったか」という答案で、今でも印象に残っている。
本来、考えるということは時間がかかるものである。共通テストなどというスピードを競う試験で思考力を問うことには本質的な無理があるのではないか。