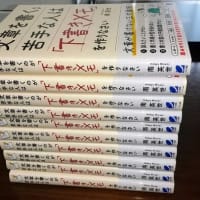いよいよ来年度から新設科目「公共」が高校で実施される。高校現場にもようやく教科書見本が届き始めた。まだ3冊しか見てないが、感想を少し述べてみたい。なお、今回は教科書の執筆には全くかかわっていないので念のため申し添えておく。
第一印象としては、各社の差は従来の「現代社会」との距離の違いに現れているように思われる。
A社は文科省に顔を立てて冒頭に「公共」らしきものを置いているが、それは申し訳程度であり、中身は従来の現代社会の教科書とほぼ同じである。
B社も似たり寄ったりの感じだが、多少は「公共」の独自性を打ち出している点がA社と異なる。
C社は大学の先生を中心とする執筆陣で固め「公共」という新設科目にかなり意欲的に取り組んでいる。その点は評価できる。しかし、残念ながら内容が難しすぎる。これでは中堅クラス以下の学校では生徒が読めないであろう。それを緩和させるように漫画を随所に入れているが、漫画を入れたのでは上位校では採用しにくい。
学習指導要領が変わっても、現場の教員はノートの書き換えを嫌がる傾向がある。忙しすぎて授業準備に十分な時間を割けないから当然かもしれない。さてさて、採択状況はどうなることやら。
そもそも「現代社会」を廃止して新設科目「公共」を導入したのはなぜか。狙いははっきりしている。「公共」の目的は道徳教育であり、自分の国を愛する人材の育成である。小中学校では道徳は「特別の教科」(道徳科)として位置づけられ、小学校では2018年度から、中学校では2019年度から全面実施されている。「公共」はその高校版という位置づけである。現代社会を公共という科目名に変えたのは、まさしくそうした教育を可能にするための方便だった、というのが私の見立てである。
そのことは「公共」の学習内容には「現代社会」で扱っている「基本的人権の保障」や「平和主義」が削除されていることからも推察される。これは現在の憲法第13条「すべて国民は個人として尊重される」を実質的に修正し、個人よりも国家、個よりも全体を重視する表れと考えられる。すなわち、全体のために個人は犠牲になっても仕方がないという戦前思想への回帰につながる可能性を持つものとみることができる。
実際の教育現場はどう動くか。まずは大学入試の動向が注目される。学習指導要領より大学入試のあり方のほうが教育現場に与える影響力は大きい。
一方、教員のほうもいろいろ知恵を絞ってくるだろう。現行の「現代社会」の第三編で政治と経済をミックスさせた「現代日本の諸課題」が文科省の鳴り物入りで導入されたにもかかわらず、現場では全く無視された。それと同じように、新設科目「公共」の狙いも骨抜きにされるかもしれない。いや、多分そうなるであろう。そうなれば、学習指導要領に忠実に作った教科書はあまり売れないということになるのかもしれない。
安倍政権が誕生した2012年以降、日本の政治は大きく右にカーブを切った。その表れが今回の「公共」という新設科目の導入である。さてさて、これから日本はどっちの方向に進むのか。
(参考)