
このブログでは移民を主題にした小説を何冊か取り上げましたが、それに加えて、映画も移民という事象をより深く理解するためには、欠かせないツールだと考えます。移民が直面する文化摩擦や差別、残された家族との絆とすれちがい。そして新天地でたくましく生きる移民の姿はまさに映画のトピックにふさわしいのです。そういう意味で昨年から日本で始まった移民映画祭の取り組みは素晴しいと思います。
出稼ぎ大国であるフィリピンでは、海外で働くフィいピン人とその家族をテーマとした映画が沢山作成されています。フィリピン人の同僚に言わせると、現バタンガス州知事の女優ビルマ・サントスが主演する、Anak(タガログ語で子供という意味)という映画がこのテーマでは有名どころだそうですが、残念ながら今まで英語版が入手できず観ていません。ちなみにフィリピンは選挙も近づいているところ、最近このサントス知事は海外出稼ぎ者のいる家族向けの特別プログラムを実施すると公表したばかりです。
Anakが見れず、残念におもっていたら、別の映画を同僚から紹介されました。タイトルはケアギバー(介護士)、フィリピンからイギリスに渡ったフィリピン人女性の物語です。主人公サラは英語の先生でしたが、すでにロンドンで働く夫のもとに行く決意を固め、介護士としてイギリスで働き始めます。
英語教師のサラが介護士として高齢者の世話をしたように、母国では医者でも、海外では看護師として働いているといったケースが実際とても多いのです。このような人材ロスが起こるのは、資格相互承認のシステム出来上がっていないことにも起因します。以前イタリアで主に家政婦として働くフィリピン人を調査したことがありますが、実に6割近くが大学教育を受けていました。賃金が高いというだけで、能力に見合わない仕事に従事し続けるということは、とても忍耐力のいること、そして時には一人の人間としてのプライドがひどく傷つくことであることが映画を観ていてひしひしと伝わってきます。
映画の主人公のサラは小学生の息子を親戚に預けて出稼ぎしました。海外で働いて、そこで居住権をとったら子供を呼び寄せしたい、というのが多くの出稼ぎする両親の願いですが、その間に子供は親を知らずに育っていってしまうことが多いのです。親が離れていても、送金によって良い教育を受け、親戚の愛を受けてしっかり育つ子もいますが、親がいないことが致命的なダメージとなる子もいて、それは子供の素質に左右されるところが多く、予想がつきにくい、と言っていた出稼ぎコミュニティーで働くNGOスタッフの話を思い出したりしました。
出稼ぎ大国であるフィリピンでは、海外で働くフィいピン人とその家族をテーマとした映画が沢山作成されています。フィリピン人の同僚に言わせると、現バタンガス州知事の女優ビルマ・サントスが主演する、Anak(タガログ語で子供という意味)という映画がこのテーマでは有名どころだそうですが、残念ながら今まで英語版が入手できず観ていません。ちなみにフィリピンは選挙も近づいているところ、最近このサントス知事は海外出稼ぎ者のいる家族向けの特別プログラムを実施すると公表したばかりです。
Anakが見れず、残念におもっていたら、別の映画を同僚から紹介されました。タイトルはケアギバー(介護士)、フィリピンからイギリスに渡ったフィリピン人女性の物語です。主人公サラは英語の先生でしたが、すでにロンドンで働く夫のもとに行く決意を固め、介護士としてイギリスで働き始めます。
英語教師のサラが介護士として高齢者の世話をしたように、母国では医者でも、海外では看護師として働いているといったケースが実際とても多いのです。このような人材ロスが起こるのは、資格相互承認のシステム出来上がっていないことにも起因します。以前イタリアで主に家政婦として働くフィリピン人を調査したことがありますが、実に6割近くが大学教育を受けていました。賃金が高いというだけで、能力に見合わない仕事に従事し続けるということは、とても忍耐力のいること、そして時には一人の人間としてのプライドがひどく傷つくことであることが映画を観ていてひしひしと伝わってきます。
映画の主人公のサラは小学生の息子を親戚に預けて出稼ぎしました。海外で働いて、そこで居住権をとったら子供を呼び寄せしたい、というのが多くの出稼ぎする両親の願いですが、その間に子供は親を知らずに育っていってしまうことが多いのです。親が離れていても、送金によって良い教育を受け、親戚の愛を受けてしっかり育つ子もいますが、親がいないことが致命的なダメージとなる子もいて、それは子供の素質に左右されるところが多く、予想がつきにくい、と言っていた出稼ぎコミュニティーで働くNGOスタッフの話を思い出したりしました。











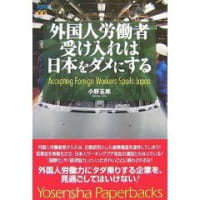
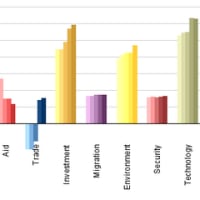
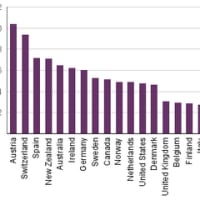
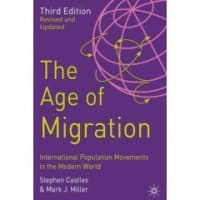
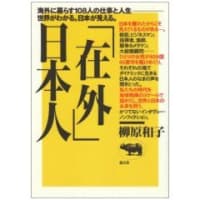
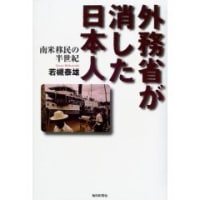
僕も映画は好きで、ハリウッド系、アジア系、日本もの、それぞれ見てるつもりです。
「移民テーマ」のもので、前に見たのは「正義の行方」っていう
ハリソン・フォードが主演の映画でした。
アメリカの移民管理官が、職務と人情の間で悩むって言う映画でした。
今回、紹介されていた「ケバー・ギア」というのも、
想像力を働かせば、わかるような気がしました。
親と子、生活と移民、お金と幸せっていう根本的な問題があるんでしょうね。