まずは「洛北諸道」の<無名の長州人>の次の記述を引用しますので、お付き合い下さい.
----------------------------------------------------------------------------------------
この元治元年ノ変のあと、長州人はことごとく幕府の犯罪者になった.かれらは京・大坂に近寄れなかった.新選組は京都に潜入する長州人を捕えたり斬ったりすることが主たる任務になった.幕府は三条大橋の袂(たもと)にたかだかと高札をたて、
「長州人をかくまってはならない」
と、市中に布告した.
この時期に、長州人河内山半吾が登場するのである.
山国(やまぐに)郷というのは、広い.
大悲山も山国郷でありい、しだれ桜で有名な常照皇寺のある土地も山国郷であり、いま町村合併で京北(けいほく)町とよばれる周山(しゅうざん)もかつては山国郷のうちに含まれていた.こんにちでは山国村というその地名を残す村のみを指すが、かつては四方六、七里ほどのひろさをもっていた.王朝のころはこのあたりを「山国庄」といい、天皇直属の荘園であった時代が長く、その後、領主は転々としたが、土地のひとびとは自分たちは御所直属の百姓であったという誇りがあり、それが幕末まで持続している.
長州人河内山半吾は、元治元年ノ変のあと、京をのがれ、山国郷およびそのまわりの南丹波の村々に出没して、どうやら扇動者、もしくは京都情勢をさぐるための探索者として活躍したらしい.
でなければ、
「官軍・山国隊」
という大旆(たいはい)をかざした山国郷の武装庶民軍が、鳥羽伏見ノ戦のあとに忽然(こつねん)として歴史に登場し、京方(薩長軍)に投ずるというふしぎが、十分には解けないのである.
毎年、京都で時代祭がおこなわれるが、その行列にもこの隊が洋式銃をかつぎ、洋式の鼓笛を鳴らして出てくる.官軍といっても武士ではない.旗には、
「魁(さきがけ)」
という文字が入っている.げんに戊辰(ぼしん)戦争のときにこの山国郷の郷士や百姓やきこりたちが、村の経費でもって武装し、旅費も兵隊個々の自弁で出てきたのである.
山国隊が歴史に登場する要因のようなものがいくつか考えられるにせよ、鳥羽伏見ノ戦という歴史の転換点でいちはやくかれらが飛びだしてくるには、早くから根まわしをしていた者がいるに相違ない.それが河内山半吾ではなかったかと思われる.
----------------------------------------------------------------------------------------
ポイント;
河内山半吾って何者?
山国郷って?
山国隊登場
こういった点について調べたい.
----------------------------------------------------------------------------------------
この元治元年ノ変のあと、長州人はことごとく幕府の犯罪者になった.かれらは京・大坂に近寄れなかった.新選組は京都に潜入する長州人を捕えたり斬ったりすることが主たる任務になった.幕府は三条大橋の袂(たもと)にたかだかと高札をたて、
「長州人をかくまってはならない」
と、市中に布告した.
この時期に、長州人河内山半吾が登場するのである.
山国(やまぐに)郷というのは、広い.
大悲山も山国郷でありい、しだれ桜で有名な常照皇寺のある土地も山国郷であり、いま町村合併で京北(けいほく)町とよばれる周山(しゅうざん)もかつては山国郷のうちに含まれていた.こんにちでは山国村というその地名を残す村のみを指すが、かつては四方六、七里ほどのひろさをもっていた.王朝のころはこのあたりを「山国庄」といい、天皇直属の荘園であった時代が長く、その後、領主は転々としたが、土地のひとびとは自分たちは御所直属の百姓であったという誇りがあり、それが幕末まで持続している.
長州人河内山半吾は、元治元年ノ変のあと、京をのがれ、山国郷およびそのまわりの南丹波の村々に出没して、どうやら扇動者、もしくは京都情勢をさぐるための探索者として活躍したらしい.
でなければ、
「官軍・山国隊」
という大旆(たいはい)をかざした山国郷の武装庶民軍が、鳥羽伏見ノ戦のあとに忽然(こつねん)として歴史に登場し、京方(薩長軍)に投ずるというふしぎが、十分には解けないのである.
毎年、京都で時代祭がおこなわれるが、その行列にもこの隊が洋式銃をかつぎ、洋式の鼓笛を鳴らして出てくる.官軍といっても武士ではない.旗には、
「魁(さきがけ)」
という文字が入っている.げんに戊辰(ぼしん)戦争のときにこの山国郷の郷士や百姓やきこりたちが、村の経費でもって武装し、旅費も兵隊個々の自弁で出てきたのである.
山国隊が歴史に登場する要因のようなものがいくつか考えられるにせよ、鳥羽伏見ノ戦という歴史の転換点でいちはやくかれらが飛びだしてくるには、早くから根まわしをしていた者がいるに相違ない.それが河内山半吾ではなかったかと思われる.
----------------------------------------------------------------------------------------
ポイント;
河内山半吾って何者?
山国郷って?
山国隊登場
こういった点について調べたい.










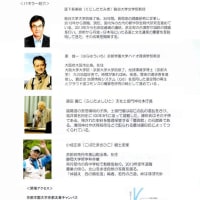
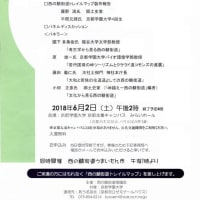
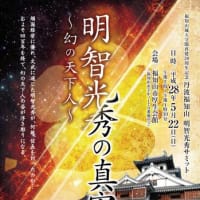


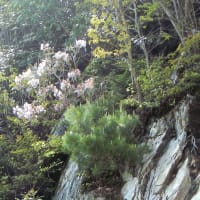


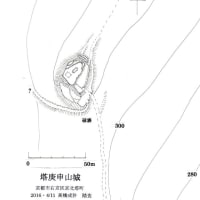


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます