
我がブログで毎回楽しいコメントを頂いている道草さんのブログ、ぶらり道草(II)に、廣野文男さんの作品が載っていた。題して、「お手伝い」。唐臼を少年が踏んでいる絵だ。興味ある方は是非<ここ>をクリックして見て下さい。傍にはお父さんが藁打ちをしている。干し柿が吊され、おくどさんの火が暖かそう。
今は建て替えられているが、我が生家にも唐臼があった。玄関(今様の家の玄関を想像することなかれ)を入った左、牛小屋(小屋というより牛が住んでいる部屋)の壁のとなりにそれはあった。我が家の餅つきはこの唐臼でやっていた。小学生だったけどそんなに力は要らずに餅つきの手伝いが出来た。杵と臼であれば小学生には杵を振り上げての手伝いは出来なかったであろう。
あれから数十年、唐臼はここ京北から、いや日本の家から姿を消してしまった。今は郷土資料館などにその姿を見るのみである。次の写真は、日吉町の郷土資料館で先日撮影したものである。美山の茅葺きの里の資料館にもある。

この懐かしくも便利な唐臼が、組み立てて移動可能な形で復活された。トップの写真がそれである。その説明をされている河原林成吏さんが設計施工され完成した。先月、京都府立ゼミナールハウスのもみじ遊山で披露され、河原林さんが説明をされている。そして京炎そでふれの女子学生もちょっとへっぴり腰ながら足で踏んで、栃餅ができあがり参加者にふるまわれた。

この唐臼は何と言っても、力が要らないのがメリットである。テコの原理で重みを利用すれば良いだけだからしっかりとつける。杵を振り上げて一臼つこうとすると大の大人でもかなりつかれるが、河原林さんも実演されていたが本を読みながらでも出来る。小学生でも出来た。何臼でも大丈夫だ。
ただ臼で餅を混ぜる人との呼吸あわせがなれないと難しく、最初はなかなかスムースに行かないケースもある。餅をつき始めるとき、杵であればつき手が臼のまわりを廻るようにして蒸し上がったばかりの餅米をつぶすのであるが、これが出来ない。
今回作られた唐臼は、分解できる、そして簡単に運べるのだ。分解された姿とトラックに乗せられた姿が次の二つの写真である。一人ではちょっとしんどいかもしれないが二人で車への積み卸しも簡単に出来る。


唐臼は米の精米にも使われたそうであるが、今使うとすれば餅つきに一番便利であろう。イベントでも活躍しそうである。この唐臼がデビューしたのは山国まつり(さきがけフェスタ)であり、ゼミナールハウスのもみじ遊山、京北ふるさと祭りでも披露された。イベントで披露され、楽に餅つきが出来、移動も簡単。そしてちょっと昔を偲ぶことが出来る。これは今後イベントで活躍しそうである。
先日河原林さんと話をしたが、もしイベントで使ってみたいという希望があれば貸し出しも可能であるとのこと。ここで河原林さんの個人情報を公表するのも気が引けますので、小生に連絡いただければ取り次ぎも可能です。
私は唐臼という名しか知りませんでしたが、ネットで検索してみると、じんがら、踏み臼、地唐(じがら)なども呼ばれていたらしい。足の代わりに水力を利用したものもあるようであり、餅つきだけでなく、というよりも精米や麦や粟などもついていたようです。古くは平安時代にまで溯るようであるが、江戸時代以降一般化したそうです。
家が新しく建て替えられ土間も無くなり、また機械化が進んで唐臼は姿を消していったのですが、家が建て替えられたときあの臼は何処へ行ったのでしょうか。今回臼が残っていたのを発見された河原林さんが復元、それも移動式で、というのが面白く、また資料館で、見る、だけでなく、実際に使うことが出来るというのは素晴らしいことだと思います。
今は建て替えられているが、我が生家にも唐臼があった。玄関(今様の家の玄関を想像することなかれ)を入った左、牛小屋(小屋というより牛が住んでいる部屋)の壁のとなりにそれはあった。我が家の餅つきはこの唐臼でやっていた。小学生だったけどそんなに力は要らずに餅つきの手伝いが出来た。杵と臼であれば小学生には杵を振り上げての手伝いは出来なかったであろう。
あれから数十年、唐臼はここ京北から、いや日本の家から姿を消してしまった。今は郷土資料館などにその姿を見るのみである。次の写真は、日吉町の郷土資料館で先日撮影したものである。美山の茅葺きの里の資料館にもある。

この懐かしくも便利な唐臼が、組み立てて移動可能な形で復活された。トップの写真がそれである。その説明をされている河原林成吏さんが設計施工され完成した。先月、京都府立ゼミナールハウスのもみじ遊山で披露され、河原林さんが説明をされている。そして京炎そでふれの女子学生もちょっとへっぴり腰ながら足で踏んで、栃餅ができあがり参加者にふるまわれた。

この唐臼は何と言っても、力が要らないのがメリットである。テコの原理で重みを利用すれば良いだけだからしっかりとつける。杵を振り上げて一臼つこうとすると大の大人でもかなりつかれるが、河原林さんも実演されていたが本を読みながらでも出来る。小学生でも出来た。何臼でも大丈夫だ。
ただ臼で餅を混ぜる人との呼吸あわせがなれないと難しく、最初はなかなかスムースに行かないケースもある。餅をつき始めるとき、杵であればつき手が臼のまわりを廻るようにして蒸し上がったばかりの餅米をつぶすのであるが、これが出来ない。
今回作られた唐臼は、分解できる、そして簡単に運べるのだ。分解された姿とトラックに乗せられた姿が次の二つの写真である。一人ではちょっとしんどいかもしれないが二人で車への積み卸しも簡単に出来る。


唐臼は米の精米にも使われたそうであるが、今使うとすれば餅つきに一番便利であろう。イベントでも活躍しそうである。この唐臼がデビューしたのは山国まつり(さきがけフェスタ)であり、ゼミナールハウスのもみじ遊山、京北ふるさと祭りでも披露された。イベントで披露され、楽に餅つきが出来、移動も簡単。そしてちょっと昔を偲ぶことが出来る。これは今後イベントで活躍しそうである。
先日河原林さんと話をしたが、もしイベントで使ってみたいという希望があれば貸し出しも可能であるとのこと。ここで河原林さんの個人情報を公表するのも気が引けますので、小生に連絡いただければ取り次ぎも可能です。
私は唐臼という名しか知りませんでしたが、ネットで検索してみると、じんがら、踏み臼、地唐(じがら)なども呼ばれていたらしい。足の代わりに水力を利用したものもあるようであり、餅つきだけでなく、というよりも精米や麦や粟などもついていたようです。古くは平安時代にまで溯るようであるが、江戸時代以降一般化したそうです。
家が新しく建て替えられ土間も無くなり、また機械化が進んで唐臼は姿を消していったのですが、家が建て替えられたときあの臼は何処へ行ったのでしょうか。今回臼が残っていたのを発見された河原林さんが復元、それも移動式で、というのが面白く、また資料館で、見る、だけでなく、実際に使うことが出来るというのは素晴らしいことだと思います。










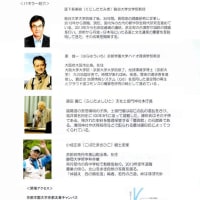
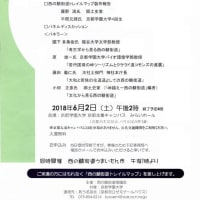
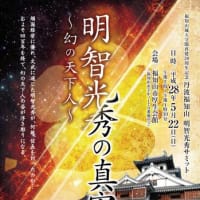


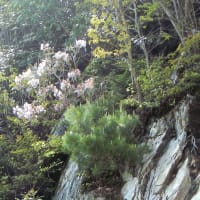


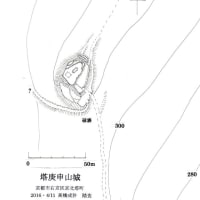


盆や正月の餅搗きも手伝いました。その時は出来上がりのお相伴が楽しみで、自主的に手伝ったと思います。小母さんが土間に屈んで臼取りをされるのですが、頭が杵に当たらないかと心配したものです。
唐臼や石臼や手水鉢など、みんな何処へ行ったのでしよう。「唐臼の重石うなづくほととぎす」羽部洞然。
こういう農機具は都会の人間には縁遠いのですが、観ると最高に素敵な器具ではないでしょうか。餅搗き器なる電化製品で搗かれて食べるお餅より、どんなに美味しいことでしょう。しかも僕自身何度か臼と杵だけで搗く餅搗きを経験したことがありますが、普段そちら方面の筋肉を使っていないホワイトカラー族では情けなく駄目で無理でした。5~6回振り下ろしたら息が上がってしまってどうしようもなかったですものねぇ。でも絶対これなら楽ちんでしょう。手作りするにしてもそんなに難しいはずではないかも。まだまだ合理的で絶やしてはならない農機具が多いはずです。過去の文化ではなく、これからの文化として見直したいものですね。
この餅つきの思いでは、寝ることなく翌日の昼ころまでかかっていたことと、毎年、餅つきをしていると年末警戒の警官が立ち寄り、お餅を食べて帰っていったことを思い出します。しかも、あちこちと配るので大変な量でしたし、水餅の大きな桶が二つあり、粟餅と普通の餅が時々水替えをして長い事食べられていました。冷蔵や冷凍の保存容器のなかったころのことですから、大量に作っても大変だったのでしょう。
このころ何処の誰だか解らない人でしたが、「腹を空かしているらしい、食べさせて泊めてやれ。」と言って祖父は海岸から人を連れてきていました。そんな時代でした。みんな貧しかった。でも、親切でしたし、人を疑わなかったのです。その代わりに誰かが帰ると何かが無くなっていましたが、気にも留めていませんでした。もちろん家に鍵をかけるなどということはありませんでした。
今は恐ろしい時代になりました。
そうか手水鉢もありました。石臼や手水鉢は何処へ行ったのでしょう。五右衛門風呂は潰してもその風呂桶は金属ですから再生可能ですが、石はどうしたのでしょう。田舎の小屋にはまだ沢山残っていると思うのですが、そうでもないように聞きました。
鎌倉街道のお宅でも相当な量をつかれたのですね。一家総出で、見知らぬ人にも振る舞われたり、餅つきは年末の大きな行事でしたね。年末警戒のお巡りさんもラッキーですね。
今日はこの月末にある職場の事業で先日書きました藁苞納豆を作る体験をして貰う準備をほんの少しだけ手伝いました。納豆作りのシーズンにも突入しました。
また楽しいお話を聞かせて下さい。