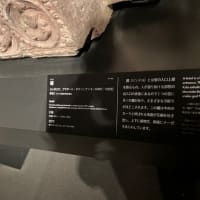かつて西洋哲学史の講義で教授がプラトンとアリストテレスの思想は歴史上に大きなうねりをもって交互に現れると述べていた。当時深くは理解できなかったがなぜか記憶の底に残り、現在に至った。
森田邦久 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sst/7/1/7_15/_pdf/-char/en
この文献で科学哲学史を眺め、おぼろげながらでも教授が言っていた意味が分かりたいと拙いながらも一層の理解のためのメモ作成を試みた。
プラトンへと続く古代原子論1
 wiki
wiki
ミレトスにいたタレス(紀元前624年頃 - 紀元前546年頃ミレトス学派)の一元論では、ただ1種類の元素から世界が成っている。万物は自律的で能動的な原理で動いているとする物活論。
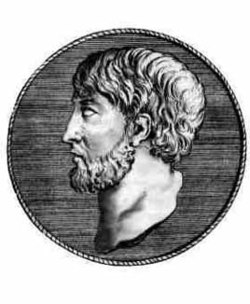 wiki
wiki
アナクシメネス(紀元前585年 - 紀元前525年)は万物は空気が希薄や濃密で他の物質になるとした。度合いで火、水、土になる。空気自身がその原理をもつ。
物質間に「隙間」があることを仮定。
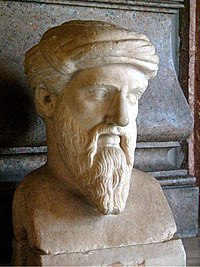
ピュタゴラス(紀元前582年 - 紀元前496年)は世界をコスモス(秩序)と呼んだ最初の人物。秩序とは幾何学的な秩序。
1オクターブ音程が違うということは弦の長さの比率が1:2 完全5度違う 弦の長さの比率が3:2 ギリシヤ語では「比」を意味するロゴス
ピュタゴラス派のヒッパソス 数は宇宙の第一の範型 宇宙を造る神がものを判別する道具。
プラトンへと続く古代原子論2
 wiki
wiki
「隙間」に対しての反論としてエレア出身のパルメニデス(紀元前520年頃-紀元前450年頃)は「あるものはある。あらぬものはあらぬ」。
パルメニデスは存在は境目なく密接している連続体で不動とした。 だから存在は1つと。
存在は不生不滅で無から有が生まれることはないと明示的に述べた。
理由は「無から有が生まれる「有の理由」が無ということになり、充足理由律に反する」とした。説得性に欠ける感がある。
物活論では元素そのものにその元素を動かす原理が備わるとするが
弟子であるゼノン( 紀元前490年頃 - 紀元前430年アキレスと亀のパラドクス)も「隙間」つまり空間の存在を否定。
「隙間」つまり「なにかがある」ということは「どこか」にある。「隙間」つまり空間が「あるもの」ならば空間も空間上のある位置を占めなければならないのでメタ空間、メタメタ空間がなければならないとして無限後退が生じる。それゆえ、空間は存在者ではない。
ゼノンの議論ではアキレスが亀に追いつけないと同様にモノは動くことができない。
 wiki
wiki
エンペドクレス(紀元前490年頃 – 紀元前430年頃)は四元素の外部にそれを動かす愛と憎しみの原理があり6種類の根本原理とした。人間の精神力を元素に加えた。
なんと精神の働きまで元素に加えた。(量子力学の観察者を想起させる)
プラトンへと続く古代原子論3
 wiki
wiki wiki
wiki
ゼノンの弟子レウキッポス(紀元前440-430年頃に活動)とその弟子デモクリトス(紀元前460年頃-紀元前370年頃)は世界を構成しているのは原子で無数に存在する、そして大きさや形が異なる、不生不滅で大きさや形状が変化しない、幾何学的な性質以外の性質をもたない。
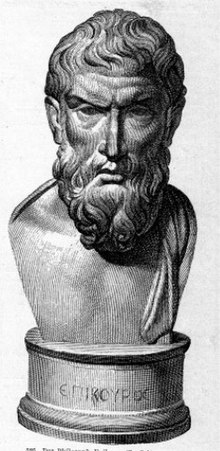 wiki
wiki
エピクロス(紀元前341年 – 紀元前270年)は「空虚中の原子は他の原子と衝突するまで等速直線運動する。」とまで付け加える。
プラトンで西洋哲学の歴史始まる
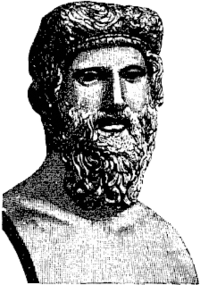 wiki
wiki
プラトン(紀元前427年 - 紀元前347年)「数と計算」を「あらゆる技術、思考、知識の基礎として共通に用いる。
「真の存在者」とはエネルギーと運動量であり生成消滅しない
に通じる。
ホワイトヘッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」という趣旨を述べた。これはよく理解できなかった。
初期のキリスト教徒はプラトンの教義を重視した。プラトンの時代は1000年以上も大きな潮流をなしたと理解した。
アカデメイアは東ローマのユスティニアヌス帝によって529年に閉じられ終焉により、キリスト教哲学の時代が訪れることとなった
アリストテレス重視

それまで体系的なアリストテレスの思想をあまり重視しなかったが11世紀以降に主として西方教会のキリスト教神学者・哲学者などの学者たちによって確立されたスコラ学においてアリストテレス(前384
キリスト教神学者・哲学者にとってプラトンの教義は危険思想化してきたようだ。
デカルトでプラトン重視に
ルネサンス期 アリストテレスの哲学・自然学を基礎とするスコラ学、教会の権威に対抗する思潮が生まれる。
新プラトン主義で15世紀に入ってから再び脚光を浴びた古代原子論が近代科学革命を起こす要因となる。
私は、それまでに私の精神に入りきたったすべてのものは、私の夢の幻想と同様に、真ならぬものである、と仮想しようと決心した。しかしながら、そうするとただちに、私は気づいた。私がこのように、すべては偽である、と考えている間も、そう考えている私は、必然的に何ものかでなければならぬ、と。そして「私は考える、ゆえに私はある」 Je pense, donc je suis. というこの真理は、懐疑論者のどのような法外な想定によってもゆり動かしえぬほど、堅固な確実なものであることを、私は認めたから、私はこの真理を、私の求めていた哲学の第一原理として、もはや安心して受け入れることができる、と判断した。『方法序説』野田又夫訳、中央公論社)
私が他のものの真理性を疑おうと考えること自体から、きわめて明証的にきわめて確実に、私があるということが帰結する。 (同上)
真理はキリストではなくてこの私の内にありとデカルトは言った。
デカルトは1,200年間の西欧世界の精神界の誤謬を見つけだし哲学の基準をプラトンに戻した。
デカルトの明察とは、「神が中心である」という中世哲学を「人間は価値基準を創造し、破棄することができる」と。
1,200年間の西欧世界の精神界の誤謬を見つけだし、それを破り、哲学の基準をプラトンに戻した。
理論優位、観察優位の弁証法的発展の歴史、西方(ギリシャ)と東方(インド)の融合発展の歴史ともいうべきうねりであることも理解できた。