
“武器=破壊=悪/文化=創造=善”という、敗戦国日本に顕著な特殊二元論。その袋小路を抜け出すための思考を養う、戦争文化論入門。その鋭利な刃物は、兵器なのか道具なのか?
序章 芸術的、宗教的、象徴的―武器へのまなざし
第1章 動物、健康、保存食―生きている武器たち
第2章 鉄道、飛行機、カメラ―組み合わせて武器にする
第3章 ネジ、工具、標準化―武器とものづくりの発想
第4章 語学、民族学、宗教―武器になりうる人文知
終章 文化、戦争、平和―結局すべてが武器になる
モザンピークの国旗には独立への苦闘の象徴として自動小銃のAK47が描かれているし、
グアテマラの国旗にも護国の象徴として2丁のライフルが描かれている。
サウジアラビアの国旗にも剣が描かれているし、
ケニアとエスワティニの国旗には盾と槍が描かれている。
ブータンの丸い国章も、中央に描かれているのは金剛杵である。
ナチスと戦うゲリラ養成のために書かれた『赤軍ゲリラ。マニュアル』のなかでは、
「白兵戦ではシャベルはすばらしい武器になる」と書かれている。
「シャベルで敵の攻撃を防ぎ、敵の銃剣の突きをかわすことができる。
シャベルの鋭い刃は、よく切れる恐ろしい武器になる。
特に込み合った状況での戦闘で重宝する」
1940年には陸海軍の要請で精工舎が兵士用の「九型腕時計」の生産を開始。
腕時計は、軍事活動に必要な装備品と認識された。
日本が太陰太陽暦からグレゴリオ暦に切り替えたのは1872年末で、ほぼ同時期に徴兵令も発布された。日本人に1日は24時間で、1時間は60分という西洋流の時間間隔を身につけさせる場にもなった。
「ボールペン」を20世紀中頃にイギリス空軍の活動に関わった意外な道具としてあげることもできる。現代のボールペンの原型となるものの特許が取得されたのは1938年であり、それが一般にも普及し始めたのは、第二次大戦が終わった後、1945年以降のことである。しかしイギリスは40年代に入ると国内でそれをいち早くライセンス生産し、3万本を空軍に支給したとされている。航空機搭乗員は機内でさまざまな計算をしたり、地図などに書き込みをしたり、通信その他をメモをしたりすることがあるが、万年質は上空では気圧の変化でインクが漏れることが多く、鉛筆も削る必要があったり折れやすかったりして不便だった。そこでこの新しい筆記具が活躍したというのである。
攻撃犬
歩哨犬
偵察犬
伝令犬
地雷探知犬
衛星犬
輸送犬
電信犬
牽引犬
衛生犬は戦場で行方不明になった負傷兵を探すよう訓練されたものであり、災害救助にも使用されている。
電信犬は電線のリールを背負って、砲弾の飛び交う戦場を走り抜け、寸断された通信網を復旧するための犬である。さまざまな役割をこなす貴重な犬たちのために、第二次大戦時は犬用のガスマスクも開発された。
靖国神社には軍馬の慰霊像と並んで、「軍犬慰霊像」もある。
軍用犬の出征時には、人間の兵士に劣らぬほどの盛大な壮行会も行われた。
第二次大戦時にソ連軍は、犬の背に地雷をくくりつけ、ドイツ軍の戦車の下にもぐって自爆するよう訓練した。「対戦車犬」「地雷犬」などと呼ばれた。それを知った現場のドイツ軍は犬を見てパニックになったというが、彼らが機関銃や火炎放射器などで必死に対抗すると、今度はその地雷を背負った犬が逃げ帰ってきて、逆にソ連軍側がパニックになったなどという話もある。
ベトナム戦争では、アメリカ兵はゲリラ兵のさまざまなトラップに悩まされた。
巧妙に偽装された落とし穴の下に尖った竹を並べたものや、足で踏むと前方から鋭く長い釘の並んだ板が跳ね上がってきて全身を突き刺すものや、地面や木の上になどにわかりにくく設置された地雷や手榴弾など、いろいろな仕掛けがあった。
それらは人の目では発見が難しく、多くのアメリカ兵が犠牲になったため、そうしたトラップを発見させようとアメリカ軍は犬の利用を試みたのである。
犬は地下のトンネルに潜むベトコンを狩り出すためにも用いられたし、その他の捜索、斥候、警備、そして一部では戦闘にも用いられた。
当時のアメリカ軍は、ベトナムの気候に少しでも近い沖縄で犬たちの訓練をしてから彼らを戦地に派遣したようである。
アメリカ軍が投入した軍用犬の数は合計で4,900頭にも達したが、戦争が終わるとその大半は現地で安楽死させられたのだった。
犬の軍事史上画期的な出来事として、インドネシア戦争で犬による最初のパラシュート部隊が作られた。実際の降下では、犬は高度400mで飛行機の外に放りだされ、自動索でパラシュートが開かれると4本の足でうまく着地することができたという。
紀元前4000年前ごろには馬を家畜化していた。
馬に引かせる二輪車を「チャリオット」といい、それは古代戦車、戦闘馬車とも訳される。
一口に「馬」といっても、品種により体格や能力はかなり異なる。
馬の速度力量を比較して馬匹(ばひつ)改良に資する1つの手段として「競馬」も有効だと考えられるようになった。賭博はすでに明治13年公布の旧刑法でも禁止されていたが、馬券購入は偶然に頼る他の賭博とは異なり、馬に関する知識を蓄積することで的中するものであると主張され、結局政府はそれを黙認したというプロセスもあった。
かつては陸軍と競馬との間にも意外なつながりがあったのである。
20世紀でも多くの馬が戦争に用いられたが、興味深いのは、時代が進むにつれて用いられた軍馬の数はむしろ増えていったことである。
『軍馬と農民』によると、軍馬の数は、
日清戦争では6万頭、
日露戦争時は17万頭
アジア太平洋戦争時は1941年の時点ですでに34万頭に達していた。
そのわけは、装備近代化の過程で、武器弾薬・兵糧など運搬すべき物資と兵員の数が激増したためである。また、戦場になると予想された場所は未舗装のため当時の自動車の走行には不向きで、燃料の十分な供給も見込めなかったため、馬はまだ大いに必要だったのである。
モネスティエによれば、ドイツ軍は1941年6月のソ連侵攻で75万頭の馬を用い、その戦争全体を通して徴募した馬の数は275万頭にのぼるとしている。だがソ連軍はそれより多く、荷物運搬用の馬を含めると350万頭になる。
結局この戦争で各国の旗のもとに集められた馬の総数を、モネスティエは800万頭にのぼると推定している。第二次大戦における日本人の死者は軍民合わせて310万人とされているが、世界中で死んだ馬の合計はその倍以上だったわけである。
ちなみに、終戦の約5ヶ月前に硫黄島で戦死した陸軍将校の西竹一は、1932年のロサンゼルス・オリンピックにおける馬術(障害飛越)の金メダルリストであった。これまで馬術でメダルをとった日本人は、この西竹一のみである。
ロバやラバは足腰が丈夫で、粗食にも耐えられ、従順であることから軍隊では非常に重宝された。
20世紀半ばの日本では、ゼロ戦をはじめとする最新鋭の戦闘機が工場から牛車で滑走路まで運ばれたという話も有名である。
日本で最初の運動会は、千八百七十四年の海軍兵学寮における「競闘遊戯会」だと言われており、それから10年ほどで広がっていった。
1880年代半ば以降の運動会の発展に大きな影響を与えたのは森有礼(ありのり)である。
ビタミンCの欠乏によって引きおこされる「壊血病」がある。
これは大昔からある病気だが、特に注目されるようになったのは大航海時代に入ってからである。果物や野菜は腐りやすいため、積み込まれなかったのである。
多くの乗務員がビタミンCの欠乏により、鼻や口から出血し、下痢や関節の痛みに苦しみ、歯も脱落して、衰弱して死んだ。
壊血病の予防法・治療薬を見出した一人に、18世紀半ばのイギリス海軍の軍医ジェームズ・リンドがいる。オレンジとレモンを与えた兵士はほぼ完治することを証明した。
柑橘類が壊血病の特効薬になることを発見した。
世界で初めて全身麻酔による手術を成功させたのは、1804年、江戸時代の日本における華岡青洲(はなおかせいしゅう)である。彼は「通仙散」という麻薬液を調合して、乳がんの摘出の手術をおこなった。
アヘンに含まれるモルヒネは、現在は医療でも用いられている。
コンデスミルクは南北戦争で北軍兵士の携帯口糧として用いられた。
20世紀初頭には食品を急速冷凍する技術も開発され、朝鮮戦争時には初めてフリーズドライされたコーヒーが兵士に支給された。
缶詰が広まっていったきっかけは、アメリカでは南北戦争、
ヨーロッパでは第一次大戦であった。
日本では日清・日露戦争においてすでに缶詰が用いられている。
チャールズ・グットイヤーは1839年に、ゴムに硫黄を加えて加熱すると耐熱性をもたらせることを発見した。彼の考えた加硫法は画期的で、後の社会を大きく変えた発明だった。
ただし、グッドイヤーの加硫ゴムが「タイヤ」として優れた性能を発揮するには、もう一人の発明家が必要だった。それはジョン・ボンド・ダンロップである。
それまでのタイヤは固形ゴムだったため、わずかな凹凸で衝撃があり、車体を傷めやすく乗り手も疲れてしまうものだった。そこでダンロップが考えたのが、中に空気を入れることで衝撃を吸収できる構造のタイヤであった。
アルミニウムに銅やマグネシウムやマンガンを加えると大幅に強度が上がることがわかり、それはジュラルミンと呼ばれるようになった。
一機のB29爆撃機は、この38本の焼夷弾を詰めたクラスター弾を40発搭載したので、1回の爆撃で投下された焼夷弾は1520本だったことになる。
オランダ人のアントニー・フォッカーであった。
彼が発明したのは、プロペラ同調式機銃発射装置である。
あらかじめ敵機との距離や自機の姿勢と速度などを計算して未来位置に向けて撃たなければ弾丸は命中しない。
「ジャイロ式照準器」
これはジャイロを利用して照準を補正する仕組みになっているため、経験や勘に頼らなくても敵機の撃墜が容易にできるようになった。
軍用機から写真を撮っていた人物のなかで、世界で一番有名なのは『星の王子さま』で知られるサン=テグジュペリであろう。
ネジこそ近代兵器を支えている最も根本的な部品といって過言ではないだろう。
「アメリカでは互換性技術が生まれ、標準化が進む上で大きな契機となったのは軍と戦争だった」
20世紀前半における両大戦では、標準規格を制定して部品の種類を絞り、大量生産体制を取れるかどうかが極めて重要だったが、日本はそれができなかった。
1950年の朝鮮戦争にともなういわゆる朝鮮特需をきっかけに、アメリカから規格化された互換性部品の加工技術や検査技術が日本の産業界に導入され、それが後の日本製品の品質向上の基礎になったと指摘している。
火気の普及によって、人々は弾丸の大きさをある程度揃える必要があることに気付き、「口径」の概念が生じた。規格化、互換性や標準化という発想とそれに基づいた製造方法は、工作機械の発展、大量生産の始まり、そして労働形態の変化なども結びついている。
「連合国翻訳通訳部」はオーストラリアのブリスベンに設置されていた。
オーストリア北部のダーウィンには、撃墜あるいは鹵獲(ろかく)された日本軍の航空機を解体し、機体や部品に書かれた文字や記号などを翻訳してその航空機および製造工場に関する情報を収集・分析する部隊もあった。部品工場などを狙った空襲計画の立案など、戦争遂行に大いに役立てられたようである。
三島由紀夫は、戦闘機に対する強い思い入れを語っている。
彼は『太陽と鉄』で自衛隊でF104戦闘機に体験搭乗したときのことを綴っている。
「あの鋭角、あの神速、F104は、それを目にするや否や、たちまち青空をつんざいて消えるのだった。あそこの1点に自分が存在する瞬間を、私は久しく夢みていた。あれは何という存在の態様だろう。何という輝かしい放埓だろう。頑固に座っている精神に対する、あれほど光輝に満ちた侮辱があるだろうか。あれはなぜ引裂くのか。あれはなぜ、一枚の青い巨大なカーテンを素早く一口の匕首(あいくち)が切り裂くように切り裂くのか。その空天の鋭利な刃になってみたいと思わぬか」
「F104、この銀いろの鋭利な男根は、勃起の角度で大空をつきやぶる。その中に1疋の精虫のように私は仕込まれている。私は射精の瞬間に精虫がどう感じるか知るだろう」










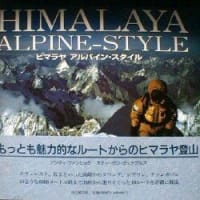
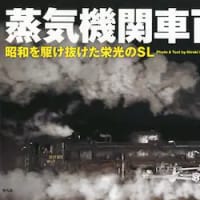
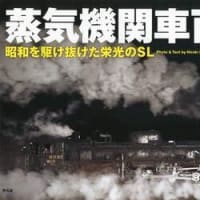
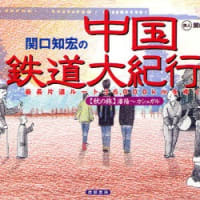
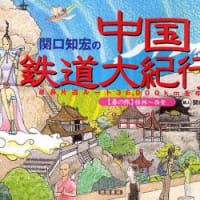
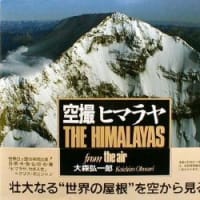

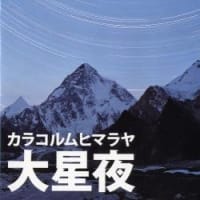
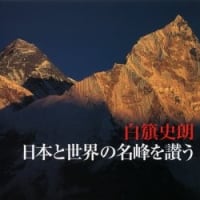
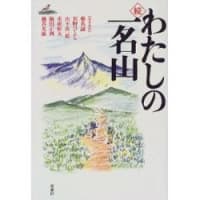
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます