四阿山(あずまやさん)の行場で体術を身につけ、動きが猿のように敏捷であるため「猿飛」とも呼ばれている。
明治13年;1880年における政府の調査によれば、当時、全国でもっとも人口が多かったのは、新潟県の154万人、東京は、12位の96万人に過ぎない。
上杉との同盟に激怒した家康が、真田一族を滅ぼすべく、上田城攻めを決断した。
落水(おちりみず)城で秀吉とひそかに会って以来・・・
大坂城は、上町台地の北端に築かれている。
かつて、一向宗の本拠、石山本願寺があった場所である。
その一方で、石田三成を通じ、上杉家の佐渡領有がみとめられるよう、秀吉に対してはたらきかけた。当時、佐渡島は土豪の本間氏がおさめており、上杉家の支配はいまだおよんでいなかった。天正17年、6月、上杉景勝は直江津、郷津の両湊から軍船を仕立てて、佐渡攻めに出陣した。上杉軍は、20里の海を越えて真野湾へ侵入。
景勝は、佐渡の支配を執政の直江兼続に命じた。上田銀山の金掘り「上田カナコ」400人を送り込むなど、佐渡金山の開発を積極的に推しすすめた。
佐渡が金山の島として全国的に知られるようになるのは、まさにこの、直江兼続の佐渡金山開発以降のことである。
佐渡からは、大判にして年に金799枚が産出。
岩船郡の高根金山など、越後国内で産する1124枚と合わせ、上杉領では年間2000枚近い金が取れるようになる。これは日本国内の産金高の、じつに6割の量を占めるものだった。
もっとも、そのうちの半分は豊臣秀吉に献上され、豊臣家が大坂城にたくわえた莫大な黄金の多くは、上杉領から出たものだったのである。
「仁愛」の思想
兼続が≪愛≫の一文字を兜にかかげたのは、謙信の「義」から発展させたみずからの思想を、
ーーこれが、わが信じる道だ。と、満天下にあまねく知らしめるためであった。
川中島四郡とは、信濃でもっとも肥沃な、
水内(みのち)郡、高井郡、更級郡、埴科(はにしな)郡のことである。
秀吉は小田原城を見下ろす丘陵地に付け城を築いた。
石垣山城、である。
鉢形城;寄居町
荒川の急流渦巻く断崖の上に築かれた要害堅固な城である。北条氏邦
「いまの言葉に、嘘いつわりはないか」
「天地神明に誓って」
関東攻め、奥羽攻めの功により、上杉家は出羽国内の、
田川郡
櫛引郡
遊佐郡
いわゆる庄内三郡を秀吉から安堵された。
庄内地方をめぐっては、ここ数年、出羽の最上光と熾烈な争奪戦が繰り広げられていたが、ここに上杉家の領有が正式に認められた。
旧領の越後、佐渡両国、信濃川中島四郡と合わせ、総石高は91万石にふくらんだことになる。しあし、何といっても、上杉家にとって大きかったのは、庄内三郡の領有により、北国船の寄港地である、酒田湊を手に入れたことだった。
軍勢をひきい、酒田湊へ入った上杉家執政の兼続は、それまで庄内地方を支配していた最上義光の勢力一掃をはかった。また、砂が積もって浅くなっていた港を浚渫。
三成は利休の罪状を並べたてて、糾弾した。
兼続は上杉家の手勢3,000をひきいて利休屋敷を取り囲んだ。
≪中央政権≫を主張する石田三成と、諸大名の仲介者として≪地方分権≫を擁護する利休との対立が、豊臣秀長の死を引き金にして火を噴いた。
秀頼が誕生したことにより、
「吾子(わこ)のために、新しい城がいるのう」
普請好きな秀吉は、伏見の地に、大坂城と並ぶ大城郭を築くことを決めた。
工事には、大工、石工、人足など、総勢25万人が動員された。
石垣に使われる大石は、瀬戸内海の小豆島などから船で運ばれ、木材のヒノキが木曽谷から大量に伐りだされた。
「しかし、上杉家の本貫の地、越後を去っていずこへ行けと?」
「会津だ」
「会津・・・」
「直江どのも、ご存じであろう。会津若松(黒川から改名)城の蒲生家が、重臣どうしのいがみ合いで混乱しておること。蒲生に会津をまかせてはおけぬ」
東国支配の拠点として、会津の地を重要視する秀吉は、国替えの必要を感じていた。
秀吉の命令と三成は言うが、それはまた、同時に三成自身の強い希望であることは間違いない。
「殿下の身にもしものことがあったとき、家康は必ずや兵をあげる」
「徳川内府(だいふ)は、めぐってきた機会をみすみす逃すような男ではあるまい」
従来の上杉家の領地は総石高91万石。
移封後は、佐渡、出羽庄内領はそのままに、旧蒲生領の会津などを合わせ、120万石となる。
このころ、100万石をこえる大名といえば、
徳川家康;265万石
毛利輝元;129万石
の2名しかいない。
増やした石高で、関東の徳川、奥州伊達に備える軍備を増強せよ、ということであろう。
上杉家の大加増の意味を、兼続はそう解釈した。
新たな上杉領120万石のうち、米沢30万石は、秀吉の命によって直江兼続の領するところになった。
一行は六十里越えで、会津へ向かった。
道は、米沢街道。
越後の塩が、会津を経由して米沢へ運ばれる塩の道である。
米沢までは14里。
浜崎、熊倉、大塩をへて
国境の檜原峠を越え、綱木峠、船坂峠を通ってゆく。
朝日軍道
兼続は父惣右衛門と連絡を取り合い、米沢城下と庄内をむすぶ軍道の開削をひそかにすすめていた。危急のさい、最上の目を気にせず、庄内と米沢を行き来できる軍道が欲しい。
といっても、その道はかぎられている。
平地の最上領を通ることができないため、朝日連峰の尾根づたいに、
大朝日岳、西朝日岳、以東岳、とまさに雲上の道である。
道の要所要所には、薪や食糧を備蓄した山小屋がもうけられ、行き来する兵たちがそこで休息を取ることができるようにした。
神指城
直江状
「わしを挑発しておる」
「上杉を討つッ!出陣の陣触れを発せよッ」
兼続の投げた一石によって、世は大きく動き出した。
徳川方についている常陸国;佐竹義宣(よしのぶ)は、じつは内々に兼続と意を通じ、会津攻めでは上杉軍と協力して家康を迎え撃つという密約をかわしている。
6月18日、家康は会津遠征の途についった。
東征軍は80余将、総勢10万余。
同じころ、近江佐和山城の石田三成も、決戦に向けて動き出している。
「だが、美しいハスの花は、泥の中より咲くことを、やつは知らぬ・・・」
兼続の≪愛≫は、すなわち民を憐れみ、家臣を憐れみ、敵をも憐れむ、広い意味での慈愛、すなわち仁愛の精神なのである。
上杉家を滅亡に導く死の美学に殉ずるのではなく、たとえ汚名にまみれても、生き残りの美学に徹する道を兼続は選んだ。
兼続は、本多政重を婿にむかえて、徳川政権との絆づくりに心を砕いた。
その一方、白布高湯に鉄砲工場をもうけ、火気の大量生産をはじめた。
幕府に対する謀反の意思がないことをしめすため、米沢城を当時流行の高石垣もなければ天守も上げない、館に毛のはえたような小城のままとどめておいた。櫓、御殿の屋根も、火がかかればひとたまりもない茅葺きであった。
この程度の貧弱な城の構造では、籠城は不可能で、戦いを最初から放棄しているにひとしい。
すべては、幕府に無用の難癖をつけられぬための用心である。
赤目屋敷;火薬の原料となる硝煙
米沢藩には、--上杉鷹山という、藩政改革によって財政の建て直しをおこなった名君が出るが、その鷹山が心の師とあおぎ、政策の手本としたのがほかならぬ直江兼続であった。
江戸時代後期、鷹山が断行した財政再建策のほとんどは、すでに200年も前に、兼続によっておこなわれていたものである。
慶長19年;1614年の正月早々、上杉家、伊達家、前田家、最上家をはじめとする東国の諸大名に、幕府から大きな普請役が課せられた。
越後国、高田城の築城である。
普請の総奉行は、伊達政宗がつとめた。
「荒れ野原であった菩提ケ原に、かように壮麗な城が築かれるとは・・・」
幸村は独自に「真田紐」なる組紐を考案し、里の女たちにつくらせて、配下の忍びに行商をおこなわせた。紐を売り歩かせたのは、ひとつには活動資金をかせぐためと、いまひとつは天下の情勢をさぐるという目的があった。
大坂と関東の手切れの日は、遠からずやってくる。そのときを、真田父子はひそかに牙をとぎつつ、一日千秋の思いで待ち望んでいたのである。
真田丸の規模は、縦横180m。
面積にして1万坪。野球場がすっぽりおさまるくらいの広さである。
直江山城守兼続は、大坂の陣から4年後の元和5年;1619年12月19日、江戸桜田の鱗屋敷で60年の波乱に富んだ生涯を閉じた。










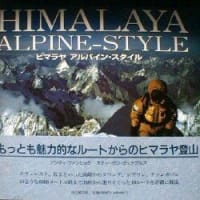
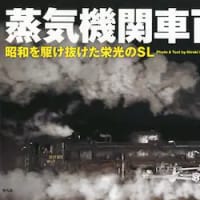
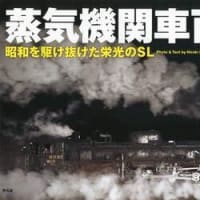
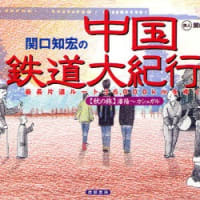
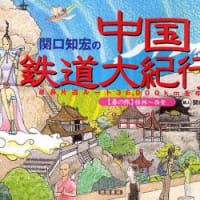
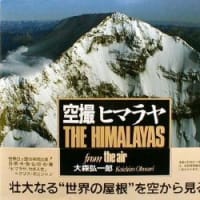

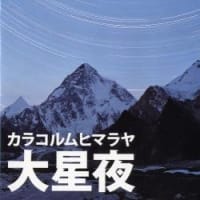
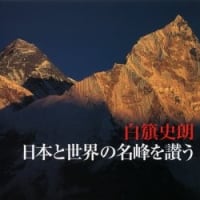
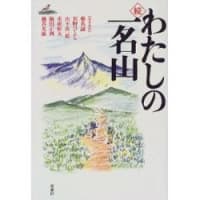
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます