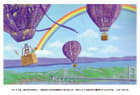森有礼の5人の兄弟は、仲が良く情愛の強い家族だったそうです。
森有礼の5人の兄弟は、仲が良く情愛の強い家族だったそうです。
お母さんの性格を有礼は一番受け継いでいました。
精神的な物を追い求め、ストイックに行きた森有礼ですが、お母さんの里は、偶像に対する信仰心の篤い人でした。
ところが、68歳の時、病気になった時、隣に住んでいたクララと母親のアンナがお見舞いに行きました。
病人の側には、健康の回復を偶像に祈るための細長い紙切れが下がっており、別の部屋には神棚がありました。
しかし、アンナが祈ると、クララは始めて神さまが生きてそこにおられるような臨在を感じたのです。
心の中に荘厳な感じが襲い、神様は本当に触れてくださり「私の心の目に、まだ見たことがないものを見せて下さった。」と生まれて初めての、神を実体験として理解したのです。
次の日、森の母親から、アンナにお祈りに来て欲しいというお使いが来たのです。
今度は、通訳もつけていて、自分の神は信じる価値が無いから、もっといい物が欲しいと言ったのです。
クララは、きっと神様は、最後に森のお母さんを救って、天国にいれてくださるつもりだと感じました。
なぜなら、お母さんは生涯偶像に仕え、偽りの神々を信じ、心を込めて仕え、正しく生きて、清らかな善良な方になろうと努力してきた方です。
「それは知らずに崇拝していたので、神様はきっとお許しになり、最後に真の神様を知らせて救ってくださるでしょう。これが、私たちの宗教の美しさです。」とアンナは説明したのです。
神さまは、知らないで、偶像を信じていた人達を許し、真の神であるご自身に立ち返るように手を差し伸べているお方です。
この方にしか、救いないのです。





 火柱の竜巻の写真を見ましたが、怖いですね。
火柱の竜巻の写真を見ましたが、怖いですね。
ところで、江戸時代、江戸の名物はけんかと火事だと言われていましたが、本当に火事が多いです。
明治に書かれた、クララの日記のの中にも火事が何件も出てきます。
築地の大火に関しては、二度ばかり出てきますが、クララの家の近くまで火がやってきました。
結局燃えなくて助かりましたが、あちこちから火事見舞いの人々がやってきて、御見舞いの品が届きました。
これは、日本人独特なのかもしれませんね。
日記の中には、初めからホイットニー家に同居している日本人が何人かいますが、その中の小野という人物が出てきます。
宮内省に勤めている役人で、天皇の衣装係りで、報知新聞記者で論説委員もしています。
友人からは、堅実で完全に信用できる友だと言われていました。
小野は、とてもひょうきんな人でしたが、突然火事見舞い狂になってしまったのです。
年中、火の手が上がると駆け出して行くようになり、クララの兄のウィリイまで連れて行くようになりました。 のため、ウィリイは、風邪をひいてしまいました。
のため、ウィリイは、風邪をひいてしまいました。
文句を言ったら、朝5時か6時に起きて、11時か12時まで帰ってこなくなり、誰にも会わなくなった。
陽気でおしゃべりだったのが、よそよそしく冷たくなり、クララは口をきかなくなりました。
それが、原因で家を出て行きましたが、その前にお礼だと言って豪華な食事を御馳走してくれました。
クララは、小野の名前と安息日に関する一節を書いて聖書をあげ、クリスチャンなのだから教会に行くように勧めた。
ところが、みんなに内緒で茶屋の娘と結婚してしまったのです。
その後、日記には出てこなくなりましたが、相当面白い性格の人ですね。

 ウイリアム・アンダーソンという 医師は、1873年(明治6)35才の時、日本にやってきました。
ウイリアム・アンダーソンという 医師は、1873年(明治6)35才の時、日本にやってきました。
品川の海軍病院に勤務しながら、海軍医学校で軍医学生を教え、脚気の研究もしていました。
当時の日本は、脚気で亡くなる方が多かったのです。
和宮・静寛院宮も、侍女が脚気で亡くなったすぐ後に、自分も脚気で39才の若さで亡くなっています。
だから、重要な働きをした方ですね。
また、日本美術に興味を持ち、1880年(明治13)イギリスに帰国しました。
膨大な日本、中国の絵画と美術品を収集した品は、今日の大英博物館における日本美術コレクションの中核をなしています。
1886年(明治19)の48才の時、『日本絵画芸術』The Pictorial Arts of Japanを発表しました。
これは、英語で著された 初めての本格的日本美術史です。
いろんな方が、明治時代活躍していましたね。
 今日は、東京アンテオケ教会で、6時半よりいやしの集いがあります。
今日は、東京アンテオケ教会で、6時半よりいやしの集いがあります。
時間を取ってお祈りいたしますので、お友達を誘って、ぜひおこし下さい。
4時40分頃から、路上ライブとチラシ配りをしますが、雨が止むように祈っています。
埼玉は、ほとんど小ぶりになってきました。
ところで、明治期に木村熊二と言う方がいましたが、勝海舟がお金を出してくれ、森有礼について、アメリカに留学しました。
ホープカレッジ、ラトガース神学校に学び12年も帰って来なかったのです。 結婚して5年後に、夫はアメリカに行ったままで奥さんの鐙子(とうこ)さんは、子供を育てながら帰国を待ち望んでいました。
結婚して5年後に、夫はアメリカに行ったままで奥さんの鐙子(とうこ)さんは、子供を育てながら帰国を待ち望んでいました。
それにしても、12年は長いですよね。
その間、向こうで愛人ができたのではないかと噂する人もいました。
1882年、やっと帰って来た夫は牧師任命書を持って、日本に遣わされてきたのです。
12年ぶりにご対面、そしてお母さんも交えての食事と言う時に、夫が祈りだしたわけです。
当然、妻はどうしていいのか分からず悩んだと思いますが、夫と子供を連れて、教会に通いその年の12月にフルベッキより洗礼を受けました。
そして、木村熊二は、家を開放してそこで勉強会を開きますが、そこに勝海舟の三男・梶梅太郎も学びに行っていたのです。 1885年に、熊二は、奥さんと計画し、その弟の田口卯吉の協力も得て明治女学校を創設します。
1885年に、熊二は、奥さんと計画し、その弟の田口卯吉の協力も得て明治女学校を創設します。
しかし、残念ながら、鐙子さんは、1886年にコレラにかかり亡くなってしまうのです。
熊二は、再婚し、1888年(後の高輪教会)の牧師になりました。
義弟の田口卯吉は、自由神学の影響を受け、教会から離れ政治家になりましたが、葬儀はキリスト教式で行いました。
人の人生は、先の読めないものですね。
しかし、すべては神様の手の内にあるのです。







 来週の日曜日は、4時から白馬賛美大会のための東京アンテオケ教会内の予選会が開かれます。
来週の日曜日は、4時から白馬賛美大会のための東京アンテオケ教会内の予選会が開かれます。
地方から、白馬に出場していたグループが移動されて来たので、またまた大混戦になる予定です。
4時から、7時まで、39グループ出場します。
久しぶりに司会に立つので、ドキドキハラハラです。
金曜日から風邪をひいていて咳がまたひどくなっているので、今朝はそのために必死で祈りました。
昨日読んだ本の中に、明治の初期に牧師になった桑田繁太郎のお話が出ていました。
彼はお金持ちの息子でしたが、早くにお母さんを失くしました。
稼業も傾いてしまい、親戚の家で育ちましたが、13歳の時クリスチャンになり同志社に入る夢を持っていました。
でもお金がないため、小学校の準教員の資格を取り、働きながらお金をためていたのです。
ところが、明治23年の紀元節の時、天皇陛下の写真に神道の儀式がなされ、それにお辞儀をするのを拒否したので、学校をやめることになりました。 その後、働きながらやっと同志社神学部に入り、楽しい生活を送るのですが、結核にかかり、余命1年半から3年と宣告されます。
その後、働きながらやっと同志社神学部に入り、楽しい生活を送るのですが、結核にかかり、余命1年半から3年と宣告されます。
そこで、残りの人生を神様に捧げ、全てをなげうって、薬も飲まないで死を覚悟して伝道しました。
すると、結核は、完全にいやされてしまいました。
ところが、同志社に新神学が入り込み、今までの聖書を否定するような自由神学が教えられるようになったのです。
そこで桑田は、当時、生きた信仰の教えのある松江のバックストンに会いに行き、いろいろ質問すると「祈りなさい。続いて祈りなさい。神様が教えてくださいます。」と言われて、信仰の確信が与えられました。
その後、桑田は、真の学びを求めて、東京の明治学院神学部に入りなおし、植村正久の教会に行きます。
ところが、結核が再発するので、夏季伝送に療養を兼ねて九十九里の松尾教会に派遣されました。
ここでも、体のことを考えないで、いっしんに伝道していたら、再び完全にいやされてしまいます。
その後、明治41年に大阪北教会の牧師となり昭和21年まで牧会し、大阪神学院の教頭などを勤めています。
いろんな、神の器がいらっしゃったのですね。(続明治人物拾遺物語・秋山繁雄著より)