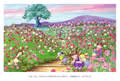バプテストの方々は、洗礼を浸礼しか認めていないので、パブテスマを訳すのに「浸め」と訳すように主張しました。
バプテストの方々は、洗礼を浸礼しか認めていないので、パブテスマを訳すのに「浸め」と訳すように主張しました。
そのため、ヘボンたちは知的レベルの高い方用の聖書をつくりましたが、バプテストのネーサン・ブラウンは、教育を受けていない方々でもわかる翻訳の聖書を作りました。
結果的に、ヘボンたちが翻訳した聖書が残りました。
ところで、このネーサン・ブラウンは、日本に来る前にビルマ(現ミャンマー)の宣教師をしていた時期があります。
1833年にミャンマーに行き、聖書翻訳にかかわっています。
そのあと、日本で聖書の翻訳にかかわったのです。
色んな賜物の方々が、いらっしゃったのですね。ほんとうに、ありがたいことです。






 ある学校の先生が、田舎に住んでいましたが、クリスチャンだということで、迫害され教師の仕事もやめざるを得ませんでした。
ある学校の先生が、田舎に住んでいましたが、クリスチャンだということで、迫害され教師の仕事もやめざるを得ませんでした。
小学生の女の子は、いじめにあいお腹をけられて、それが原因でなくなってしまいました。
しかし、お父さんは、いつも学校の前の道の雪かきをし、みんなのために働きました。
そして、東京の神学校に入るために、田舎を去る日が来ました。
すると、駅には、村中の人々が見送りに来たのです。 その中に、宮沢賢治がいました。
その中に、宮沢賢治がいました。
彼が、そのクリスチャンをモデルに書いた詩が「雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている・・・・そう言う人に私はなりたい。」の、あの有名な詩でした。
聖書では、「迫害する人のために祈りなさい。」とあります。
自分の子供を殺した少年を、養子にして人もいました。
これは、人の力ではなく、神様の力でないとできないですよね。
主には、不可能は無いのです。








 勝海舟は、クララたちホイットニー家を本当に家族のように親切に面倒を見て、自分の敷地に家を建てて住まわせます。
勝海舟は、クララたちホイットニー家を本当に家族のように親切に面倒を見て、自分の敷地に家を建てて住まわせます。
そのため、ホイットニー家で持たれた聖書の学びや祈祷会に家族たちがいつも参加していました。 勝さんには、昔の大名たちがそうだったように母親の違う子供ががたくさんいましたが、みんな本宅で仲良く暮らしていました。
勝さんには、昔の大名たちがそうだったように母親の違う子供ががたくさんいましたが、みんな本宅で仲良く暮らしていました。
本妻が本当にやさしくい方で、主人から預かった子として面倒を見ていた様子が、クララの日記からうかがえます。 本妻の子である二人の娘は洗礼を受け、婚家との宗教の違いで悩むとこともありました。
本妻の子である二人の娘は洗礼を受け、婚家との宗教の違いで悩むとこともありました。
長男(小鹿・ころく)のお嫁さんも、聖書の学びはしていましたが、心から信じることができませんでしたが、20歳で亡くなる時、クララと夢(長女)で福音を語りました。
その後も、夢が伝道し続け、亡くなる前には、「信じます。私は、キリスト信者です。」とクララの兄である医師のウイリィに伝えました。
また、勝さんの三男の梅太郎は、長崎の神学校に入りアメリカに行き、日本人のための宣教師になると計画しますが、精神的に幼いからと言ってクララを始めみんなに反対されます。
しかし、ついに牧師になることをゆるされ、明治学院の創設者の木村熊二のところに学びに行き、クララと結婚することになります。
勝さんは、臨終の1週間前に「キリストを信じる」と子供たちの一人に言ったとクララはクラークへの手紙に書いています。
 クラークは、ニューヨークで「勝安芳・日本のビスマルク・その高貴な生涯」という本を出版し、その中にそのことが書いてあるそうです。
クラークは、ニューヨークで「勝安芳・日本のビスマルク・その高貴な生涯」という本を出版し、その中にそのことが書いてあるそうです。
本当に嬉しいですね。


















 軍人で「舞姫・雁」などを書いた小説家・森鴎外は、ご飯の上にお饅頭を載せて、お茶をかけて食べる饅頭茶漬が好きだったそうです。
軍人で「舞姫・雁」などを書いた小説家・森鴎外は、ご飯の上にお饅頭を載せて、お茶をかけて食べる饅頭茶漬が好きだったそうです。
さすがに、甘い物好きの私でも、これは真似しょうとは思いませんでした。

 また、果物には、砂糖をかけていたそうですが、いかめつい軍人のイメージとは、ほど遠いですね。
また、果物には、砂糖をかけていたそうですが、いかめつい軍人のイメージとは、ほど遠いですね。
でも、偉大な人の意外な面を知ると親近感が湧くものです。