 ガロアムシの話
ガロアムシの話ガロアムシは、昆虫綱ガロアムシ目(非翅目、Grylloblattodea、Notoptera)の昆虫の総称である。フランスの外交官ガロア E. Galloisが、栃木県日光市中禅寺湖湖畔でこの目の昆虫を最初に発見したのにちなんで1914年にガロアムシと名づけられた。ガロアムシは1951年出版の北隆館版「日本昆虫図鑑」には直翅目の一種としてコオロギモドキ科に置かれている。同書の素木得一博士の解説によると咀嚼口を有し、触角は糸状で多数の節からなり、複眼は小さく、単眼はなく、肢は3対で5節の付節を備え、1対の尾毛は多数の節からなり、雄は尾突起を有し、雌の産卵管は剣状で突出しているとある。それに続けてこの目はコウロギモドキ科だけからなり、Grylloblatia, IshianaおよびGalloisianaの3属知られている。また最初の属は北アメリカに産し、後二つは日本に産し、Ishianaは九州にGalloisianaは本州に産する。日本産は砂礫傾斜地の石下等に産するなどとある。下線は私が加えたもので、目とあるのは図鑑の編集方針に従えば明らかに科の誤植だが、素木博士は無翅昆虫だと認識していたらしくガロアムシ目として、この種を直翅目に含める気はなかったようだ。なおIshianaは福岡県太宰府市の石穴神社境内で発見されたらしい。
今回写真を掲載したガロアムシは滋賀県大津市で2016年3月20日、中川優さんが採集した生虫体を撮影した。そのガロアムシは雄で体長約2~3cm、体形はコオロギやシロアリに似るが、生涯無翅で、ガロアムシ目に分類される。
インターネットで調べると、「2015-08-24 朝日新聞 朝刊 栃木全県・1地方」を引用した記事などがあり、肉食性で、約7年かけて卵から成虫になる。初期の幼虫は白いが、齢を重ねると琥珀色になる。暗い場所で生きているので複眼は退化しているが、長い触角を動かし探索する。氷河期の生き残りと考えられている。現在知られているのは2亜科4属に属する25種。日本からは8種が知られているなどとある(ただし諸説があり研究者によって異論ありという)。
上の記事によるとガロアムシは触角による探索に頼り、目が見えないかのように書かれている。写真は琵琶湖博物館の床に白いティッシュペーパを敷いてガロアムシ生虫体を置いて撮影した。複眼が退化して目が見えないとあったので、ガロアムシはじっと動かないか、触角で探り探りゆっくり動くと思っていたが、活発に動き回り、障害物をよけ、行き先を邪魔しても巧みに回避しなかなか止まってくれないので写真を撮るのが難しかった。たくさん撮った写真の中から2枚掲載した。この虫体は体長約30mmである。
インターネットなどでガロアムシを検索すると氷河期の生き残りだという一面だけが強調されているが、氷河期の生き残りは一杯いるのにどうしてそんなことを強調するのか不思議に思う。ガロアムシについてもっと重要なことが忘れられているのではなかろうか。
昆虫の先祖は翅を持たない陸地を這いまわる節足動物であった。その昆虫の仲間に翅を持つ有翅昆虫が出現したことは、昆虫の進化史上他の節足動物と一線を画す最も大きな事件であった。ガロアムシの体形だけを見れば、昆虫学者のだれもがコオロギの仲間に分類してもおかしくない。成長すれば体長20~30mmにもなる一見直翅型昆虫と紛らわしいガロアムシが、なぜ翅を持っていないのだろうか?
こういう疑問が頭に浮かぶと、私はファーブルと違って必ず仮説を立てて考える。しかし、彼は仮説を立てることを嫌った。この場合、私はガロアムシがコオロギに似ているから、次の対立する二つの仮説を考えた。
①もともとガロアムシは直翅類の仲間だから翅を持っていたが、石の下などに潜んで何百世代にわたって翅を使わなかったから、今では痕跡も残さず翅が退化した。
②もともとガロアムシは翅を持っていない原始的な無翅昆虫の嫡流だから翅を必要としない暮らしにしっかり適応しているのだ。
おそらく、本来、有翅昆虫であった虫の翅が退化した場合、卵発生の経過を継続観察すれば必ず翅芽の元になる「何か」(仮に原基と呼ぶ)の痕跡が見られ、その原基が退化あるいは消失する過程がわかるだろう。
かつて蚤は翅を持っていた有翅虫だったが、寄生生活を採用し長い間翅を使わなかったから翅が退化して無翅昆虫になってしまった。一方、ガロアムシはもともと翅を持っていない無翅昆虫である。つまり分類段階で言えばガロアムシ一家もその親類筋もみな有翅昆虫と比べると驚くほど古い系統に属する無翅昆虫である。そんな虫が氷河時代より遥か昔から度重なる生息環境の変化に耐えて今までその姿を変えることなく、日本とアメリカに細々と生き残っていたことが興味深いのだ。










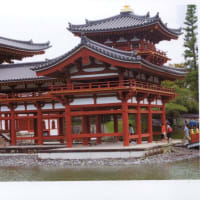
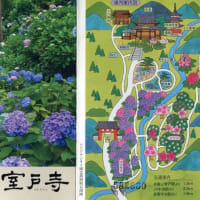








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます