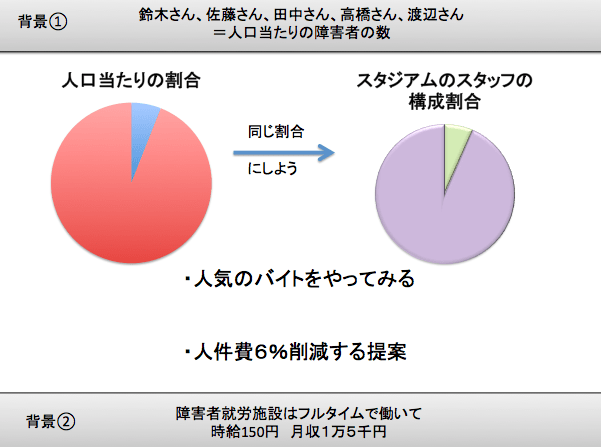Change Makers Day(半年に一回CMSP関係者が集まるイベント)やってきました!今回は会場内に100人弱が集まるという最大規模のものでした。
90分のトークセッションに
NPO法人ソコアゲ 斉藤祐輔(ゆっけさん)
NPO法人コモンビート安達亮(りょうさん)
NPO法人SET三井俊介(三井さん)
をお招きし、Visionに生きるとは。について話しました。

会場からは
「自分らしく生きるとか難しい」という声が会場からありました。
実際「やりたいこと」を見つけるって難しいような気がしますよね。
すごく共感できるこの声と、トークセッションの話が僕の中では繋がったので書いておきます。
僕的に一番印象に残っているのが
想像力の話。
例えば、どの銀行にお金を預けるか今まで頓着しなかったけど、預けられたお金がいったい何に使われているかを想像することで自分の行動は変えることができる。安いからと言って買ったコーヒー豆、洋服。もしかしたら海外での児童労働の産物かもしれません。一方僕らは良いと思った記事をシェアすることで世の中に訴えかけることもできます
これだけ世界が繋がっている今、ちょっと想像を働かすだけで僕らの日常は世界の裏側につながります。
さて、この話から僕が思い出した言葉があります
それは
「私たちは微力だが無力ではない」という言葉でした。
(長崎の高校生平和大使のスピーチに出てくるそうです)
僕らは実際にあなたと社会と世界と接続している。影響しあえる。
でもすごく見えづらい。ただそれだけ。
そこに必要なのは想像力。その想像力さえあれば、無力じゃない。ことに気づけると思います。
これを「横の想像」。とします。

さあ、無力じゃない自分がいます。
すると
未来を想像したくなりませんか?
逆に、自分を無力だと思っている人は未来を想像しないと思いませんか?
だって、想像したところでできない未来しか浮かばない。想像することが楽しくないからです。
子供の頃。ぼくらは自分が思っているより微力なことを知りませんでした。
だから、なんでも想像、空想ができました。
学年中の女子から告白されちゃったら
運動会で僕のおかげで大逆転勝利とかいかすじゃん
クラスの男子いっぺんに喧嘩して圧勝しちゃうんじゃないか
プロ野球選手になってるんだろうな。
恥ずかしいですが、ふつーにこんなこと考えてました。
でも気づきます。案外自分はたいしたことないのです。
今、どうでしょう。僕らは自分が思っているよりも微力なことを知りません。
自分の人生の想像が、妄想、空想が始まらないのです。
仮にあったとしてもそれは未来を考えて見てるだけ。
誰かの、みんなの、「予想」を見て、自分もこうなるんだろうな〜って思ってるだけです。
でも、気づきましょう。案外僕らは無力じゃないのです。
これは「縦(未来)の想像」と言えるのじゃないでしょうか

想像するのは自由。それこそ自由に想像していいのです
横の想像をしてみる
自分が無力じゃないこと自覚をする
すると縦の想像ができるようになる
想像を阻む無力感を微力感に変えてみる。
ただそれだけなのかもしれません。
ですし、CMSPというプログラムで、SETという場所で、自分と周囲(横)を、自分の人生(縦)を想像することを楽しいと思える人を生み出していきたいと改めて思いました。

CMSPは次の半年間でいよいよ広田町全地区での実施となります!
90分のトークセッションに
NPO法人ソコアゲ 斉藤祐輔(ゆっけさん)
NPO法人コモンビート安達亮(りょうさん)
NPO法人SET三井俊介(三井さん)
をお招きし、Visionに生きるとは。について話しました。

会場からは
「自分らしく生きるとか難しい」という声が会場からありました。
実際「やりたいこと」を見つけるって難しいような気がしますよね。
すごく共感できるこの声と、トークセッションの話が僕の中では繋がったので書いておきます。
僕的に一番印象に残っているのが
想像力の話。
例えば、どの銀行にお金を預けるか今まで頓着しなかったけど、預けられたお金がいったい何に使われているかを想像することで自分の行動は変えることができる。安いからと言って買ったコーヒー豆、洋服。もしかしたら海外での児童労働の産物かもしれません。一方僕らは良いと思った記事をシェアすることで世の中に訴えかけることもできます
これだけ世界が繋がっている今、ちょっと想像を働かすだけで僕らの日常は世界の裏側につながります。
さて、この話から僕が思い出した言葉があります
それは
「私たちは微力だが無力ではない」という言葉でした。
(長崎の高校生平和大使のスピーチに出てくるそうです)
僕らは実際にあなたと社会と世界と接続している。影響しあえる。
でもすごく見えづらい。ただそれだけ。
そこに必要なのは想像力。その想像力さえあれば、無力じゃない。ことに気づけると思います。
これを「横の想像」。とします。

さあ、無力じゃない自分がいます。
すると
未来を想像したくなりませんか?
逆に、自分を無力だと思っている人は未来を想像しないと思いませんか?
だって、想像したところでできない未来しか浮かばない。想像することが楽しくないからです。
子供の頃。ぼくらは自分が思っているより微力なことを知りませんでした。
だから、なんでも想像、空想ができました。
学年中の女子から告白されちゃったら
運動会で僕のおかげで大逆転勝利とかいかすじゃん
クラスの男子いっぺんに喧嘩して圧勝しちゃうんじゃないか
プロ野球選手になってるんだろうな。
恥ずかしいですが、ふつーにこんなこと考えてました。
でも気づきます。案外自分はたいしたことないのです。
今、どうでしょう。僕らは自分が思っているよりも微力なことを知りません。
自分の人生の想像が、妄想、空想が始まらないのです。
仮にあったとしてもそれは未来を考えて見てるだけ。
誰かの、みんなの、「予想」を見て、自分もこうなるんだろうな〜って思ってるだけです。
でも、気づきましょう。案外僕らは無力じゃないのです。
これは「縦(未来)の想像」と言えるのじゃないでしょうか

想像するのは自由。それこそ自由に想像していいのです
横の想像をしてみる
自分が無力じゃないこと自覚をする
すると縦の想像ができるようになる
想像を阻む無力感を微力感に変えてみる。
ただそれだけなのかもしれません。
ですし、CMSPというプログラムで、SETという場所で、自分と周囲(横)を、自分の人生(縦)を想像することを楽しいと思える人を生み出していきたいと改めて思いました。

CMSPは次の半年間でいよいよ広田町全地区での実施となります!