年明け、最初の週末に街なかの図書館へ行きました。ついでに六角堂広場をのぞいてみると、新春のイベントで獅子舞が披露されていました。

二人獅子です。

一人が笛を吹き、もう一人が芸をします。

演じていたのは女性でした。この後、皆さん無病息災を願って獅子に頭を噛んでもらっていました。子どもだと学力向上ですね。獅子舞を生で見るのは随分久し振りになります。中学生の時だったか、正月に町へ出たときに見て以来です。その当時でも、獅子舞の門付けは珍しかったと思います。

図書館へ戻りながら、いまは無くなってしまった、私も一度だけ出会ったような、むかしの路上での商い風景を思い出していました。ちょうど図書館では「むかしの暮らし展」を開催中だったのです。
「虚無僧」町の民家の前で尺八を吹いて門付けをしていました。
「豆腐屋」低く高く、小さなラッパを鳴らしながら、リヤカーで流し売りをしていました。
「風鈴屋」私が住んでいた長屋の住宅街に来ました。移動式の屋台に沢山の風鈴が吊されていた。
「みたらし団子」これも私の住宅街で見ました。小さな屋台を引いていました。
「鍋の修繕」 口上は覚えていませんが、声がかかると玄関先で穴の開いた鍋を修繕していました。母に言いつかって鍋を持って行ったことがあります。
「ポン菓子」 家の近くで。ポン菓子屋が来ると丼に米を入れて駆けて行きました。お代も一緒に持って行ったのか覚えていない。子どもに人気のあった商売で、いまもイベントなどで見かけます。
「よろず修繕」 私が保育園児のころ。園があった五穀神社の大楠の下で商売をしていました。「下駄ん歯替えや・・・・・」という歌のような口上の節回しを覚えています。傘の修繕もしていたような。
「菱売り」 これは筑後地方独特のものでしょう。秋口になると、近郊から絣のモンペ姿の小母さんがクリークで採った菱の実を売りに来ていました。栗に似た淡い味がします。
「針金細工」 町の商店街の通りでの商売。針金をペンチで曲げて玩具を作っていた。もちろん売り物。掌に乗るような小さな自転車を覚えている。いまでいえばバルーンアートのようなもの。
ついでに・・・
ある夏の夕暮れ時、近くの米屋の店先で。裸電球の下、米屋の主人と隣の亭主がステテコ姿で縁台将棋をしていた。何人か見物人がいて、店のラジオからは広沢虎造の浪曲が聞こえていた。まだ道路が遊び場だったころの路上の記憶。
ここまで書き並べてきて、なんだか年寄りの繰り言みたいになりました。でもボケ防止策に「回想法」というのがあるそうです。たまには記憶の棚卸しも必要です。













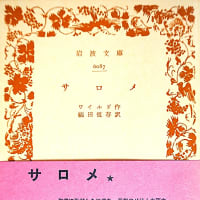

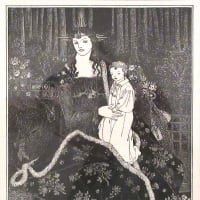

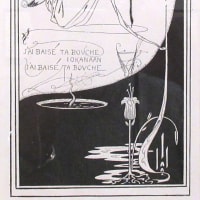
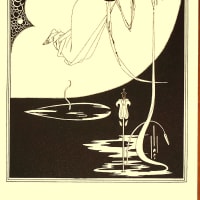






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます