
第41回「SGIの日」記念提言-4 池田SGI会長 2016年1月26日
聖教新聞(1/26-2016年の5面) より抜粋要約・箇条書き(連続掲載予定)
A
「誰も置き去りにしない」世界を築くために対話は絶対必要
「厳しい状況に置かれている人々の目線」から出発し、解決の道筋を一緒に考えることが肝要であり、その足場となるのが対話。
防災対策として、一人暮らし高齢者の家の耐震化を進めたとしても、それだけでは、その人が日々抱えてきた問題-例えば、病院通いや買い物にいつも難儀してきたような状況は取り残されてしまう。
こうした被災前から存在する、見過ごすことのできない課題も含めて、復興のプロセスの中で解決を模索していく「ビルド・バック・ベター」の重要性に注目すべき。
「ビルド・バック・ベター」とは、復興を進めるにあたって、災害に逢う前から地域が抱えていた課題にも光を当てて、その解決を視野に入れながら、皆にとって望ましい社会を共に目指す考え方。
(仙台防災枠組-2030年までの国際的な防災指針をまとめたものの中の原則の一つ。2015年3月採択)
B
「一人一人の尊厳」をすべての出発点に据えなければ、本当の意味で前に進むことはできない。
そこで重要なのが、危機の影響や被害を最も深刻に受けてきた人たちの声に耳を傾けながら、一緒になって問題解決の糸口を見出していく対話。
深刻な状況にあるほど、声を失ってしまうのが人道危機の現実であり、対話を通し、その声にならない思いと向き合いながら、「誰も置き去りにしない」ために何が必要となるのかを、一つ一つ浮かびあがらせていかねばならない。
C
国際社会の結束を強めるための要諦。
国連の新目標の推進において、厳しい状況にある人たちの声に耳を傾けることが必要。
「この問題は、私たちの人間性の居場所を見つけることにもつながります。課題や紛争が山積し、来る日も来る日も、良いニュースがほとんどないような世界へと迷い込む過程で、私たちが落としてきたものを再び拾い上げる、ということです」
(国連のアミーナ・モハメッド事務総長特別顧問が、国際社会の結束を強めるための要諦について語った言葉。)
D
排他主義や扇動主義に押し流されない社会を築く。
「一対一の対話」を通して自分の意識から抜け落ちているものに気づくことが重要な土台になっていく。
自分の意識にないことは、「自分の世界」から欠落してしまう。
人間はともすれば、自分の近しい関係のある人々の思いは理解できても、互いの間に地理的な隔たりや文化的な隔たりがあると、心の中でも距離が生じてしまう傾向がある。
E
難民となった人たちの物語紹介キャンペーン
(国連難民高等弁務官事務所-2015年)
この物語に触れた人が周囲や友人にも知らせる呼びかけ。
難民となった人たちの名前と共に紹介されていたのは、「園芸家・母親・自然愛好家」や「学生・兄・詩人」など、国籍に関係なく”身近に感じられる姿”を通して語られる人生の物語であり、境遇への思い。
F
心の世界地図を友情で描き出す。
対立や緊張があるから、対話が不可能なのではない。相手を知らないままでいることが対立や緊張を深める。だからこそ自分から壁を破り、対話に踏み出すことが肝要であり、すべてはそこから始まる。
現代において切実に求められているのは、国家と国家の友好はもとより、民衆レベルで対話と交流を重ね、民族や宗教といった類型化では視界から消えてしまいがちな「一人一人の生の重みや豊かさ」を、自分の生命に包みこんでいくことでないか。










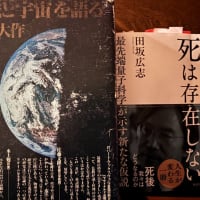









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます