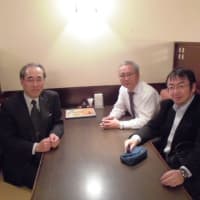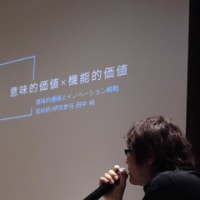※「横浜スマートコミュニティ」代表、dSPACE日本法人社長、東京大学特任教授の有馬仁志さん(写真左)と私(同中央)。
有馬さんは、技術者としてはもちろん、経営者としてもきわめて有能な方として知られています。以前に有馬さんの経営参謀やアドバイザーを務めさせていただいたご縁で、かれこれ10年近くのお付き合いをさせていただいてます。私にとって有馬社長は、心から尊敬する、かけがえのない友人でもあります。
(写真右は、当日急きょ駆けつけてくださった筑波大学院の宮崎均教授)
● ● ●
8月最後のきょうも暑い一日でしたね。
さて、昨日、「横浜スマートコミュニティ」の代表をつとめる、世界的なIT企業「dSPACE」社(本社ドイツ)の日本法人代表である有馬仁志(ありまひとし)社長にお会いしてきました。
横浜市が全面的に支援する横浜スマートコミュニティ(以下、横浜SC)は、従来のコンソーシアムや都市開発プロジェクトとは違って、「人の顔が見える、人のつながりが見える、生き生きとしたコミュニティとしての街づくり」をコンセプトに据えた取り組みで注目を集めています。
その代表をつとめる有馬さんは、同様のコンセプトで「福岡スマートハウス・コンソーシアム」を大成功に導いた実績を持っている方です。

※「食」の専門家である谷口雄二郎さん(左から二人目)の鋭い指摘に耳を傾ける皆さん。写真左から、筑波大学院の宮崎教授、谷口さん、Nさん、横浜SC代表の有馬社長。

※改めて写真右は、横浜SC事務局を担当するdSPACE社のNさん。当日、私はほぼ半日、dSPACE社に滞在していたのですが、行き届いた対応のみならず、議論にも参加していただくなど、たいへんお世話になりました(ちなみにカメラマンは有馬社長です)。
この種の取り組みは、どうしても短期的な利益を求める企業や資本にモノを言わせようとする企業が入ってきます。また、そうした企業の声が大きくなりがちです。
さらに、参加者のみならず、主催者の運営方法においても、必ずと言っていいほど、投資利益率や経済性計算が行われたうえで、定量的な目標やゴールが設定されるということが行われます。例えそれが、この世に存在しない、新しい価値の創造をめざすものであっても、です。
しかし、有馬さんは、第一級の技術者として、社会の重要な活動に対して技術を提供してきた経験を持つため、技術の本質や本来の役割を適切に理解しています。
すなわち「技術やツール(ハードウェア)は、あくまでも社会や人間の営みを豊かにするもの」という信念を持っている方です。ゆえに、盲目的にそれらの資本力や経済的な影響力にとらわれて、技術や道具の開発それ自体が目的化してしまう、という、大多数のプロジェクト主催者がたどる道に迷い込んでしまうことはありませんでした。
むしろ、そうした経済性とは対極にある、生物の生態系モデルや芸術作品が持つ社会的意味合い、街の歴史・文化が形成されるプロセスなどを深く研究し、社会生態系のメカニズムの本質に迫ろうとしました。
そして、それら経済尺度では測れない要素が持つ本質的な機能や影響力をコンソーシアムの運営手法や理念に取り入れるなど、独自の方法論を体系化し、福岡の取り組みへ投入しました。
その結果、たんに経済的な影響力を持つ事業主体が幅を利かすだけではなく、まず、プラットフォーム上に、さまざまな多様性が生まれました。
さらに、「社会生態系をいかに活性化するか」ということに対して深い思い入れやアイデアを持つ個性がいたるところで顕在化し、融合を始めました。そうしてエネルギーを得た創造力が、既存の技術やハードウェアに新たな魂を吹き込み、新しい意味合いを持たせ、結果として、真に「人や社会を生かす」ための、数々の革新的な技術が生まれることになったのです。

※私がお連れした10人近いお客さまへの対応を終えて一段落しているところ(右が有馬社長)。雑談がてら二人で記念撮影。裏表がなく、誰に対しても敬う姿勢をもって接する有馬さんですが、実は、まったくブレることなく信念を持ち続けることができる精神力の持ち主でもあります。
ドラッカーは、昔から「社会生態系への貢献ができる事業体が、もっとも多くの利益を得ることができる」ということを指摘してきました。ただ、残念ながら、いちじるしい経済成長や競争環境の時代が長らく続き、そうした指摘は理想論として片づけられがちでした。
しかし、経済効率性の獲得を目指して作られた社会・組織システムや価値観が疲弊してきたいまの時代において、ドラッカーが理想とした事業活動の本来のあり方が、ようやく本格的に求められる時代が到来しつつあるように思われるのです。
有馬さんとさまざまな議論を交わし、彼の成果の本質を深く知るにつれて、その思いが確信へと変わっていった一日でした。
[サイト管理者]
◇ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所◇
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての転載を固くお断りいたします。
Copyright (C) 2011 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆
有馬さんは、技術者としてはもちろん、経営者としてもきわめて有能な方として知られています。以前に有馬さんの経営参謀やアドバイザーを務めさせていただいたご縁で、かれこれ10年近くのお付き合いをさせていただいてます。私にとって有馬社長は、心から尊敬する、かけがえのない友人でもあります。
(写真右は、当日急きょ駆けつけてくださった筑波大学院の宮崎均教授)
● ● ●
8月最後のきょうも暑い一日でしたね。
さて、昨日、「横浜スマートコミュニティ」の代表をつとめる、世界的なIT企業「dSPACE」社(本社ドイツ)の日本法人代表である有馬仁志(ありまひとし)社長にお会いしてきました。
横浜市が全面的に支援する横浜スマートコミュニティ(以下、横浜SC)は、従来のコンソーシアムや都市開発プロジェクトとは違って、「人の顔が見える、人のつながりが見える、生き生きとしたコミュニティとしての街づくり」をコンセプトに据えた取り組みで注目を集めています。
その代表をつとめる有馬さんは、同様のコンセプトで「福岡スマートハウス・コンソーシアム」を大成功に導いた実績を持っている方です。

※「食」の専門家である谷口雄二郎さん(左から二人目)の鋭い指摘に耳を傾ける皆さん。写真左から、筑波大学院の宮崎教授、谷口さん、Nさん、横浜SC代表の有馬社長。

※改めて写真右は、横浜SC事務局を担当するdSPACE社のNさん。当日、私はほぼ半日、dSPACE社に滞在していたのですが、行き届いた対応のみならず、議論にも参加していただくなど、たいへんお世話になりました(ちなみにカメラマンは有馬社長です)。
この種の取り組みは、どうしても短期的な利益を求める企業や資本にモノを言わせようとする企業が入ってきます。また、そうした企業の声が大きくなりがちです。
さらに、参加者のみならず、主催者の運営方法においても、必ずと言っていいほど、投資利益率や経済性計算が行われたうえで、定量的な目標やゴールが設定されるということが行われます。例えそれが、この世に存在しない、新しい価値の創造をめざすものであっても、です。
しかし、有馬さんは、第一級の技術者として、社会の重要な活動に対して技術を提供してきた経験を持つため、技術の本質や本来の役割を適切に理解しています。
すなわち「技術やツール(ハードウェア)は、あくまでも社会や人間の営みを豊かにするもの」という信念を持っている方です。ゆえに、盲目的にそれらの資本力や経済的な影響力にとらわれて、技術や道具の開発それ自体が目的化してしまう、という、大多数のプロジェクト主催者がたどる道に迷い込んでしまうことはありませんでした。
むしろ、そうした経済性とは対極にある、生物の生態系モデルや芸術作品が持つ社会的意味合い、街の歴史・文化が形成されるプロセスなどを深く研究し、社会生態系のメカニズムの本質に迫ろうとしました。
そして、それら経済尺度では測れない要素が持つ本質的な機能や影響力をコンソーシアムの運営手法や理念に取り入れるなど、独自の方法論を体系化し、福岡の取り組みへ投入しました。
その結果、たんに経済的な影響力を持つ事業主体が幅を利かすだけではなく、まず、プラットフォーム上に、さまざまな多様性が生まれました。
さらに、「社会生態系をいかに活性化するか」ということに対して深い思い入れやアイデアを持つ個性がいたるところで顕在化し、融合を始めました。そうしてエネルギーを得た創造力が、既存の技術やハードウェアに新たな魂を吹き込み、新しい意味合いを持たせ、結果として、真に「人や社会を生かす」ための、数々の革新的な技術が生まれることになったのです。

※私がお連れした10人近いお客さまへの対応を終えて一段落しているところ(右が有馬社長)。雑談がてら二人で記念撮影。裏表がなく、誰に対しても敬う姿勢をもって接する有馬さんですが、実は、まったくブレることなく信念を持ち続けることができる精神力の持ち主でもあります。
ドラッカーは、昔から「社会生態系への貢献ができる事業体が、もっとも多くの利益を得ることができる」ということを指摘してきました。ただ、残念ながら、いちじるしい経済成長や競争環境の時代が長らく続き、そうした指摘は理想論として片づけられがちでした。
しかし、経済効率性の獲得を目指して作られた社会・組織システムや価値観が疲弊してきたいまの時代において、ドラッカーが理想とした事業活動の本来のあり方が、ようやく本格的に求められる時代が到来しつつあるように思われるのです。
有馬さんとさまざまな議論を交わし、彼の成果の本質を深く知るにつれて、その思いが確信へと変わっていった一日でした。
[サイト管理者]
◇ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所◇
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての転載を固くお断りいたします。
Copyright (C) 2011 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆