毎日クリックありがとうございます!
1つのパソコンから1日1回だけで良いですから
(2回クリックして頂いても2回目はカウントされません)
毎朝ヨーグルト食べるみたいに(ヨーグルトじゃなくてもいいけど)
習慣にして頂けると嬉しいです。
毎日続けると・・・いいことあるかも!?
なんだか天気予報が暖かくなるなる詐欺のような気がしてきました。
雲が多いせいか暖かくない気がするんですけど・・・
午前中に じざいやカラーの爪搔き綴れの帯が届くのを待ってたのですが
来ないので すくい綴れでお茶を濁すことにします。
ヤマトさんが値上げして メーカーさんがヤマト以外の業者を使うようになったら
とたんに荷物の届くのが遅くなりました。
昨日の夕方京都を出たものが翌朝に横浜に届くというのは
凄いことだったのだと、今更ながらに思います。
で。綴れのお話です。以前も書いたのですがちと、長いです。
綴れと聞くと 高価な爪掻綴れを思い浮かべる方が多いと思いますが
綴れとは本来、織上がりの生地に
経糸が見えない織りの組織のことで
織る時に 緯糸を反幅より長く使って織り込みます。
(具体的に言いますと 緯糸の杼を通す時に斜めに飛ばして緯糸の長さを多くします)
そうすると、筬で打ち込んだ時に余った緯糸が経糸の間で
折りたたまれるように経糸を覆い隠します。
その断面図がジグザグのつづれ折りの山道のようなので
つづれ織り、と呼ばれたものです。
ですから 柄がなくても無地の帯地でも綴れが存在します。
柄のある綴れには2種類があり
爪に刻みを入れて 手織りにされるのものが本爪掻綴れ、と呼ばれます。
もうひとつは、掬いつづれ、と呼ばれるものです。
まず、本爪搔き綴れについて。
綴れで柄を織る時には まず 柄の図案を経糸の下に置いて
その図の色彩の色ごとに 色の数だけ縫取杼という、小さな杼を用意します。
普通の織物のように 反物の耳から耳へと 緯糸を通すのではなく
例えば 白地に赤い花の柄でしたら 緯糸を一段織るのには
白糸の杼で赤い花の柄の始る部分まで通し
柄の始まりの分部から赤い花をはめ込むように、赤い糸の縫取杼で織り込みます。 花の部分が終われば まだ白糸で織ります。
柄によっては 一列の緯糸上に何色もの色が使われ
そのたびに縫取杼を持ち替えて織り進む細かい作業です。
この細かい作業で こまかい柄を織るのに
爪先に刻みを入れて爪でかき寄せるので 爪掻綴れの名があります。
実演の画像は夕方にアップしますね。
絣のように先に糸を染め分けて柄を織り出すのではなく
糸ごとに違う糸で織られるために
色と色の境目に接点がありません。
この部分に糸が渡らないための隙間ができ、それを「羽釣(はつり)」と呼びます。
羽吊りは、爪掻き綴れを見分けるポイントの1つでもあります。
(丁寧な仕事で後から羽釣をかがっているものもあります)
また 綴れは色糸ごとに柄を織り出していて
柄と柄の間に糸が渡らないので 裏返して見ると同じ柄です。
一応 裏側で糸の処理をするので 糸留めが裏にありますが
この糸留めを表に引き出すことが出来、
そうすると裏表を返すことが出来るので
表が汚れてしまった時に 裏表を返すことが出来るのも
本爪掻き綴れの強みです。
爪掻綴れのぼかしの部分は
職人さん一人一人が自分の感性で色を作り
また曲線の曲げ具合なども 職人さんに任せられるので
同じ柄でも 職人さんによって微妙な差がでるのも手織ならではです。
それに対してすくい綴れは爪は使いません。
柄の部分をすくい分けて織る、ということでそう呼ばれています。
組織としては経糸を覆うことはなく 経糸が見えます。
すくい織り、と呼ぶ技法ですが
見た目が 柄を嵌め込んだ爪掻綴れに似ているので
すくいで織った綴れ、ということで、すくい綴れと呼ばれています。
爪先ではなく 小さな、櫛のような筬を使って織られます。
爪掻き綴れも すくい綴れも 紋紙を使わないので
1点づつから織ることができて 細かい表現が可能なので
じざいやでオリジナルの帯を作るときに良く使います。
爪搔綴れが届かないので すくい綴れの帯で。 小鳥を刺繍で散りばめた小紋に。すくい綴れの紫雲の帯。小物の水色を空に見立てて。
小鳥を刺繍で散りばめた小紋に。すくい綴れの紫雲の帯。小物の水色を空に見立てて。
銀砂子の生地に雲の部分だけ色糸で織り込まれているのが解ります。
着物には可愛いインコや文鳥があちこちに。

これもすくい綴れです。
この帯は洒落袋なんですけ 短くカットして名古屋として使った方が良いなぁ。
お正月の木綿更紗とのセットにも入れちゃえばよかった。
今でも こっそりお安くしちゃいますよ^^










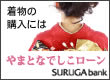 やまとなでしこローン
やまとなでしこローン
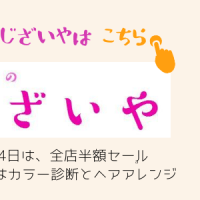











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます