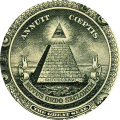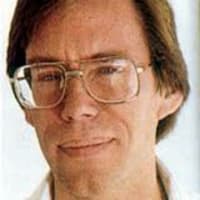1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊し、そこから「東西冷戦」は終焉に向かいました。当時私は22歳、世界は次の新しい時代に向かう事を、当時の世界の人達は期待をしていました。
当時言われていたのは「共産主義の終焉」であり「資本主義の勝利」でした。
今の若い世代の人達は、学校の歴史の教科書の中で見聞きした事かもしれませんが、第二次世界大戦が終わってから、世界はアメリカを中心とする西側諸国(資本主義)と、ソビエト社会主義共和国連邦(現:ロシア)を中心とする東側諸国(共産主義)で二分され、冷戦と言われる両陣営の主要国が戦火を交えない「冷たい戦争」の状態となりました。
当初は私有財産を原則認めない「共産主義」の世界では、資本格差の無い理想社会を謳っていました。それまでの資本主義社会では労働者は資本家に搾取されていると言い、そこから貧困格差のある社会になったと言っていました。
共産主義では全ての財産は原則、社会(国家)の共有財産となり、もの凄い大雑把に言えば国家が財産を管理して、国家の下で国民の賃金格差を無くして皆が平等に暮らせる社会を目指していたのです。
企業は基本的に国有企業となり、そこには資本主義の中である競争原理はなく、皆が平等な仕事をして平等な収入を得て生活するという、簡単に言えば国民は皆が国家公務員の様な社会と言っても良いでしょう。そこには資本主義でいう競争原理が無いので、仕事で努力をしようが、努力をしまいが国民の収入は保障され、生活出来る社会だったのです。
しかしこうなると、人々の中には「勤労意欲」というのは低下してしまうのか、有名な話として、当時、ソ連の首都モスクワのデパートは実に飾りっけなく、店員の姿勢もやる気がないという状況でした。簡単に言えば仕事を一生懸命しようがしまいが、得られる給料には差が出ません。だったら最低限やる事やっていれば良いか。共産主義者で人々の勤労姿勢とは、そんな感じだったのです。
この共産主義社会では、お金による貧富の差こそないと言われていましたが、その共産主義を指導する共産党の階級格差のある社会でもありました。簡単に言えば、共産党幹部になれば贅沢が出来るが、それ以外は質素な生活に甘んじなければならない。場合によっては生きていく最低限の衣食住は国家により保証されますが、その生活レベルが向上する事は無い階級格差社会。そんな感じですね。
そんな社会なので、共産主義の社会では、国家から支給される生活必需品などの品質もけして良いものとはならず、資本主義社会の様な「品質の良い製品」、一般の人が偶に味わえる「裕福な生活」も出来ない事。また仕事で努力をしても報われない等、国民の中には様々な不満もあったのでしょう。このベルリンの壁を乗り越え、東ベルリンから西ベルリンに亡命する人達も当時は多く居て、その中いは亡命途中で東ベルリンの国境警備隊から逮捕されたり射殺される人もいたのです。
要は「人の欲望を肯定する社会(資本主義)」と「人の欲望を否定する社会(共産主義)」のせめぎ合いが「冷戦」であり、このベルリンの壁の崩壊を切っ掛けとして、共産主義国家は次々と倒れ、今では世界の大半が資本主義国家になりました。(中国や北朝鮮、ベトナムなど一部の国では、いまだ共産主義を維持していると言っています。)
そもそも資本による貧困格差をなくす事を目指した社会が、共産党の階級による格差による貧困を生み出す社会になった事に「人間の業」があると感じますし、そこに人の欲望の根深さを感じてしまいます。「共産主義は大いなる社会実験だった」と言われるのも、そういった事からかもしれません。
以前の記事にも紹介しましたが、私が昔よく見たアニメ映画で「オネアミスの翼」というのがありました。そこでは主役のシロツグが訓練をサボっていると、そこに宇宙軍の教官が来て、彼に以下の言葉を言いました。
「これがなんだか分かるか、1リーム硬貨だ。パンなら一斤、油なら1本分の価値がある。だがごぜの追いはぎはこれ一つの為に人を殺す。えー?そう思えば大金だろ?」
人というのは「お金」の為であれば何でもしてしまいます。お金が集まり大きな「資本」を持てば、その持てる人は多くの人々を自由に動かす事が出来ますし、裕福な生活をする事も出来ます。また人はお金の為であれば言われるままに動かされてしまいますし、場合によっては主義主張や心すら売り渡してしまう人もいます。例えば会社でどんなに辛く苦しい事があり、嫌いな上司がいても、真面目な人であれば会社の中で歯を食いしばり仕事をしますが、それもお金の為と言っても良いでしょう。なにせ資本主義社会では、お金がないと社会の中で生きていけません。
また別の角度で考えると、人の持つお金の多寡が、即ちその人が社会の中でどれだけ自由に生活できるかのバロメータであると言っても良いでしょう。
そう考えてみると、やはり人というのは「お金(資本)」に踊り、踊らされてしまう宿命を持っているのかも知れませんね。
今の日本の政治とは、この資本の生み出す利権構造に雁字搦めになっている様に思います。
自民党政治がおかしい、自民党政治が変だ、国民の大半はその様に考えているでしょう。しかし思う事は思えますが、それを実際に変革しようというと、この利権構造からはみ出さなければならず、それは即ち自分自身が社会で得られる収入にも関わりますし、やはり守る存在があれば、人というのはとことん保守的になりますので、そこから抜け出す事は極めて困難なのです。
日蓮は信徒の池上兄弟への手紙で以下の様にこの事について語っていますので、少し見てみたいと思います。
「此の世界は第六天の魔王の所領なり一切衆生は無始已来彼の魔王の眷属なり六道の中に二十五有と申すろうをかまへて一切衆生を入るるのみならず妻子と申すほだしをうち父母主君と申すあみをそらにはり貪瞋癡の酒をのませて仏性の本心をたぼらかす、但あくのさかなのみをすすめて三悪道の大地に伏臥せしむ、たまたま善の心あれば障碍をなす」
(兄弟抄)
これは鎌倉時代の古文なので、平易な現代語にすると以下の様になります。
「この世界は第六天の魔王の領土なのである。全ての人々は人類の歴史が始まってよりこの方、この第六天の魔王の眷属なのである。(第六天の魔王は)地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天という心で生死流転する牢屋を構えて、全ての人々を入れるだけではなく、そこに妻子という絆(縛り付けるもの)で縛り付け、父母や主君という網を天井に張り、日々の生活で汲々とする様な酒を飲ませて、人が本来持っている智慧や能力に気付かない様にさせて、ひたすら自分は無力だと感じるような酒の肴を進めて、三悪道という苦しむ大地に組み伏せている。中にはそれに気空く人がいれば、それを邪魔するのだ」
こんな感じでしょうか。
ここでいう「第六天の魔王」とは、人が「お金(資本)」により操られてしまうという心の中にある「脆弱性」と言っても良いでしょう。心の中にある存在なので、けして見る事は出来ませんが、こと「お金(資本)」に関する事で、個々の人々はそれを自身の中に感じる事が出来るかもしれません。しかしその為には、日々の生活の中で「洞察深く」自分の心の中を見回さなければなりません。
かくして人は「資本(お金)」に縛られてしまうのでしょう。そしてそれを社会として肯定しているのが「資本主義」の問題点なのかもしれませんね。