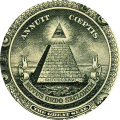私が初めて「折伏(しゃくふく)」という言葉を使ったのは何時頃だったのだろうか。これは恐らく私が19歳で男子部という組織に入ってからの頃だった。
当時教わったのは、折伏とは相手の邪義を徹底的に破折(論理的に否定)し、正しい教えに屈服をさせることを折伏と呼び、法華経では摂受(しょうじゆ)と折伏の二つの修行法が説かれていて、日蓮大聖人は末法の修行法は折伏だと教えている。だから創価学会は折伏精神を持って弘教拡大に努めてきたと言うのである。
何も知らない私はこの先輩の言葉を信じて、友人に片っ端から仏法対話を行ってきたが、そこでやったのは相手の生き方を徹底的に否定して、創価学会の生き方こそ正しいという事だった。しかし結果として多くの友人をここで失ってしまった。しかしこれは先輩に言わせると「お前から離れていったのは、真の友人では無い奴らなんだから、落ち込むことは無い」という事だった。
この創価学会の教義だが、以前は日蓮正宗大石寺の堅樹院日寛師が展開した、中古天台惠心流の亜流とも言うべき教えであり、例えば創価学会の歴史の中の「小樽問答」では日蓮宗と対論して勝利したと未だ喧伝していたりもするが、私が最近、少し学んだ結論としては日蓮宗とガチにやっていたら、当時も大敗していた事だろう。最近ではめっきり見かけなくなったこの小樽問答の音声記録だが、以前に男子部の先輩の家にレコードがあって、それを聞かせていただいた事があるが、その内容たるや対論と呼ばれる様な内実はなく、当時司会であった池田氏の「ごり押し」ともいえる進行の結果、日蓮宗は「負け」という姿を晒された様に感じたのである。
この日寛師の教学というのは江戸中期に日興門流の中にあった、天台回帰への流れに乗って確立された理論であり、そもそも日蓮の本義とは異なっていたし、日蓮本仏とか久遠元初なる考え方、また後世の偽作である大石寺大曼荼羅を中心としたものは、結果として創価学会や公明党を生み出してしまう根源にもなってしまった。
2014年になり、創価学会としてその問題点に気がついたのかどうか、そこは定かでは無いが、それまでの日蓮本仏という考え方を変更し、堅樹院日寛師の教学を見直すと言い始めたが、それから10年以上経過しても、この教義改正に関しては未だ組織内に徹底されていないのが実情だ。ただ最近になり、ネット上で一部の創価学会の活動家が、この2014年に行われた創価学会の教義改正はおかしいと言っているが、私個人からすれば10年以上も経過して騒ぐなんて、何とも教学的なアンテナの低い人たちだと少々あきれ返ってもいる。
折伏とは破折する側の教義が「絶対的に正しい」という事が前提にもなるが、この様な状況に於いては、日蓮正宗であったとしても創価学会であったとしても、折伏という事は成り立たないと思うが、それを理解できる宗門信徒や創価学会活動家はほぼ居ないだろう。
日蓮は鎌倉時代、立正安国論を上呈してより常にこの折伏の先頭にあって、当時の鎌倉仏教界の僧侶や幕府役人に対して一歩も引かない言動をして生涯を閉じている。そしてその姿を通して自分達も続けとばかりに、戦後の創価学会も折伏にまい進してきたのだが、果たしてこの折伏にどれだけの意味があったのだろうか。
日蓮は僧侶という立場から、多宗派の僧侶に対して論戦をもちかけ、折伏をしてきたのは解る。そしてこの折伏では常に「負けた方が相手方の宗派に下る」というルールがあった。つまり仏教を学する僧侶という立場でこそ、この折伏という行為(修行法)は成り立ったのではないだろうか。しかしこと信徒(宗派を信じる在家)の立場では、この折伏は成り立たないのではないだろうか。
私も四半世紀にわたり創価学会の中で取り組んできたが、信徒というのは教えられた信心(信仰と言ってもいいだろう)を忠実に守り、そこで功徳(これは御利益だろう)を得る事を主眼にしているが、そこで教えられた事について否定をされた時に「ああ、この教えは間違えていたんだな」と素直に受け入れられる人というのは、ほぼ皆無ではないだろうか。特に信心による信仰体験があった場合には、ほぼ受け入れる事は不可能になってしまうだろう。
私も広宣部という組織にいて、そこで多くの宗門信徒や顕正会の活動家幹部とも論戦を行ってきた。そこではいくら論理的に「貴方の宗派の教えは間違えている」と指摘をしても、素直に受け入れる人は一人もおらず逆に感情的に切れまくって来る人というのが大半だった。そして最近では創価学会の活動家に対して同じ事を行っても、こちらも同様に感情的に切れまくるか、話をはぐらかす、逆に理屈にもならない話を吹っかけてくるというのが実情だ。
仏教を学ぶ僧侶という事であれば、学んだ事を互いにぶつけ合い、そこで勝負が決まるのでまだ折伏という事は成立するのかもしれないが、その教えを学ばされ、そこで信仰体験を経験した立場の信徒であれば、実際には折伏という事は成り立たないのだろう。そこでは教えられた事への執着心がより強固になり、そこを論理的に否定しても、心理学でいう「合理性」が働いてしまい、結果として議論という事が成り立つ事はありえない。それが私の折伏に対する結論でもある。
これはX(旧ツイッター)にも投稿したことだが、先日私のところに壮年部の総県幹部が訪問してきて、衆議院選挙の時だったが公明党議員への投票と、友人への投票依頼の話をしてきた。私は選挙は政治の世界であり、自身の政治的な代弁者足りうる人物への投票を行うという事が、議会制民主主義の制度の在り方であって、結果として公明党議員が落選するのであれば、それは致し方ない事ではないのかと話をした。するとその幹部は「池田門下として同志を国政に送り出す事こそが、弟子の道ではないか」と言うのである。いやいや、選挙は信仰ではないし、そこは個人の政治信条の話ですからと言うと「君は批評家だ」と言い始め、「私は自民党の有力議員とも昵懇の中で、そこでは云々」という話をし続けてきた。そんな事言われても私だった自民党議員くらいは知っているし、そういう話を聞いたうえでの判断だと言うとろうがとも思ったが、あえてそこは反論を取りやめた。折伏が言論戦だというのであれば、その前提となる対話や議論の前提の事をよく理解して欲しいものだが、やはり長年、創価学会の中で折伏という言葉に浸り続けていると、そういった基礎的な事に耳を貸す事も出来なくなる様だ。
もし自分自身の信仰を、相手に理解と共感をしてほしいのであれば、そこは理性的な対話を心掛けるべきであり、相手の立場を尊重しつつ、「聖人」という文字に示された「耳(話を聞くこと)と口(言葉を尽くす)の王」という姿勢に徹するべきではないだろうか。どうも創価学会や日蓮正宗系では、日蓮の「激しい言論戦」ばかりを教えられているせいか、そういった基礎的な事を蔑ろにしている傾向が強すぎると思うのである。