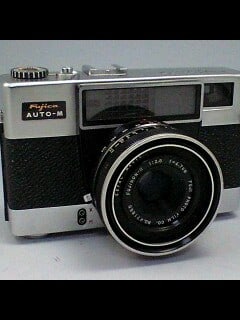夕べ風呂から上がってテレビを見たら、辞任表明の特番が始まったところでした。
最初に感じたのは、ああ日本中の放送局がばたばただろうな、無駄なエネルギーだよねということでした。仕事だからしょうがないけど、あんな男のために、番組を中断したり中止しなければならないのはむなしいですよ。私たちだけではないでしょうが。振り回されるのは。
政治家になるべくして生まれた安倍や福田が、望んでなった日本のリーダー。その志を1年以下で挫いてしまう何か、足を引っ張って潰すシステムがあるのでしょうね。一方的に本人たちが無責任だと言い放ちたくは無い思いです。出来ると信じて就いたポジションでしょうから。
泥沼です。与党も野党もだめ。
求心力を持った人がいれば、それがどこから出て来るとしても、政権を取れるかもしれない大きなチャンスのような気がしますね。
でも戦後の日本の教育・社会にどっぷりつかった人にはもう無理かもしれないなあ。
しかし見事にNHKだけがニュースをやってる時間に発表って偶然???
ところで、α300やら、D90、EOS50Dと使いやすそうデジタル一眼が続々発表されていますが、私が注目した最近の新製品はこれ

Nikon Coolpix P6000
ギザ格好良いですね、惚れ惚れします。
GPS内蔵で撮った場所まで記録されるのですよ。性能もデジ一並み。

それからコンパクト系だったらこれ
春にR8が出てそのグッドデザインとコストパフォーマンスの良さにびっくりしたら、もうR10ですよ。Ricohさん

お奨めです。
最初に感じたのは、ああ日本中の放送局がばたばただろうな、無駄なエネルギーだよねということでした。仕事だからしょうがないけど、あんな男のために、番組を中断したり中止しなければならないのはむなしいですよ。私たちだけではないでしょうが。振り回されるのは。
政治家になるべくして生まれた安倍や福田が、望んでなった日本のリーダー。その志を1年以下で挫いてしまう何か、足を引っ張って潰すシステムがあるのでしょうね。一方的に本人たちが無責任だと言い放ちたくは無い思いです。出来ると信じて就いたポジションでしょうから。
泥沼です。与党も野党もだめ。
求心力を持った人がいれば、それがどこから出て来るとしても、政権を取れるかもしれない大きなチャンスのような気がしますね。
でも戦後の日本の教育・社会にどっぷりつかった人にはもう無理かもしれないなあ。
しかし見事にNHKだけがニュースをやってる時間に発表って偶然???
ところで、α300やら、D90、EOS50Dと使いやすそうデジタル一眼が続々発表されていますが、私が注目した最近の新製品はこれ

Nikon Coolpix P6000
ギザ格好良いですね、惚れ惚れします。
GPS内蔵で撮った場所まで記録されるのですよ。性能もデジ一並み。

それからコンパクト系だったらこれ
春にR8が出てそのグッドデザインとコストパフォーマンスの良さにびっくりしたら、もうR10ですよ。Ricohさん

お奨めです。