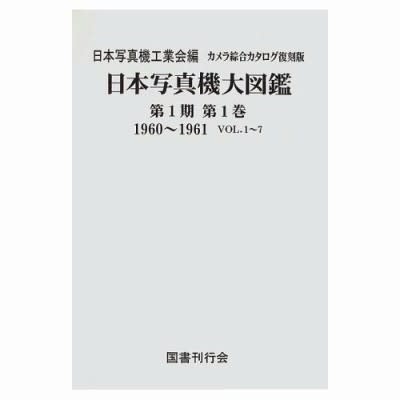ひさしぶりの社食ネタ

昨日は480円で、はらこ飯を食べることが出来ました。宮城の秋の味覚です、鮭の親子丼。なかなか。
先日の盛岡グルメツアーに持っていった蔵亀があります。くらかめ、クラシックカメラ。

Nikomat EL
1972年発売の一眼レフです。

プロ用のカメラとして開発されたNikon Fに対して、アマチュア用の一眼レフはいろいろ作られたのですが、Nikonとして、初めて成功したのがNikomatですね。ニコマート。
シルバーのほうは1967年発売のNikomat FTNです。ELのほうが電子回路の基板を格納するため、プリズム周りが太め。
カニ爪と称される、絞り連動レバー金具がこの時代のNikonの特徴です。

TTL露出計のセンサーは、レンズを通ってフィルムに達する光の明るさを測定するわけですが、レンズの絞りを絞るとファインダーが暗くなってしまい、見にくくなってしまいます。それで絞りをまわしても、実際に絞られるのはシャッターが降りるときだけにして普段は開けておくのが開放測光。そうすると当然露出測定が狂いますので、絞りの位置をカメラに知らせて、計算させる必要があるわけです。そのための爪。

Nikon Fには、露出計がなかったので、Nikomatは同じレンズが使えて、露出計付のプロ用サブカメラとしての需要もあったと思われます。でもELのころはF2Photomicがあったので、よりアマチュア向けの味付けかな。
最初の開放測光モデルFTNの変わっている点、シャッタースピードのリングがレンズマウントの根元にあったのですが

ELでは、Fと同じシャッターボタンの横に移されています。Aは絞り優先自動露出。

おまけに8秒までのスローシャッターが選べるんですね、目盛りは4までしかないけど。これも変わっていると言えば変わっています。

もっと変わっている点。
電池を入れる場所が見つからないと思ったら

なんとミラーボックス内ミラーをアップした底にあるんです。そこだよそこ!! 底だって!!

Nikon Fは、F2,F3そしてD1,D2とNikonの最高級カメラ、一桁シリーズの基になったと言えますが、Nikomatは、その後のFE,FAそして現在の中級カメラシリーズ、二桁や三桁の番号カメラの先祖様といえますね。
そして盛岡ツアー
もちろんデジカメもDP1を持っていきましたが、このカメラもテストしてきたのでした。
今日その現像とCDR書き込みが上がってきたのです。

紺屋町の、白沢せんべい店前

紺屋町番屋

その夜の宴会場、彩四季 お料理はこちら→サエモンさんのブログを見てください。

ござ九


奥に中庭があるようですね。


ぶらり歩きです


F8か5.6あたりでオート撮影しましたが、綺麗に中央部重点測光で露出計はOKのようです。



昨日は480円で、はらこ飯を食べることが出来ました。宮城の秋の味覚です、鮭の親子丼。なかなか。
先日の盛岡グルメツアーに持っていった蔵亀があります。くらかめ、クラシックカメラ。

Nikomat EL
1972年発売の一眼レフです。

プロ用のカメラとして開発されたNikon Fに対して、アマチュア用の一眼レフはいろいろ作られたのですが、Nikonとして、初めて成功したのがNikomatですね。ニコマート。
シルバーのほうは1967年発売のNikomat FTNです。ELのほうが電子回路の基板を格納するため、プリズム周りが太め。
カニ爪と称される、絞り連動レバー金具がこの時代のNikonの特徴です。

TTL露出計のセンサーは、レンズを通ってフィルムに達する光の明るさを測定するわけですが、レンズの絞りを絞るとファインダーが暗くなってしまい、見にくくなってしまいます。それで絞りをまわしても、実際に絞られるのはシャッターが降りるときだけにして普段は開けておくのが開放測光。そうすると当然露出測定が狂いますので、絞りの位置をカメラに知らせて、計算させる必要があるわけです。そのための爪。

Nikon Fには、露出計がなかったので、Nikomatは同じレンズが使えて、露出計付のプロ用サブカメラとしての需要もあったと思われます。でもELのころはF2Photomicがあったので、よりアマチュア向けの味付けかな。
最初の開放測光モデルFTNの変わっている点、シャッタースピードのリングがレンズマウントの根元にあったのですが

ELでは、Fと同じシャッターボタンの横に移されています。Aは絞り優先自動露出。

おまけに8秒までのスローシャッターが選べるんですね、目盛りは4までしかないけど。これも変わっていると言えば変わっています。

もっと変わっている点。
電池を入れる場所が見つからないと思ったら

なんとミラーボックス内ミラーをアップした底にあるんです。そこだよそこ!! 底だって!!

Nikon Fは、F2,F3そしてD1,D2とNikonの最高級カメラ、一桁シリーズの基になったと言えますが、Nikomatは、その後のFE,FAそして現在の中級カメラシリーズ、二桁や三桁の番号カメラの先祖様といえますね。
そして盛岡ツアー
もちろんデジカメもDP1を持っていきましたが、このカメラもテストしてきたのでした。
今日その現像とCDR書き込みが上がってきたのです。

紺屋町の、白沢せんべい店前

紺屋町番屋

その夜の宴会場、彩四季 お料理はこちら→サエモンさんのブログを見てください。

ござ九


奥に中庭があるようですね。


ぶらり歩きです


F8か5.6あたりでオート撮影しましたが、綺麗に中央部重点測光で露出計はOKのようです。