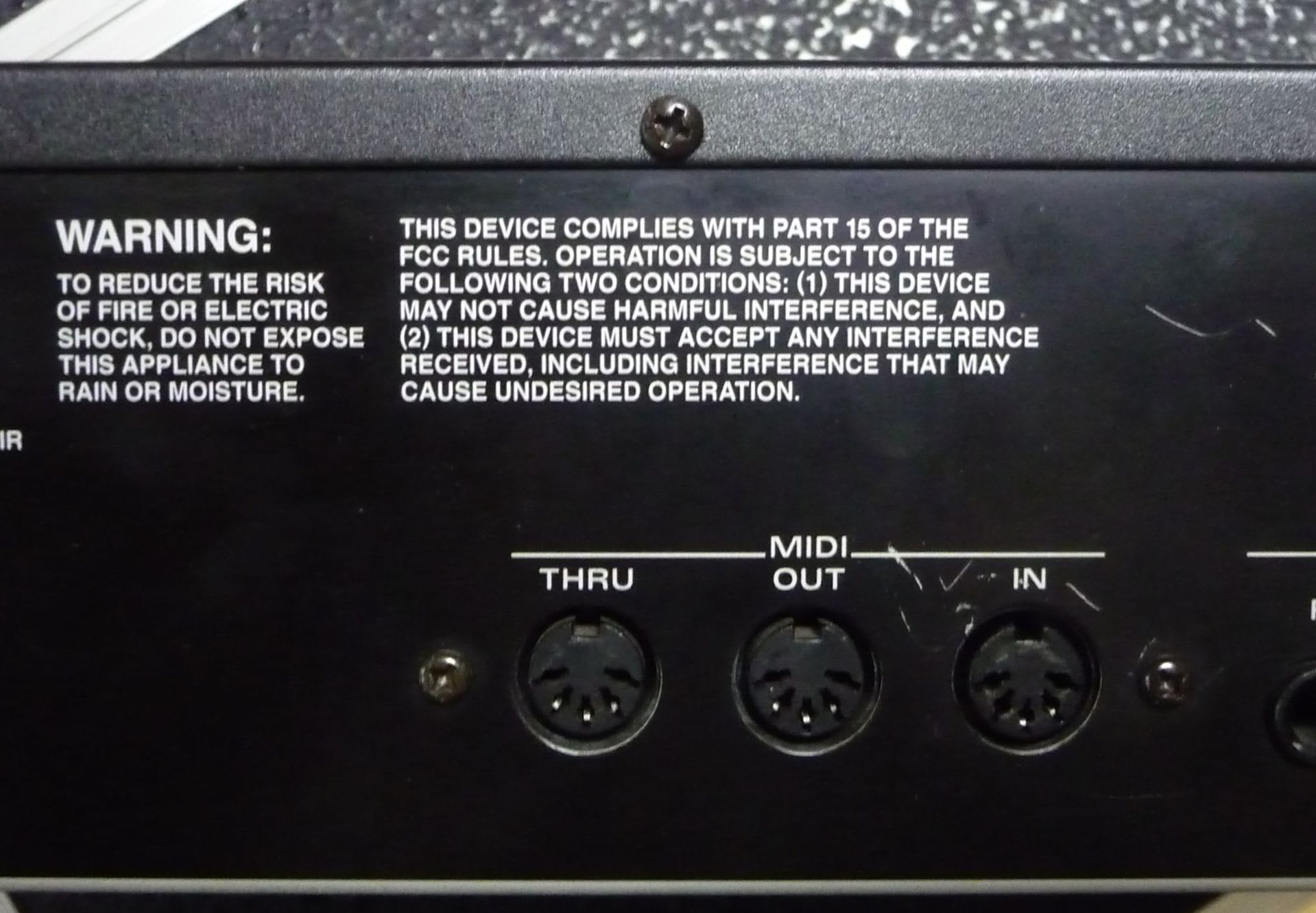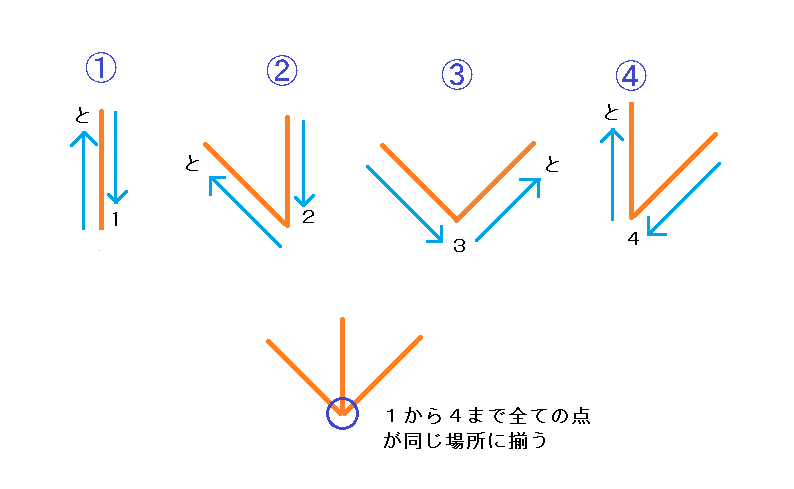本日は、声の劇団イマージュさんの公演
「さようならを一緒に」にご招待いただき、観劇してきました。
安く泊まれるアットホームな宿、ユースホステルを舞台にしたお話。
近年のイマージュさんは舞台美術も力を入れられていて、
良い感じのステージに仕上がっていました。
お芝居の序盤はなかなか波に乗ってくるまで雰囲気作りが難しいものですが、
最初から、宿の従業員数人で物語の世界観を作られていて、
皆さんお上手になったなあと思いました。
その後少しずつお客さんが増えていくのですが、その割にはなかなか物語が
進展しない脚本に、少し中だるみを感じました。
ユースホステルのリビングでお客同士が仲良く触れ合うアットホームさを
出したかったのかもしれませんが、新たな登場人物が増えると観客は無意識のうちに
話が動き出すことを期待してしまうものなんだなあ、と気が付きました。
後半には、世界観が変わるあっと驚く展開があり(後から思えば伏線は張られていましたが)、
最初戸惑いましたが、お話がとても良い内容なのでだんだん違和感も薄れ見入ってしまいました。
「恩は返すものではなく未来へ送るもの」
天国へ旅立とうとする宿のオーナー(おばあさん)に
「良くしてもらったのに何も恩を返せなかった」悔いる男に向けて
オーナーがかける言葉がとても印象的でした。
その思いを残されたこれからの人のために使いなさいというものです。
この脚本もそうですが、物語を見終わった後にタイトルを見て
「そういうことだったのか」と感慨深く思える題名は大好物です(笑)。
「さようならを一緒に」にご招待いただき、観劇してきました。
安く泊まれるアットホームな宿、ユースホステルを舞台にしたお話。
近年のイマージュさんは舞台美術も力を入れられていて、
良い感じのステージに仕上がっていました。
お芝居の序盤はなかなか波に乗ってくるまで雰囲気作りが難しいものですが、
最初から、宿の従業員数人で物語の世界観を作られていて、
皆さんお上手になったなあと思いました。
その後少しずつお客さんが増えていくのですが、その割にはなかなか物語が
進展しない脚本に、少し中だるみを感じました。
ユースホステルのリビングでお客同士が仲良く触れ合うアットホームさを
出したかったのかもしれませんが、新たな登場人物が増えると観客は無意識のうちに
話が動き出すことを期待してしまうものなんだなあ、と気が付きました。
後半には、世界観が変わるあっと驚く展開があり(後から思えば伏線は張られていましたが)、
最初戸惑いましたが、お話がとても良い内容なのでだんだん違和感も薄れ見入ってしまいました。
「恩は返すものではなく未来へ送るもの」
天国へ旅立とうとする宿のオーナー(おばあさん)に
「良くしてもらったのに何も恩を返せなかった」悔いる男に向けて
オーナーがかける言葉がとても印象的でした。
その思いを残されたこれからの人のために使いなさいというものです。
この脚本もそうですが、物語を見終わった後にタイトルを見て
「そういうことだったのか」と感慨深く思える題名は大好物です(笑)。