ギリシャ神話における子殺しの異常さ:日本の子殺しと比較して
親が我が子を殺す話は古今東西を問わず必ずある。日本の上代における文学にもいくつかの話が語られている。日本最古の仏教説話集「日本霊異記」の下巻第十六話「女人、濫(みだりがは)シク嫁ぎて、子を乳に飢ゑしむるがゆえに、現報を得る縁」は、美しい母は子育てより男女の愛欲に生き、子どもに乳を与えなかった話である。子どもたちは死ぬことは無かったが、早死にした母親は成仏できず其の霊は苦しんでいた。長い年月が過ぎた時、霊が寂林という法師の夢に現れて懺悔したたため、彼が子供たちにその話をしたところ、子どもたちは母を悲しみ、仏像を作り写経して母の罪を償った。その後、母は再び寂林法師の夢に現れ、許されたと告げた。
この話は親としての努めを放棄した母に報いがあったという因果応報思想の説話ではあるが、子どもにとっては生命線である乳を与えないのは子殺しにも通ずるものであろう。
平安時代末期に成立した今昔物語には貧しさゆえに子供を間引かねばならなかった話がいくつか出て来る。生まれても成人するまでに死んでしまう事が多かった時代であり、生まれた子供を殺してしまう事については現代とは異なる思いがあったであろう。それは300年間人口がほとんど変化しなかった江戸時代でも同じであった。歌舞伎や人形浄瑠璃の演目には、菅原伝授手習鑑や伽羅先代萩のように恩がある主君の跡取り息子の命が危険にさらされたときに身代わりに我が子の首あるいは命を差し出すという場面があり涙なしには見ていられない。特に先代萩では小刀をお腹に突き刺され、死にきれずに痛いようと泣く我が子をじっと見守るしかない母政岡の心中はいかばかりであろうか。
万葉集には亡き子を思う山上憶良の長歌とその反歌「銀(しろかね)も金(くがね)も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも」が有名であるが、子殺しの歌はない。和歌という形式が子殺しという主題に合わないという事もあるだろう。
ただ、古事記には一つ子殺しの神話がある。
イザナミノ命は火の神を生んだ時に御陰部を焼かれて臥し、それが原因で亡くなった。「可愛い妻を、一人の子と換えてしまったのか」(引用:「現代語訳「古事記」蓮田善明、岩波現代文庫)と男泣きに泣いたイザナギノ命は、腰に帯びた十挙剣(とつかつるぎ)を抜いて息子である火の神ヒノカグツチノ神の首を切った。神代の話なので、切られたヒノカグツチノ神から別の神々が生まれてくるので、そこには子殺しの悲惨さはあまりない。
ギリシャ神話にも親が子供を殺してしまう話はいくつか出て来るが、そこには日本の神話や古典文学作品には見られないケースがある。
まずは、神託により生まれてくる子供に自分が殺されると知らされたため、先手を打って生まれたばかりの子供を殺してしまう話。この形式の話は複数ある。
神の時代に、おまえは生まれてくる子どもに殺されることになるという神託を受けたクロノスは、生まれてきた子どもを次から次へと食べてしまった。しかし最後に生まれたゼウスは危うく難を逃れ、逆襲して父親クロノスを殺した。すると飲み込まれた子供たちが後の者が先になってクロノスの口から飛び出してきた。そこで、最初に地に出たゼウスが神々の長となり、生まれた順とは逆順に兄弟神の序列が決まった。
人間の時代の典型的な子ども殺しがオイディプス神話である。テーバイ国王のライオスは、生まれた息子に将来殺されるだろうという神託を受けたので、息子オイディプスが生まれるとすぐに踝(くるぶし)を縛ったうえで家来に殺すように命じた。ここでその話の筋追ってゆくスペースはないが、この神話はソフォクレスによって戯曲化されギリシャ悲劇として有名になったのでご存知の方も多いだろう。
英雄アガメムノンの長女であったイーピゲネイアも神託の犠牲者であった。
ギリシャ軍はトロイアに攻め込むために結集したもののいつまでたっても良い風が吹かず、停滞を余儀なくされていた。その時に、生娘を生贄としてささげれば状況が改善されるという神託があった。もともと戦争の発端は弟メネラオスの妻ヘレネがトロイアに連れ去られたことであり、諸国の王を戦争に駆り出した手前、総司令官のアガメムノンは自分の長女イーピゲネイアを生贄として出さざるを得なくなった。
納得できないのはアガメムノンの妻でありイーピゲネイアの母クリュタイメストラである。そもそもアガメムノンの弟でありスパルタ王メネラオスの王妃ヘレネがトロイの王子にさらわれたことがトロイ戦争の原因であり、王は弟メネラオスとの約束のために戦争に巻き込まれただけにもかかわらずなぜメネラオス王夫妻の子供は無傷で自分の子供だけが犠牲にならねばならないのか、と怒る。この話はソフォクレスのギリシャ悲劇「エレクトラ」の中でも語られる。
いずれの話も事の発端は神託なので当事者にはなすすべがなく、自分の命を守るために子供を殺してしまったり、その神託に従って生贄として捧げたりする。それは当事者にとっては不条理であり泣く泣く子供を手放す(オイディプスでは生まれた子を殺させ、アガメムノンは娘を生贄として差し出す)ことになった。
しかし、ギリシャ神話には神託もなく、全く持って母親の事情だけで我が子を殺ししてしまう恐ろしい話が二つある。
英雄テレウスは妻プロクネの頼みによって義理の妹を母国に迎えに行った帰り、美しい妹ピロメラに対する愛欲ゆえに秘密裏に彼女と結婚したうえで幽閉し、口封じのためにしゃべれないように舌を切った。それを知った妻プロクネは復讐のために[父親似の]我が子を殺し、その首を宴会中のテレウスの足元に投げだした。
この話には、プロクネの復讐心の強さもさることながら、愛する我が子を夫を苦しませるためだけを目的として殺ししてしまう異常さがある。たとえその子の容姿が父親に似ていたとしても、それはその子の責任ではないし、母親としてその子を愛してもいたのに、である。
もう一つの神話はエウリピデスが脚本を書いたギリシャ悲劇「メディア」である。
王女であったメディアは人生をかけて父王を裏切り、母国を去って英雄イアソンに付いてきて結婚した。しかし後に彼が心変わりしたため、復讐のために彼が(もちろん母親である自分も)愛している息子を殺し、遺体も連れ去ったのである。
メディアはもともと激しい気性の持ち主で、薬草を扱う魔女であった。その知識を使って、恋敵の王女と、自分を追い出そうとした恋敵の父王を殺した。
エウリピデスの悲劇では、外出から城に戻ってきたイアソンは子供の叫び声を城門の外で聞くと、中からメディアが現れて事の顛末を話したうえで、戦車に子供の遺体を乗せて空に駆け上ってゆく。子ども殺しは、愛していた夫イアソンをもっとも深く苦しめるために選んだ手段だった。
この話の異常さは、ピロメラとプロクネの話と同様、愛する子どもを殺すことが単に心変わりした夫を一番苦しめる手短な手段だったからであり、そこでは自分が子どもを愛しているという状況は全く考慮されていないし、子どもがかわいそうだという気持ちのかけらも斟酌されず、女の一方的な憎しみ・復讐心だけが浮き彫りにされている。
エウリピデスの悲劇はイタリアの映画監督パゾリーニが「王女メディア」として映画化しており、子どもを殺しても平然としてる王女メディアをオペラ歌手のマリア・カラスが好演している。ちなみに彼女はギリシャ系米国人である。
日本の上代の文学にはこのような形の異常な子ども殺しの例は見られないだろう。平安時代になると、源氏物語の六条の御息所の怨霊が源氏の新しい恋人にとりついて殺してしまうというような話は出て来るが、それは嫉妬心が背景にあるという点ではギリシャ神話と類似するものである。しかし、夫を苦しめるために自分たちの最愛の子ども殺すというような形は取っていないし、おそらくそのような例はないだろう。
つまり、日本では多くの女は心変わりした男に直接復讐しようとはしない。男が(源氏が)心変わりした時には、六条の御息所のように新しい恋敵に対して復讐をしようとする。それは現代の夫婦或いは恋人同士であっても同じである。夫に復讐するために最愛の我が子を殺し、夫を悲しみの淵に突き落とそうという発想は日本女性にはないだろう。それは現代でも変わることが無い。
逆に女が心変わりした場合はどうだろうか。ギリシャ神話にはそのような例はほとんどないし、有ったとしたら男はすぐに女を殺すか、切り捨てて終わりになるだけだろう。しかし、日本ならそんな時に男は女を手に掛けるより先に横取りした男に復讐しようとすることのほうが多いのではないだろうか。
以上 2024/Oct.
追記: 2024/Nov.
メディアの子ども殺しについて、こんな見方もあったので紹介する。
演出家 宮城 聰
『つまりメデイアは「男から男へと家督が相続されていく」というシステムそのものへ復讐したのではないか。イアソンという男がこの「男性原理」の使いっ走りとなって自分(女)をゴミのように捨てようとしたとき、その「原理」自体を破壊しようとしたのではないでしょうか。 』
1999年の公演サイトからの引用です。
http://www.kunauka.or.jp/jp/work/play/medea99_01.htm
メディアは自尊心の高い女で、嘲笑されることを極端に嫌う。自分の夫であったイアソンにごみのように捨てられた時、彼女の怒りは頂点に達したであろう。しかし、本当の敵はイアソンというよりも古代ギリシャの「男性原理」にあったのだ、という見方である。面白い見方だが、本文には「男性原理」を示唆する会話や言葉は出てこない。実際の公演で、そこをどう表現されたのであろうか。観てみたかった。
西洋古典学 逸見喜一郎
ネットに公開されている下記論文(出典は不明)によると、エウリピデスの描くメディアには「魔女」と「人間の女」と「(ギリシャ神話の)神」の三つの側面がある。最後に子供を自らの手にかけ、返ってきた夫イアソンにそれを見せつけていたいと一緒に戦車で去ってゆくときには、メディアは神になっている、ということだ。
/https://www.seijo.ac.jp/pdf/falit/109/109-03.pdf
この論文は原典のギリシャ語の分析まで遡って議論されており、専門外の私には理解できない部分も多々あるが、示唆に富む指摘が多かった。確かにメディアの祖父は神であったし、彼女自身も自国に居る時は巫女であり、魔女(おそらく薬草使い)でもあったわけで、激高した時に神の側面が立ち上り、人間の女としては考えられないような子ども殺しをし、元夫のイアソンを嘲笑しながら去ってゆくことができるのだろう。
以上
親が我が子を殺す話は古今東西を問わず必ずある。日本の上代における文学にもいくつかの話が語られている。日本最古の仏教説話集「日本霊異記」の下巻第十六話「女人、濫(みだりがは)シク嫁ぎて、子を乳に飢ゑしむるがゆえに、現報を得る縁」は、美しい母は子育てより男女の愛欲に生き、子どもに乳を与えなかった話である。子どもたちは死ぬことは無かったが、早死にした母親は成仏できず其の霊は苦しんでいた。長い年月が過ぎた時、霊が寂林という法師の夢に現れて懺悔したたため、彼が子供たちにその話をしたところ、子どもたちは母を悲しみ、仏像を作り写経して母の罪を償った。その後、母は再び寂林法師の夢に現れ、許されたと告げた。
この話は親としての努めを放棄した母に報いがあったという因果応報思想の説話ではあるが、子どもにとっては生命線である乳を与えないのは子殺しにも通ずるものであろう。
平安時代末期に成立した今昔物語には貧しさゆえに子供を間引かねばならなかった話がいくつか出て来る。生まれても成人するまでに死んでしまう事が多かった時代であり、生まれた子供を殺してしまう事については現代とは異なる思いがあったであろう。それは300年間人口がほとんど変化しなかった江戸時代でも同じであった。歌舞伎や人形浄瑠璃の演目には、菅原伝授手習鑑や伽羅先代萩のように恩がある主君の跡取り息子の命が危険にさらされたときに身代わりに我が子の首あるいは命を差し出すという場面があり涙なしには見ていられない。特に先代萩では小刀をお腹に突き刺され、死にきれずに痛いようと泣く我が子をじっと見守るしかない母政岡の心中はいかばかりであろうか。
万葉集には亡き子を思う山上憶良の長歌とその反歌「銀(しろかね)も金(くがね)も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも」が有名であるが、子殺しの歌はない。和歌という形式が子殺しという主題に合わないという事もあるだろう。
ただ、古事記には一つ子殺しの神話がある。
イザナミノ命は火の神を生んだ時に御陰部を焼かれて臥し、それが原因で亡くなった。「可愛い妻を、一人の子と換えてしまったのか」(引用:「現代語訳「古事記」蓮田善明、岩波現代文庫)と男泣きに泣いたイザナギノ命は、腰に帯びた十挙剣(とつかつるぎ)を抜いて息子である火の神ヒノカグツチノ神の首を切った。神代の話なので、切られたヒノカグツチノ神から別の神々が生まれてくるので、そこには子殺しの悲惨さはあまりない。
ギリシャ神話にも親が子供を殺してしまう話はいくつか出て来るが、そこには日本の神話や古典文学作品には見られないケースがある。
まずは、神託により生まれてくる子供に自分が殺されると知らされたため、先手を打って生まれたばかりの子供を殺してしまう話。この形式の話は複数ある。
神の時代に、おまえは生まれてくる子どもに殺されることになるという神託を受けたクロノスは、生まれてきた子どもを次から次へと食べてしまった。しかし最後に生まれたゼウスは危うく難を逃れ、逆襲して父親クロノスを殺した。すると飲み込まれた子供たちが後の者が先になってクロノスの口から飛び出してきた。そこで、最初に地に出たゼウスが神々の長となり、生まれた順とは逆順に兄弟神の序列が決まった。
人間の時代の典型的な子ども殺しがオイディプス神話である。テーバイ国王のライオスは、生まれた息子に将来殺されるだろうという神託を受けたので、息子オイディプスが生まれるとすぐに踝(くるぶし)を縛ったうえで家来に殺すように命じた。ここでその話の筋追ってゆくスペースはないが、この神話はソフォクレスによって戯曲化されギリシャ悲劇として有名になったのでご存知の方も多いだろう。
英雄アガメムノンの長女であったイーピゲネイアも神託の犠牲者であった。
ギリシャ軍はトロイアに攻め込むために結集したもののいつまでたっても良い風が吹かず、停滞を余儀なくされていた。その時に、生娘を生贄としてささげれば状況が改善されるという神託があった。もともと戦争の発端は弟メネラオスの妻ヘレネがトロイアに連れ去られたことであり、諸国の王を戦争に駆り出した手前、総司令官のアガメムノンは自分の長女イーピゲネイアを生贄として出さざるを得なくなった。
納得できないのはアガメムノンの妻でありイーピゲネイアの母クリュタイメストラである。そもそもアガメムノンの弟でありスパルタ王メネラオスの王妃ヘレネがトロイの王子にさらわれたことがトロイ戦争の原因であり、王は弟メネラオスとの約束のために戦争に巻き込まれただけにもかかわらずなぜメネラオス王夫妻の子供は無傷で自分の子供だけが犠牲にならねばならないのか、と怒る。この話はソフォクレスのギリシャ悲劇「エレクトラ」の中でも語られる。
いずれの話も事の発端は神託なので当事者にはなすすべがなく、自分の命を守るために子供を殺してしまったり、その神託に従って生贄として捧げたりする。それは当事者にとっては不条理であり泣く泣く子供を手放す(オイディプスでは生まれた子を殺させ、アガメムノンは娘を生贄として差し出す)ことになった。
しかし、ギリシャ神話には神託もなく、全く持って母親の事情だけで我が子を殺ししてしまう恐ろしい話が二つある。
英雄テレウスは妻プロクネの頼みによって義理の妹を母国に迎えに行った帰り、美しい妹ピロメラに対する愛欲ゆえに秘密裏に彼女と結婚したうえで幽閉し、口封じのためにしゃべれないように舌を切った。それを知った妻プロクネは復讐のために[父親似の]我が子を殺し、その首を宴会中のテレウスの足元に投げだした。
この話には、プロクネの復讐心の強さもさることながら、愛する我が子を夫を苦しませるためだけを目的として殺ししてしまう異常さがある。たとえその子の容姿が父親に似ていたとしても、それはその子の責任ではないし、母親としてその子を愛してもいたのに、である。
もう一つの神話はエウリピデスが脚本を書いたギリシャ悲劇「メディア」である。
王女であったメディアは人生をかけて父王を裏切り、母国を去って英雄イアソンに付いてきて結婚した。しかし後に彼が心変わりしたため、復讐のために彼が(もちろん母親である自分も)愛している息子を殺し、遺体も連れ去ったのである。
メディアはもともと激しい気性の持ち主で、薬草を扱う魔女であった。その知識を使って、恋敵の王女と、自分を追い出そうとした恋敵の父王を殺した。
エウリピデスの悲劇では、外出から城に戻ってきたイアソンは子供の叫び声を城門の外で聞くと、中からメディアが現れて事の顛末を話したうえで、戦車に子供の遺体を乗せて空に駆け上ってゆく。子ども殺しは、愛していた夫イアソンをもっとも深く苦しめるために選んだ手段だった。
この話の異常さは、ピロメラとプロクネの話と同様、愛する子どもを殺すことが単に心変わりした夫を一番苦しめる手短な手段だったからであり、そこでは自分が子どもを愛しているという状況は全く考慮されていないし、子どもがかわいそうだという気持ちのかけらも斟酌されず、女の一方的な憎しみ・復讐心だけが浮き彫りにされている。
エウリピデスの悲劇はイタリアの映画監督パゾリーニが「王女メディア」として映画化しており、子どもを殺しても平然としてる王女メディアをオペラ歌手のマリア・カラスが好演している。ちなみに彼女はギリシャ系米国人である。
日本の上代の文学にはこのような形の異常な子ども殺しの例は見られないだろう。平安時代になると、源氏物語の六条の御息所の怨霊が源氏の新しい恋人にとりついて殺してしまうというような話は出て来るが、それは嫉妬心が背景にあるという点ではギリシャ神話と類似するものである。しかし、夫を苦しめるために自分たちの最愛の子ども殺すというような形は取っていないし、おそらくそのような例はないだろう。
つまり、日本では多くの女は心変わりした男に直接復讐しようとはしない。男が(源氏が)心変わりした時には、六条の御息所のように新しい恋敵に対して復讐をしようとする。それは現代の夫婦或いは恋人同士であっても同じである。夫に復讐するために最愛の我が子を殺し、夫を悲しみの淵に突き落とそうという発想は日本女性にはないだろう。それは現代でも変わることが無い。
逆に女が心変わりした場合はどうだろうか。ギリシャ神話にはそのような例はほとんどないし、有ったとしたら男はすぐに女を殺すか、切り捨てて終わりになるだけだろう。しかし、日本ならそんな時に男は女を手に掛けるより先に横取りした男に復讐しようとすることのほうが多いのではないだろうか。
以上 2024/Oct.
追記: 2024/Nov.
メディアの子ども殺しについて、こんな見方もあったので紹介する。
演出家 宮城 聰
『つまりメデイアは「男から男へと家督が相続されていく」というシステムそのものへ復讐したのではないか。イアソンという男がこの「男性原理」の使いっ走りとなって自分(女)をゴミのように捨てようとしたとき、その「原理」自体を破壊しようとしたのではないでしょうか。 』
1999年の公演サイトからの引用です。
http://www.kunauka.or.jp/jp/work/play/medea99_01.htm
メディアは自尊心の高い女で、嘲笑されることを極端に嫌う。自分の夫であったイアソンにごみのように捨てられた時、彼女の怒りは頂点に達したであろう。しかし、本当の敵はイアソンというよりも古代ギリシャの「男性原理」にあったのだ、という見方である。面白い見方だが、本文には「男性原理」を示唆する会話や言葉は出てこない。実際の公演で、そこをどう表現されたのであろうか。観てみたかった。
西洋古典学 逸見喜一郎
ネットに公開されている下記論文(出典は不明)によると、エウリピデスの描くメディアには「魔女」と「人間の女」と「(ギリシャ神話の)神」の三つの側面がある。最後に子供を自らの手にかけ、返ってきた夫イアソンにそれを見せつけていたいと一緒に戦車で去ってゆくときには、メディアは神になっている、ということだ。
/https://www.seijo.ac.jp/pdf/falit/109/109-03.pdf
この論文は原典のギリシャ語の分析まで遡って議論されており、専門外の私には理解できない部分も多々あるが、示唆に富む指摘が多かった。確かにメディアの祖父は神であったし、彼女自身も自国に居る時は巫女であり、魔女(おそらく薬草使い)でもあったわけで、激高した時に神の側面が立ち上り、人間の女としては考えられないような子ども殺しをし、元夫のイアソンを嘲笑しながら去ってゆくことができるのだろう。
以上










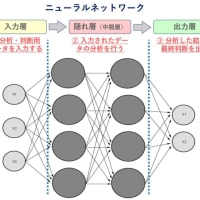
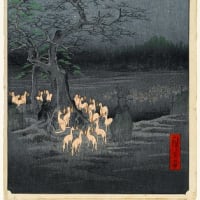






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます