家まで走ってゆき、敷居を超える。その時初めて僕は悟った。敷居とは、ぼくだけの世界の、ぼくの聖域の境界だということを。
あるのは変容だけだ。
なかでもディケンズの『炉辺のコオロギ』のイメージが、ぼくの心を強くとらえた。
グリェルモ、幼年時代にはなにか腐敗したものがある。ぼくたちは自分の起源にあまりにも近くいすぎるんだ。
生きのびるにはこうするよりほかにないんだ。たえず、べつの存在に変身してゆくことだ。グリェルモ、時間につかまれば、きみは殺されるんだぞ、時間には始りがあり、発展があり、終わりがある。変身するといっても、君はある状態からべつの状態に移行するだけなんだ。
なにもかも飛越えて、忘れてしまうこと。そうすれば、いずれ今以上の人間、もつと立派な人間になれるかも知れないわ。
私は言葉でいっぱいよ。でも名前やむつかしい考えは持ち合わせてはいない。感覚があるだけよ。
「自分の姿を見るのはもう沢山、あきあきしたわ」
どんな気分だい?
自力でやるってのは。
ぼくにとっては空間と思考とは同一のものなのだ。これ以上知ることはないだろう。世界の神秘とは可視のものなのだ。
カルロス・フェンテスとメキシコの現代小説――木村栄一
この小説(『脱皮』)を理解する唯一の方法は、作品の絶対的な虚構性を受け入れるかどうかにかかっています。(フェンテス)
完全な虚構としての作品、すなわち現実の外部にあって、それと拮抗しうるだけの存在感をそなえたもうひとつの現実としてある虚構
言いかえれば、ギリェルモの変身は、ユダヤ教が編み出し、キリスト教が受けつぎ、今もヨーロッパやイスパノアメリカで脈々と生きている「始めと終わり」のある時間を否定し、彼が新しい生に再生したことを意味している。
作品世界の虚構性(『聖域』
「小説とは、本質的に、方法論を模索する芸術」(三島由紀夫)
理性の暴力が言葉からリズムを奪い取ってしまう(オクタビオ・パス)
……詩は純粋な時間に到達する道、存在の始源の水の中に身をひたすことにほかならない。(パス『弓と竪琴』)
*平成三十年六月二十六日抜粋終了。
*一九六〇年代後半から八〇年代にかけてのフェンテスは、手法的実験にはしりすぎるあまり、『脱皮』(一九六七) (『聖域』(一九六七)のようにほとんど意味不明の作品を幾つか残したが……
(フェンテス『澄みわたる大地』 寺尾隆吉訳 現代企画室 二〇一二 訳者あとがき) 尊大な評価だこと。
*拙著『述語は永遠に……』(四〇歳)方法論の模索ではあったが、理解や成功とは縁遠かったようである。連想過多症の積習による「ひかり」を駆っての脱出行であったのだが。
*喰うための実業(年金)にかまけて、四〇歳以降、五十四歳の『情緒の力業』をのぞいて為す術がないまま、まもなく七十七歳を迎えようとしているのが現状である。













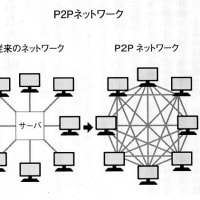
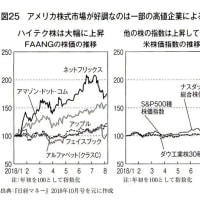

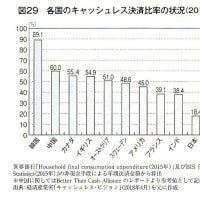
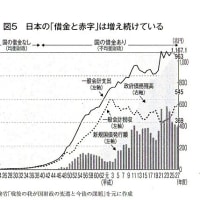

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます