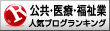「ハロー・トウキョウ」というタクシー会社があるらしい、利用したことがないのでよく知らないが、その会社のことを
http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20081020/174523/
日経ビジネスオンラインが紹介している。
この会社では運転手を「乗務担当の従業員」と呼び社員である意識づけをしているらしい。
社員間で乗客がひろえる場所や時間帯を共有する。普通だとこうした情報は運転手は自分のものだけにして公開しないようだが、この情報を公開することでお互いの乗車率が向上し給与も増えるから会社が進めているタクシーはサービス業という仕事も納得して行うのだろう。
会社が仕掛ける様々な車内でのサービスを提供することは運転手にとって負担となるのだが、情報を共有する仕組みや会社の仕掛けは自分たちにとって利益となることが実感できるから運転手は嫌がらずに行うのだろう。
わが社のことに置き換えるとどうだろうかと思った。わが社ではケアマネジメントで特別なことを行っているとは思わないが徹底して行っていることは事実だろう。
たとえばケアマネがお互いのケースを持ち寄ることで他のケースが参考になり、その結果担当しているお客様の状態がよくなる、ケアの導入が出来る、コミュニケーションができる、などの成果を出す。その結果は介護度の更新のときに介護度が継続するとか改善するとかの結果がでるだろうと期待し、その結果は手当を支給するという方法で評価する。
はたしてこの方法が有効なのかいましばらく様子見です。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20081020/174523/
日経ビジネスオンラインが紹介している。
この会社では運転手を「乗務担当の従業員」と呼び社員である意識づけをしているらしい。
社員間で乗客がひろえる場所や時間帯を共有する。普通だとこうした情報は運転手は自分のものだけにして公開しないようだが、この情報を公開することでお互いの乗車率が向上し給与も増えるから会社が進めているタクシーはサービス業という仕事も納得して行うのだろう。
会社が仕掛ける様々な車内でのサービスを提供することは運転手にとって負担となるのだが、情報を共有する仕組みや会社の仕掛けは自分たちにとって利益となることが実感できるから運転手は嫌がらずに行うのだろう。
わが社のことに置き換えるとどうだろうかと思った。わが社ではケアマネジメントで特別なことを行っているとは思わないが徹底して行っていることは事実だろう。
たとえばケアマネがお互いのケースを持ち寄ることで他のケースが参考になり、その結果担当しているお客様の状態がよくなる、ケアの導入が出来る、コミュニケーションができる、などの成果を出す。その結果は介護度の更新のときに介護度が継続するとか改善するとかの結果がでるだろうと期待し、その結果は手当を支給するという方法で評価する。
はたしてこの方法が有効なのかいましばらく様子見です。