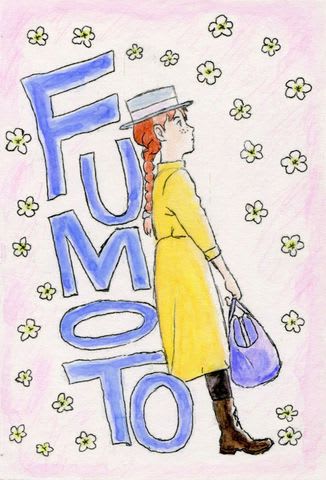リスク管理で世界水準だった 業績好調の日揮を襲った悪夢
2013年1月28日(月)09:10
世界のプラント・エンジニアリング史上でも、あり得ない規模の大惨事である。
1月16日に、北アフリカにあるアルジェリアの内陸部の天然ガス施設で起きたイスラム武装勢力による人質事件で、エンジニアリング専業大手の日揮の国内外のスタッフが10人以上死亡した。
皮肉にも、今回の事件を通じて、普段われわれがあまり気に留めることのなかった海外に軸足を置くプラント・エンジニアリングの仕事に注目が集まった。そしてその仕事は困難で、リスクを伴うものであることも如実に示された。
例えば、LNG(液化天然ガス)プラントの心臓部「中核装置」(地中から掘り出した天然ガスをマイナス162度で液化・圧縮する設備)を手がけられる企業は世界に五つしかない。日本の日揮と千代田化工建設、米国のベクテルとKBR、フランスのテクニップだ。扱える企業が限定されるために、資源国から声がかかるのである。
また、資源の多くは政情不安定な国々に眠ることが多く、技術を持つ企業は、必然的にそのような地域が“仕事場”となる。そして、エンジニアリング会社は、砂漠の真ん中や、ジャングルの奥地で、原野を開拓して街を造成することから始める。そうやって、最終的には巨大生産設備を立ち上げる。
「プラントの建設ばかりではなく、現地人の技術者教育などを通して資源国の発展に貢献してきたのがエンジニアリング会社だ。今も誇りに思っている」(日揮のOB)
日揮にとって、アルジェリアは縁の深い国である。1969年の「アルズー製油所」の建設プロジェクトは、過酷な環境下で幾多の困難に直面し、多額の損失を出して会社がつぶれかけた。それでも、設備を完成させて同国政府の信頼を勝ち得たことが、後の大型受注へとつながり、日揮は発展の礎を築く。最初に調査で接点ができて以来、45年以上の関係がある。
翻って現在、日揮は2011年度の連結決算で、売上高5569億円、営業利益670億円、純利益391億円と、過去最高益を出した。長い年月をかけて、体系化した独自のリスク管理手法により、実績と信頼を積み重ねてきた。


「ちいむら」では
2月11日3月10日(日曜日)予定に「復興支援デイ」を設けようと思っております

宮城から参加していた小学生が、3月3日(彼の誕生日)に麓の家に引っ越してきます
彼も含め、子どもたちと一緒にあらかじめケーキやお菓子を焼き
地元の方々の善意の品を集め
値段つけ、展示もし、募金箱も設置し
チラシも作成し、売上は全部被災地に送るというイベントです
子どもたちに「被災地で苦しんでおられる方々のことを考える日 & 行動を起こす日」をしたいと思っております
もし、みなさまの手元に「これをその復興支援デイに使っても」という品がありましたら
是非ご協力お願いいたします
左サイドバーに「メッセージを送る」という欄がありますのでそちらか
麓の夢のブログの下の方にある「川湯ビレッジ」宛にお願いいたします
麓の夢のブログは
 こちら
こちら
ご訪問ありがとうございます

 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
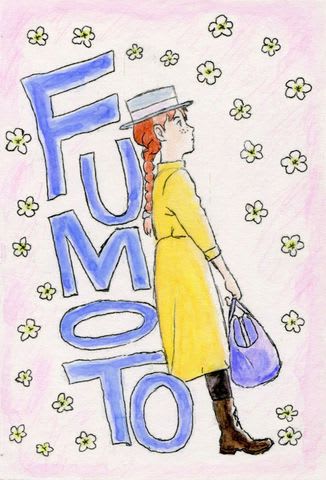 みなさん、最近コメントお返し&訪問できてなくてごめんなさいm(_ _)m
みなさん、最近コメントお返し&訪問できてなくてごめんなさいm(_ _)m 明日アップしますが、雪で大変な事態になっており
明日アップしますが、雪で大変な事態になっており
って言い訳ですが、ほぼ陸の孤島状態ですw

記録的な大雪 2013年
みなさま、クリック募金にご協力お願いいたします
別に自慢ではありませんので誤解していてほしくないのですが
始めてから毎日で
こちら (全体)
こちら(個人)
の結果です
私たちは助け合うべきではないでしょうか???
一年前の流氷記事
復興支援
 東京電力は28日、福島第一原発の港湾内で2月17日に捕獲したアイナメから、1キロ・グラムあたり51万ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。
東京電力は28日、福島第一原発の港湾内で2月17日に捕獲したアイナメから、1キロ・グラムあたり51万ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。
国の規制値(100ベクレル)の5100倍に相当し、原発事故後、魚介類で最も高い値。これまでの最高値は、昨年12月20日に同じ港湾内でとれたムラソイの25万4000ベクレルだった。
東電は、港湾の外に魚が流出しないよう海中に網を設置したり、湾内の魚を捕獲したりする作業を進めている。
.
最終更新:2月28日(木)18時50分
命の海が今も怖い。東日本大震災の津波で福島県浪江町請戸の自宅と漁船を流された浮渡(うきと)宣夫さん(43)は、約20年続けていた漁師にもう戻れないと思い始めている。間近に迫った津波の記憶、仲間を「死なせた」後悔が、まだ胸をふさぐ。東京電力福島第1原発事故で海が汚され、県内漁業は復活の緒についたばかりだ。「2年」が近づく今、先が見えない。
【漁船やがれきが放置されたままの浪江町】写真で見る 空から見た福島第1原発3キロ圏の惨状
あの日、バックミラーを見る余裕も勇気もなかった。海沿いの自宅へ車で戻ろうとした浮渡さんは、100メートル手前で堤防を越す津波を見てすぐUターン。狭い農道を全速力で逃げた。視界の端に水の塊が映る。約2キロ西の避難場所・大平山で車を飛び降り、やぶをかき分け斜面を上って、振り返ると「町がなくなっていた」。コンクリート製の建物4棟を除き、古里は真っ黒い海に沈んでいた。
たとえ一つでも違う行動を取っていたら、命はなかった。それを思うとぞっとする。
津波で漁協の青壮年部の仲間2人を亡くした。揺れが襲った時は部の活動で、海から約6キロのショッピングセンターで一緒だったのに……。「仲間が自宅に戻るのを部長だった自分が止めれば、誰も死なずにすんだ」。自責の念が消えることはない。
津波禍は免れたが、原発事故で県内外を転々と避難した。隣の南相馬市の借り上げ住宅に父通正(みちまさ)さん(73)と落ち着き、昨年10月から市内にある浪江町役場の出張所で働く。高校卒業後に2年弱、家業を継ぐ前にバス会社に就職して以来約20年ぶりの事務仕事だ。日の出前に出航し海を相手にしてきた漁師とは、仕事の内容も生活のリズムも大きく変わった。だが県の期間限定の雇用事業なので最大1年間しか勤められない。
かつての仲間は船に乗り、放射線のモニタリング検査やがれき処理などで海に出る。漁を始めたと聞けばうれしいし、自分も頑張ろうと思える。「しかし、いつ震災前のような漁ができるのか。生活できるのか」
小さいころから海を見て育った。海の近くに住むのが当たり前だった。震災後、たとえ静かな海でも落ち着かない。どっちへ逃げたらいいか、と考える自分がいる。「海の近くにはいたいけれど、できれば少し距離を保ちたい」と吐露する。
津波ですべてを流され、原発事故で仕事場を奪われた。立ち入り禁止の警戒区域となった浪江町内の田んぼに、漁船は放置されたままだ。11年秋に一時帰宅した際、船舶免許証と網の修理道具などを持ち帰った。手にすると、断ち切れぬ思いが頭をもたげる。「天気の良い日は漁に出たら気持ちがいいだろうな」と。【長田舞子】
川湯ビレッジでは随時生徒を募集しております
詳しくは
こちら
ご訪問ありがとうございます




 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ にほんブログ村
にほんブログ村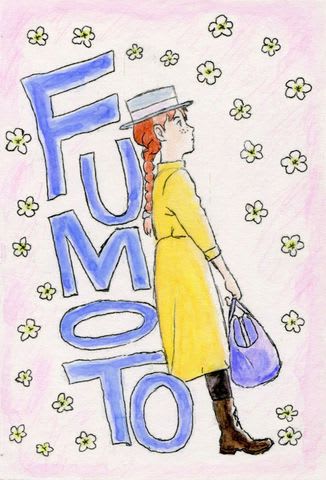









 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ にほんブログ村
にほんブログ村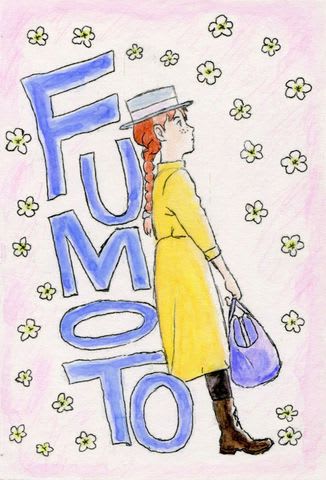










 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ にほんブログ村
にほんブログ村