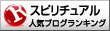「しかし、多くの先の者はあとになり、あとの者は先になるであろう」。
(ルカによる福音書10章31節)
このような言葉を、かつてキリストはしばしば語られました。実に不思議で、意味深な言葉です。聖書のパラドックスの1つです。福音書を読んでいくと、聖書に精通し、神をよく知っているはずの神の民、選民と呼ばれている人たちの多くが神の国の救いにあずかれないでいた一方で、
「すべての人を照すまことの光があって、世にきた。彼は世にいた。
そして、世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。
彼は自分のところにきたのに、自分の民は彼を受けいれなかった。」
(ヨハネによる福音書1章9~11節)
聖書の知識も持ち合わせておらず、聖書の神についてはほとんど知るはずもないような異邦人の多くが、キリストも感心されるような信仰を働かせて神の救いにあずかっていったという事実がわかってきます(マタイによる福音書8章5~13節などを参照)。いったい何故なのでしょうか?
私たち誰もが、十字架上の強盗がはりつけの刑で亡くなる直前に、キリストの隣りにおられた強盗に救いを宣言される記事を読んだりすると、驚きを禁じ得ません。なぜ、後の者が我先にと救いを確実なものにしていけるんだろうか(?)・・・と。 そのわけは何なのでしょうか?
山上の説教の中でキリストは、聖書をよく学び、神やキリストのこともよく知っていて、信仰告白もし、さらに信じるだけでなく、めざましい神のわざも行なっていた“信者”の多く(=先の者)が、天国から閉め出されることになるであろうことも述べておられます。
「その日には、多くの者が、わたしにむかって『主よ、主よ、わたしたちは
あなたの名によって預言したではありませんか。また、あなたの名によって
悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力あるわざを行ったではありま
せんか』と言うであろう。そのとき、わたしは彼らにはっきり、こう言おう、
『あなたがたを全く知らない。不法を働く者どもよ、行ってしまえ』。」
(マタイによる福音書7章22~23節)
何ゆえ、このような矛盾が、あってはならないような悲劇が、一見 不公平と思われるような出来事が 現実となって、起こってしまうのでしょうか? まじめに聖書を読み、祈りにも十分すぎる程に時間を費やしてきた信者さん、教会にもほとんどサボらず毎週のように出席していたような信者さん、十一献金やその他の献金も惜しまず率先してやってきた信者さん、信仰歴も長く、教会出席率もずば抜けているような信者さん、信仰に熱心で神のわざにもいそしんできたような信者さん、ボランティアや教会における奉仕活動や伝道活動にも熱心にやってきた信者さんなど、・・・このような教会の信者さんこそが誰よりも先んじて神の国の救いにあずかれそうなのに、なぜ後回しにされたり、最悪の場合には、神の国から閉め出されたりしてしまうのでしょうか?
腑に落ちないこのような謎、パラドックスは一刻も早く解明しておかなければなりません。しかも、自分に与えられたのこの人生を生きている間に、私たちはキチンと解明し、納得しておきたいもの。“こんなはずではなかった!”と、あとになって後悔したり、嘆いたりすることがないためにも。また、“主よ、主よ、この自分がなぜ神の国に入れてもらえないのか、私には納得がいきません。あまりにも不公平ですよ。何かの間違いでしょう!?”と、主イエス・キリストに直談判して抗議したり、クレームをつけたりするようなグループの一員にならないためにも・・・。
* * *
さて、キリストが私たち人類に伝えようとしたかった真理、救いの極意、奥義は一体どこにあるのでしょうか?
それについて、“十字架のシンボリック座標”から 私なりの説明と謎解きを試みてみたいと思います。
さて、“十字架のシンボリック座標”の縦軸は“時間軸”と呼ばれ、交点より上の方が未来を表わし、交点より下の方が過去を表わしています。
時間軸
(未来)




↓
時間軸
(過去)
なお、横軸は“相対軸”と呼ばれ、交点より右方の端が善や義などに対応し、交点より左方の端が悪や不義や罪などに対応していることは先に述べた通りです。つまり、私たちが住んでいる相対世界を示しています。私たちはこの相対軸のいずれかの地点で自分に与えられた人生を現在生きているわけです。
悪・不義・罪など 
 善・義など
善・義など


![]()
そして、以上の縦軸(時間軸)と横軸(相対軸)をクロスさせると、下図の“十字架シンボリック座標”なるものが出来上がるわけです。時間軸と相対軸の2つの軸をクロスさせた交点である●の印をつけたポイントが十字架の中心であり、“絶対ゼロ座標点”、あるいは “絶対ゼロ次元”とも言い換えることができるところです。

絶対世界におられる根源なる神と相対世界の住民である私たちヒトとの唯一の接点は、実は、十字架の中心である“絶対ゼロ座標点”(=“絶対ゼロ次元”)にしかなかったということに、ようやく最近になって私は気づかされたわけです。
しかも、私が聖書を研究し始めてから35年目にして、ようやく・・・。随分、年月を費やしてしまったなぁ・・・。単純なことなのに・・・。(独り言)
* * *
『十字架座標から解く―先の者はあとになり、あとの者は先になる②』
に 進む
トップページに戻る
十字架座標から解く―先の者はあとになり、あとの者は先になる②
H2.9.7公開 / H22.9.12 改訂更新
時間軸における“未来”
“今というこの時”をしっかりと生きることをせずに、この世における私たちの軸足を時間軸の“未来”に移して、自分の将来に幻想を抱いたり、過度に期待を膨らませたりして生きようとしてはなりません。キリストは山上の説教において、
「だから、あすのことを思いわずらうな。あすのことは、あす自身が思いわずらう
であろう。一日の苦労は、その日一日だけで十分である」(マタイによる福音書6章34節)
と語られたのでした。明日というような未来にシフトして生きようとするのではなく、今日という一日を確実に着実に生きていくことが大切だとキリストは諭されるのです。明日に生きようとする時に、思いわずらいが生じてしまいます。そのようにして生じた思いわずらいというものは、この相対世界に住んでいる私たちが生きた信仰が働かせることを妨害するノイズとなってしまうのです。
時間軸
(未来)



↓
時間軸
(過去)
私たちの軸足を“今”というこの時に置かずして、この瞬間、瞬間という現実の時間をしっかりと生きるということをしないまま、単に未来という不確かな時間にブレて生きてしまう時、神から賜った人生というものを最高に生きるということに、私たちは失敗してしまうのです。
まだ見ぬ未来の出来事に対する取り越し苦労や思い煩いという重荷を“今”わざわざ自分で背負い込んでしまって、その不安と心配のストレスから心身のエネルギーを無駄に消耗して、場合によっては病気を誘発してしまうこともあるのです。
また、“今”という時を大切にしないで、自分の将来に幻想を抱いたり、過度に期待を膨らませながら生きようとする時、それが現実にならなかった際の失望や絶望、ショックはいかばかりでありましょう。
旧約聖書におけるヨブが自分の人生に災難や苦難が訪れたきっかけが、自分の心のスクリーンに未来に起こるかもしれない恐れという幻想を映し出してしまったことと関係があることに気づいたようです。
「わたしの恐れるものが、わたしに臨み、わたしの恐れおののくものが、
わが身に及ぶ。」
(ヨブ記3章25節)
ヒトとしての本来の生き方、それは今というこの瞬間、瞬間をしっかりと着実に確実に生きていくことにあります。私たちが絶対世界におられる生ける根源の神にアクセスするが可能な時間座標は、実は、今というこのリアルタイムだけなのです。逆に言うと、私たちが今というこの瞬間、瞬間 根源の神と繋がり、1つになっている時にのみ、決して失望に終わることのない確かな希望を未来に描くことがはじめて可能にもなるのです。
時間軸における“過去”
また、私たちは未来だけではなく、さらに過去という時間をも超越していく必要があります。
私たちがヒトとして確固たる人生を送っていくためには、過去という呪縛から開放されていなければならないのです。。私たちは時間という流れの中で、後ろを振り返ってはならないのです。つまり、すでに過ぎ去ってしまった過去の事に囚われたり、引きずられたり、こだわってたり、固執したりしていてはならないのです。もしそのようにしてしまうなら、私たちの人生から喜びや輝きが消え去り、生きがいや生きる気力なども たちまちのうちに失われていってしまうことでしょう。そして、私たちは、今というこの時に身動きが取れなくなってしまいます。ここで私は、うしろを顧みたために塩の柱になってしまったロトの妻の悲劇を思い出します。
「夜が明けて、み使たちはロトを促して言った 『立って、ここにいるあなたの妻と
ふたりの娘とを連れ出しなさい。そうしなければ、あなたもこの町の不義のために
滅ぼされるでしょう』。・・・彼らを外に連れ出した時そのひとりは言った、『のがれて、
自分の命を救いなさい。うしろをふりかえって見てはならない。低地にはどこにも
立ち止まってはならない。山にのがれなさい。そうしなければ、あなたは滅びます』。
・・・・しかしロトの妻はうしろを顧みたので塩の柱になった。」(創世記19章15~26節)
旧約聖書のヨブは、どうだったでしょうか? ヨブの人生に耐え難いような災難、苦難が訪れた時に、ヨブはやがて自分の過去のデータを一生懸命に検索しようと試みました。そうすることで、自分になぜこのような災難や苦難がやってきたか、その訳を知ることができるのではないかと考えたのかも知れません。しかし、自分自身の過去のデータベースをくまなく探しても、自分の人生において起こった難問題を解く根本的な解決策は見い出せなかったのでした。
キリストは、このように祈りなさいと弟子たちに教えられたいわゆる”主の祈り”というのは、
「天にいますわれらの父よ、御名があがめられますように。
御国がきますように。みこころが天に行われるとおり、地にも行われますように。
わたしたちの日ごとの食物を、きょうもお与えください。
わたしたちに負債のある者をゆるしましたように、わたしたちの負債をもおゆるしください。
わたしたちを試みに会わせないで、悪しき者からお救いください。」
(マタイによる福音書6章9~13節)
という内容でした。ここで、私が特に注目したい箇所を太文字にしましたが、私たちが自分にとっての加害者を赦していくという行為です。このことは、とりわけ重要なために、主の祈りを教えられたすぐ後に、さらに、キリストは続けてこのように語られました。
「もしも、あなたがたが、人々のあやまちをゆるすならば、あなたがたの天の父も、
あなたがたをゆるして下さるであろう。もし人をゆるさないならば、あなたがたの
父も、あなたがたのあやまちをゆるして下さらないであろう。」
(マタイによる福音書6章14~15節)
たとえ自分に深くかかわりのあるような過去の忘れられない出来事や事件があったとしても、もしそれにこだわり続けたり、とらわれたり、翻弄されたりしながら生きていこうとするなら、それは絶対世界の根源の神との接点を自ら絶ってしまうことを意味します。
私たちは、過去という時間を超越した時、つまり、過去という呪縛から自由となった時に初めて、どんな相手であっても、あるがまま、そのまま包み込むように受け入れて、赦せるようになるのです。その時が、絶対世界の根源の神へのアクセスが開かれた時です。逆に、絶対世界の根源の神へのアクセスが開かれた時に、私たちは、どんな相手でも当たり前のように赦せるようになれるとも言えるでしょう。
ヨブのケース
絶対世界の根源の神から以前の2倍の祝福が戻ってくる直前に、ヨブは、ヨブの苦しみを一層強めることをしてしまった3人の友の過去を赦し、とりなしの祈りをささげました。これはヨブの軸足(●)が、今や根源の神への唯一の接点である十字架シンボリック座標の原点、絶対ゼロ座標(●)にあったことを物語っているのです。

ちなみに、災難・苦難にあう直前のヨブ の軸足があったのは、相対軸上ではずーっと右寄りの地点だったのです。
の軸足があったのは、相対軸上ではずーっと右寄りの地点だったのです。
左寄り 右寄り
悪・不義 

 善・義
善・義
![]()
もっと正確にいいますと、ヨブが未来に恐れおののきを抱いていた時は、下図の十字架シンボリック座標の●地点にいたのでした。

また、ヨブが自分の人生の中でなぜ災難・苦難が起こってしまったか(?)と、自分の過去のデータを一生懸命に検索して、その理由を探していた時には、下図の十字架シンボリック座標の●地点にいたのでした。

* * * 十字架座標から解く―先の者はあとになり、あとの者は先になる③
十字架座標から解く―先の者はあとになり、あとの者は先になる③
に 進む
トップページに戻る
“相対的世界”を表わしている相対軸
「狭い門からはいれ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、
そこからはいって行く者が多い。命にいたる門は狭く、その道は細い。
そして、それを見いだす者が少ない。」(マタイによる福音書7章13~14節)
「イエスは彼に言われた、“わたしは道であり、真理であり、命である。
だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない。”」
(ヨハネによる福音書14章6節)
このイエス・キリストは、父なる神(=絶対世界におられる根源なる神)への入り口、すなわち、アクセス可能なゲートがどこにあるか、父なる神(=絶対世界におられる根源なる神)に至る道は何であるかを私たちに伝えようとしておられたことがわかります。
時間軸(=十字架座標の縦軸)においては、父なる神(=絶対世界におられる根源なる神)にアクセス可能なゲートというのは、未来にでも過去にでもなく、実に私たちが生きているリアルタイムである“今”というこの一瞬一瞬(●)にのみ開かれていることを述べてきました。
未来 
過去
では、横軸である“相対世界”においては、父なる神(=絶対世界におられる根源なる神)へのゲートはどこに開かれているのでしょうか?
キリストの山上の説教の中に、実は、そのヒントが書いてあります。それは何かと申しますと、「人をさばくな」(マタイによる福音書7章1節)ということです。相対世界という二極に分極した世界に住んでいる私たちは、すべてのことを比較して判断した上で、それらに優劣をつけてみたり、善か悪かの識別をしたり、価値の有る無しを判定したりと・・・そのような発想の習慣を身に着けてしまっています。実は、私たちがそのような相対的な見方に捕らわれている限り、絶対世界へのゲートを見い出すことはできないのです。
絶対世界におられる父なる神(=絶対世界におられる根源なる神)というのは愛において完全であり、良い人と悪い人、敵と味方というふうな区別はなく、偏り見ることなく、一様にそのまま、あるがままを受け入れ、包み込んで愛して下さっておられる方なのです。私たちが想像してしているよりもはるかに、神の「愛は寛容であり、愛は情深い」(コリント第1の手紙13章4節)のです。このことをキリストは、山上の説教の中で次のように語られたのでした。
「『隣り人を愛し、敵を憎め』と言われていたことは、あなたがたの聞いている
ところである。しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者の
ために祈れ。こうして、天にいますあなたがたの父の子となるためである。
天の父は、悪い者の上にも良い者の上にも、太陽をのぼらせ、正しい者
にも正しくない者にも、雨を降らして下さるからである。あなたがたが自分を
愛する者を愛したからとて、なんの報いがあろうか。そのようなことは取税人
でもするではないか。兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのすぐれた事を
しているだろうか。そのようなことは異邦人でもしているではないか。それだから、
あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となり
なさい。」(マタイによる福音書5章43~48節)
そして、相対世界に住んでいる私たちが相対軸上で左寄りに偏ることなく、右寄りにも偏ることなく、相対軸の中心(=絶対ゼロ座標)にしっかりと立って、“神の視点”で相対世界でもろもろの現象、自分の人生の中で起こり得る1つ1つの出来事や人間模様をそのまま、あるがまま観て、包み込むようにして受容していく時に、絶対世界の存在に自ずと気づき、父なる神(=絶対世界におられる根源なる神)へのゲートが実に自分の目の前に開かれていることをやがてわかってくるのです。
左寄り  右寄り
右寄り
悪・不義(-)  絶対ゼロ座標
絶対ゼロ座標  善・義(+)
善・義(+)
![]()
以上、時間軸(縦軸)と相対軸(横軸)を別々にとらえてきましたが、これらの2つの軸をオーバーラップさせて垂直にクロスさせてみると、ここに“十字架シンボリック座標”が完成します。

この“十字架シンボリック座標”において、時間軸(縦軸)と相対軸(横軸)とが垂直に交わる交点(●)こそが、“十字架シンボリック座標”の“原点”であり、“絶対ゼロ次元”とも呼ばれる地点で、ここに相対世界に生きている私たち人間が父なる神(=絶対世界におられる根源なる神)にアクセスできる唯一のゲートが開かれているわけです。
繰り返して申しますが、時間軸において未来にも過去にもブレずに“今”この瞬間を生きること、それと同時に、相対的世界に住んでいながらも相対軸の左寄りにも右寄りにもブレずに生きる、さばかずに生きる、絶対世界におられる根源なる神の視点から 私たちがそれぞれ置かれている相対世界において起こるすべてのことをそのまま、あるがまま観て、受け入れていく時に私たちは絶対世界におられる根源なる神に至るゲートを通過して行くことになるのです。
次に進む
トップページに戻る
H22年9月12日(日)公開 ・ H22年9月15日(水)改訂更新!
「神は無秩序の神ではなく、平和の神である。」
(コリント第1の手紙14章33節)
聖書に啓示されている神というのは、無秩序の神ではなく、平和の神であり、“秩序”の神です。従って、そのような神を知っているゆえに使徒パウロも、以下のように勧めているわけです。
「すべてのことを適宜に、かつ秩序を正して行うがよい。」(コリント第1の手紙14章40節)
「たとい、わたしは肉体においては離れていても、霊においてはあなたがたと一緒にいて、
あなたがたの秩序正しい様子とキリストに対するあなたがたの強固な信仰とを見て、喜ん
でいる。」(コロサイ人への手紙2章5節)
無秩序は、混乱、カオス、争い、摩擦、不統合、不一致、不調和な状態を意味し、そこには“法則性”というものがみられません。一方、神には秩序、平和、一致、調和があり、そこには“法則性”というものを見つけることができるはずです。
理路整然とし、秩序だっている学問の中に、“数学”があります。私たちに数学の問題が与えられ、それを解くように言われた時に、もし私たちがそれをやみくもに解き明かそうと努力したとしても時間が膨大にかかったり、あるいは、解くことが困難なケースもあるわけです。しかし、誰かが発見した“公式”というものに当てはめてそのような問題を解いてみると、難なく、短時間のうちにアッという間に解けてしまうことになるのです。
これと同様に、“秩序”の神が監修(?)しておられる聖書の真理を解明しようとする時、あるいは、自分の人生に生じてしまった難しい問題を解こうと試みる時に、“公式”というものがあったとしたらどんなにか助かることでょう。また、これまで未解決のままずーっと保留してきた諸問題がスーッと消えていくかも知れません。
聖書には“奥義”というものがあります。
「そこで言われた、「あなたがたには、神の国の奥義を知ることが許されて
いるが、ほかの人たちには、見ても見えず、聞いても悟られないために、
譬で話すのである。」 (ルカによる福音書8章10節)
「願わくは、わたしの福音とイエス・キリストの宣教とにより、かつ、長き世々に
わたって、隠されていたが、今やあらわされ、預言の書をとおして、永遠の
神の命令に従い、信仰の従順に至らせるために、もろもろの国人に告げ
知らされた奥義の啓示によって、あなたがたを力づけることのできるかた、
すなわち、唯一の知恵深き神に、イエス・キリストにより、栄光が永遠より
永遠にあるように、アァメン。」 (ローマ人への手紙16章25~27節)
「御旨の奥義を、自らあらかじめ定められた計画に従って、わたしたちに
示して下さったのである。」(エペソ人への手紙1章9節)
「また、わたしが口を開くときに語るべき言葉を賜わり、大胆に福音の奥義を
明らかに示しうるように、わたしのためにも祈ってほしい。」
(エペソ人への手紙6章19節)
「その言の奥義は、代々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の
聖徒たちに明らかにされたのである。」 (コロサイ人への手紙1章26節)
「十字架の言は、滅び行く者には愚かであるが、救にあずかるわたしたちには、
神の力である。」 (コリント第1の手紙1章18節)
その奥義は、キリストが私たちに伝授しようとされた“秘伝”と言えます。そして、その奥義を解明していくためのヒントもキリストは山上の説教などに残されたわけです(十字架座標から解く―先の者はあとになり、あとの者は先になる②③を参照)。
それらを私なりに整理してまとめて“公式化”してみたのが、“十字架のシンボリック座標”と私が呼んでいるものなのです。

今後、この“キリストの十字架シンボリック座標”という“公式”を用いて、聖書の重要ながらも 一見謎めているように思える教えの数々を実際に紐解いていってみたいと思うわけです。
* * *
(H22年9月13日 公開) (H22年9月15日 改訂更新)
ヒトの人生の歩みは“ベクトル”
ヒトがこの相対世界の中で自分の人生を生きている時、通常、方向性をもっているものです。つまり、あるヒトは左寄りに向かって生きようとし(キリストのたとえ話の中の放蕩息子やキリストと共に十字架につけられた強盗たちがこのいい例です)、
悪・不義 


![]()
他のヒトはそれとは反対に右寄りに向かって生きようとするわけです(旧約聖書の災難・苦難に会う前のヨブもこのいい例です)。


 善・義
善・義
![]()
その人の価値観、考え方、判断で左方向か右方向へ向かって、自分の人生を選択しながら生きているわけです。すなわち、ヒトの人生の歩みというものは、“ベクトル”であり、それぞれのヒトは一定の方向性をもって与えられた人生を生きている存在と言えるのです。
さらに、これに時間軸の“過去”や“未来”の方向も加わると、ヒト(●)というのは実に様々な方向へ向かう“ベクトル”となって、色とりどりの人生、千差万別の人生というものが、この世という“相対世界”の中で営まれているのです。

* * * 次へ 進む * * *
トップページに戻る
H22年9月15日 更新(公開)
十字架上の強盗
「十字架にかけられた犯罪人(=強盗)のひとりが、「あなたはキリストではないか。
それなら、自分を救い、またわれわれも救ってみよ」と、イエスに悪口を言いつづけた。
もうひとりは、それをたしなめて言った、「おまえは同じ刑を受けていながら、神を
恐れないのか。お互は自分のやった事のむくいを受けているのだから、こうなった
のは当然だ。しかし、このかたは何も悪いことをしたのではない」。 そして言った、
“イエスよ、あなたが御国の権威をもっておいでになる時には、わたしを思い出して
ください”。イエスは言われた、“よく言っておくが、あなたはきょう、わたしと一緒に
パラダイスにいるであろう”。」(ルカによる福音書23章39~43節)
キリストの弟子のマタイは、この強盗について、「同時に、ふたりの強盗がイエスと一緒に、ひとりは右に、ひとりは左に、十字架につけられた。・・・一緒に十字架につけられた強盗どもまでも、同じようにイエスをののしった。」(マタイによる福音書27章38~44節)と記し、キリストの弟子のマルコも全く同じようなことをコメントしている(マルコによる福音書15章27~32節参照)。キリストの弟子のヨハネは、「彼らはそこで、イエスを十字架につけた。イエスをまん中にして、ほかのふたりの者を両側に、イエスと一緒に十字架につけた」(ヨハネによる福音書19章18節)とさりげなく記載しているだけです。同じ現場にいても、観る視点がだいぶ異なるものです。従って、十字架上の二人の強盗のうちの一人がキリストに神の国における救いを宣言された現場を見逃さず、注目していたのは福音書を記した弟子たちの中ではルカだけでした。
では、“相対世界”であるこの世の一般常識では神の国に絶対に救われるはずもないようなこの強盗(←神の救いから程遠い最も“あとの者”と見なされているのに)が、なぜキリストによって救いを保障されたのでしょうか? この世で神とキリストへの信仰を告白し、洗礼も受け、過去に立派な行ないの実績も持ち、日々神が要求される律法の義に近づこうとして自分を磨く努力を惜しまなかったような“先の者”があとに回され、逆に、この強盗のように善いことを自分の人生でほとんどやってこなかったような“あとの者”が、十字架で自分がやった罪の報いとして死刑に処せられ、まもなく死を迎えようとしていたこの強盗(=“あとの者”)なのに、何ゆえ“先の者”に先んじて キリストに神の国の救いを宣言されることになったのでしょうか? 実に私たちの誰もが首をかしげてしまいたくなるような“パラドックス”と言えます。この謎を解くことは、果たしてできるのでしょうか?
〔あとの者〕 〔先の者〕
悪・不義 




 善・義
善・義
![]()
“相対世界”での筋(スジ)を通して考えた場合、神の国の救いが提供されるためには、それなりに悪いことをやってきた人なら、まず報いや罰を受けて罪滅ぼしをした上で出直すとか、真に生まれ変わって自分の人生をもう一度 真面目にやり直してみるとか、自分が成長したことを具体的な実績で示して見せるとか、“悪”を離れて それとは正反対の“善”の方向に向かってわき目も振らずに邁進し、努力を惜しまず、怠惰にならず、一生懸命に善いわざに励み、忍耐力も働かせながら、これまでの自分とは全く違って、“善”の側で目を見張る程のレベルアップした自分を自他共に認めることができるようになっていく・・・。 キリスト教を信じているクリスチャンにとっては、キリストを信じることが大前提とした上で、神の聖なる律法を軽んじることなく、さらに言葉と行ないや日々の生活においても、それが“律法の要求する義”に照らしても太鼓判を押される程に成長したヒトこそが、神の国の救いに最も近いのであり、誰よりも先に神の国へのパスポートをゲットできるはず・・・と見るかも知れません。 果たして、本当にそうなのでしょうか? “絶対世界”においてもこのような考え方が通用するのでしょうか?
実は、“相対世界”で筋(スジ)が通ることであっても、“絶対世界”では全く筋(スジ)が通らないということが往々にしてあるのです。時間・空間・次元の中に組み込まれている“相対世界”に住んでいる私たちは、時間・空間・次元を超越しているところにある“絶対世界”におられる神”の“深い思い”を知らないがゆえに、私たちと“神”との間には、考え方、観る視点、とらえ方においてかなりのギャップが生じてしまっているのです。旧約聖書と新約聖書には、それぞれ次のように記されています。
「わが思いは、あなたがたの思いとは異なり、わが道は、あなたがたの道とは
異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、わが道は、あなたがたの
道よりも高く、わが思いは、あなたがたの思いよりも高い。」
(イザヤ書55章8~9節)
「いったい、人間の思いは、その内にある人間の霊以外に、だれが知っていようか。
それと同じように神の思いも、神の御霊以外には、知るものはない。」
(コリント第1の手紙2章11節)
「わたしは、彼らが神に対して熱心であることはあかしするが、その熱心は深い知識に
よるものではない。なぜなら、彼らは神の義を知らないで、自分の義を立てようと努め、
神の義に従わなかったからである。キリストは、すべて信じる者に義を得させるために、
律法の終りとなられたのである。」 (ローマ人への手紙10章2~4節)
さて、十字架につけられたキリストの両側では、強盗の罪を犯した犯罪人もまた十字架上にはりつけられていました。



強盗 キリスト 強盗
初めのうちは二人の強盗は一緒になって、キリストをののしっていました。ところが、そのうちの一人はどう思ったか、もう一人をたしなめて、「おまえは同じ刑を受けていながら、神を恐れないのか。お互は自分のやった事のむくいを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、このかたは何も悪いことをしたのではない」(ルカによる福音書23章40~41節)と言います。そして、その強盗は、続けてイエスに向かって言います、「イエスよ、あなたが御国の権威をもっておいでになる時には、わたしを思い出してください」(ルカによる福音書23章42節)と。
このように言った強盗に一体、何が起こったのでしょうか? 一方で、もう一人の強盗には何が起こらなかったのでしょうか?
* * * 次へ進む * * *
トップページに戻る
H22年9月17日公開、9月19日改訂更新
一つ前のセクションに戻って読み返す
つい先程まで、十字架上の二人の強盗は口をそろえてキリストを罵っていたのに、いつの間にか、そのうちの一人の強盗におけるキリストに対する観かたが急に変わってしまったことに皆さんはお気づきになられたでしょうか?
「お互は自分のやった事のむくいを受けているのだから、こうなったのは当然だ。
しかし、このかたは何も悪いことをしたのではない。」(ルカによる福音書23章41節)
自分の隣りで十字架刑を受けているキリストという方は、どんな罪で死刑を受けることになったかは具体的にはわからないながらも、自分たちと同様に十字架にはりつけにされるくらいだから、そのなりの犯罪でも犯したんだろうと・・・と考えてながら、始めのうちはこの二人の強盗はキリストを罵っていたと思います。この世の“相対基準”でキリストをさばこうとするならば、キリストのような“罪なき人”も死刑に値する極悪人にさえなってしまうのです。
ところが、二人の強盗うちの1人は長年にわたってもっていた“相対基準でさばく”というこの世的な“相対的な観かた”というものを“今”やめてしまったのです。言い換えれば、「人をさばくな」というキリストの山上の教えを無意識のうちに、この強盗は実行していたことになるのです。この強盗は“ワレに返って”冷静に、自分の目の前で十字架に自分たちと同じようにはりつけにされていたキリストを“今” 先入観、偏見、回りから刷り込まれた情報などにもはや捕らわれることなく、そのまま、あるがまま しっかりと見つめ、感受していったのでした。
すると、どうでしょう。この強盗は、“今”この瞬間 “相対世界の色眼鏡”で歪曲されていない“キリストの真実”が、また“キリストの内から溢れ出るように現わされていた“絶対根源の神の栄光の輝き”が リアルにハッキリと見え始めてきたようです。これまでのように“相対的な尺度”でこの世におけるあらゆる事象や現象などを比較・検討・評価し、その上で善悪や優劣や価値の有る無しを決めつけたり、レッテルを貼ったりしていくというような“相対的な思考プロセス”をキッパリとやめた時に、“絶対世界”に属する真理、真実、リアリティが何であるのかについて この強盗は気づくのです。十字架上で自分の死に直面してしていたこの強盗が 「お互は自分のやった事のむくいを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、このかたは何も悪いことをしたのではない」と相手の強盗をたしなめながら語ったこの言葉の中に、また、「イエスよ、あなたが御国の権威をもっておいでになる時には、わたしを思い出してください」と続けてイエス・キリストに言ったこの言葉の中に、“相対的尺度でさばく”ということをこの強盗がキッパリと捨て去ったという事実を読み取ることができます。つまり、この“相対世界”に充満している“霊的な闇”が長い間にわたって彼の心の目を厚く覆っていたのが、今や“絶対世界”における光の中でその闇が消え去り、“絶対基準”の中で様々な事象や現象の真実が見え出してきたことを意味しているわけです。
彼の心の中で現実に起こっていた大きな変化を、もちろん、キリストが見逃されるはずはありませんでした。すかさず、キリストはこの強盗に優しく語りかけます、「よく言っておくが、あなたはきょう、わたしと一緒にパラダイスにいるであろう」(ルカによる福音書23章43節)と。つまり、この強盗は今や“絶対世界”へ通じる“狭いゲート”(=“狭い門”)に軸足を確かに置いて、そして、そのゲートから“命の源なる絶対根源の神”へ至る“細い道”を確かな信仰によって歩み始めていたのです。
「狭い門からはいれ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、
そこからはいって行く者が多い。命にいたる門は狭く、その道は細い。
そして、それを見いだす者が少ない。」
(マタイによる福音書7章13~14節)
しかし、それだけではありません。この強盗はキリストに神の国への救いを宣言されるに先立って実は同時にもう1つとても重要で、かつ、貴重なプロセスを通っているのです。それは何かと申しますと、“時間を超越した”ということです。つまり、この強盗は“過去という時間”と“未来という時間”を超越していったのです。実は、“過去”と“未来”という両方の時間を超越しないと、“命の源なる絶対根源の神”のおられる“絶対世界”への“狭いゲート”の在りかを この“相対世界”において見い出せないものなのです。
キリストは山上の説教において、次のように述べておられます。
「だから、あすのことを思いわずらうな。あすのことは、あす自身が思いわずらうで
あろう。一日の苦労は、その日一日だけで十分である。」
(マタイによる福音書6章34節)
つまり、“未来”という“不確定な時間”、“リアルでない時間”というものにとらわれることなく、“今というこの時を生きる”ということです。もし、この強盗がこれから起こるであろう出来事、事象に心が捕らわれて生きようとするならば、間もなく自分が十字架上で命が絶たれてしまうという思いから、その重荷に押しつぶされそうになり、心に充満する“思い煩い”のために心の目が曇ってしまい“絶対世界”へのゲートの存在と所在を見い出すことができないばかりではなく、また、見い出そうとする心の余裕すらなかったことでしょう。 「あすのことを思いわずらうな」、すなわち、“今この瞬間を生きていく”ということは、実に私たちを“絶対世界”への“狭いゲート”を通過させて、“命の源である絶対根源の神”へ至る“細い道”へと進ませるための“重要なヒント”の1つだったのです。
「あすのことを思いわずらうな」(=“未来という時間”にとらわれずに“今を生きる”ということ)ということと同じくらい重要なことは、“過去という時間にとらわれずに生きる”ということです。このことについて、キリストは山上の説教の中で次にように述べられました。
「わたしたちに負債のある者をゆるしましたように、わたしたちの負債をもおゆるし
ください。・・・もしも、あなたがたが、人々のあやまちをゆるすならば、あなたがたの
天の父も、あなたがたをゆるして下さるであろう』(マタイによる福音書6章12~15節)
赦すということは、“過去という時間”に根をもっている限り 絶対にできない行為です。私たちが“過去という時間”を超越した時に初めて“赦す”ということが現実的に可能になるのです。過去に“誰かが自分に過ちを犯したという出来事に関する記憶”にこだわりを持ち続け、あくまでもそれに固執して、いつまでも過ぎ去ってしまった時間に根にもって生きている限り、“今、神から与えられている現実の人生”を輝かすことはできないのです。体は今を生きているはずなのに、心は過去の特定の時間にいつまでもいつまでも止まっているというような人々が、この“相対世界”に実際に多くおられる可能性があるのです。このように、体が“今という時間”に、心が“過去という時間”に分断されて、バラバラで不調和・不統合になっている時に、そこから“大きなストレス”というものが生み出されます。そして、そのようなストレスは知らないうちに、徐々にではあるかも知れませんが、着実にその人の心身を蝕んでいく可能性があるのです。そして、健康をジワジワと害していくかも知れないのです。
弟子のペテロに、「主よ、兄弟がわたしに対して罪を犯した場合、幾たびゆるさねばなりませんか。七たびまでですか」と尋ねられた時に、「わたしは七たびまでとは言わない。七たびを七十倍するまでにしなさい」とお答えになられたキリストは、実に私たちの想像をはるかに越えた寛容の愛の“絶対根源の神”について語っておられたのでした(マタイによる福音書18章21~22節)。
「たといわたしたちの心に責められるようなことがあっても、神はわたしたちの心よりも
大いなるかたであって、・・・。」 (ヨハネ第1の手紙3章20節)
キリストが現わそうとされた“絶対根源の神”の寛容の愛、永遠の愛、無償の愛のリアリティに私たちが気づかされ、触れ、感受し始めていく時に(=つまり、十字架のシンボリック座標の中心に私たちが回帰した時に)、私たちは“過去”へのこだわりがスーッと消え、もはや“過去”に囚われることも、執着することもなくなってしまうのです。また、“未来”に対しても思い煩うこともなくなり、“今というこの時”をイキイキと生きるということが本当の意味で私たちの体験となるのです。

* * * 次へ進む * * *
トップページに戻る
〔H22年9月21日公開〕
一つ前のセクションに戻って読み返す
私たちが“キリストの聖なる御名”をお題目のように ただ唱えれば、“絶対根源の神がおられる絶対世界”へ通じるゲートが私たちの目の前に自動的に開かれ、現われてくるというわけではありません。キリストが山上の垂訓の中に意図的に残していかれたヒントに示された神の御旨のままに実際に行なっていく時にこそ、そのゲートが私たちの前に開かれていくのです。
「わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいるのではなく、
ただ、天にいますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのである。その日には、
多くの者が、わたしにむかって『主よ、主よ、わたしたちはあなたの名によって
預言したではありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの
名によって多くの力あるわざを行ったではありませんか』と言うであろう。そのとき、
わたしは彼らにはっきり、こう言おう、『あなたがたを全く知らない。不法を働く者
どもよ、行ってしまえ』。 それで、わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、
岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。雨が降り、洪水が
押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、倒れることはない。岩を土台と
しているからである。 また、わたしのこれらの言葉を聞いても行わない者を、
砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り、洪水が
押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。そしてその倒れ方は
ひどいのである」。」 (マタイによる福音書7章21~27節)
ここでキリストが言及しておられるいわゆる“先の者”たちは、“過去”における自分たちがやってきた功績に囚われているのです。“過去の時間”に生きていて、“今という時間”を生きていないのです。また、彼らは“相対基準”からすべてのことを観る習慣をもっていて、天国に入っていっている人たちと自分たちを比較してみた時に、自分たちがこれまでやってきたことの方がはるかに優っていると考えているのです。つまり、彼らは、“過去という時間を超越していない”がゆえに、また、“相対軸上で生きている”ゆえに、神のおられる“絶対世界”への“ゲート”がどこにあるか、あるいは、どうやったらその“ゲート”が開かれるかを知らないでいるわけです。彼ら自身が主イエス・キリストに語っている言葉の中に、彼らが天国から締め出されてしまう 確かで十分な理由が実はあるのです。
十字架上の二人の強盗うちの一人は、キリストが山上の垂訓でヒントとして残していかれた“神の御旨”を無意識のうちに実行していたわけです。すなわち、「人をさばくな」と言われたように、この強盗はこの世の常である“相対基準”に照らして人や事象や現象などの善悪、優劣、価値の有る無しの判定をすることをやめ、“絶対基準から”、すなわち、“絶対根源の神が観る視点から”すべてのことをそのまま、あるがままに 包み込むように受容していくことを実行していったのでした。また、「あすのことを思いわずらうな」とキリストに言われたように、自分に身に間もなく起ころうとしていた“命が絶たれてしまう”という思いにも思い煩わされることなく、“まだ現実化していない未来という不確定な時間”に操られるのではなく、むしろそれを超越して、“今、この時に”自分自身をもあるがまま、そのまま受け入れ、さらに、自分の目の前に“今”現実におられるキリストをもあるがまま認め、そのまま受容していったのでした。さらに、この強盗は“過ぎ去った過去という時間”をも超越したのでした。「負債のある者をゆるし・・・、人々のあやまちをゆるす』というのキリストのメッセージの通り、彼は“自分の過去”(この強盗が犯罪を犯した遠因は、自分が生まれ育ってきた悪しき環境や人々の影響もあったかも知れないが、そのような過去のことにこだわったり、固執したりするのではなく)をそのまま受け入れ、とらわれることなく、むしろそれを超越していき、“今、この瞬間において”自分のすぐそば近くにおられて、“罪なき小羊”として十字架上で死のうとしておられたリアルなキリストをしっかりととらえ、受け入れていったのでした。 この時、この強盗は、実に “自分の人生を生きていく上での軸足”というものを十字架シンボリック座標の中心、原点、ゼロ座標点にしっかりと置いたと言えます。







“十字架上のキリスト”から溢れ出ていた“神の栄光”というのは、“神の純粋な愛”です。相対世界における相対基準を超越し、未来や過去という時間を超越した時にたどり着くところ、それは“相対軸”と“時間軸”が垂直に交わる“十字架シンボリック座標”の中心、ゼロ座標点です。この地点に立ったその時に、この強盗が感受したもの、見えてきたもの、それはこの“絶対根源の神の純粋な愛”だったと思われます。それは、私たちの想像をはるかに超えるような“寛容の愛”であり、“永遠に変わることのない愛”でもあり、私たちからの見返りや犠牲を求めたりすることもない“無償の愛”、“与えて、与えて、与えつくす愛、無尽蔵の愛”なのです。このような“絶対世界”におけるリアリティ、真実、真理がわかってくると、“からし種一粒ほどの信仰”が彼の心の中に生まれてくるのです。このような信仰は、“絶対根源の神の純粋な愛”を感受して生み出されてくるものであり、“絶対根源の神の純粋な愛”に呼応して“絶対根源の神”の方向に向かっていく“ベクトル”として、あたかも、“神の純粋な愛”に引き寄せられるかのように、グイグイと動き始めるのです。この“神の純粋な愛”こそが、この強盗ばかりではなく、私たち一人一人を真に生かしていくものであり、救う力そのものなのであり、私たちの人生そのものを祝福し輝かせていくものなのです。
「『・・・そして、わたしがこの地から上げられる時には、すべての人をわたしのところに
引きよせるであろう』。イエスはこう言って、自分がどんな死に方で死のうとしていたかを、
お示しになったのである。」(ヨハネによる福音書12章32~33節)
「しかし、まだ罪人であった時、わたしたちのためにキリストが死んで下さったことによって、
神はわたしたちに対する愛を示されたのである。」(ローマ人への手紙5章8節)
「愛さない者は、神を知らない。神は愛である。神はそのひとり子を世につかわし、彼に
よってわたしたちを生きるようにして下さった。それによって、わたしたちに対する
神の愛が明らかにされたのである。わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたち
を愛して下さって、わたしたちの罪のためにあがないの供え物として、御子をおつかわし
になった。ここに愛がある。」(ヨハネ第1の手紙4章8~10節)

十字架シンボリック座標における“ゼロ座標点(●)”、そこは私たちが住んでいる“相対世界”と、“絶対根源の神”がおられる“絶対世界”とがオーバーラップし交差する唯一の接点であり、“狭いゲート”があるところなのです。その“ゲート”は“狭い”とはいえ、 “絶対世界”におられる“命の源なる絶対根源の神”へ至る“細い道”が続いている“確かなゲート(入り口)”でもあるのです。



* * 次へ 進む * *
トップページに戻る