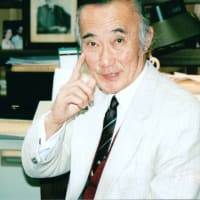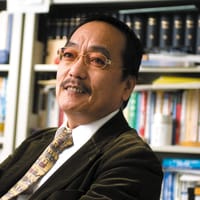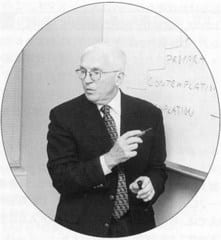
<プロチャスカ先生のTTMは禁煙行動形成の核プログラム>
私と健康心理学第8話 行動変容-2「タバコを止めた人から学ぶルール」
前回紹介した禁煙開始の院生二人は、六ヶ月の禁煙期間を過ぎ、禁煙成功者の仲間入りを果たした。今回は、禁煙成功者から行動変容のルールを学びたい。
禁煙スタートに大切な四要素
健康心理学では、半年間禁煙が続いたら、禁煙成功とみなすことにしている。前回お話しした禁煙を始めた院生二人は、この定義からすると二〇〇八年二月で無事禁煙成功者となったわけである。禁煙開始に至るまでの秘訣を整理しておこう。前回私は、四つの行動科学の用語をつかって解説した。
一 止めようという明確な「動機」があること
二 報酬、すなわち「強化刺激」が明確に存在すること
三 禁煙によって「得られることと、失うこと」を天秤にかけること
四 行動記録をとること、すなわち「セルフモニタリング」
など四つであった。これらの要素を彼ら二人は、自分なりに持ち合わせていた。私はただ、それらを積極的に活用するようアドバイスしただけであった。行動科学による禁煙などの行動修正は、無理やり他者が個人の行動を修正することではない。個人の自由意思に従って、禁煙したいという動機が生まれるのを待ち、行動変化のためのルールを活用して援助するに過ぎない。
TTMでみる禁煙ステージ
禁煙六ヶ月で禁煙成功とする定義は、プロチャスカのトランス・セオレティカル・モデル(TTM)という理論からきている。TTMでは、行動が変化するには5つの段階があると考える。禁煙に当てはめて考えてみよう。
一 前熟考期:たばこをやめるなどと考えたこともない無関心な段階
二 熟考期:たばこをやめることを考え始める段階。
三 準備期:たばこを止めようと決心がつき、止める計画をたてる準備の段階。
四 実行期:たばこを止めはじめるも、期間が六ヶ月以内。
五 維持期:たばこを止めて六ヶ月が過ぎ、禁煙状態が維持されている段階。
貴方はどの段階だろうか。私は禁煙を始めて八年八ヶ月なので、もちろん維持期にある。先の院生二人はちょうど六ヶ月の維持期に入り立てで、実行期から維持期に至る間の生々しい体験をやり過ごしたばかりである。
逆戻り防止策
実行期から維持期に至る間が一番辛い時期である。忘年会などの酒席は喫煙者がつきもの。誘惑も多く、一本吸ってしまうと終わり。一本が二本と増え、せっかくやめていた三ヶ月間が無駄となりがち。段階を後戻りしてしまう「逆戻り」である。
こうした逆戻りリスクを低下させるために彼らがどんな工夫をしたかを聞いた。
ニコチンバッチを効果的に利用したY君は、三ヶ月後にはニコチンパッチの容量を30mgのものから10mgへ下げ、使用頻度も減らし、四ヶ月目には不要となった。呼気中に含まれる一酸化炭素(CO)濃度は0になったという。ニコチンへの身体依存は克服したものの精神的依存は残る。家族が喫煙するので、逆戻りリスクは高かったが、彼は子どもへの間接喫煙を防ぐことが重要だと認識し、家族にも子どもの前では吸わないとルールを作り、自らのリスクにも対処した。
禁煙パイポで喫煙行動を代替したTさんは、早期に身体依存も消失し、喫煙再開による喘息症状悪化リスクを根絶したいという強い動機と家族のサポートが功を奏した。
彼ら二人に共通する要因にも注目したい。それは、彼ら自身が他の禁煙希望者のサポータとして活動したことである。また大学祭と禁煙科学学会で、自らの取り組みについて報告する機会を得たことも関係していそうだ。禁煙を志した人が抱く生々しい葛藤を、同じ目線で聞き取り、共感することのできる禁煙サポータという役割は、自身の認知的再統合にも役だつ。TTMの理論からこうした体験を整理し直し、後進の指導を行うためのマニュアル作りは、逆戻り防止のための「認知-行動」の絆を強化するのに役だったはずである。
生理心理学も貢献した。二人には、呼気中CO測定を定期的に測定してもらった。二人とも、禁煙期間の延長でCOは低下し、遂には0になることを身をもって知った。喫煙の客観的指標を得たことで、喫煙が健康に悪いこと、禁煙が健康によいことを目の当たりにしたわけである。自身にとっては理論を体験的に受け止め、冷静に理解するのに役だったという。他の禁煙希望者にもCO測定をしてもらったので、他者への説明にも役だつことを知った。
彼らは、逆戻り阻止の工夫を自分で考え実行した。「認知の鎧」を完璧に仕立て、見事に着こなしたわけである。今や彼らは後輩の院生達に禁煙サポータの役割を譲り、禁煙成功者として自立への道を歩き始めた。二度と逆戻りのないよう祈るばかりである。
余談:嫌悪療法による禁煙
実はもう一人、私の周りに維持期ほやほやの人がいる。彼は、四〇年間喫煙者であった。長い前熟慮期のあと、中年を迎えて健康への不安から熟慮期を過ごした。実行期へと一歩進んだきっかけは、昨年一月に参加した同窓会への出席であった。青春時代の想い出話に花が咲き、一泊二日の間に五箱、百本の紙巻きたばこを平らげた。喫煙者ばかりの集いは、温泉旅館の一室を副流煙で満たした。帰宅した翌日は二日酔いと喉の痛みなどで一服も吸わなかったとのこと。そしてそのまま一週間、一月と延長していった。あらゆる誘いにも動じず、無事半年を通過して、一年の禁煙期間を迎えた。
行動科学で彼の禁煙行動を解釈すると、いわゆる嫌悪療法に合致する。喫煙行動が、長時間不快な気分と対提示され続けることによって、喫煙行動を回避する新たな行動の回路が作られたわけである。こうした喫煙による嫌悪体験を演出することは、禁煙治療の動機作りに有効であることはわかっている。とくに理性豊かな中高年には、準備期から実行期に一気に引き上げる強い効果が期待できる。
筆者が毎週訪れる警察関係の施設は、数年前に喫煙コーナが設けられ、三年前からはガラスで囲われた喫煙室が設置されるに至った。聴聞や検査、研修、試験を終えた喫煙者達が、この狭い部屋で一服ふかす様は、さながら嫌悪療法室である。咳き込む人も多い。
ニコチン欠乏で身体が喫煙を求めても、不愉快な気分を回避したいという脳からの強い指令で、冷静な大人は禁煙行動をスタートさせることができる。次なる一手は、施設内に禁煙サポート室を作り、禁煙成功者による相談やサポートを開始することではないだろうか。
--------------------------------------
余計な注釈
呼気中に含まれる一酸化炭素CO濃度は、非喫煙者では0である。ところが先日ある小学生の呼気を調べたところ、僅かだが喫煙者並みの数値が出た。家族に喫煙者がいるか尋ねたところ、お父さんが大の愛煙家であった。副流煙による健康被害はこうして親から子へと及ぶ。数値を記録した用紙に間接喫煙の可能性をメモしてその子に渡したことは言うまでもない。
2008/2/25校了
私と健康心理学第8話 行動変容-2「タバコを止めた人から学ぶルール」
前回紹介した禁煙開始の院生二人は、六ヶ月の禁煙期間を過ぎ、禁煙成功者の仲間入りを果たした。今回は、禁煙成功者から行動変容のルールを学びたい。
禁煙スタートに大切な四要素
健康心理学では、半年間禁煙が続いたら、禁煙成功とみなすことにしている。前回お話しした禁煙を始めた院生二人は、この定義からすると二〇〇八年二月で無事禁煙成功者となったわけである。禁煙開始に至るまでの秘訣を整理しておこう。前回私は、四つの行動科学の用語をつかって解説した。
一 止めようという明確な「動機」があること
二 報酬、すなわち「強化刺激」が明確に存在すること
三 禁煙によって「得られることと、失うこと」を天秤にかけること
四 行動記録をとること、すなわち「セルフモニタリング」
など四つであった。これらの要素を彼ら二人は、自分なりに持ち合わせていた。私はただ、それらを積極的に活用するようアドバイスしただけであった。行動科学による禁煙などの行動修正は、無理やり他者が個人の行動を修正することではない。個人の自由意思に従って、禁煙したいという動機が生まれるのを待ち、行動変化のためのルールを活用して援助するに過ぎない。
TTMでみる禁煙ステージ
禁煙六ヶ月で禁煙成功とする定義は、プロチャスカのトランス・セオレティカル・モデル(TTM)という理論からきている。TTMでは、行動が変化するには5つの段階があると考える。禁煙に当てはめて考えてみよう。
一 前熟考期:たばこをやめるなどと考えたこともない無関心な段階
二 熟考期:たばこをやめることを考え始める段階。
三 準備期:たばこを止めようと決心がつき、止める計画をたてる準備の段階。
四 実行期:たばこを止めはじめるも、期間が六ヶ月以内。
五 維持期:たばこを止めて六ヶ月が過ぎ、禁煙状態が維持されている段階。
貴方はどの段階だろうか。私は禁煙を始めて八年八ヶ月なので、もちろん維持期にある。先の院生二人はちょうど六ヶ月の維持期に入り立てで、実行期から維持期に至る間の生々しい体験をやり過ごしたばかりである。
逆戻り防止策
実行期から維持期に至る間が一番辛い時期である。忘年会などの酒席は喫煙者がつきもの。誘惑も多く、一本吸ってしまうと終わり。一本が二本と増え、せっかくやめていた三ヶ月間が無駄となりがち。段階を後戻りしてしまう「逆戻り」である。
こうした逆戻りリスクを低下させるために彼らがどんな工夫をしたかを聞いた。
ニコチンバッチを効果的に利用したY君は、三ヶ月後にはニコチンパッチの容量を30mgのものから10mgへ下げ、使用頻度も減らし、四ヶ月目には不要となった。呼気中に含まれる一酸化炭素(CO)濃度は0になったという。ニコチンへの身体依存は克服したものの精神的依存は残る。家族が喫煙するので、逆戻りリスクは高かったが、彼は子どもへの間接喫煙を防ぐことが重要だと認識し、家族にも子どもの前では吸わないとルールを作り、自らのリスクにも対処した。
禁煙パイポで喫煙行動を代替したTさんは、早期に身体依存も消失し、喫煙再開による喘息症状悪化リスクを根絶したいという強い動機と家族のサポートが功を奏した。
彼ら二人に共通する要因にも注目したい。それは、彼ら自身が他の禁煙希望者のサポータとして活動したことである。また大学祭と禁煙科学学会で、自らの取り組みについて報告する機会を得たことも関係していそうだ。禁煙を志した人が抱く生々しい葛藤を、同じ目線で聞き取り、共感することのできる禁煙サポータという役割は、自身の認知的再統合にも役だつ。TTMの理論からこうした体験を整理し直し、後進の指導を行うためのマニュアル作りは、逆戻り防止のための「認知-行動」の絆を強化するのに役だったはずである。
生理心理学も貢献した。二人には、呼気中CO測定を定期的に測定してもらった。二人とも、禁煙期間の延長でCOは低下し、遂には0になることを身をもって知った。喫煙の客観的指標を得たことで、喫煙が健康に悪いこと、禁煙が健康によいことを目の当たりにしたわけである。自身にとっては理論を体験的に受け止め、冷静に理解するのに役だったという。他の禁煙希望者にもCO測定をしてもらったので、他者への説明にも役だつことを知った。
彼らは、逆戻り阻止の工夫を自分で考え実行した。「認知の鎧」を完璧に仕立て、見事に着こなしたわけである。今や彼らは後輩の院生達に禁煙サポータの役割を譲り、禁煙成功者として自立への道を歩き始めた。二度と逆戻りのないよう祈るばかりである。
余談:嫌悪療法による禁煙
実はもう一人、私の周りに維持期ほやほやの人がいる。彼は、四〇年間喫煙者であった。長い前熟慮期のあと、中年を迎えて健康への不安から熟慮期を過ごした。実行期へと一歩進んだきっかけは、昨年一月に参加した同窓会への出席であった。青春時代の想い出話に花が咲き、一泊二日の間に五箱、百本の紙巻きたばこを平らげた。喫煙者ばかりの集いは、温泉旅館の一室を副流煙で満たした。帰宅した翌日は二日酔いと喉の痛みなどで一服も吸わなかったとのこと。そしてそのまま一週間、一月と延長していった。あらゆる誘いにも動じず、無事半年を通過して、一年の禁煙期間を迎えた。
行動科学で彼の禁煙行動を解釈すると、いわゆる嫌悪療法に合致する。喫煙行動が、長時間不快な気分と対提示され続けることによって、喫煙行動を回避する新たな行動の回路が作られたわけである。こうした喫煙による嫌悪体験を演出することは、禁煙治療の動機作りに有効であることはわかっている。とくに理性豊かな中高年には、準備期から実行期に一気に引き上げる強い効果が期待できる。
筆者が毎週訪れる警察関係の施設は、数年前に喫煙コーナが設けられ、三年前からはガラスで囲われた喫煙室が設置されるに至った。聴聞や検査、研修、試験を終えた喫煙者達が、この狭い部屋で一服ふかす様は、さながら嫌悪療法室である。咳き込む人も多い。
ニコチン欠乏で身体が喫煙を求めても、不愉快な気分を回避したいという脳からの強い指令で、冷静な大人は禁煙行動をスタートさせることができる。次なる一手は、施設内に禁煙サポート室を作り、禁煙成功者による相談やサポートを開始することではないだろうか。
--------------------------------------
余計な注釈
呼気中に含まれる一酸化炭素CO濃度は、非喫煙者では0である。ところが先日ある小学生の呼気を調べたところ、僅かだが喫煙者並みの数値が出た。家族に喫煙者がいるか尋ねたところ、お父さんが大の愛煙家であった。副流煙による健康被害はこうして親から子へと及ぶ。数値を記録した用紙に間接喫煙の可能性をメモしてその子に渡したことは言うまでもない。
2008/2/25校了