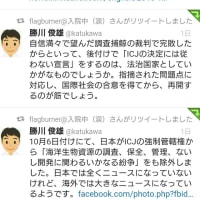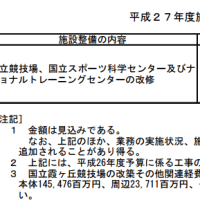2014年の上半期で一番印象に残った話題といえば、国際司法裁判所(ICJ)でオーストラリア政府が日本政府が行ってる南極海「調査捕鯨」の中止を求める訴えに関する判決が下されたこと。
判決は、南極海「調査捕鯨」は「科学的」でないとして国際捕鯨委員会(IWC)の条約違反と判定→日本政府が持ってた南極海「調査捕鯨」の許可を取り上げるものだった。
これに対し、日本政府は懲りずに「調査捕鯨」の続行を宣言→今年の国際捕鯨委員会(IWC)で見事に各国から反発を受ける結果となった。
とはいえ、この判決の影響は相当なもので、日本政府は敗訴の原因について色々分析していた。
これに関して、先月参議院の外交防衛委員会で意味深なやりとりが行われていた・・・。
・第187回国会 外交防衛委員会 第7号(2014年11月13日 kokkai.ndl.go.jp)
問題の場面は、岸田 文雄(Fumio KISHIDA)外務大臣と佐藤 ゆかり(Yukari SATOH)議員、秋葉 剛男(Takeo AKIBA)外務省国際法局局長と都築 政則(Masanori TSUZUKI)法務大臣官房訟務総括審議官とのやりとり。
以下、2014年11月13日分 kokkai.ndl.go.jp『第187回国会 外交防衛委員会 第7号』からその部分を(略)
---- 以下引用 ----
(中略)
○佐藤 ゆかり君 自由民主党の佐藤 ゆかりでございます。
今日は、南極海の調査捕鯨の差止め訴訟で日本が全面敗訴した件から始めたいと思います。
今年の三月三十一日に、国際司法裁判所にオーストラリアが提訴した第二期南極海調査捕鯨、いわゆるJARPA IIですけれども、この訴訟で調査捕鯨の差止め判決が言い渡され、日本の完全敗訴となりました。
一方で、実は今年の四月、要するにこの完全敗訴から一月以内の出来事ですが、同じオーストラリアに対して日豪EPA協定の交渉を日本は当時行っておりましたけれども、この日豪EPA協定はこの四月に大筋合意に達しております。
南極海の調査捕鯨敗訴確定から一月以内のことでありました。
そこで、岸田大臣へお伺いしたいと思いますが、日豪EPAをオーストラリアから勝ち取る代わりに調査捕鯨の方は敗訴を認めるよとか、そういったオーストラリアとの内々のバーターといいますか、あるいはそういう方向にオーストラリアを誘導するような日本側の戦略といいますか、そういったものが、交渉戦略があったかどうか、確認させてください。
○国務大臣(岸田 文雄君) 日豪EPA交渉につきましては、七年余りにわたりまして、我が国は、国益にかなう最善の道を追求すべく、政府一体となって取り組んでまいりました。
結果、国益にかない、我が国として利益になる協定を実現することができた、成果を得たと考えております。
捕鯨について日豪間で立場の相違があることは事実ですが、日豪EPAにつきましては、両国間におきまして、貿易、投資を促進させる、あるいは関係を強化する、そして地域のルール作りに資するといった意義があることから、締結をいたしました。
そして一方、この捕鯨問題に関する我が国の基本方針については、これまで豪州に対して度々説明してきているところでもあり、今後も国際社会の理解を求めていく考えであります。
このように、それぞれにつきまして、我が国としましては政府一丸となって全力で努力をしてきた次第であります。
○佐藤 ゆかり君 そうしますと、日本政府の目的として、この調査捕鯨訴訟及び日豪EPAの交渉の双方において勝つことを目指していたということだと御答弁いただいたと思います。
そこでお伺いしたいんですが、ちょっと具体的になりますけれども、この調査捕鯨訴訟で昨年六月から七月の間に口頭弁論が国際司法裁判所で実施されました。
日本側の専門家の証人、そして政府弁護人として登用したのがオスロ大学名誉教授のラース・ワロー氏、及び弁護人の一人としてエジンバラ大学教授のアラン・ボイル氏を任命しております。
このお二方の任命理由というのは何だったでしょうか。
事務方にお願いします。
○政府参考人(秋葉 剛男君) ICJの場における証人につきましては、近年のICJ判決におきまして、当事国の補佐人ないし弁護団の一員としての専門家による証言の有用性に疑義が呈されました。
すなわち、科学者が科学的見地に従って意見を述べる場合は、弁護団としてよりも、鑑定人ないし証人としてICJの場に出てくることが望ましいという判決がございました。
そうした事情があることから、我が国として、欧州における学術団体会長を務め、長年にわたって国際捕鯨委員会の科学委員会へ参加してきたワロー教授から、ノルウェーの捕鯨国としての立場を踏まえ、科学委員会における我が国に有利な議論を独立した立場から御提起をいただくべく紹介させていただいたということがございます。
それからボイル教授につきましては、この方は弁護団の一員として我々が任命させていただきました。
この方は、国際法としての海洋法及び環境法の分野に精通しておられ、またICJにおける訴訟に弁護人として参加して業績を積んでこられた方でございます。
そうした理由から、顧問団、弁護団の一員として任命させていただいたという経緯でございます。
○佐藤 ゆかり君 そうしますと、このJARPA IIの訴訟の争点の一つ、今おっしゃられましたように、その科学的根拠で、日本の調査捕鯨というものがいかに調査捕鯨として統計的に大規模な展開が必要であるかということを科学的に立証するということが争点の一つであったわけであります。
ともすれば、調査捕鯨という名目の下で商業捕鯨ではなかろうかというような疑義も一部の国から言われている中で、どうやって科学的にそうではないということを立証するかということが一つの争点でありました。
そこで、この日本の調査計画にある最大年間捕獲枠ですね、JARPA IIで日本が提出している計画では、実際のところ、ミンククジラが年間九百三十五頭、ザトウクジラ五十頭、ナガスクジラ五十頭の規模で計画を提出しておりまして、これが規模的に大き過ぎる、商業捕鯨ではないかということが言われておりまして、こうしたことに対する科学的立証が必要であったと。
それに対して、日本側で登用したこの専門家の証人、まずオスロ大学のラース・ワロー名誉教授が昨年口頭弁論で陳述をされた一部引用しますと、ザトウクジラとナガスクジラは調査捕鯨の対象に含まれるべきではない、また、ミンククジラの捕獲枠がなぜこの頭数に設定されたのか本当のところ分からないという、JARPA IIに疑義をあたかも投じているかのごとくの想定外のコメントを陳述をしております。
また、日本政府の弁護人のエジンバラ大学アラン・ボイル教授も、この規模の統計的な妥当性については日本の捕獲の頭数が何を意味するのか私はまるで分からないと批判めいた陳述をしているわけであります。
ですから、JARPA IIのこの捕獲規模ですとか捕獲方法に疑義が上がったわけでありますが、日本側が任命した証人や弁護人が口頭弁論で疑問を唱えるという、むしろこの訴訟戦術上不手際とも見られることが致命傷になったという指摘をする専門家もあるわけでありますが、この対応についてまずかったというふうに、事務方、思いませんでしょうか。
○政府参考人(秋葉 剛男君) そもそも、先ほど申し上げましたように、証人という方は独立した立場で御意見を述べる、そして宣誓の上、意見を述べられる、御自身の真実と思うところを述べるという制度でございます。
その人に対して、裁判官あるいは相手方から、いわゆるクロスエグザミネーションということも可能になるということでございます。
現にオーストラリア側の証人も、オーストラリアの主張に反することを証言されたという経緯もございます。
例えば、鯨を殺さなければ得られないデータもあるというような証言もしております。
いずれにしましても、独立した立場から証言していただくということが本旨でございます。
そして、その上で、我々が依頼したラーズ・ワロー教授は、ミンククジラ、最も重要な鯨、我々の捕鯨にとって最も重要な鯨、頭数の多い鯨ですが、その数については妥当であるという証言をしていただいたわけでございます。
それから、佐藤先生の御指摘の発言もあったのは事実だと思います。
その点につきましては、裁判所が判示した七つの理由、国際捕鯨条約八条一項の調査捕鯨の特別許可に関する条件、発給の条件として七つの基準ということを言いましたけれども、ワロー教授の指摘した点はそのうちの一部。
さらに、その一部についても、裁判所は独自の意見で、ワロー教授の意見プラス独自の意見で判示をしたということでございますので、このワロー教授の発言があったから結果がどうなったということはなかなか確定的なことは言えないということだと考えております。
○佐藤 ゆかり君 法廷闘争というのはやはり闘いでありますから、どのように闘争を進めていくかという戦略というのは極めて大事であるという意味で、少し今回の対応には問題があったのではないかという指摘が多いとおりであります。
実際、外務省はもう訴訟から通商交渉から全て外交案件を多数抱えて大変忙しい省でありまして、そういう意味では、外交関係の窓口として、ある意味多数の案件を抱えた言わば私はジェネラリストだというふうに考えるわけでございます。
そういう意味で、今回、捕鯨調査に対する訴訟案件をジェネラリストである外務省が窓口になったということについて少し、それで本当に体制としてよかったのかということが疑問に思われるわけでありますが、実際のところ、この調査捕鯨訴訟で提訴国のオーストラリアがどうであったかと申しますと、オーストラリア政府の代理人は法の番人である司法長官が務めました。
そして、弁護人団も、司法副長官、司法省司法参与等、政府代理人と弁護人七人中四人が司法畑で固めております。
一方、日本はどうであったかというと、政府代理人は外務審議官でした。
そして、弁護人、代理人合わせた八人中六人が大学教授、そして司法専門家の登用は全くゼロであったということでございます。
そこで、法務省にお伺いしたいんですけれども、司法省が前面に出たオーストラリアに対して、ジェネラリストの外務省が法廷闘争に当たる日本の体制が一つの敗因ではなかったかと私は考えるわけでありますが、国際法上の訴訟事案が増えると今後想定しますと、こうした国際司法裁判所に法務大臣が関われるような体制が必要ではないかと思いますが、現体制では法務大臣権限法でこうした関わりはできるのでしょうか。
○政府参考人(都築 政則君) 国を当事者とする訴訟につきましては、今御指摘のいわゆる法務大臣権限法に基づきまして法務大臣が国を代表するということになっております。
海外の裁判所に我が国を当事者とする訴訟等が提起された場合にも、ただいま申し上げました法務大臣権限法によりまして法務省が対応することは可能でありますが、我が国では慣行的に外務省が直接の窓口となっておりまして、法務省においてはこれまでそれを尊重してきたところであります。
他方、国際司法裁判所等の国際法上の司法手続は、先ほど申し上げました法務大臣権限法が適用される訴訟ではないというふうに解されておりまして、現行法の下では法務省が国際法上の司法手続に直接関与することとなってはおりません。
ただし、国際司法手続におきましても、国内の訴訟における事実認定や証拠の評価における知見やノウハウを活用できると思われる場面も多々あろうかと思います。
今後は、法務省としましても、広角的に国際訴訟等へ関与していくことが必要であるというふうに考えているところでありまして、その前提といたしまして訟務体制を強化することは不可欠であるというふうに考えておりまして、予算概算要求におきまして訟務局の新設や訟務体制の強化の充実を要求させていただいているところであります。
○佐藤 ゆかり君 ちょっと時間がないので御答弁を短くしていただきたいと思いますが、国際司法裁判所では法務大臣が出ていく法的根拠がないという御答弁でありました。
是非、岸田大臣、こういった外交関係、これから国際司法裁判所を使った訴訟事案というのは増えるということも想定しますと、外務省と法務省との連携強化という意味で法務大臣権限法を改正する部分というのがあろうかと思われるんですが、その辺りは検討をお願いしたいというふうに思います。
(以下略)
---- 引用以上 ----
要は、日本政府側は、ICJにおける裁判に関する準備があまり行っていなかったということになる。
実際、真田 康弘(Yasuhiro SANADA)氏はこの裁判に関する見解を今年5月に公開した際、オーストラリア政府と日本政府の裁判における姿勢の差を指摘していた。。
・捕鯨判決とその後の展開(2014年11月7日 ika-net.jp;再紹介申し訳)
以下、2014年11月7日分 ika-net.jp『捕鯨判決とその後の展開』から『2. 日本側の敗因』を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
2. 日本側の敗因
こうした判決となった理由として、以下のものが考えられる。
第一に、口頭弁論に先立って行われていた豪州側と日本側で日本側の訴訟書面の「出来」の問題がある。豪州側の申述書は文章自体は本文だけでも280 ページに及び、必ずしも短くはないが、豪州側が強調したい事実やフレーズは繰り返して強調するなど、統一したストーリー展開が感じられ、この問題についての前提知識がなくとも容易に読めるような工夫が凝らされた書面であったと思料される。
この問題で重要となるであろう日本語の資料をくまなく調べ上げ書証として引用している。
これに対し日本側の答弁書は本文の分量でも豪州の1.5 倍と分量的には遥かに上回るのだが、全体的に冗長であることに加え、法律論の部分と科学議論の部分との部分は全く違った書きぶりで、官僚や担当者が縦割りで作成したような印象が拭えなかった。
なぜこの頭数の捕獲が必要か、なぜJARPA IとJARPA IIでサンプル数が大きく異なるのか等といった科学的説明も、これまでIWCなどに提出した文書をただなぞっただけのような内容になっており、説得力に乏しかった。
ICJ提訴という戦略については、豪州政府部内で「勝ち目があるのか」との異論もあったが、仄聞するところによると、届いた答弁書を読んだ豪州側は、かえって「日本側の弱点に気が付いた」との印象を持ったようである。
第二に、豪州側の巧みな専門家証人への反対尋問の活用などの訴訟指揮、及び日本側の口頭弁論での失敗、特に日本側専門家証人のラース・ワロー教授の証言を挙げる必要がある。
ICJの口頭弁論は、各国の弁護人が丁々発止にやり合うかたちではなく、1週毎に日豪が入れ替わって一方的に発言する形式を取っていた。
従って双方は事前に準備した上で相手側の主張に答えることができる。
ところが専門家に対する証人尋問では唯一例外的に、質疑形式の反対尋問の時間が設けられている。
豪州側はこの機会を十全に活用し、日本側証人のワロー教授を激しく攻め立てた。
この結果豪州は、ワロー教授から「ナガスクジラの調査計画については気に入ってはいない。これでは何も情報は得られない。ザトウクジラも問題だ」「ナガス・ザトウとミンクでサンプル数計算の根拠が違っている理由はわからない」「ザトウは獲らなくても生態系モデルを構築できる」という発言を引き出すことに成功した。
判決の行方を決定づける証言であった。
他方日本側は、専門家に対する反対尋問で持ち時間を半分程度しか使わなかったばかりか、捕獲頭数の設定について「私にもさっぱりわからない」(日本側弁護人アラン・ボイル教授の発言)と述べるなどの失点が目立った。
捕獲計画頭数は科学的に算定されたと主張する一方で、実際の捕獲頭数が計画と大幅に異なっていることについて、その頭数でも調査目的は達成できるとの弁明も行っているが、ならば捕獲頭数を大幅に少なくする、あるいはゼロでもよくなってしまうことになる。
日本の科学面での弁論は論理破綻を来していたと言える。
(以下略)
―――― 引用以上 ----
こうして振り返ると、例の裁判で日本政府が負けたのは「まさか」じゃなくて「やっぱり」というか「またか」という感が否めない。
相手側の対応を見極めることもできなかったのはともかく(これはこれで問題だが)、裁判に臨む態勢すら整えられなかったのだから本当に呆れるしかない。
一応、オーストラリア政府と(ニュージランド政府)による訴えに関する書面審理終結(2012年5月)から最初の口頭弁論まで1年以上の時間はあったはずなのに、その間日本政府の方々は何をやっていたのやら・・・。
っていうか、負けるべくして負けたこの裁判に関して「日本側の主張が認められた云々」と言い張る一部の人達は、本当の問題点に気づいていないかあるいは無視してるとしか・・・。
判決は、南極海「調査捕鯨」は「科学的」でないとして国際捕鯨委員会(IWC)の条約違反と判定→日本政府が持ってた南極海「調査捕鯨」の許可を取り上げるものだった。
これに対し、日本政府は懲りずに「調査捕鯨」の続行を宣言→今年の国際捕鯨委員会(IWC)で見事に各国から反発を受ける結果となった。
とはいえ、この判決の影響は相当なもので、日本政府は敗訴の原因について色々分析していた。
これに関して、先月参議院の外交防衛委員会で意味深なやりとりが行われていた・・・。
・第187回国会 外交防衛委員会 第7号(2014年11月13日 kokkai.ndl.go.jp)
問題の場面は、岸田 文雄(Fumio KISHIDA)外務大臣と佐藤 ゆかり(Yukari SATOH)議員、秋葉 剛男(Takeo AKIBA)外務省国際法局局長と都築 政則(Masanori TSUZUKI)法務大臣官房訟務総括審議官とのやりとり。
以下、2014年11月13日分 kokkai.ndl.go.jp『第187回国会 外交防衛委員会 第7号』からその部分を(略)
---- 以下引用 ----
(中略)
○佐藤 ゆかり君 自由民主党の佐藤 ゆかりでございます。
今日は、南極海の調査捕鯨の差止め訴訟で日本が全面敗訴した件から始めたいと思います。
今年の三月三十一日に、国際司法裁判所にオーストラリアが提訴した第二期南極海調査捕鯨、いわゆるJARPA IIですけれども、この訴訟で調査捕鯨の差止め判決が言い渡され、日本の完全敗訴となりました。
一方で、実は今年の四月、要するにこの完全敗訴から一月以内の出来事ですが、同じオーストラリアに対して日豪EPA協定の交渉を日本は当時行っておりましたけれども、この日豪EPA協定はこの四月に大筋合意に達しております。
南極海の調査捕鯨敗訴確定から一月以内のことでありました。
そこで、岸田大臣へお伺いしたいと思いますが、日豪EPAをオーストラリアから勝ち取る代わりに調査捕鯨の方は敗訴を認めるよとか、そういったオーストラリアとの内々のバーターといいますか、あるいはそういう方向にオーストラリアを誘導するような日本側の戦略といいますか、そういったものが、交渉戦略があったかどうか、確認させてください。
○国務大臣(岸田 文雄君) 日豪EPA交渉につきましては、七年余りにわたりまして、我が国は、国益にかなう最善の道を追求すべく、政府一体となって取り組んでまいりました。
結果、国益にかない、我が国として利益になる協定を実現することができた、成果を得たと考えております。
捕鯨について日豪間で立場の相違があることは事実ですが、日豪EPAにつきましては、両国間におきまして、貿易、投資を促進させる、あるいは関係を強化する、そして地域のルール作りに資するといった意義があることから、締結をいたしました。
そして一方、この捕鯨問題に関する我が国の基本方針については、これまで豪州に対して度々説明してきているところでもあり、今後も国際社会の理解を求めていく考えであります。
このように、それぞれにつきまして、我が国としましては政府一丸となって全力で努力をしてきた次第であります。
○佐藤 ゆかり君 そうしますと、日本政府の目的として、この調査捕鯨訴訟及び日豪EPAの交渉の双方において勝つことを目指していたということだと御答弁いただいたと思います。
そこでお伺いしたいんですが、ちょっと具体的になりますけれども、この調査捕鯨訴訟で昨年六月から七月の間に口頭弁論が国際司法裁判所で実施されました。
日本側の専門家の証人、そして政府弁護人として登用したのがオスロ大学名誉教授のラース・ワロー氏、及び弁護人の一人としてエジンバラ大学教授のアラン・ボイル氏を任命しております。
このお二方の任命理由というのは何だったでしょうか。
事務方にお願いします。
○政府参考人(秋葉 剛男君) ICJの場における証人につきましては、近年のICJ判決におきまして、当事国の補佐人ないし弁護団の一員としての専門家による証言の有用性に疑義が呈されました。
すなわち、科学者が科学的見地に従って意見を述べる場合は、弁護団としてよりも、鑑定人ないし証人としてICJの場に出てくることが望ましいという判決がございました。
そうした事情があることから、我が国として、欧州における学術団体会長を務め、長年にわたって国際捕鯨委員会の科学委員会へ参加してきたワロー教授から、ノルウェーの捕鯨国としての立場を踏まえ、科学委員会における我が国に有利な議論を独立した立場から御提起をいただくべく紹介させていただいたということがございます。
それからボイル教授につきましては、この方は弁護団の一員として我々が任命させていただきました。
この方は、国際法としての海洋法及び環境法の分野に精通しておられ、またICJにおける訴訟に弁護人として参加して業績を積んでこられた方でございます。
そうした理由から、顧問団、弁護団の一員として任命させていただいたという経緯でございます。
○佐藤 ゆかり君 そうしますと、このJARPA IIの訴訟の争点の一つ、今おっしゃられましたように、その科学的根拠で、日本の調査捕鯨というものがいかに調査捕鯨として統計的に大規模な展開が必要であるかということを科学的に立証するということが争点の一つであったわけであります。
ともすれば、調査捕鯨という名目の下で商業捕鯨ではなかろうかというような疑義も一部の国から言われている中で、どうやって科学的にそうではないということを立証するかということが一つの争点でありました。
そこで、この日本の調査計画にある最大年間捕獲枠ですね、JARPA IIで日本が提出している計画では、実際のところ、ミンククジラが年間九百三十五頭、ザトウクジラ五十頭、ナガスクジラ五十頭の規模で計画を提出しておりまして、これが規模的に大き過ぎる、商業捕鯨ではないかということが言われておりまして、こうしたことに対する科学的立証が必要であったと。
それに対して、日本側で登用したこの専門家の証人、まずオスロ大学のラース・ワロー名誉教授が昨年口頭弁論で陳述をされた一部引用しますと、ザトウクジラとナガスクジラは調査捕鯨の対象に含まれるべきではない、また、ミンククジラの捕獲枠がなぜこの頭数に設定されたのか本当のところ分からないという、JARPA IIに疑義をあたかも投じているかのごとくの想定外のコメントを陳述をしております。
また、日本政府の弁護人のエジンバラ大学アラン・ボイル教授も、この規模の統計的な妥当性については日本の捕獲の頭数が何を意味するのか私はまるで分からないと批判めいた陳述をしているわけであります。
ですから、JARPA IIのこの捕獲規模ですとか捕獲方法に疑義が上がったわけでありますが、日本側が任命した証人や弁護人が口頭弁論で疑問を唱えるという、むしろこの訴訟戦術上不手際とも見られることが致命傷になったという指摘をする専門家もあるわけでありますが、この対応についてまずかったというふうに、事務方、思いませんでしょうか。
○政府参考人(秋葉 剛男君) そもそも、先ほど申し上げましたように、証人という方は独立した立場で御意見を述べる、そして宣誓の上、意見を述べられる、御自身の真実と思うところを述べるという制度でございます。
その人に対して、裁判官あるいは相手方から、いわゆるクロスエグザミネーションということも可能になるということでございます。
現にオーストラリア側の証人も、オーストラリアの主張に反することを証言されたという経緯もございます。
例えば、鯨を殺さなければ得られないデータもあるというような証言もしております。
いずれにしましても、独立した立場から証言していただくということが本旨でございます。
そして、その上で、我々が依頼したラーズ・ワロー教授は、ミンククジラ、最も重要な鯨、我々の捕鯨にとって最も重要な鯨、頭数の多い鯨ですが、その数については妥当であるという証言をしていただいたわけでございます。
それから、佐藤先生の御指摘の発言もあったのは事実だと思います。
その点につきましては、裁判所が判示した七つの理由、国際捕鯨条約八条一項の調査捕鯨の特別許可に関する条件、発給の条件として七つの基準ということを言いましたけれども、ワロー教授の指摘した点はそのうちの一部。
さらに、その一部についても、裁判所は独自の意見で、ワロー教授の意見プラス独自の意見で判示をしたということでございますので、このワロー教授の発言があったから結果がどうなったということはなかなか確定的なことは言えないということだと考えております。
○佐藤 ゆかり君 法廷闘争というのはやはり闘いでありますから、どのように闘争を進めていくかという戦略というのは極めて大事であるという意味で、少し今回の対応には問題があったのではないかという指摘が多いとおりであります。
実際、外務省はもう訴訟から通商交渉から全て外交案件を多数抱えて大変忙しい省でありまして、そういう意味では、外交関係の窓口として、ある意味多数の案件を抱えた言わば私はジェネラリストだというふうに考えるわけでございます。
そういう意味で、今回、捕鯨調査に対する訴訟案件をジェネラリストである外務省が窓口になったということについて少し、それで本当に体制としてよかったのかということが疑問に思われるわけでありますが、実際のところ、この調査捕鯨訴訟で提訴国のオーストラリアがどうであったかと申しますと、オーストラリア政府の代理人は法の番人である司法長官が務めました。
そして、弁護人団も、司法副長官、司法省司法参与等、政府代理人と弁護人七人中四人が司法畑で固めております。
一方、日本はどうであったかというと、政府代理人は外務審議官でした。
そして、弁護人、代理人合わせた八人中六人が大学教授、そして司法専門家の登用は全くゼロであったということでございます。
そこで、法務省にお伺いしたいんですけれども、司法省が前面に出たオーストラリアに対して、ジェネラリストの外務省が法廷闘争に当たる日本の体制が一つの敗因ではなかったかと私は考えるわけでありますが、国際法上の訴訟事案が増えると今後想定しますと、こうした国際司法裁判所に法務大臣が関われるような体制が必要ではないかと思いますが、現体制では法務大臣権限法でこうした関わりはできるのでしょうか。
○政府参考人(都築 政則君) 国を当事者とする訴訟につきましては、今御指摘のいわゆる法務大臣権限法に基づきまして法務大臣が国を代表するということになっております。
海外の裁判所に我が国を当事者とする訴訟等が提起された場合にも、ただいま申し上げました法務大臣権限法によりまして法務省が対応することは可能でありますが、我が国では慣行的に外務省が直接の窓口となっておりまして、法務省においてはこれまでそれを尊重してきたところであります。
他方、国際司法裁判所等の国際法上の司法手続は、先ほど申し上げました法務大臣権限法が適用される訴訟ではないというふうに解されておりまして、現行法の下では法務省が国際法上の司法手続に直接関与することとなってはおりません。
ただし、国際司法手続におきましても、国内の訴訟における事実認定や証拠の評価における知見やノウハウを活用できると思われる場面も多々あろうかと思います。
今後は、法務省としましても、広角的に国際訴訟等へ関与していくことが必要であるというふうに考えているところでありまして、その前提といたしまして訟務体制を強化することは不可欠であるというふうに考えておりまして、予算概算要求におきまして訟務局の新設や訟務体制の強化の充実を要求させていただいているところであります。
○佐藤 ゆかり君 ちょっと時間がないので御答弁を短くしていただきたいと思いますが、国際司法裁判所では法務大臣が出ていく法的根拠がないという御答弁でありました。
是非、岸田大臣、こういった外交関係、これから国際司法裁判所を使った訴訟事案というのは増えるということも想定しますと、外務省と法務省との連携強化という意味で法務大臣権限法を改正する部分というのがあろうかと思われるんですが、その辺りは検討をお願いしたいというふうに思います。
(以下略)
---- 引用以上 ----
要は、日本政府側は、ICJにおける裁判に関する準備があまり行っていなかったということになる。
実際、真田 康弘(Yasuhiro SANADA)氏はこの裁判に関する見解を今年5月に公開した際、オーストラリア政府と日本政府の裁判における姿勢の差を指摘していた。。
・捕鯨判決とその後の展開(2014年11月7日 ika-net.jp;再紹介申し訳)
以下、2014年11月7日分 ika-net.jp『捕鯨判決とその後の展開』から『2. 日本側の敗因』を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
2. 日本側の敗因
こうした判決となった理由として、以下のものが考えられる。
第一に、口頭弁論に先立って行われていた豪州側と日本側で日本側の訴訟書面の「出来」の問題がある。豪州側の申述書は文章自体は本文だけでも280 ページに及び、必ずしも短くはないが、豪州側が強調したい事実やフレーズは繰り返して強調するなど、統一したストーリー展開が感じられ、この問題についての前提知識がなくとも容易に読めるような工夫が凝らされた書面であったと思料される。
この問題で重要となるであろう日本語の資料をくまなく調べ上げ書証として引用している。
これに対し日本側の答弁書は本文の分量でも豪州の1.5 倍と分量的には遥かに上回るのだが、全体的に冗長であることに加え、法律論の部分と科学議論の部分との部分は全く違った書きぶりで、官僚や担当者が縦割りで作成したような印象が拭えなかった。
なぜこの頭数の捕獲が必要か、なぜJARPA IとJARPA IIでサンプル数が大きく異なるのか等といった科学的説明も、これまでIWCなどに提出した文書をただなぞっただけのような内容になっており、説得力に乏しかった。
ICJ提訴という戦略については、豪州政府部内で「勝ち目があるのか」との異論もあったが、仄聞するところによると、届いた答弁書を読んだ豪州側は、かえって「日本側の弱点に気が付いた」との印象を持ったようである。
第二に、豪州側の巧みな専門家証人への反対尋問の活用などの訴訟指揮、及び日本側の口頭弁論での失敗、特に日本側専門家証人のラース・ワロー教授の証言を挙げる必要がある。
ICJの口頭弁論は、各国の弁護人が丁々発止にやり合うかたちではなく、1週毎に日豪が入れ替わって一方的に発言する形式を取っていた。
従って双方は事前に準備した上で相手側の主張に答えることができる。
ところが専門家に対する証人尋問では唯一例外的に、質疑形式の反対尋問の時間が設けられている。
豪州側はこの機会を十全に活用し、日本側証人のワロー教授を激しく攻め立てた。
この結果豪州は、ワロー教授から「ナガスクジラの調査計画については気に入ってはいない。これでは何も情報は得られない。ザトウクジラも問題だ」「ナガス・ザトウとミンクでサンプル数計算の根拠が違っている理由はわからない」「ザトウは獲らなくても生態系モデルを構築できる」という発言を引き出すことに成功した。
判決の行方を決定づける証言であった。
他方日本側は、専門家に対する反対尋問で持ち時間を半分程度しか使わなかったばかりか、捕獲頭数の設定について「私にもさっぱりわからない」(日本側弁護人アラン・ボイル教授の発言)と述べるなどの失点が目立った。
捕獲計画頭数は科学的に算定されたと主張する一方で、実際の捕獲頭数が計画と大幅に異なっていることについて、その頭数でも調査目的は達成できるとの弁明も行っているが、ならば捕獲頭数を大幅に少なくする、あるいはゼロでもよくなってしまうことになる。
日本の科学面での弁論は論理破綻を来していたと言える。
(以下略)
―――― 引用以上 ----
こうして振り返ると、例の裁判で日本政府が負けたのは「まさか」じゃなくて「やっぱり」というか「またか」という感が否めない。
相手側の対応を見極めることもできなかったのはともかく(これはこれで問題だが)、裁判に臨む態勢すら整えられなかったのだから本当に呆れるしかない。
一応、オーストラリア政府と(ニュージランド政府)による訴えに関する書面審理終結(2012年5月)から最初の口頭弁論まで1年以上の時間はあったはずなのに、その間日本政府の方々は何をやっていたのやら・・・。
っていうか、負けるべくして負けたこの裁判に関して「日本側の主張が認められた云々」と言い張る一部の人達は、本当の問題点に気づいていないかあるいは無視してるとしか・・・。