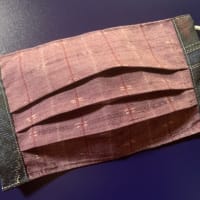かなり久しぶりの更新になりました。
皆さま、明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
さて、三が日も明けた早々、
「中国の職業資格の1つであった「茶芸師」が、先月国の指定した職業資格リストからはずされたようだ。」
というニュースが入りました。
正確には先月中旬の出来事のようです。
私は最近この類のニュースにはアンテナを張っていなかったので、噂は耳にしていたものの、いずれ…位の認識でしたが、いざ起きてみると何ともあっさりとした結末でした。
中国のこの手の資格は、茶芸師に限らず、90年代に始まった国営企業の解体と共に大量の人材が解雇され、行き場のなくなった人達が社会不安を起こすのを恐れた政府が、彼らが再就職のチャンスを得られるよう雇用対策として制度化したのが始まり…という経緯があります。(←意外とこの背景を知らない人は多い。)
私達外国人にとって、この資格の意義は色々あって良いのですが、現地では当初から生活に直結するものだったのです。
ですから、その時々の社会状況で、国の思惑に合わせて変化して行く…というのは、ある意味当然の流れでしょう。
もう何年も前から中国の茶葉販売店や茶芸館の経営者からはこの資格に対して懐疑的な意見が出ていたのは確かです。有資格者よりも、無資格でも筋の良い経験者や無経験の新人を雇ってゼロから教えた方が良い…と、はっきり主張する方もいました。
日本ではこれらの実情とは別に、ネーミングからか、一部の中国茶ファンの中に資格取得のための動きが出て、この資格取得を目指す人達のために国内の中国茶専門店を始め、色々なところがこの動きを牽引しました。
資格取得の証書等は無効になるようですが、勉強の成果は各々の中に残っていると思いますし、この資格がなくなるからと言って、お茶や茶芸が無くなるわけではありません。資格取得を目指し始めたばかりの中国の若者や、外国人は少なからずショックを受けるかもしれませんが、学んだことは消えませんから、お茶を学ぶ上での良い通過点だったと胸を張られて良いのではないでしょうか。
もしかしたら、また形を変えて残るかもしれないし…。
これらの流れと併走しているのかはわかりませんが、また新たな組織も出来ていて、お茶に関する政治の世界も変革・再編が起きているようです。
中国大陸のお茶の世界も、新たな局面に舵を切りつつあるのでしょう。