今朝のNHKラジオでレジ袋の有料化を期間限定で導入した東京都杉並区の事例が取り上げられました。マイバック持参率が85%だったそうです。是非群馬でも実験して欲しいです。
過剰包装の代名詞になっいるレジ袋ですが、スーパー以外で使われている袋に対して世間は甘いと思います。洋品店や土産屋の袋、空港免税店の袋など、頻度は少ないもののそのまま捨てるにはかさばるし、リユースするには用途が限られるし、レジ袋よりタチが悪いです。スーパーは企業努力でスタンプカードを作るなど、レジ袋削減に努めていますが、他の業態では当たり前のように袋が配布されます。この事についてどう思いますか?私は不公平感が否めません。
杉並区ホームページhttp://www2.city.suginami.tokyo.jp/
へクリックしていただけたら幸いですCopyright(C) 2007 SAKATANI MIHO All Rights Reserved.
過剰包装の代名詞になっいるレジ袋ですが、スーパー以外で使われている袋に対して世間は甘いと思います。洋品店や土産屋の袋、空港免税店の袋など、頻度は少ないもののそのまま捨てるにはかさばるし、リユースするには用途が限られるし、レジ袋よりタチが悪いです。スーパーは企業努力でスタンプカードを作るなど、レジ袋削減に努めていますが、他の業態では当たり前のように袋が配布されます。この事についてどう思いますか?私は不公平感が否めません。
杉並区ホームページhttp://www2.city.suginami.tokyo.jp/
へクリックしていただけたら幸いです












![当ブログは[エコプル]に参加しています](http://www.ecople.net/logos/ecolog_banner_ss.gif)






![当ブログは[チーム・マイナス6%]に参加しています](http://team-6.net/images/banner_rectangle.gif)






![当ブログは[チーム・マイナス6%]に参加しています](http://team-6.net/images/banner_square.gif)

![当ブログは[にほんブログ村]に参加しています](http://eco.blogmura.com/img/eco80_15_femgreen.gif)
![当ブログは[人気blogランキング]に参加しています](http://blog.with2.net/img/banner_04.gif)



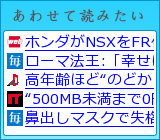







![当ブログは[人気blogランキング]に参加しています](http://blog.with2.net/img/banner_02.gif)



