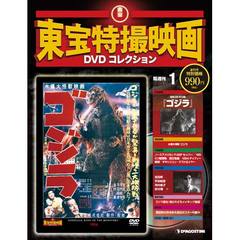ミッシェルガンエレファントの「THEE MOVIE」を昨年の暮れに観る。
年末の渋谷の映画館は全席完売で立ち見まで出るほどの盛況だった。
幕張メッセのラストライブが2003年10月11日。もう6年以上経つんだな・・・
解散してしまったことへの感慨や、アベフトシが亡くなってしまったという未だ信じ難い事実を差し引いても、大画面で大音量でライブ映像を観ることができたのは単純に楽しめた。冒頭の「ドロップ」はイントロを聴いた瞬間にパブロフの犬みたいに涙が出てしまったけれど。豊田監督の「青い春」でも「赤毛のケリー」と共に強烈な目に見えない残像をスクリーンに焼き付けた曲だ。そういえば「ドロップ」も「赤毛のケリー」もイントロはアベフトシのギターから始まる。アベがイントロを奏でそこからどっと音がなだれこんできて本編が始まる。ドロップの切なくも力強いあのリフは誰も同じように弾くことはできない。大画面に写しだされたアベの顔を観ながらそんな思いに囚われた。他に演奏された曲は懐かしく大好きだった曲群ばかりであって、「BIRDMAN」「ジェニー」「GET UP LUCY」等々・・・「ダニーゴー」も聴きたかったな。
確実に演じ手と受け手が共有した時間 二度と再生することができないその刹那を そのとき胸に去来した感情を記憶によって“生き物”として甦らせることができた二時間だった。
年末の渋谷の映画館は全席完売で立ち見まで出るほどの盛況だった。
幕張メッセのラストライブが2003年10月11日。もう6年以上経つんだな・・・
解散してしまったことへの感慨や、アベフトシが亡くなってしまったという未だ信じ難い事実を差し引いても、大画面で大音量でライブ映像を観ることができたのは単純に楽しめた。冒頭の「ドロップ」はイントロを聴いた瞬間にパブロフの犬みたいに涙が出てしまったけれど。豊田監督の「青い春」でも「赤毛のケリー」と共に強烈な目に見えない残像をスクリーンに焼き付けた曲だ。そういえば「ドロップ」も「赤毛のケリー」もイントロはアベフトシのギターから始まる。アベがイントロを奏でそこからどっと音がなだれこんできて本編が始まる。ドロップの切なくも力強いあのリフは誰も同じように弾くことはできない。大画面に写しだされたアベの顔を観ながらそんな思いに囚われた。他に演奏された曲は懐かしく大好きだった曲群ばかりであって、「BIRDMAN」「ジェニー」「GET UP LUCY」等々・・・「ダニーゴー」も聴きたかったな。
確実に演じ手と受け手が共有した時間 二度と再生することができないその刹那を そのとき胸に去来した感情を記憶によって“生き物”として甦らせることができた二時間だった。