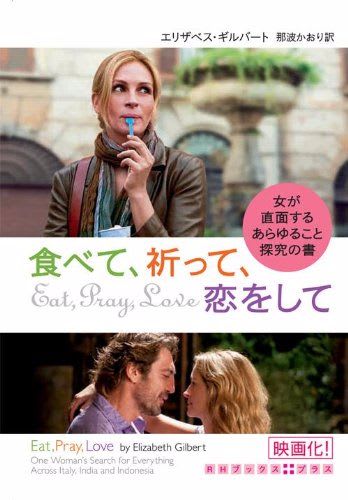
ここのブログは、キリスト教に関する何がしかについて書く……といった主旨のブログなので、本のチョイスとしてはちょっと「?
 」といったところなのですけれども、本の中にキリスト教のことも少し出てくるということで(^^;)
」といったところなのですけれども、本の中にキリスト教のことも少し出てくるということで(^^;)たまたま某古本屋さんで100円で売られていたもので、「あー、そういえばテレビで映画のCM見たことあったっけ
 」と思って、買ってきて読んでみたのです
」と思って、買ってきて読んでみたのです
いえ、正直「なんか人生で躓いた女性がインドへ行って自分の人生を見つめ直す的話だっけ☆」と漠然と思っていたため……「いや、インドに行って人生変わるくらいなら、そもそも最初の悩み自体大したことないんだって
 」とか思い、わたし的には少し冷笑的な態度でこの本は読みはじめたのです。。。
」とか思い、わたし的には少し冷笑的な態度でこの本は読みはじめたのです。。。
んが、実際読み終わってみると――
なめてました。すみません。こんなわたしを許してください

といったような気持ちになります(笑)
なんていうか、これだけ凄い話をむしろ、どうやってどんなふうに映画にしたんだろう……って思ったんですけど、映画は映画でそれなりにうまく編集されてるなといった印象でした
 ただ、本の内容のほうがとても素晴らしいので、映画だけ見てむしろ本のほうを手に取らない方がいたとしたら――何かちょっともったいないかもしれないですね(^^;)
ただ、本の内容のほうがとても素晴らしいので、映画だけ見てむしろ本のほうを手に取らない方がいたとしたら――何かちょっともったいないかもしれないですね(^^;)なんにしても、まずお話の説明のほうを先にしてみますね。お話、なんていっても、この本自体がノンフィクションで、著者のエリザベス・ギルバートさん自身、本の中で何か自分をごまかしたりとか美化したりとか、そうした部分がほとんど感じられないような筆致によって書き綴られているといっていいと思います。
わたしも1ページ残さずすべて読んだ……というわけではなく、一部ナナメ読み気味なのですが(なので、もし間違ってるところがあったりしたらごめんなさい・汗)、エリザベスさんは三十台の前半で離婚され、その時にどろ沼の裁判を経てようやく離婚し、夫と離婚することを決めてからつきあいはじめた男性とも離れることにし――まずはイタリア、それからインド、インドネシアのバリ島といったように、旅行した先で彼女が考えたこと、感じたこと、経験したことなどが素晴らしい文章によって表現されています。
とにかく、読みはじめてすぐわかるのは、エリザベス・ギルバートさんがとても頭のいい、賢い女性であり、恋愛経験も豊富で、ウィットに富んだ友人も多い素晴らしい女性だということかもしれません。
けれど、ある時子供を欲しいと思えない自分の気持ちを偽ることが出来ず、そのことをきっかけに夫と別れることを心に決めます。もちろん、このような素晴らしい女性と結婚している夫のほうでは当然離婚なんてしたくありません。エリザベスさんが他の男性とつきあいはじめたのは、夫と別れることを決めてからなので、彼女自身の不貞といったことが離婚の原因ではありませんでした。
離婚協議が裁判までもつれこんだ場合……しかも一方が一方に執着していた場合のどろ沼の離婚協議というのは、当然エリザベスさんに強い罪悪感を抱かせましたし、結局のところ経済的な部分で多くのものを夫に譲り渡す形で――ようやく彼女は離婚するということが出来たのでした。
そして、この離婚協議の間からずっとつきあっていた男性との関係も、愛しあっているがゆえにうまくいかないという、難しい局面を迎え……エリザベスさんはイタリアへと旅立つことにします。もともとイタリアが大好きで、イタリア語を習ってみたいとずっと思ってきたエリザベスさんは、持ち前のウィットに富んだ素敵な明るさから、友人にも恵まれてローマで楽しく過ごします。
たぶん、わたしが思うに――普通の人であれば、旅はこのあたりでやめにするはずです(笑)けれど、エリザベスさんというのは、明るくウィットに富んだ人好きのする女性であると同時に……物凄く物事の根本というものを考える女性なんですね、とても頭のいい賢い女性であるだけに(^^;)
まあ、日本的にわかりやすい言い方をするとしたら、<三十代、バツイチのこじらせ女子>といったカテゴリー(?)に入れられるのかもしれませんが、エリザベスさんの思想の深さというのは、そんなものすら超えています。。。

十五の時から一週間と間を置かずにずっと男がいた、いつでも恋をしていたというエリザベスさんは、「これからもこんなことをずっと続けるのか?」、「もう相手にすべてを捧げ尽くして自分がなくなってしまうような恋はしたくない」といった思いから、男断ちしようと考えます。すなわち、禁欲。そして心の平安を求めて今度はインドのアシュラムへと向かうのです。
ええと、わたしがこの本のことを取り上げてみたのは、実はこのあたりのことからでした(^^;)
そのう、なんていうか……エリザベスさんというのは、いわゆる欧米を代表するような「ススんでる女性」といっていいと思うんですよね。そして、わたしたちクリスチャンの目からしてみると、「真の心の平安といったものは、イエスさまからしか与えられない」といったように感じますよね。普通はキリスト教国に住んでいるエリザベスさんのほうが、そのことをわかっていそうですし、実際、聖書やキリスト教の思想についてのこともお話の中に出てきます。
でも、今のアメリカ女性の、というかアメリカの人々の価値観というのは、都市部では特にこうした感じのことが主流なのではないか……と思いました。べつにイエス・キリストを否定するわけではない、聖書にもなかなかいいことが書いてあると思う、でももうこの古い価値観によって縛られるのはごめんだし、夫が妻のかしらだなんていう考え方も、まっくもって「おえっ!」だわ……とでも言ったらいいのでしょうか(いえ、こういう書き方はされてないんですけどね^^;)
こうした旧来の女性を縛る思想からも解放され、自分を縛る自我からも解放されるにはどうしたらいいのか――といったことを求めて、エリザベスさんはインドへと旅立ちました。自分的にもしかしたら一番面白かったのは、このあたりのことかもしれません。正直、わたし自身「インドで瞑想なんてして、本当に人生が変わるとでも??」と決めてかかってました。
でも、このあたりのエリザベスさんの心の変遷というか、精神の平安や安定を手に入れる過程というのは、誰しもが「その気持ち、わかる」と共感できるものがあると思います。たとえば、瞑想を続けていくうちに>>「全宇宙に自分の内臓が出されて、内と外とがひっくり返る」といったのにも似た経験をエリザベスさんはし、また、ある時には「わたしがどんなに深く愛してるか、その愛をわかってなぁーい!!」と大声で叫びます。
このあたりとか、誰でもよくわかると思うんですよ。人が宗教に求めるものって、ある種の超越体験ですし、それと「おまえらはわたしのことをわかってなぁーい!!」みたいに叫びたいこと、誰でもありますよね(^^;)
奥さんが自分の夫や子供に対して、「おまえらはわたしをわかってなぁーい!!」と叫びたいこともあれば、わからずやの上司にそう叫びたいこともあれぱ、知ったかぶりの同僚や友人に対してそう叫びたいと思うこともある(笑)
たぶん、仏教の内観療法などでもよいのかもしれませんが、瞑想や滝に打たれるといったことをして、食事は栄養はあるけど質素、また朝早く起きて寺院を掃除する……といった生活を続けていれば、ある時何かの<気づき>が与えられたり、人生が変わるようなある種の超越的体験を経験するというのはあることだと思います(書き忘れてましたが、エリザベスさんはヨガもやってます)。
そして、こうしてインドで心の平安を手に入れ、すっかり男断ちもして「もう自分は色恋沙汰なんかに心を乱されないわ」というくらいに思っていたエリザベスさんなのですが――次にバリ島で、運命の相手のような男性と出会って結ばれます。
こう完結に旅の終わりについて書いてしまうと「あー、ハイハイ。結局そうなるのね
 」とか「ちょっと出来杉だなあ
」とか「ちょっと出来杉だなあ 」と思われるかもしれません。でも結局のところ……エリザベスさんは「自分の心がもっとも求めるもの」を手に入れたのだと思いますし、その過程についてもとても説得力があるんですよね。というよりむしろ、この点については著者であるエリザベスさんのほうがそうと確信できなくても、読んでるわたしたちのほうこそが、「きっと絶対にそうよ!」と感じることがあるというか。
」と思われるかもしれません。でも結局のところ……エリザベスさんは「自分の心がもっとも求めるもの」を手に入れたのだと思いますし、その過程についてもとても説得力があるんですよね。というよりむしろ、この点については著者であるエリザベスさんのほうがそうと確信できなくても、読んでるわたしたちのほうこそが、「きっと絶対にそうよ!」と感じることがあるというか。つまり、何のどんな神を信じるにしても――エリザベスさんのように真摯な態度で熱心に求め続けたとすれば、自分がもっとも望むものを納得できる形で手に入れることが出来る、そしてそのような人のありようを神さまは喜んでおられるのではないか……ということです。
もちろん、わたしはキリスト教徒ですので、イエスさまを通して人が救われることが最善であると信じています。けれど、アフリカなどの発展途上国に行ってクリスチャンを増やすよりも、欧米のキリスト教国の、特に都市部で宣教するのが何故より困難なのか――ということを考える一助になる本だとは思うんですよね(^^;)
そうした都市部で育ち、また両親とも信仰については曖昧……といった家庭で育った場合、ティーンエイジャーになった頃にはキリスト教を信じるのはダサいというのか、そうした旧来の古い価値観に縛られるよりも、インドのグルに教えを乞うたり、ヨガをしたり瞑想したりすることのほうが、古い言い方をすればナウいというんでしょうか(笑)何かそんなような印象を受けたりします。。。
だから、結局のところイスラエル民族が神さまに選ばれた特別な民でありながら、その恩寵を失ったように――欧米諸国というのも、だんだんに信仰の本質を失いつつあり、それにかわってヒューマニズムやリベラル主義というか、そちらにシフトしつつあるというか……その、こうしたことというのは前から言われていたことですけれども、今まではなんだかんだ言っても全体にバランスが取れているといった感じだったと思います。
キリスト教の信仰の本質と、ヒューマニズムやリベラル主義の間のバランスのようなものがある程度取れていた。でも、やっぱりだんだんに後者のほうが力を持ってきて、キリスト教的価値観というのは、古い、そこにしがみついている人々は自分の保守主義について他人を批難する前にもっと考え直すべきだ……という潮流のほうが力を持ってきているのではないでしょうか。
ここからは本の感想から話がずれてきますので(汗)、「食べて、祈って、恋をして」の感想としては、このあたりで終えておきたいと思いますm(_ _)m
なんにしても、内容の濃さという意味では、映画の百万倍くらい原作のほうが面白いと感じるという、本当に一読に値する本だと思いました(あ、でも男の人にはあんまりススめられない内容かもしれません^^;)
それではまた~!!











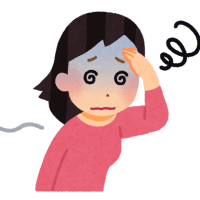
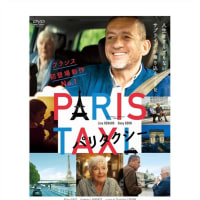












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます