
「健康」というものは、損なってみて初めてその有難みがわかる……とはよく聞くことですが、今回はちょっと体ではなく、精神上の不健康について、何か書いてみたいと思いました

というのもつい先日、ある方に「お元気ですか? 」と何気なく聞いてみたところ、「元気そうに見えるだけで、全然元気じゃないよ
」と何気なく聞いてみたところ、「元気そうに見えるだけで、全然元気じゃないよ 」と言われたからなのです(^^;)
」と言われたからなのです(^^;)
もっとも、実は何か病気があって内なる苦しみを隠している……ということではなく、「今は世の中全体がそうでしょ」みたいにおっしゃっていて。というのもこの方、SNSを見て落ち込むことがあるけれど、自分の側ではもう「実はこーいうことがあって今落ち込んでるんだよねー 」とは書かないことにしたそうです。
」とは書かないことにしたそうです。
なんでかっていうと、人に弱味を見せたくないとかプライドがどーたらということではなく……自分のSNSを見てはっきり「嫌っている人がいる」と気づいたっていうことなんですよね。たぶんそれは「身近な人ではなく、元は全然知らない人」である可能性が高く、いわゆるリア充系の人に反感を覚えやすい人なんじゃないか――ということでした。
つまり、まるでストーカーのように自分のSNSをチェックしていると思われるが、「こんなことでドジ踏んじゃった!てへ☆ 」といった投稿をした場合そいつが喜びそうなので、今はもうあたりさわりのない文面や写真を心がけるようになった……という話。
」といった投稿をした場合そいつが喜びそうなので、今はもうあたりさわりのない文面や写真を心がけるようになった……という話。
いえまあ、「考えすぎじゃない?」とまではこの方の場合、わたしには言えませんでした(^^;)なんと言いますか、わたし自身「うわあ~。すごい人だなあ~ 」みたいに感じる方で、レベルの違いすぎる遥かに上の人っていうんでしょうか。そうした女性なので、そのくらいレベルが違うと嫉妬すらすでに生じない……とでも言いますか。でも確かに、そうした生活の一部のいいところを写真でだけ見てたら「なんかムカつく
」みたいに感じる方で、レベルの違いすぎる遥かに上の人っていうんでしょうか。そうした女性なので、そのくらいレベルが違うと嫉妬すらすでに生じない……とでも言いますか。でも確かに、そうした生活の一部のいいところを写真でだけ見てたら「なんかムカつく 」みたいになるということなのかどうか。
」みたいになるということなのかどうか。
その後の会話については端折ろうと思うのですが、ようするに「社会全体が元気じゃない」と言いますか、何を言ってもやってもある一定の割合でアンチが生まれることがわかっている。有名人の方の場合はアンチがいること自体がすでにそれだけ人気のある証拠……とまで言われたりしますけど、「元気そうに見えるだけで、本当は元気じゃない芸能人っていうかタレントの人って多いんじゃない?」ということでした(※具体的に誰か知ってるということではなく、ただの世間話として^^;)。
つまり、何かのことで成功してある分野で有名になったりすると、その後待ってるのは必ず足を引っ張ったり何かと批判したりする人々が多少なり現れることであり、となるともう、「元気そうに見える振り」だけでもしておくしかなく、あとはそうした人々に何かうるさく言われぬために発言のほうも「あたりさわりなく」、そうした人々が何かちょっとした失言によってでも喜ばぬよう守りに入るしかない――となった時点で、「はい、元気のない社会の出来あがり!」というそうしたことになるようで。。。
そのあたりのことっていうのは、「ツイッター?(エックスですとも。わかってますとも・笑)そんな毎日何か書くことあったっけ? 」、「インスタグラム?わざわざ写真に撮るほどのことは何も起きてないような……
」、「インスタグラム?わざわざ写真に撮るほどのことは何も起きてないような…… 」という、違う意味でカワイソウな人生を送ってるわたしなどにはわからないのですが(笑)、でも、百人の人がいて、八十五人が賛同してくれたり、「いいね!
」という、違う意味でカワイソウな人生を送ってるわたしなどにはわからないのですが(笑)、でも、百人の人がいて、八十五人が賛同してくれたり、「いいね! 」と言ってくれても、残り十五人がアンチ的な意見を持っていてこちらを攻撃しようとする気配を感じたとしたら――具体的にネットで書かれた悪口の質などにもよるかもですが、確かに八十五人の賛同者や味方の人の言葉なんてかき消えちゃうかもしれませんよね。
」と言ってくれても、残り十五人がアンチ的な意見を持っていてこちらを攻撃しようとする気配を感じたとしたら――具体的にネットで書かれた悪口の質などにもよるかもですが、確かに八十五人の賛同者や味方の人の言葉なんてかき消えちゃうかもしれませんよね。
そして、その十五人の人の言葉にだけ耳を傾けるうち、最後には自殺することまで考えるくらい落ち込むことに ……って、本当にあるんだろうなって思います。今回のタイトル、「痛みと苦しみの檻」というものなんですけど、これは簡単にいうと記憶のことだったりします。何かのことで本当に心が傷つく、痛む、その後遺症に苦しむ……といった時、大抵は記憶が悪さをしていて、何度も何度も繰り返し、過去にあった嫌な経験、人から言われた言葉などを思い返したりしているのではないでしょうか。
……って、本当にあるんだろうなって思います。今回のタイトル、「痛みと苦しみの檻」というものなんですけど、これは簡単にいうと記憶のことだったりします。何かのことで本当に心が傷つく、痛む、その後遺症に苦しむ……といった時、大抵は記憶が悪さをしていて、何度も何度も繰り返し、過去にあった嫌な経験、人から言われた言葉などを思い返したりしているのではないでしょうか。
つまり、その苦しい体験をした瞬間が100%マックスの痛みを心に感じたとして、心の傷の場合、その時のことをその後も何度も脳内で繰り返しては100%とまでは言わなくても、90%とか80%とか、それが仮に70%や60%くらいでも、気分がクサクサしてきて今目の前にあることを100%は楽しめないなど……時間が経つにつれ、それがトラウマというほどのものではないことなら、ある程度は忘れられるかもしれない。でももしそれが小さな棘程度のものでも、「そんな小さなことのために、また暫くクサクサした気分にさせられるのもなんだしな~ 」という感じで、人はやっぱり少し用心深くなる(一番ひどい場合そのことがループ状になって孫悟空の輪っかみたいにギリギリ☆苦しめることすらあるので
」という感じで、人はやっぱり少し用心深くなる(一番ひどい場合そのことがループ状になって孫悟空の輪っかみたいにギリギリ☆苦しめることすらあるので
 ^^;)
^^;)
この種のことで、わたし的に割と役立ったのは、やっぱりマーリン・キャロザースさんの「すべてのことを(良いことも悪いことも)神さまに感謝する 」という感謝と賛美のメッセージに関してでした。正確な文面のほうは忘れてしまいましたが、マーリンさんがある時本を読むか何かしてると、大きな音でラジカセをかけている人がいて、内容に集中できなかった。でも、神さまに祈るとラジカセの音が気にならなくなり、本の内容に集中できた……みたいなお話だったと思います。こういう時、神さまならそのラジカセの音を小さくするなり止めるなり、その人がラジカセととともに時空の彼方に消えるなり
」という感謝と賛美のメッセージに関してでした。正確な文面のほうは忘れてしまいましたが、マーリンさんがある時本を読むか何かしてると、大きな音でラジカセをかけている人がいて、内容に集中できなかった。でも、神さまに祈るとラジカセの音が気にならなくなり、本の内容に集中できた……みたいなお話だったと思います。こういう時、神さまならそのラジカセの音を小さくするなり止めるなり、その人がラジカセととともに時空の彼方に消えるなり
 (笑)、なんでもお出来になりそうなものですが、イエスさまがおっしゃったのはおそらく、「問題(ラジカセの音)に集中するよりも、人生の実質や信仰に集中することのほうがもっと大切なことだよ
(笑)、なんでもお出来になりそうなものですが、イエスさまがおっしゃったのはおそらく、「問題(ラジカセの音)に集中するよりも、人生の実質や信仰に集中することのほうがもっと大切なことだよ 」ということだったのだと思います、たぶん。
」ということだったのだと思います、たぶん。
また、これは他の本で読んだことなのですが、たとえば人が何か学校の授業や講義を受けている時、それが退屈な内容であればあるほど、集中しないと頭に入ってこない。でも、それが嫌でも耳に入ってくるような大きな声で言われているものであれ、人は他に心配ごとがあったり、心を取られることがあったりすると、その言われたことをまったく覚えてないことがよくある。この聴覚の、ある一定の音を心の中に入れて記憶するかどうか、微妙な調節というのを人間は耳と心の両方でどんなふうにやっているのか……実は科学的にはよくわかってないというお話でした
これって、よく考えると本当に不思議ですよね。選挙カーが大声で横を通っていったんだから、その連呼される名前や政策について、その後三日くらい覚えていてもよさそうなのに、人は自分の興味のないことはその後三時間ですら覚えてないことがある(わたしだけ?笑)。一方、直接・間接に自分に嫌なことをしてきたり言ってきたりした人の言葉のほうこそ、同じような形で忘れるべきと思うのに――むしろ褒められたり、いいこと言われたその体験や言葉自体は割合早く忘れてしまい、「嫌な言葉」のほうはその後も覚えていたくもないのに覚えている……というのは、なんとも不思議なことのような気がします(^^;)
なんにしても、基本的な原理というのは「何かそんなよーなことなのかも 」と、ちょっとクールダウンするだけでも、時と場合によっては気分を切り換えるのに役立つことがあるかもしれません。もちろん、クリスチャン的な解答としては「イエスさまに頼って祈ればいいだけ!
」と、ちょっとクールダウンするだけでも、時と場合によっては気分を切り換えるのに役立つことがあるかもしれません。もちろん、クリスチャン的な解答としては「イエスさまに頼って祈ればいいだけ! 」というのは間違いなく絶対そうです
」というのは間違いなく絶対そうです
それではまた~!!













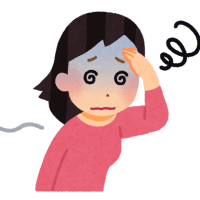
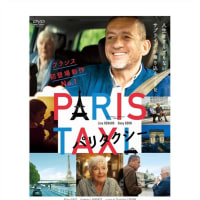









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます