日経サイエンス(2025年4月)に「量子力学100年の難問 観測問題」と題して3つの記事が載っています。これを読んで、自分がまだまだ量子力学を理解できていないということがわかりました。うんうん、無知を知ることは一歩前進ですね。
1番目の谷村省吾へのインタビュー記事と2番目の「シュレーディンガーの猫は量子AIで救えるか」という記事は題材としてはシュレーディンガーの猫(Schrödinger's cat)およびウィグナーの友人(Wigner's friend)に焦点が当たっています。
1番目の記事は全体概説なので二重スリット実験についても十分に解説していますが、二重スリット実験は実験科学的には何が起きるのかは既に確立されているように思えます。例えばボーム理論は二重スリット実験の結果とは矛盾する事が明らかとなり否定されています。それが今回の3番目の記事では復活していてちと驚きましたが。
さてシュレーディンガーの猫については「猫が死んだ状態と生きている状態との重ね合わせ」などというものが実際に存在している(観測的証拠が見つかる?)という解釈は既に少数派だろうと勝手に考えていましたが、そうでもない雰囲気です。私が多数派だろうと思っていたのはwikipediaの記事で言うと「自発的収縮理論」のイメージの一部ですが、「少なくとも粒子検知器の時点で(意識ある者による)観測とは無関係に、波動関数が収縮する」というイメージです。「じゃあ粒子放出から検出器による検知までのどこに境界があるのか?」とか「そもそも収縮とは何ぞや?」とかいうのが現在の問題なのかなと考えていたのですが、そうでもないみたいです。
何しろ2番目の記事では、重ね合わせ状態になりえる知性体、その名も量子AIを実際に作り出してウィグナーの友人の実験をやってみようということが主要テーマですから。
私見では知生体(意識の有無は仮定しない)などという複雑な系が長時間収縮せずに存在するのは無理なんではないかとしか思えないのですが。実はウィグナーの友人のパラドックスについてはほぼ初耳の状態で、以前に知っていたとしてもすぐにまじめに考えることを却下していたかも知れません。
それはさておき、マクロな物体であるシュレーディンガーの猫は重ね合わせになっていなかったことは実証できるのではないかと思いつきました。検死をすれば死亡時刻が推定できるではありませんか! [Ref-1]。もちろん正確には無理としても、それは観測精度の問題であり本質的な問題ではありません。「箱を開いた後でも原理的には死亡時刻を推定できる」ということ、これを認めるか否かが大切です。
もっと明確にするなら、猫ではなく放射線検出器とタイマーを入れておけばよいでしょう。原子崩壊による放射線を検出したらタイマーがスタートするようにしておけば、どの時刻に放射線を検出したのかは明らかになります。ここでまあ2つの解釈は成り立ちます。箱を開けた時刻を0とし、タイマーが示していた経過時間をtとすれば、検出器の状態として、
1.時刻-tまでは検出しない状態で、時刻-t以降は検出した状態だった。
2.時刻-tまでは、検出しない状態と検出した状態との重ね合わせだった。
(ただし両状態の割合は時刻により変化していたと解釈する)
いや1の解釈が当然のような気がしますが。これはタイマーという多数の状態を持ちうるものを持ち込んだ故とも言えます。1日で開けるとして精度1秒とすれば、少なくとも3600個の状態を持たないとタイマーとして役立ちませんから。でも猫はもっともっと多数の状態を持ち得るものです。
そうしたらば3番目の記事では「標準的な量子力学では時間に対応する演算子が存在しない」との御宣託です。なので「粒子がいつ到着したのかは予測できない」。えっ、まさかタイマーなんて認めないとか・・・。
そう言われれば時間対応の演算子はなかったような・・、少なくとも非相対論的な場合は時間は単なるパラメーターでしかなかった・・のかな? 相対性理論では時間は位置と同等の扱いになるのだから相対論的量子力学ではどうなんだろう・・・勉強不足で知らない。
でも時間とエネルギーとは不確定性関係にあったはずで・・。あれ、もしかしてエネルギーの演算子もなかったんだっけ?
1番目の記事の解説者である谷村先生が詳しい解説を発表していました[Ref-2]。これによれば、「時間とエネルギーの不確定性関係は何を表しているのかという疑問は古く,幾度となく議論されており」とのことです。上記の私の疑問はだいたいは「3.素朴な見解」と「4.否定的な見解」で尽くされているようです。
相対論的なら時間演算子があるのではということは、「ナイーブに期待される」のですが「この期待は正当化されない」。
形式的には時間物理量と呼べるような演算子は導けるけれど、「時間演算子と現実的なモデルは両立しない」。
<=なるほど、未だに相対論と量子論とが統一されていないということの一端なのでしょうね。
一つのミューオンの生存時間は測りようがない。「(崩壊時間は)観測者の時計で定義されるものである.時間の経過につれて単調増加あるいは単調減少するような量を一つ一つのミューオンが持っているとは思えない。」 <=確かに
「一般の物理系の運動を記述するために参照されるパラメータが時間である,というのがいまのところ物理学者に定着している時間観であろう.」
なお3番目の記事のテーマは、その標準的な量子力学では予測できない到着時間の分布を予測する理論の話ですが、詳しくは次回とします。
----------------------------
Ref-1) 検死とは?
1-a) 「いい葬儀」の記事
1-b) 「家族葬のらくおう」の記事
Ref-2) 谷村省吾 "時間とエネルギーの不確定性関係 — 腑に落ちない関係" 素粒子論研究 電子版, Vol.16, No.3 (2014)
1番目の谷村省吾へのインタビュー記事と2番目の「シュレーディンガーの猫は量子AIで救えるか」という記事は題材としてはシュレーディンガーの猫(Schrödinger's cat)およびウィグナーの友人(Wigner's friend)に焦点が当たっています。
1番目の記事は全体概説なので二重スリット実験についても十分に解説していますが、二重スリット実験は実験科学的には何が起きるのかは既に確立されているように思えます。例えばボーム理論は二重スリット実験の結果とは矛盾する事が明らかとなり否定されています。それが今回の3番目の記事では復活していてちと驚きましたが。
さてシュレーディンガーの猫については「猫が死んだ状態と生きている状態との重ね合わせ」などというものが実際に存在している(観測的証拠が見つかる?)という解釈は既に少数派だろうと勝手に考えていましたが、そうでもない雰囲気です。私が多数派だろうと思っていたのはwikipediaの記事で言うと「自発的収縮理論」のイメージの一部ですが、「少なくとも粒子検知器の時点で(意識ある者による)観測とは無関係に、波動関数が収縮する」というイメージです。「じゃあ粒子放出から検出器による検知までのどこに境界があるのか?」とか「そもそも収縮とは何ぞや?」とかいうのが現在の問題なのかなと考えていたのですが、そうでもないみたいです。
何しろ2番目の記事では、重ね合わせ状態になりえる知性体、その名も量子AIを実際に作り出してウィグナーの友人の実験をやってみようということが主要テーマですから。
私見では知生体(意識の有無は仮定しない)などという複雑な系が長時間収縮せずに存在するのは無理なんではないかとしか思えないのですが。実はウィグナーの友人のパラドックスについてはほぼ初耳の状態で、以前に知っていたとしてもすぐにまじめに考えることを却下していたかも知れません。
それはさておき、マクロな物体であるシュレーディンガーの猫は重ね合わせになっていなかったことは実証できるのではないかと思いつきました。検死をすれば死亡時刻が推定できるではありませんか! [Ref-1]。もちろん正確には無理としても、それは観測精度の問題であり本質的な問題ではありません。「箱を開いた後でも原理的には死亡時刻を推定できる」ということ、これを認めるか否かが大切です。
もっと明確にするなら、猫ではなく放射線検出器とタイマーを入れておけばよいでしょう。原子崩壊による放射線を検出したらタイマーがスタートするようにしておけば、どの時刻に放射線を検出したのかは明らかになります。ここでまあ2つの解釈は成り立ちます。箱を開けた時刻を0とし、タイマーが示していた経過時間をtとすれば、検出器の状態として、
1.時刻-tまでは検出しない状態で、時刻-t以降は検出した状態だった。
2.時刻-tまでは、検出しない状態と検出した状態との重ね合わせだった。
(ただし両状態の割合は時刻により変化していたと解釈する)
いや1の解釈が当然のような気がしますが。これはタイマーという多数の状態を持ちうるものを持ち込んだ故とも言えます。1日で開けるとして精度1秒とすれば、少なくとも3600個の状態を持たないとタイマーとして役立ちませんから。でも猫はもっともっと多数の状態を持ち得るものです。
そうしたらば3番目の記事では「標準的な量子力学では時間に対応する演算子が存在しない」との御宣託です。なので「粒子がいつ到着したのかは予測できない」。えっ、まさかタイマーなんて認めないとか・・・。
そう言われれば時間対応の演算子はなかったような・・、少なくとも非相対論的な場合は時間は単なるパラメーターでしかなかった・・のかな? 相対性理論では時間は位置と同等の扱いになるのだから相対論的量子力学ではどうなんだろう・・・勉強不足で知らない。
でも時間とエネルギーとは不確定性関係にあったはずで・・。あれ、もしかしてエネルギーの演算子もなかったんだっけ?
1番目の記事の解説者である谷村先生が詳しい解説を発表していました[Ref-2]。これによれば、「時間とエネルギーの不確定性関係は何を表しているのかという疑問は古く,幾度となく議論されており」とのことです。上記の私の疑問はだいたいは「3.素朴な見解」と「4.否定的な見解」で尽くされているようです。
相対論的なら時間演算子があるのではということは、「ナイーブに期待される」のですが「この期待は正当化されない」。
形式的には時間物理量と呼べるような演算子は導けるけれど、「時間演算子と現実的なモデルは両立しない」。
<=なるほど、未だに相対論と量子論とが統一されていないということの一端なのでしょうね。
一つのミューオンの生存時間は測りようがない。「(崩壊時間は)観測者の時計で定義されるものである.時間の経過につれて単調増加あるいは単調減少するような量を一つ一つのミューオンが持っているとは思えない。」 <=確かに
「一般の物理系の運動を記述するために参照されるパラメータが時間である,というのがいまのところ物理学者に定着している時間観であろう.」
なお3番目の記事のテーマは、その標準的な量子力学では予測できない到着時間の分布を予測する理論の話ですが、詳しくは次回とします。
----------------------------
Ref-1) 検死とは?
1-a) 「いい葬儀」の記事
1-b) 「家族葬のらくおう」の記事
Ref-2) 谷村省吾 "時間とエネルギーの不確定性関係 — 腑に落ちない関係" 素粒子論研究 電子版, Vol.16, No.3 (2014)










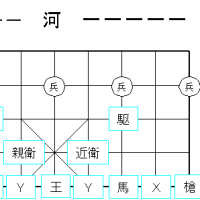
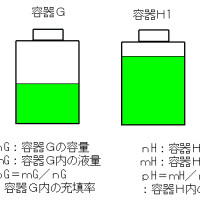
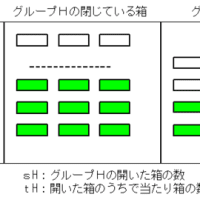
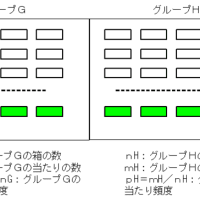
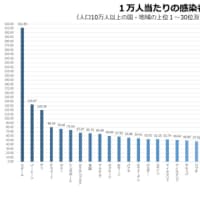
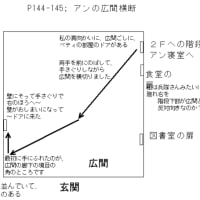
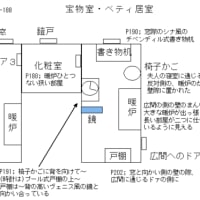
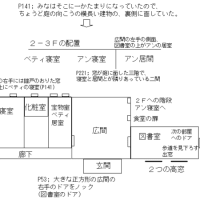
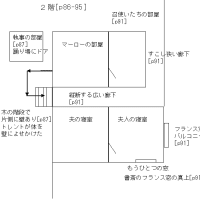
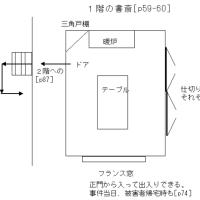






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます