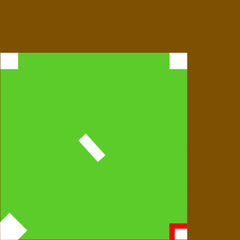私も今年で76歳。古きよき野球と時代を振り返り、語り継ぐのもよいかな、と思う年齢であり、心境にもなってきた。
あらたまって文を書くということになると大変だが、気楽につぶやくくらいならできるだろうと思い、今年からはじめてみようと思う。
私は現在、阪神大学野球連盟2部西リーグに所属する神戸大学海事科学部野球部監督とKBA(カマタベースボールアカデミー)中学硬式野球の総監督の両方を同大学のグラウンドでやっている。
大学は週4日、中学は土、日、祝祭日に若いひとたちに囲まれ汗を流している。
私も今年で76歳。古きよき野球と時代を振り返り、語り継ぐのもよいかな、と思う年齢であり、心境にもなってきた。
あらたまって文を書くということになると大変だが、気楽につぶやくくらいならできるだろうと思い、今年からはじめてみようと思う。
私は現在、阪神大学野球連盟2部西リーグに所属する神戸大学海事科学部野球部監督とKBA(カマタベースボールアカデミー)中学硬式野球の総監督の両方を同大学のグラウンドでやっている。
大学は週4日、中学は土、日、祝祭日に若いひとたちに囲まれ汗を流している。