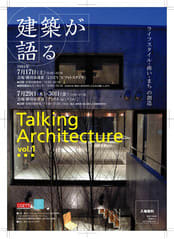間人(たいざ)の民家は、その多くに杉板が外壁として使われていた。海に向かう路地に入って見渡すと、見事に全ての民家が杉板で囲われ、その向こうに海が微かに見えていたりする。
峰山という駅に降り立つ前から、車窓から見える里山と民家の佇まいが気になっていた。京丹後市商工会の松井さんと、駅からクルマで会場へ向かう。その間じゅう、道路脇の民家とその連なり方に眼を奪われっぱなしだった。杉板を多用した民家や蔵は、瓦屋根が反っくり返るでもなく、非常にベーシックな佇まいを見せていた。ハウスメーカーの家が全く無いわけではないが、ごく僅かだ。
里山は、トンネルを抜けると、海べりのまち「間人」へ出た。海に近い家の多くがコンクリートに固められている昨今、これほどまでに木造の家が残っているのは希少だろう。宿の若い男性は「ちりめんを織っていたからですよ」と言った。聞けば、ちりめんを織るからコンクリートの空間ではなく“呼吸する家”でなくてはならないのだ、と。これもひとつの“機能美”なのだ。