『朝焼けの中で』 森崎和江
八つか九つくらいの年ごろだった。
朝はまだひんやりしていた。私は門柱に寄りかかって空を見ていた。
朝日が昇ろうとしていたのだろう、透明な空が色づいていた。
朝早く戸外にノートと鉛筆を持ち出して、私は何やら書きつけていた。
が、空があまりに美しいので、その微妙な光線の変化を書き留めておきたくなって、
雲の端の朝焼けの色や、雲を遊ばせている黄金の空に向かって感嘆の叫びをあげつつ、
それにふさわしい言葉を並べようとし始めた。
けれどもなんという絶妙な光の舞踏・・・・・。
わたしあの朝、初めて言葉という物の貧しさを知ったのである。
絶望というもののあじわいをも知ったのだった。
自然の表現力の見事さに、人のそれは及びようのないことを、魂にしみとおらせた。
うちしおれる心と見事な自然の言葉に声を失う思いとを、共に抱き、涙ぐむようにしていると、
父が出てきて、笑顔を向けてくれた。
何を話してくれたか、もう記憶にない。ただあの時の強い体験にふさわしいようないたわりが、
父から流れてきたことだけが残っている。
空が白くなり、人間たちの朝が動いていく気配が満ちた。
いつのまにか文筆にかかわって生きてきたけれど、言葉に対する私の感じ方の中には、あの朝の体験が
深く広がっているようである。それは人間たちの深々とした生の営みの中で、言語化されている
部分の小ささ、貧しさへの思いである。いや、まだ言葉になっていない広い領域のあることに対する、愛しさである。
言葉は朝焼けの中の八歳の少女のようだ。













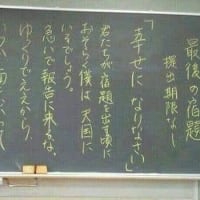

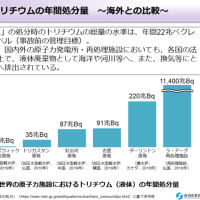
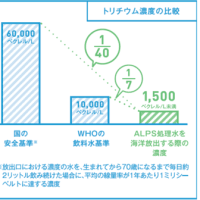
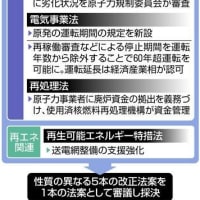








返信が遅れ、申し訳ありません。
この詩はインターネットで拾いました。
URLは分かりません。