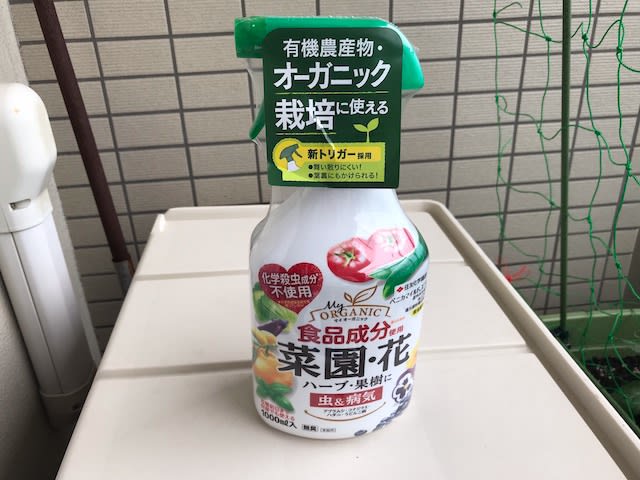晴れは多摩川へ、曇りは洗足池へ、が最近の傾向(嗜好)ですので、今朝は洗足池へ。
白い花が綺麗に咲いていました。


と思ったのですが、よくよく見ると、

花ではなく、葉が白いんです。しかも、葉元から葉先に向かって白く変わっていくようです。

とりあえず、Googleで画像検索すると、Crepe Ginger(ホウズキアヤメ)。
はい、違います。
類似画像から、同じようなものを選んで、WEBページを表示すると、
ツル植物であれば、マタタビの葉が白化したものでは、という説がいくつかありましたが、
ツルではなかったですし、花の感じも異なるので、マタタビでもありません。
他のWEBページも探していると、
これですね。
「ハンゲショウの主な見どころは、この葉の花期の様子です。花の咲く頃になると花穂のすぐ下の数枚の葉が、付け根の部分から先端にかけて白く変色します。白い斑の面積はまちまちで、花が終わる頃には緑に戻ります。群生している姿はとても風情があり、幻想的で美しいものです。」
なるほど、確かに幻想的でした。
さて、おおた区民大学「健康維持に役立つ食の知識」の第2回「おおた健康プロジェクトと健康寿命の延伸」の第3回(最終回)です。
健康寿命の延伸のための「(仮称)おおた健康プロジェクト」のアクションプランの「適切な食事」から再開します。
- 適切な食事(毎日プラス一皿の野菜)
- 朝食の欠食率は若者が高い。寝ていたいから。高齢者の朝食を食べる割合が高い(早起きになる。食べる時間ができる。)
- 食塩摂取量は、男性が9.6g、女性が8.4g。これをそれぞれ、8g、7gに改善したい。
- 調味料などでの摂取割合は、醤油16.7%、塩12.4%、味噌11.4%
- その他が20.8%あるが、ドレッシング、出汁の素など。出来合いのドレッシングには塩が多く入っている。出汁の素も塩分が高く、昆布と鰹節でとる出汁とは大違い。塩分ゼロという商品を選んで買うこと。
- お年寄りは塩分を多く摂取しがちだが、これは味蕾がないから(未来がないから、とジョーク)。舌で味を感じる味蕾が少なくなり、味の感じ方が悪くなり、塩を加えないと美味しくない。物足りないと思うくらいでやめるべき。
- 野菜は1日に350gと言われるが、大田区平均は300gくらい。野菜ジュースは栄養としては代わりになるが、食物繊維がとれない。果物は簡単だが、血糖値が上がってしまう。自分はトマトを1個食べるようにしている。
- 食生活指針というものに、こういう食べ方をすれば良い、というのが策定されている(農水省、厚労省、文科省)
- 低糖質ダイエットとか流行しているが、管理栄養士の適切な管理の下でないと、効果は期待できない。
言い過ぎのような気もしますが、栄養士を要請している学校の校長としては、そういう印象なのでしょうね。
第1回の「認知症と食事」の時、医師が「炭水化物を多くとるのは血糖値が上がってよくない」と言っているのを、どう聞いていたのでしょうか(苦)
- おおた健康プロジェクトとしては、
- 毎日プラス一皿の野菜をとる
- よく噛んで食べる
- 注意する3つの「あ」:摂ってはいけない訳ではなく、量の問題。昼に天丼、夜にカツ丼とか、”甘いものは別腹”というのはダメ。注意して摂りましょう、ということ。
- アルコール
- あまいもの
- あぶら
- 主食+9品目でバランス食:マゴタチワヤサシイ(孫たちは優しい)
- ま:豆類(大豆製品含む)
- ご:ごま(種実類)
- た:たまご
- ち:乳(牛乳・乳製品)
- わ:わかめ(海藻類)
- や:野菜、果物
- さ:魚介、肉類
- し:しいたけ(きのこ類)
- い:いも類
- さあにぎやかにいただく:毎日食べたい10食品群・7点以上が目標
- さ:さかな(干物、いか、えび、かにも)
- あ:あぶら(炒め物、バター、ドレッシング)
- に:にく(タンパク質をたっぷりと)
- ぎ:牛乳、乳製品(チーズ、ヨーグルト)
- や:緑黄色野菜(たっぷりと)
- か:海藻(のり、ひじきなども)
- い:いも(蒸して、おやつの代わりに)
- た:たまご(少量でも)
- だ:大豆製品(豆腐、納豆も)
- く:果物(朝食やデザートに)
- 毎日の食事の基本は”おさかなすきやね”:それぞれに健康によい作用(コレステロール値、血糖値を下げる、抗酸化作用など)がある。
- お:お茶(カテキン)
- さ:さかな(DHA、EPA)
- か:海藻(ヨード、アルギン酸)
- な:納豆(ナットウキナーゼ)
- す:酢(クエン酸)
- き:きのこ(β-グルカン)
- や:野菜(各種ビタミン、ミネラル、食物繊維)
- ね:ねぎ(アリシン)
- 休憩(十分な睡眠)
- 健康づくりのための睡眠指針というものがあるが、読んだら眠くなるようなもの(ややウケ)
- おおた健康プロジェクトとしては、
- 十分な睡眠をとる
- 昼休みに10分の仮眠をとる
- アロマオイルやヨガなど、くつろげる方法を取り入れる
- 喫煙・飲酒のリスクの理解と行動(受動喫煙に配慮する。飲酒は節度をもって)
- 大田区の男性の喫煙割合は、25%と東京都の24%よりやや高いが、女性の喫煙割合は9.7%と、東京都の5.2%よりかなり高い。
- 飲酒は、男性が20.6%と東京都の15.1%より高い。女性は全体では4.3%と、東京都の4.6%より低いが、40歳代では23.8%と極端に高い。
- アルコールには身体に悪いアセトアルデヒドが含まれ、24時間経たないと身体から出ない。脳をやられるとアル中。休肝日は、肝臓だけでなく脳にも必要。むかい酒は、アセトアルデヒドに頭を混乱させられているだけ。また、たくさん飲むと、慣れて依存症になりやすい。女性の方がアルコールを受け入れる容量が少ないので、なりやすい。
- お酒と食事の付き合い方:飲みに行く前に乳・乳製品や軽い食事をしていく、など
- 健康によいお酒の量(適量):日本酒1合、ビール大1本(633ml)、など
- 生活習慣病とタバコ:がんになりやすい。主流煙、副流煙、環境たばこ煙(受動喫煙)でも
- リラックスできる、ストレス解消など喫煙の理由はあっても、身体の中では、血管の収縮、心拍数の上昇、中性脂肪の増加など悪いことしかない
- 喫煙に食事は有効:ビタミンA、C、E、緑黄色野菜
- 禁煙は早ければ早いほど効果があり、喫煙を止めたその時点でがん化の進行も阻止できる。
とりわけ、ベトナムはタバコが安いので(一箱100円くらい)、 随分吸っていましたが、勤務時間、飲食の場では吸わない、というコントロールができていたこともあり、日本に帰ってきて、日本のタバコの値段を見て、スパッと止めました。
まあ、健康が理由ではありませんでしたが、健康的にはいい事だったとは思いますね。
- 健康診断・がん検診の受診(定期的に受診し、自分のからだの状態を知る)
- 平成22年から、29年まで、受診率は上がっているが、がん患者も増えている
- 日本人におけるがんの要因:男性は喫煙が一位、二位は感染。女性は逆に感染が一位で、喫煙が二位。
- がんの予防法
- 喫煙:タバコは吸わない。他人のタバコの煙を避ける
- 飲酒:飲むなら、節度のある飲酒をする。
- 食事:偏らずバランスよくとる。
- 身体活動:日常生活を活動的に。
- 体形:適正な範囲内に。
- 感染:肝炎ウイルス感染検査と適切な措置を。機会があればピロリ菌感染検査を。
- 生活習慣の改善
- 食事:1日30品目の食品を目標に
- 運動:1日に30分の速度を
- 休養:1日30分自分の時間をみつけよう(30、30、30と覚える)
- 飲酒:節酒または禁酒、健康によい飲酒量を(百薬の長ではあるが、考えて飲む事)
- 喫煙:禁煙が理想(こちらは、百害あって一利なし)
- ストレス:社会参加や趣味を見つけて楽しむ
- フレイル(虚弱)予防
- 体重減少、疲労感、筋力の低下など
- 加齢性筋肉減弱症、運動器症候群からフレイルティ(虚弱・廃用症候群)に
国、東京都、大田区、大田区の4つの地域(大森、調布、蒲田、糀谷・羽田)の比較です。
特徴的なところだけ言うと、
- 糀谷・羽田は、運動実施率が一番高いものの、喫煙者割合、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている割合も一番高い。
- 日頃の食生活で栄養バランスやカロリーに注意している割合が、男性では調布が、頭一つ高い。
- 朝食をあまりとっていない、ほとんどとっていないは、男性は蒲田が、女性は糀谷・羽田が一番高い。
そして、それらの特性に応じた重点的な取り組みを策定しています。
- 大森地域:がん対策・喫煙、食育の推進、こころの健康・自殺対策
- 調布地域:がん対策、食育の推進、こころの健康・自殺対策
- 蒲田地域:がん対策・喫煙、飲酒、歯と口腔、食育の推進、こころの健康づくりと自殺対策の推進
- 糀谷・羽田地域:がん対策・喫煙、飲酒、歯と口腔、食育の推進
池上は大森地域でした。私個人としては「こころの健康」ですね。
飲酒は、大森地域の重点取り組みに入っていないから、いいか(笑)
これで、以上です。
全3回、校長のコメントにフォーカスして、簡潔に紹介したい思ってはいたのですが、盛り沢山のスライドの内容抜きでは、コンテキストが伝わらないと思い、スライドの内容も、随分と転記しましたので、長くなりました。
タイプするのも疲れました。。。(笑)
おおた区民大学「健康維持に役立つ食の知識」の第3回(最後)「食の国際化について〜世界の国々の食文化への理解と食の安全について〜」は、来週末6/29(土)です。また、自分の理解の整理と共に、ここに紹介します。
ではでは