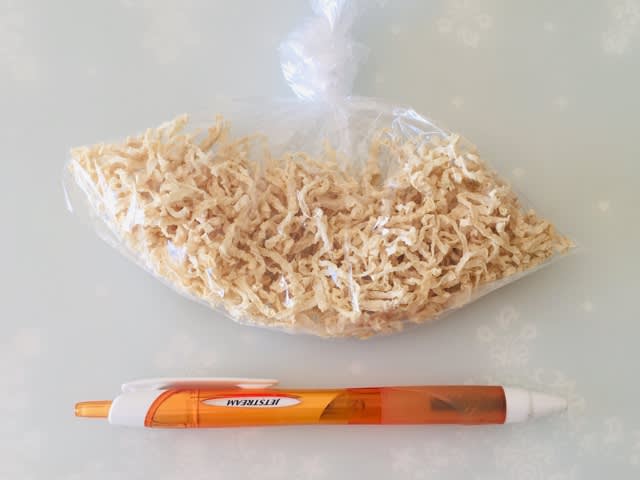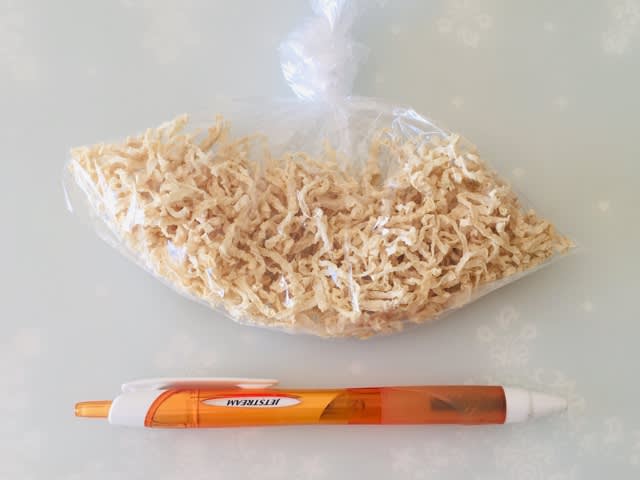英語に「時制の一致」という規則があります。
主節の動詞が「過去時制」のとき、従属節の中の動詞は、主節の動詞のその「過去」を基準にして過去形(またはそれより前を表す形)にシフトさせる必要がある、
というようなことです。
人の言った内容を、例えば日本語だと「かぎかっこ」付きで「直接引用」して別の人に伝えるのか、
あるいは、「◯◯さんはこう言ったよ」という「伝聞」のような形で伝えるのか、の違い(直接話法と間接話法と言います)の時に問題になることが多いです。
例を挙げると、
A: She said, "I'm very busy."
彼女は、「(私は)とても忙しい。」と言った。
という直接話法の文を、
B: She said that she was very busy.
彼女は(自分が)とても忙しいと言った。
という間接話法の文に書き換える場合です。
(注: 私は、自分が、の部分をかっこに入れてあるのは、日本語では何度も主語を繰り返さないのが普通なためです。)
Aの文で、
She
said, "I'
m very busy."
主節の動詞は「
過去形」、
引用部分の動詞は「
現在形」(その人が発した言葉
そのままだから。)
対してBでは、
She
said that she
was very busy.
主節の動詞は「
過去形」、
従属節の動詞も「
過去形」(「彼女が言った」という、
過去の時点での事実だと考えて。)
このコンセプトを生徒に教え込むために、世の英語教員は苦労するわけですが、
さてその反対を論理立って説明しなければならない時が来たのは、
英語教師になって初めてだったかも(^_^;)
そもそも、
「日本語には、英語のような時制の一致の規則は『ない』と断言して良い」
かどうかを、
私はこれまで考えたことがなかったです(-_-)
(ま、日本語教師ではないので…^_^;)
発端はもちろん、
職場の、
その語学能力の高い外国人講師です(^^;)
昨日彼から、
彼女は英語を勉強していると言いました。
という日本語の文について、彼女はいったいいつ英語を勉強しているのか、
というような質問を受けました。
彼の疑問の核心のところを理解するまでが長かったのですが(日本語教師じゃないので^_^;)、
英語と照らして考えると、
もしそれを英語で書くとすると、
直接話法では:
She
said "I'
m studying English."、
間接話法では:
She
said that she
was studying English.
の2通りの書き方が可能だろうけれども、
元の日本語も、実は直接話法と間接話法との両方での表現が可能、ということをまず説明することになりました。
彼はそもそもその、日本語にも直接話法があるということにピンと来ていなかったようです。
日本語では、
直接話法:
彼女は、「(私は)英語を勉強
している。」と
言いました。
間接話法:
彼女は(自分が)英語を勉強
していると
言いました。
で、直接引用しようと、話者の言葉として言い直そうと、「している」の部分の時制は「現在形」のまま。
わざわざそこを、「していた」とすれば、
それは彼の言語では、
She
said, "I
was studying English."
または、
She
said that she
had been studying English.
ということになり、
緑の部分は「過去より前の過去(=過去完了)」を表すので、伝えたい事実が変わって来ます。
実は私のような文系感覚人間には、
そもそもこういうことを即座に把握して論理立って説明するのはとても難しいです(^^;)
ましてこれまでは、日本語の視点から英語文法を教えているだけだったのが、
英語視点の人から見たときの日本語文法を英語で説明しろとは、
これはまあほぼ反対方向の図式であり、
英語が母語ではない身にいきなり、は、
実際問題かなり無理なことではないでしょーか?(^^;)
(まあ、これは、海外で英語を使って教えていらっしゃる日本語教師の方はやっていらっしゃること、あるいはやるべきことではないかと思います。とすると、現在実は公の資格としては存在していない日本語教師というものは、日本語話者なら誰でもなれるものでは到底なく、実際にはかなりのスキルを必要とすることでしょう。)
というような具合で、
かなりのすったもんだというか、
もうここでは書ききれないくらいのあれこれのあった後に、
「彼女が英語を勉強している」のは、彼女がそれを言った「過去の時点」での話だと考えるのが妥当である、というのを確認した上で、
最終的に何とか、
「そーか日本語では動詞の部分を全部過去形にしなくても良いのか💡」
という、とても単純なところにカナダ人を導いた私でした。
もう、ゼイゼイヽ(;▽;)ノ
いや、ここまで読んで下さった方こそゼイゼイ( ;´Д`)でしょう…。
申し訳ありません…(*゚▽゚)ノ