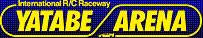◆ メンテナンスノート ◆
さてそれでは、DB02の気になる部分について、私のマシンがどういった経緯を辿っているのか、ここでまとめて書きとめておくことにしましょう。私が所有している1台は、マシンに最も高い基本性能を要求する、
全日本選手権のレギュレーションに基づいたレースを戦い続けています。DB02というモデルのそもそもの位置付けを考慮すれば、ストックに近い状態での使用であちこちに破綻をきたしてしまうのも、ある程度は仕方の無いこと。私としてはリリースと同時にメイン機として採用することを決意した以上、簡単には諦めたくないという意地の気持ちもあって、問題箇所については知恵を絞り、何とかレースへの出場を継続しようと奮起してきました。そうこうしているうちにデビューから半年が経過し、今ではメーカーからも立派な対策・強化品が提供されつつあるという状況。ハードなレースシーンへの投入も、当初に比べれば敷居が低くなってきています。
■ドライブカップについて■
シェイクダウン以来、大いに私を苦しめてきたドライブカップ。リヤインプット部の破損が発覚した当時のショックは相当なもので、DB02計画を早々に頓挫させ兼ねない、非常に深刻な問題でした。別シャーシからのパーツ流用を思い付けていなかったらと思うと、本当に背筋の寒くなる思いです。

数ヶ月に渡り頑張ってくれた当の
TBエボV用ユニバーサルジョイントも、とうとう写真のようなみすぼらしい状態に。ニードルピンの受け部が楕円形に引き伸ばされています。アルミ製であるだけに、いつまでも持ち堪えられるものではないということは分かっていましたが、どちらかと言えば予想よりも長く、私に快適な走行環境を与え続けてくれました。

…で、ここで出てくるのが大方の予想に反し、キットノーマルのドライブカップ。この樹脂製カップについては過去記事でも言及しました通り、きちんとグリスアップさえしておけば、そうそう壊れるシロモノでもないという話があります。これが私にとっては非常に懐疑的な訳で、まずはこいつが本当に問題のないパーツなのか、確認しておく必要があったわけです。今回は写真の通り、はみ出るくらいにたっぷりと
AWグリスを充填した上で、いざ走行開始。

実は本心では結構期待していたのですが、結果としては見ての通り。こうなるのに3分掛かりませんでした…正に
瞬殺。やはり私が今の環境で操縦すると、どうやっても壊れてしまうようです。少し残念。

と言う訳で最終的には切り札、メーカー純正の強化カップ
(Op.1389:399 YEN)がお出まし。こいつは金属製なので、今後は注意深くこの部分の損耗チェックをする必要も無くなるでしょう。
【
補足01:樹脂製カップとの使い分け】
現時点で上記の金属製カップを投入しているのは、リヤのインプットシャフト側のみです。他はグリスアップした樹脂製のカップで十分の印象で、今のところは壊れそうな雰囲気も見られません。
【
補足02:ピン抜け防止処理の続報】
樹脂製カップのピン抜け対策として紹介しました受け穴の拡大工作(過去記事
第14回を参照)について、これは有効に機能しています。私は2.2mmのピンバイスを用いて穴の径を大きくしていますが、この処置がカップの耐久性にマイナスの影響を及ぼすことはないでしょう。
【
補足03:ユニバーサル化の是非】
メーカーからは既に、ドライブトレイン強化の最終兵器と目されるユニバーサルジョイント
(Op.1404:3,465 YEN)がリリースされています。駆動効率の点で、このパーツが他の追随を許さない効果を発揮するのは明らか。ただ、耐久性のみにフォーカスすれば、現状の装備でも問題はないはずですので、投入の判断は全日本選手権の本戦をこのマシンで戦うか否か、に連動する形になると思います。
■リヤのデフギヤについて■
先のカップに並ぶDB02の泣きどころ、それがデフギヤ(ベベル/リング両ギヤ)の脆弱性です。重要な局面で幾度となく破損し、その度にベソをかきながら必死の修復を行ってきました。これまでは現場の処理で適当にシムを入れたりしてきましたが、これは一度、本格的に腰を据えてクリアランスの確認を行う必要があると判断。

その手法は極めて単純で、ベベルギヤ側とリングギヤ側、各々について、シムを0.1mm追加してはギヤボックスを閉める(ちゃんとビス留め迄します)という作業を繰り返し、動きが極端に渋くなるギリギリ手前のポイントを探り出す… という行程です。なお、取り掛かりの前段として、ギヤボックスは強化品
(Op.1349:840 YEN)への交換を済ませています。ギヤ舐めはケースのたわみが原因となることもある、というアドバイスを戴いてのことですが、これも正直、個人的には信じ難い話。一応、ということでやっておきました。
で、実際に作業をやってみて分かったのは、まずベベル側にはせいぜい、0.1mmくらいのシムしか追加出来ない、ということ。具体的にどこ、というのは分からないままなのですが、それ以上のシムを追加すると、ボックスを閉めた時に干渉が生じ、動きが渋くなります。一方のリングギヤ側は、先に紹介した(過去記事
第10回を参照)0.3mmシムの短い側への入替に加え、その短い側にさらにもう1枚、0.1mmを追加するぐらいがギリギリでした。
上記の検証を経た現在、私のDB02のリヤデフギヤは耐久記録を更新中です。ただ、最近は駆動系への負担が比較的少ない、ABCでの走行が続いており、その辺りを加味すれば、実際どの程度の効果があったのかを推し量るのは難しいところですね。
【
補足01:調整の誤差について】
シムを使った調整は、個人の好みとマシン個体差、2つの要素でその結果が微妙に変わってきます。本記事では具体的な数値を出しておきましたが、最終的には自身の感覚を信じて作業をする方が良いでしょう。
【
補足02:ストレスが掛かるのはリヤのみ】
フロントのデフギヤについては、上述したような神経質なバックラッシュ調整を行う必要は無いと思います。リングギヤ側の0.3mmを短い側に移動するだけで、十分に耐え続けてくれる筈です。
■デフジョイントカップについて■
これも負荷の大きいリヤで顕著に見られる症状ですが、キットノーマルのジョイントカップは、連結部の磨耗がかなりの速度で進行します。

TRF511を使っていた当時は全く削れる様子がなかったことから、念の為502Xのパーツ取り寄せ表をチェックしてみると、正にビンゴでした。DB02用のものと全く同形である筈なのに、価格は502X用の方が高いのです。で、確証を得る為カスタマーどのに質問をしてみると、やはり両者にはその硬度に違いがあるとのこと。早速購入
(品番 19804434:1,806 YEN)し、リヤ側については既に交換、使用中です。502X用になって以後、連結部の磨耗は全く見られなくなりました。