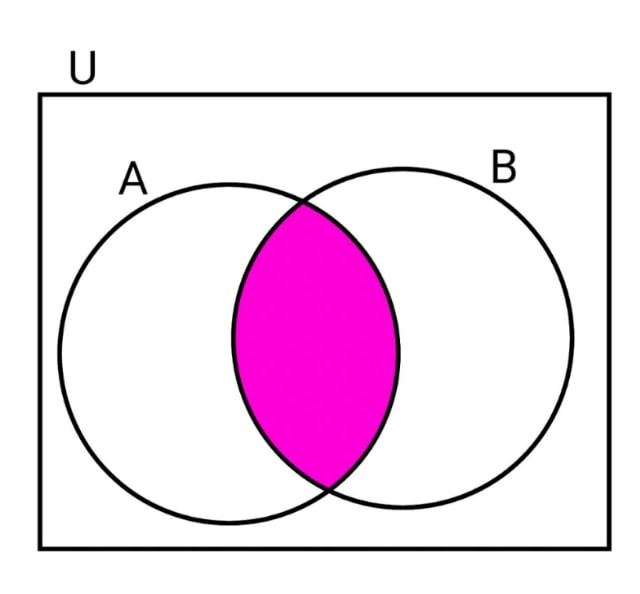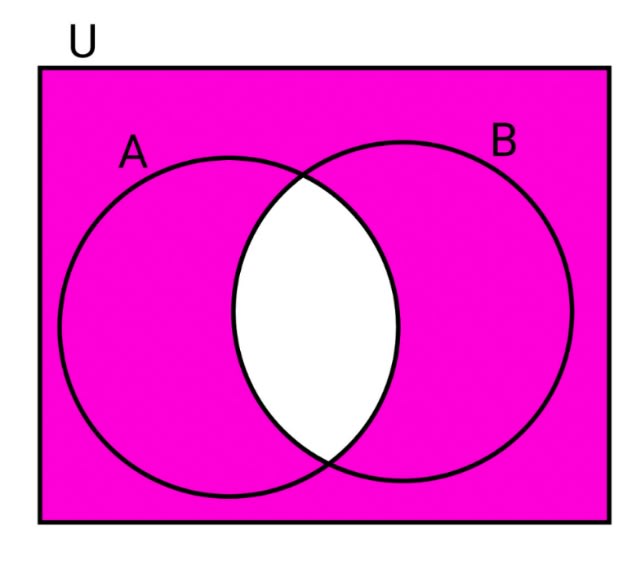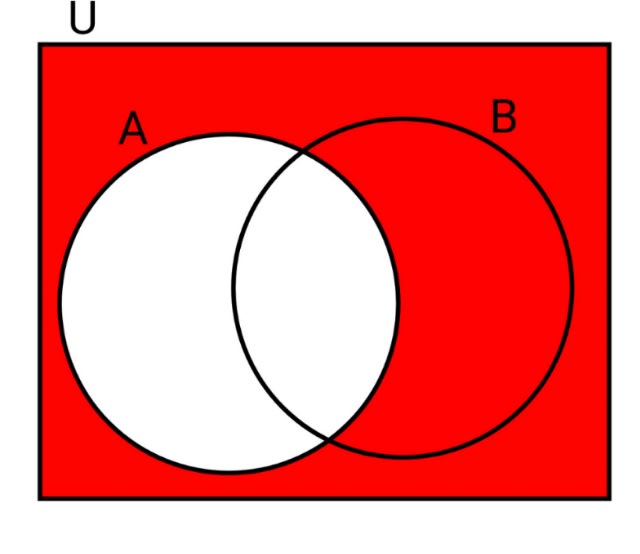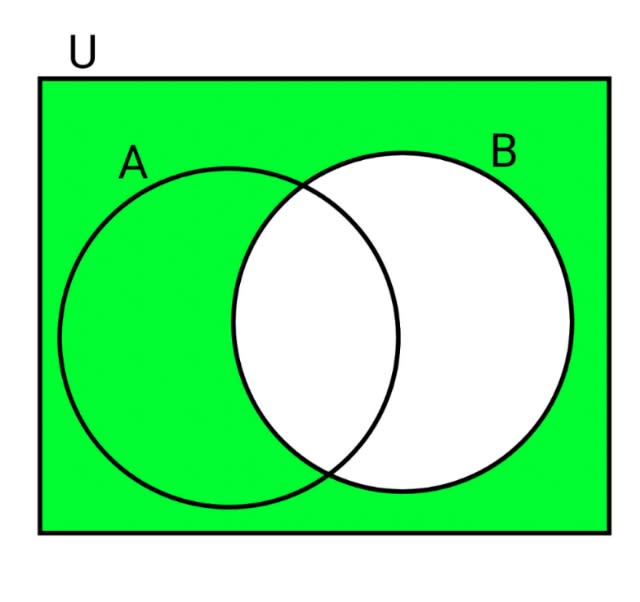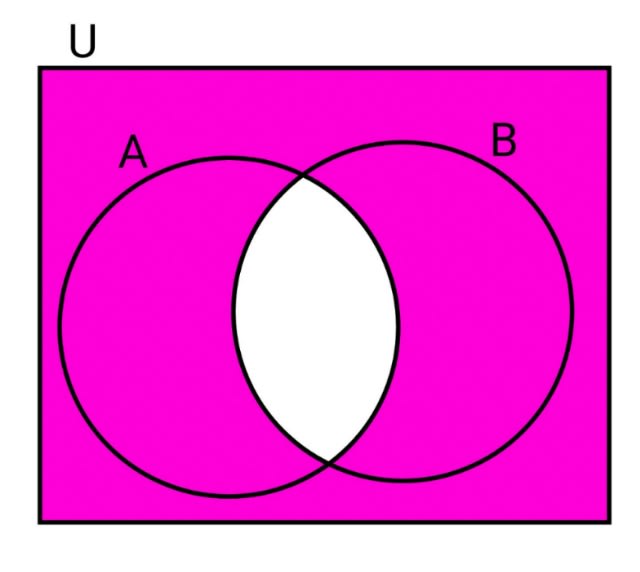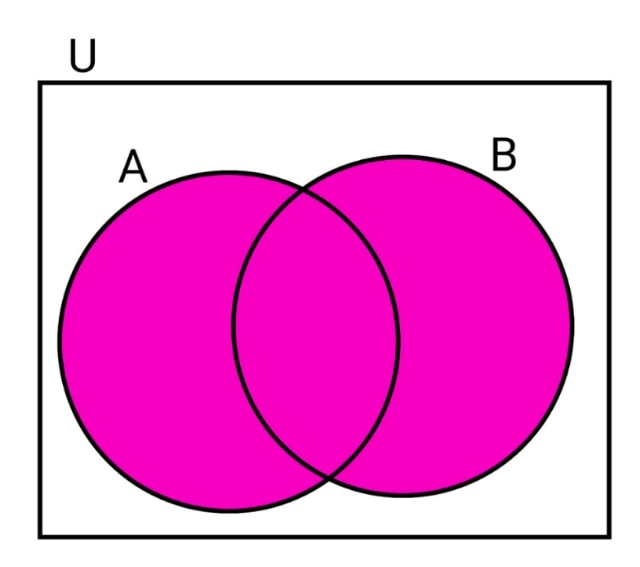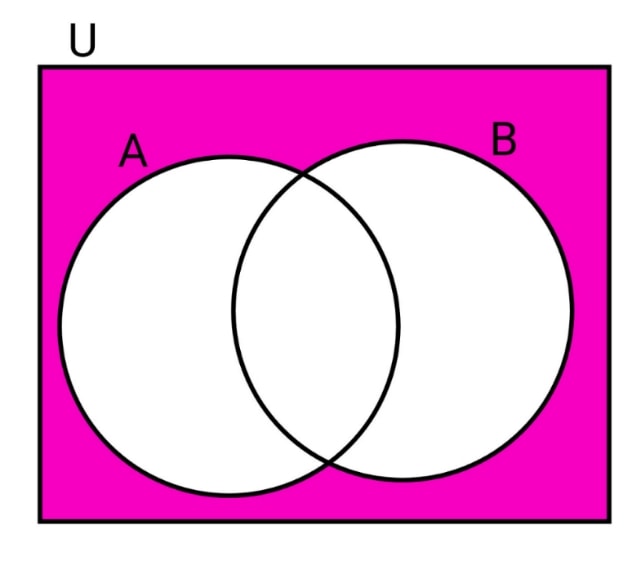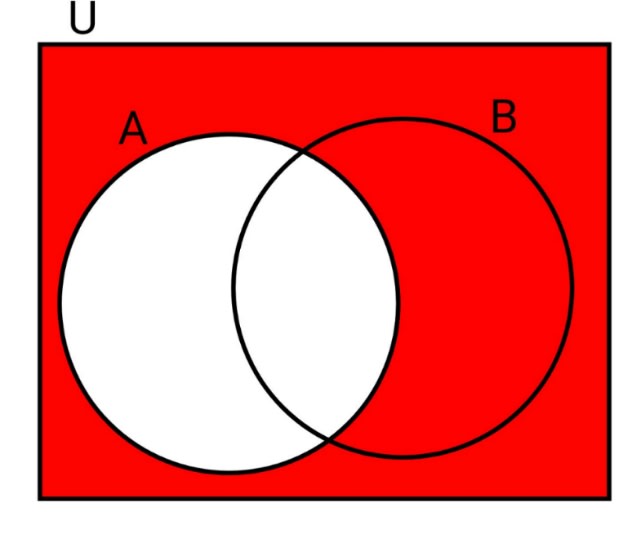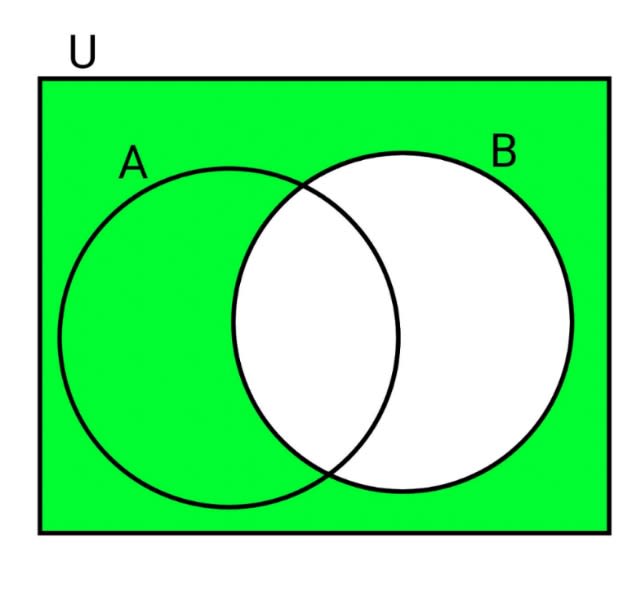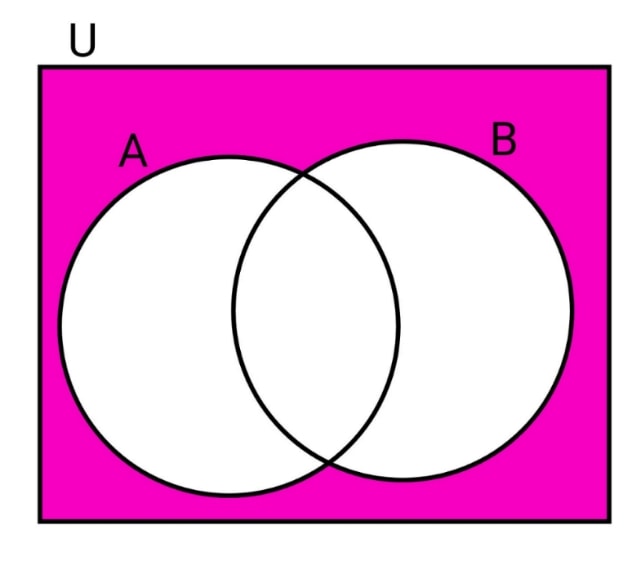【第5章】
(9)命題
正しいか正しくないか判断できる文を、「命題」という。正しい場合は「真」といい、正しくない場合は「偽」という。偽である例を「反例」という。
条件「p」に対し、条件「p でない」を、
条件「p」の「否定」といい、¬p で表す。
例)否定¬p
偶数↔奇数
=↔≠、>↔≦、<↔≧
p「nは偶数」、¬p「nは奇数」
p「x>3」、¬p「x≦3」
命題p⇒qの真偽は、条件pが真であるすべての場合の条件qの真偽を問うているのである。
条件qがすべて真のとき、命題p⇒q は真
条件qが偽の場合があるとき、命題p⇒qは偽
p を「仮定」、q を「結論」という。
命題の真偽の判定には集合を使う。
条件p が真であることがらの集合をP,
条件q が真であることがらの集合をQ
とする。
・P⊂Q ⇔ 命題p⇒q が真
・P⊂Q でないときは、命題p⇒q は偽で、
P の要素だがQ の要素でないことがらが
反例になる。
例5)p:xは馬である
q:xは動物である
馬⊂動物 だから、命題p⇒q は真
例6)p:xは3の倍数である
q:xは9の倍数である
(3の倍数)⊃(9の倍数)だから
命題p⇒q は偽、反例はx=3