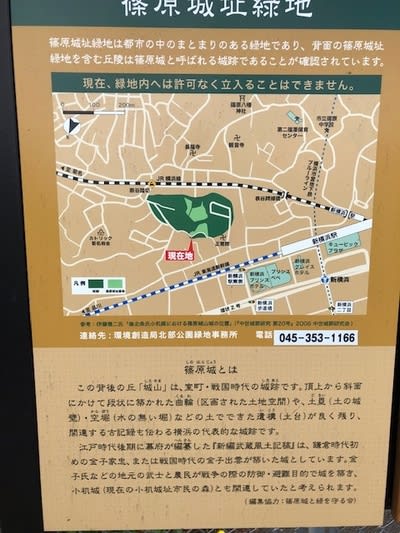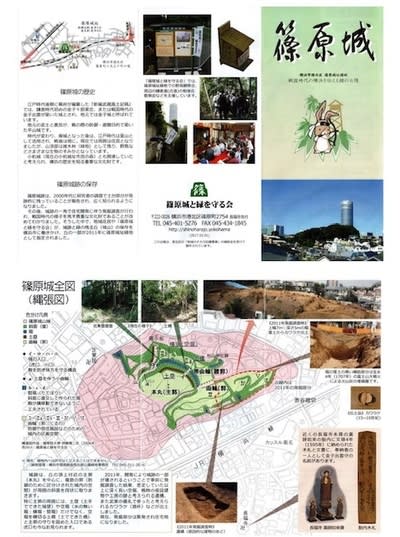近所の城址巡りもかなりこなしてきた結果、だんだんと遺構が少ない城址のレベルまで探索の範囲が広がってきた。しかし、調べるとまだまだ沢山の城址が存在することがわかった。今回紹介するのは『川和城』と『佐江戸城』。この2つの城址は、かなり近い距離に並んで創られていたようで、一気に2か所の城址を周れるのは何ともラッキーである。
1) 川和城
川和とは横浜市青葉区の市ヶ尾駅から少し港北方面に進んだエリアで、横浜市営地下鉄グリーンラインに新設された川和駅のすぐそば。実はこの川和はかなり歴史のあるエリア。その昔は江戸に続く中原街道とその他の街道(現旧上麻生道路)が近くを通る交通の要であり、多くの人が通過したことで賑わいを見せた町だったらしい。今では街道沿いはかなりの田舎だが、川和の北部は新興住宅街であり、閑静な町並みに様変わりしている。

そんな川和に、その昔川和城というお城があったらしい。やはり小机城の支城として機能していたらしいのだが、この川和のエリアはかなり小高い丘になっており、鶴見川と恩田川がちょうど合流する地域でもあって、城を築くには最高のロケーションであったに違いない。
まずは車を川和駅近くのTimes駐車場に停め、旧上麻生道路沿いを南下。途中にある妙蓮寺に立ち寄った。どうやらこの妙蓮寺の裏にある墓地と空き地が、川和城跡らしいのだ。どこまで遺構らしきものに遭遇出来るかわからないが、とりあえずきなこと行ってみることに。



妙蓮寺は雰囲気のある良いお寺であった。お地蔵さんたちはみなコロナ対策のマスクをしていた(笑)。



本堂は残念ながら改修工事中だったが、薬師堂は歴史を感じさせる創り。


そして妙蓮寺の右側にあった細い路地を登って、お寺の裏手に周ってみる。すると妙蓮寺の墓地に出た。墓地エリアとお寺の境内の間には大きな段差があったが、これも土塁の跡かもしれない。



ちょっと高台になっている墓地からの眺めは抜群。ここにお城の本丸があったのだとすると、昔お城からもこの見事な景色を見ていたのだろうか。

更に墓地を登って行くと、墓地の一角に土塁らしき遺構を発見。そしてその先には広い空き地エリアが。ここがまさに川和城の本丸跡なのだ。本丸跡にはなにやらデコボコした形状もあり、何かの遺構ではないかとも思えてくる。また、確かに城址らしき土塁跡も何箇所かに見てとれる。これは思ったより大きな収穫だった。



川和城から少し北に行くと、川和市民の森という自然公園がある。しかし、その昔はこのエリアも城の一部であったのではないだろうか。立派な貞Mエリアで現在は遊歩道なども作られ、最高に気持ちが良い散歩スャbトになっているが、城の北を守るにはとても良い環境だ。





更に北に進むと、川和富士見ヶ丘公園がある。ここにはかなり立派な富士塚があり、まるで古墳のような見事な形状。昔から、町の人々はこの富士塚から富士山を眺めて楽しんでいたのだ。


頂上に登ると、何とも絶景。川和城辺りも良く見えるし、遠くは横浜みなとみらいの高層ビル群まで見える。川和城があった頃は、この富士塚も良い見晴らしャCントであったことは間違いないだろう。



また注目すべきは、この富士見ヶ丘公園のすぐとなりには、遊歩道で繋がっている都田公園という公園もある。そしてこの公園の周辺の地名が、『二の丸』というのだ。まさに川和城の二の丸がこの辺りだったのではないかと思うし、都田公園の敷地こそが二の丸の跡なのかもしれない。あまり遺構らしきものは確認出来なかったが、地名は歴史を物語ってくれるものだ。

更に興味深いことに、この近くには月出松公園という公園もあり、何か歴史を感じさせる名前だと思っていたら、ここには古墳が残っていた。縄文・弥生時代から、この川和エリアにも人がかなり住んでいたことを物語っているのだ。

2) 佐江戸城
川和城から更に20分ほど住宅街を南に歩くと、佐江戸城がある。まずはツツジが見事な石橋の交差点が大きな目印。


この横の坂を上がって行くと、杉山神社と無量寺というお寺が並んで建っているが、この無量寺の裏手の墓地エリアが佐江戸城だったらしい。無量寺は、南港北では一番歴史のあるお寺らしく、かなり立派な創りであった。




お寺の敷地の一部(しかも墓地エリア)が昔の城址とは、まさに川和城と同じパターンである。無量寺の周辺には多くの畑エリアがあったが、この辺りも城址の一角であったらしい。



無量寺の墓地から細い路地を登ると、『御嶽三柱大神』の碑があったが、まさにこの碑が建っているエリアが本丸跡だったとのこと。

杉山神社の裏に周ると、川和城同様、ここにも土塁や堀切跡らしき地形が見て取れたが、これが恐らく遺構なのだろう。佐江戸城ではあまり遺構が確認出来るとは期待していなかっただけに、大きな収穫とあった。



佐江戸城は、猿渡氏が創ったお城と言われているが、無量寺にはこの猿渡氏のお墓がある。これも重要な史跡である。

それにしても、川和と佐江戸は共に自宅から車で20分くらいの場所だが、こんなところにも城址があったとは驚きだ。でも鶴見川沿いに建っていた小机城、獅子ヶ谷城、亀井城、三輪城、などを考えれば、川和・佐江戸エリアも川と小高い丘に囲まれ、街道沿いという絶好のロケーションであったことを考えると、城址があっても全く不思議ではない、いやむしろ好都合な場所であったわけで、すっかり納得してしまった。
1) 川和城
川和とは横浜市青葉区の市ヶ尾駅から少し港北方面に進んだエリアで、横浜市営地下鉄グリーンラインに新設された川和駅のすぐそば。実はこの川和はかなり歴史のあるエリア。その昔は江戸に続く中原街道とその他の街道(現旧上麻生道路)が近くを通る交通の要であり、多くの人が通過したことで賑わいを見せた町だったらしい。今では街道沿いはかなりの田舎だが、川和の北部は新興住宅街であり、閑静な町並みに様変わりしている。

そんな川和に、その昔川和城というお城があったらしい。やはり小机城の支城として機能していたらしいのだが、この川和のエリアはかなり小高い丘になっており、鶴見川と恩田川がちょうど合流する地域でもあって、城を築くには最高のロケーションであったに違いない。
まずは車を川和駅近くのTimes駐車場に停め、旧上麻生道路沿いを南下。途中にある妙蓮寺に立ち寄った。どうやらこの妙蓮寺の裏にある墓地と空き地が、川和城跡らしいのだ。どこまで遺構らしきものに遭遇出来るかわからないが、とりあえずきなこと行ってみることに。



妙蓮寺は雰囲気のある良いお寺であった。お地蔵さんたちはみなコロナ対策のマスクをしていた(笑)。



本堂は残念ながら改修工事中だったが、薬師堂は歴史を感じさせる創り。


そして妙蓮寺の右側にあった細い路地を登って、お寺の裏手に周ってみる。すると妙蓮寺の墓地に出た。墓地エリアとお寺の境内の間には大きな段差があったが、これも土塁の跡かもしれない。



ちょっと高台になっている墓地からの眺めは抜群。ここにお城の本丸があったのだとすると、昔お城からもこの見事な景色を見ていたのだろうか。

更に墓地を登って行くと、墓地の一角に土塁らしき遺構を発見。そしてその先には広い空き地エリアが。ここがまさに川和城の本丸跡なのだ。本丸跡にはなにやらデコボコした形状もあり、何かの遺構ではないかとも思えてくる。また、確かに城址らしき土塁跡も何箇所かに見てとれる。これは思ったより大きな収穫だった。



川和城から少し北に行くと、川和市民の森という自然公園がある。しかし、その昔はこのエリアも城の一部であったのではないだろうか。立派な貞Mエリアで現在は遊歩道なども作られ、最高に気持ちが良い散歩スャbトになっているが、城の北を守るにはとても良い環境だ。





更に北に進むと、川和富士見ヶ丘公園がある。ここにはかなり立派な富士塚があり、まるで古墳のような見事な形状。昔から、町の人々はこの富士塚から富士山を眺めて楽しんでいたのだ。


頂上に登ると、何とも絶景。川和城辺りも良く見えるし、遠くは横浜みなとみらいの高層ビル群まで見える。川和城があった頃は、この富士塚も良い見晴らしャCントであったことは間違いないだろう。



また注目すべきは、この富士見ヶ丘公園のすぐとなりには、遊歩道で繋がっている都田公園という公園もある。そしてこの公園の周辺の地名が、『二の丸』というのだ。まさに川和城の二の丸がこの辺りだったのではないかと思うし、都田公園の敷地こそが二の丸の跡なのかもしれない。あまり遺構らしきものは確認出来なかったが、地名は歴史を物語ってくれるものだ。

更に興味深いことに、この近くには月出松公園という公園もあり、何か歴史を感じさせる名前だと思っていたら、ここには古墳が残っていた。縄文・弥生時代から、この川和エリアにも人がかなり住んでいたことを物語っているのだ。

2) 佐江戸城
川和城から更に20分ほど住宅街を南に歩くと、佐江戸城がある。まずはツツジが見事な石橋の交差点が大きな目印。


この横の坂を上がって行くと、杉山神社と無量寺というお寺が並んで建っているが、この無量寺の裏手の墓地エリアが佐江戸城だったらしい。無量寺は、南港北では一番歴史のあるお寺らしく、かなり立派な創りであった。




お寺の敷地の一部(しかも墓地エリア)が昔の城址とは、まさに川和城と同じパターンである。無量寺の周辺には多くの畑エリアがあったが、この辺りも城址の一角であったらしい。



無量寺の墓地から細い路地を登ると、『御嶽三柱大神』の碑があったが、まさにこの碑が建っているエリアが本丸跡だったとのこと。

杉山神社の裏に周ると、川和城同様、ここにも土塁や堀切跡らしき地形が見て取れたが、これが恐らく遺構なのだろう。佐江戸城ではあまり遺構が確認出来るとは期待していなかっただけに、大きな収穫とあった。



佐江戸城は、猿渡氏が創ったお城と言われているが、無量寺にはこの猿渡氏のお墓がある。これも重要な史跡である。

それにしても、川和と佐江戸は共に自宅から車で20分くらいの場所だが、こんなところにも城址があったとは驚きだ。でも鶴見川沿いに建っていた小机城、獅子ヶ谷城、亀井城、三輪城、などを考えれば、川和・佐江戸エリアも川と小高い丘に囲まれ、街道沿いという絶好のロケーションであったことを考えると、城址があっても全く不思議ではない、いやむしろ好都合な場所であったわけで、すっかり納得してしまった。