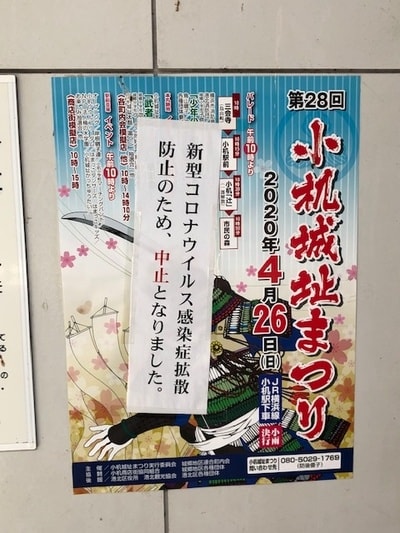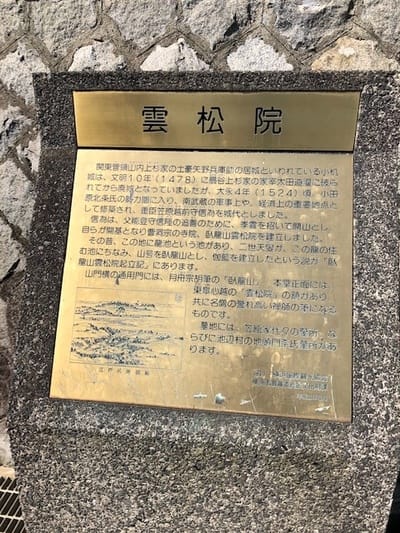城マニアにも関わらず、最近お寺巡りに明け暮れていたが、まだ攻略出来ていなかった念願の城址に週末挑戦した。
これまで比較的近所の城址を多く散策してきた。茅ヶ崎城址、小机城址、枡形山城址、亀井城址、沢山(三輪)城址、深見城址、成瀬城址、荏田城址・・・。近所である武蔵の国にも、その昔かなり数多くの城が築かれており、城址マニアには見所満載である。
そして、近所でまだ訪問出来ていなかった武蔵地区最後の大物城址、小澤城址を今回ついに訪れた。

小澤城址は、よみうりランドの上の小高い多摩丘陵に存在する。このエリアを地図で俯瞰して見ると、その昔浅間山という、この辺りでは一番小高い山があり、そして山の麓には三沢川、近くには多摩川が流れており、遠くの敵を監視し、周囲に睨みを効かせつつ、川を使った天然の要塞として築くにはちょうど良い立地の山城であったと想像される。多摩川の下流には枡形山城があり、鶴見川の西方面には、亀井城、沢山城もあり、地域で連携しながら守りを固めていたと思われる。

小澤城は小澤郷を領地とした稲毛三郎重成の城であり、妻は源頼朝の妻政子の妹であり、頼朝の重臣として信頼を受けていた人物。晩年この城を長男の小澤小太郎重政に譲り、自分は枡形山城に移ったと言われている。
そんな小澤城だが、現在は小澤城址多摩自然遊歩道として、自然公園のように整備されており、その遺構を見に行くことが出来る。場所は京王線よみうりランド駅からすぐ南。自宅からは百合が丘駅を抜けて世田谷通りに出て、そこから車でよみうりランドへ向かうコース。車で片道20分ほどなので、港北に行くのと時間的にはあまり変わらないか。

城址へのアプローチは、まず京王よみうりランド駅そばの駐車場に車を停め、徒歩でジャイアンツVロードという坂を上がっていく。ここは駅からジャイアンツ球場への続く道で、歩道にはジャイアンツ選手の手形プレートが埋められている。僕の好きな原監督、坂本選手、阿部現二軍監督、往年の名プレイヤー篠塚、高橋由伸前監督などの手形を観賞。






ジャイアンツVロードの途中に穴澤天神社という神社への入り口がある。

なんとこの神社、創建423年というから、かなり歴史のある神社。






また神社直下の崖下には東京の名湧水57選に選ばれている湧水が湧き出ており、地元民が汲みにくるらしいのだ。

そして、全く目立たないのだが、この穴澤天神社から小澤城址に登る小さな入り口があるが、いきなり結構険しい。

ここをきなこと何とか登って行くと、途中から城跡らしき遺構が満載でテンションが上がる。空堀や堀切らしきが盛りだくさんなのだ。



そして暫く山道を登ると、少し開けた場所に出るが、ここが城の本丸的な場所だろう。小澤城址の碑が建っており、眺めながらきなことしばし当時に思いを馳せる。



ここから東に進むと、浅間山の山頂まで道が続くが、途中に遺構が満載。土塁や空堀などが至るところにあり、城址としてはかなり質の良い状態で遺構が残っているのは素晴らしい。





昔使われていた古井戸の跡もあり、かなり興味深い。

少し進むと、小澤峰と呼ばれる物見台があり、昔はここから遠く江戸から秩父方面まで広く見渡せたという。



そして浅間山の山頂へ。小澤城は、高さ90mのこの浅間山、先程通過した小澤峰、八州台という3つの峰を中心に構成されていた城であり、地元では一般に“天神山”と呼ばれ親しまれていたようだ。




平場なども結構あるが、武士の居館などがあったらしい。


この小澤城、幾つも散策コースがあり、軽めのハイキングにはちょうど良いコースとなっている。入り口も全部で4か所からアプローチ出来るようになっており、帰りはジャイアンツ球場の脇から出てきた。


今回、念願であった小澤城址をついに攻略したが、手付かずの自然な状態で遺構も多く保存されており、城址としては小机城址にも匹敵する見事な城址であった。このエリアを管理・整備・保存している多摩地区の皆さんの努力には本当に一城マニアとして感謝したいし、歴史的な城址の遺構を後世に残すのはやはりとても尊い仕事である。
これまで比較的近所の城址を多く散策してきた。茅ヶ崎城址、小机城址、枡形山城址、亀井城址、沢山(三輪)城址、深見城址、成瀬城址、荏田城址・・・。近所である武蔵の国にも、その昔かなり数多くの城が築かれており、城址マニアには見所満載である。
そして、近所でまだ訪問出来ていなかった武蔵地区最後の大物城址、小澤城址を今回ついに訪れた。

小澤城址は、よみうりランドの上の小高い多摩丘陵に存在する。このエリアを地図で俯瞰して見ると、その昔浅間山という、この辺りでは一番小高い山があり、そして山の麓には三沢川、近くには多摩川が流れており、遠くの敵を監視し、周囲に睨みを効かせつつ、川を使った天然の要塞として築くにはちょうど良い立地の山城であったと想像される。多摩川の下流には枡形山城があり、鶴見川の西方面には、亀井城、沢山城もあり、地域で連携しながら守りを固めていたと思われる。

小澤城は小澤郷を領地とした稲毛三郎重成の城であり、妻は源頼朝の妻政子の妹であり、頼朝の重臣として信頼を受けていた人物。晩年この城を長男の小澤小太郎重政に譲り、自分は枡形山城に移ったと言われている。
そんな小澤城だが、現在は小澤城址多摩自然遊歩道として、自然公園のように整備されており、その遺構を見に行くことが出来る。場所は京王線よみうりランド駅からすぐ南。自宅からは百合が丘駅を抜けて世田谷通りに出て、そこから車でよみうりランドへ向かうコース。車で片道20分ほどなので、港北に行くのと時間的にはあまり変わらないか。

城址へのアプローチは、まず京王よみうりランド駅そばの駐車場に車を停め、徒歩でジャイアンツVロードという坂を上がっていく。ここは駅からジャイアンツ球場への続く道で、歩道にはジャイアンツ選手の手形プレートが埋められている。僕の好きな原監督、坂本選手、阿部現二軍監督、往年の名プレイヤー篠塚、高橋由伸前監督などの手形を観賞。






ジャイアンツVロードの途中に穴澤天神社という神社への入り口がある。

なんとこの神社、創建423年というから、かなり歴史のある神社。






また神社直下の崖下には東京の名湧水57選に選ばれている湧水が湧き出ており、地元民が汲みにくるらしいのだ。

そして、全く目立たないのだが、この穴澤天神社から小澤城址に登る小さな入り口があるが、いきなり結構険しい。

ここをきなこと何とか登って行くと、途中から城跡らしき遺構が満載でテンションが上がる。空堀や堀切らしきが盛りだくさんなのだ。



そして暫く山道を登ると、少し開けた場所に出るが、ここが城の本丸的な場所だろう。小澤城址の碑が建っており、眺めながらきなことしばし当時に思いを馳せる。



ここから東に進むと、浅間山の山頂まで道が続くが、途中に遺構が満載。土塁や空堀などが至るところにあり、城址としてはかなり質の良い状態で遺構が残っているのは素晴らしい。





昔使われていた古井戸の跡もあり、かなり興味深い。

少し進むと、小澤峰と呼ばれる物見台があり、昔はここから遠く江戸から秩父方面まで広く見渡せたという。



そして浅間山の山頂へ。小澤城は、高さ90mのこの浅間山、先程通過した小澤峰、八州台という3つの峰を中心に構成されていた城であり、地元では一般に“天神山”と呼ばれ親しまれていたようだ。




平場なども結構あるが、武士の居館などがあったらしい。


この小澤城、幾つも散策コースがあり、軽めのハイキングにはちょうど良いコースとなっている。入り口も全部で4か所からアプローチ出来るようになっており、帰りはジャイアンツ球場の脇から出てきた。


今回、念願であった小澤城址をついに攻略したが、手付かずの自然な状態で遺構も多く保存されており、城址としては小机城址にも匹敵する見事な城址であった。このエリアを管理・整備・保存している多摩地区の皆さんの努力には本当に一城マニアとして感謝したいし、歴史的な城址の遺構を後世に残すのはやはりとても尊い仕事である。