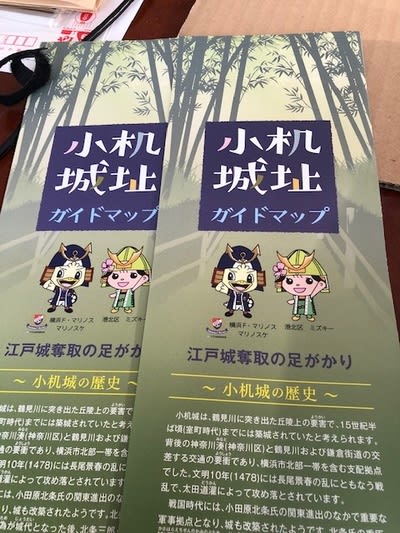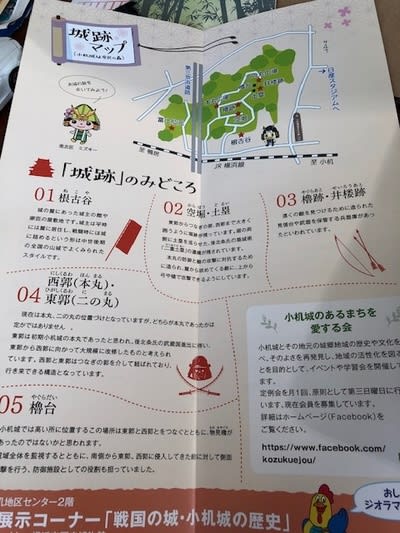近所の城跡を色々と探している中で、まだ行ってない近所の城跡をまた一つ見つけてしまった。それは『有馬城』という城跡で、なんと自宅から相当近い東急田園都市線/鷺沼駅から徒歩10分くらいの場所にある城跡である。
早速、またきなこと一緒に散歩がてら行ってみることに。鷺沼駅近くの駐車場に車を停め、鷺沼駅ロータリーから出発。鷺沼駅はちょうど丘の上にある駅で、南北に下り坂となっている。


駅から南方面に下って行くと、約10分くらいで『有馬城』エリアに到着。このエリアは少し小高い丘になっており、有馬川という小さな鶴見川の支流があるのだが、その昔はこの有馬川も大きな川だった可能性があるし、大山街道が見渡せた場所だったらしい。



現在“せど梨園”という広いエリアの梨園があるが、まさにこの梨園こそが『有馬城』のあった場所らしい。またせどとは井戸・水源を意味する言葉らしいので、歴史が地名に刻まれて残されている。遺構らしきエリアはかなり少ないが、このせど梨園の両側にせり立つ斜面は有馬城の面影を見ることが出来る。ブラタモリをいつも見ているせいか、地理を見ているだけで色々と想像が出来るようになってしまった。





西側には有馬城に関する内容が記載された看板を発見。

有馬城の近くには、結構古い家屋が残っている。鷺沼エリアは新興住宅街として有名だが、この有馬城エリアにはかなり古い家が残されているというのはとても面白いし、家の近所にも歴史を感じられるスャbトが残っているのも素晴らしい。

城跡の近くには、神社やお寺が残されていることが多いが、例に漏れず、有馬城の近くにも神明神社と福王寺があった。まずは神明神社を訪れたが、きなこと一緒に長い階段を登ると、比較的立派な境内があった。この神明神社の裏側の道は神明坂と呼ばれているようだ。





そして有馬城の西側には、福王寺がある。このお寺もなかなか立派で、裏側の道も土塁のような跡が見受けられる。昔はこの神明神社と福王寺も含めて、有馬城エリアを形成していたのだろう。また色々と妄想すると結構楽しいものだ。




田園都市線沿いの街は、すっかり開拓されて新しい街になっているが、昔から家屋や旧道などの面影が僅かに残っているエリアもあり、歴史を感じさせてくれる。城跡の醍醐味も、僅かに残されている遺構などを確認しながら、色々と妄想を膨らませて、その歴史に思いを馳せることが出来るところにある。自宅近くは、多摩川と鶴見川に挟まれているエリアでもあり、また鎌倉街道や大山街道などの旧道も通っていたエリアでもあり、江戸に向かう通過点、そして鎌倉時代から防衛ラインとして多くのお城がこの地域に築かれたのである。
早速、またきなこと一緒に散歩がてら行ってみることに。鷺沼駅近くの駐車場に車を停め、鷺沼駅ロータリーから出発。鷺沼駅はちょうど丘の上にある駅で、南北に下り坂となっている。


駅から南方面に下って行くと、約10分くらいで『有馬城』エリアに到着。このエリアは少し小高い丘になっており、有馬川という小さな鶴見川の支流があるのだが、その昔はこの有馬川も大きな川だった可能性があるし、大山街道が見渡せた場所だったらしい。



現在“せど梨園”という広いエリアの梨園があるが、まさにこの梨園こそが『有馬城』のあった場所らしい。またせどとは井戸・水源を意味する言葉らしいので、歴史が地名に刻まれて残されている。遺構らしきエリアはかなり少ないが、このせど梨園の両側にせり立つ斜面は有馬城の面影を見ることが出来る。ブラタモリをいつも見ているせいか、地理を見ているだけで色々と想像が出来るようになってしまった。





西側には有馬城に関する内容が記載された看板を発見。

有馬城の近くには、結構古い家屋が残っている。鷺沼エリアは新興住宅街として有名だが、この有馬城エリアにはかなり古い家が残されているというのはとても面白いし、家の近所にも歴史を感じられるスャbトが残っているのも素晴らしい。

城跡の近くには、神社やお寺が残されていることが多いが、例に漏れず、有馬城の近くにも神明神社と福王寺があった。まずは神明神社を訪れたが、きなこと一緒に長い階段を登ると、比較的立派な境内があった。この神明神社の裏側の道は神明坂と呼ばれているようだ。





そして有馬城の西側には、福王寺がある。このお寺もなかなか立派で、裏側の道も土塁のような跡が見受けられる。昔はこの神明神社と福王寺も含めて、有馬城エリアを形成していたのだろう。また色々と妄想すると結構楽しいものだ。




田園都市線沿いの街は、すっかり開拓されて新しい街になっているが、昔から家屋や旧道などの面影が僅かに残っているエリアもあり、歴史を感じさせてくれる。城跡の醍醐味も、僅かに残されている遺構などを確認しながら、色々と妄想を膨らませて、その歴史に思いを馳せることが出来るところにある。自宅近くは、多摩川と鶴見川に挟まれているエリアでもあり、また鎌倉街道や大山街道などの旧道も通っていたエリアでもあり、江戸に向かう通過点、そして鎌倉時代から防衛ラインとして多くのお城がこの地域に築かれたのである。