こんにちはJです(第55話)
今日はJのまじめなブログ第3弾!
前回の 化粧品の歴史(世界編) に続きまして、
化粧品の歴史日本編をお伝えいたします。
日本では最初に縄文時代の土偶や弥生時代の埴輪の顔面に
赤い顔料が塗られていて、(最初はやっぱり赤ですねー )
)
顔に赤土を塗ることが当時の風習であり
日本の化粧のルーツであるとされております。
6世紀の後、中国から紅や白粉が輸入されるようになりました。
同じ時期に日本からは椿(ツバキ)が輸出されています。
この時代の美的感覚は当時の先進国、中国でのトレンドを意識したものが主流で、
唇を濃い赤で染めあげ、
額と口元には鮮緑色の花鈿(かでん)靨鈿(ようでん)を付けるスタイルが
宮廷を中心にして流行しました。 
692年に国産初の鉛で出来た白粉を完成し、
続いて713年には水銀で出来た白粉も登場します。
(身体に悪そうですね~ )
)
平安時代になると宮廷の女性たちが
鳳仙花を使って『爪紅』をするようになります。
現在のマニキュアのルーツと言われております。 
平安末期になると男も女性と同じような化粧をするようになり、
お歯黒文化も復活しています。
実力のある男が、派手派手なファッションを身にまとい、
時には傍若無人な行動を取る…。
後に登場する織田信長、前田慶次、伊達正宗らにも共通する
こんな風習はこの時代では『バサラ』と呼ばれていて
奇抜な化粧も生まれています。
(傾奇物ですね )か~ぶ~け~♪か~ぶ~け~♪
)か~ぶ~け~♪か~ぶ~け~♪
応仁の乱を機に、時代は戦国時代へと移ります。
戦いの中で、武士の間では
「首を取られたときに恥ずかしくないように」
という意識が化粧に結びつきます。
(なんじゃそりゃ!!? )
)
江戸時代には化粧をする層が広がりますが、
そのトレンドを引っ張っていたのが歌舞伎役者や遊女達でした。
当時の白粉はまだまだ鉛や水銀製のモノが多く、
いつも使用するうちに慢性毒が体内に蓄積され一種の職業病として
多くの悲劇が生まれておりました。
一方、紅花は最高級の口紅用材料として珍重されていましたが
非常に高い値段でまだまだ庶民に手に入るような物ではなかったようです。 
明治時代、文明開化と共に欧米の
人工科学化粧品も輸入されるようになりまして、
日本の既存の化粧品メーカーも対抗上、
大きく転換を余儀なくされることになり、
現在も主要メーカーの製品は
この方向性の延長線上にあります。
・・・・・
なかなか奥が深いです。
時代はめぐるといいますので、
また男性が化粧をする時代が来るかもしれませんね (笑)
(笑)
以上Jからでした。
「高知ブログランキング」に参加中^^みなさん、ポチッと応援よろしくお願いします♪

















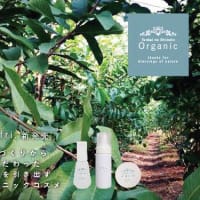




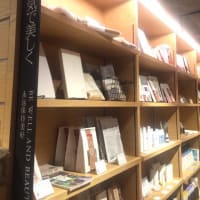



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます