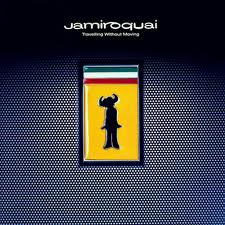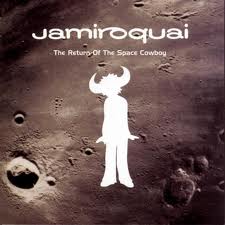R&B、ファンク、あるいはトリップ・ホップなどと形容される the INTERNET。
こんなに “没個性的” なバンド名を持ちながら、その音楽性は唯一無二。
もはや、彼ら自身が自らの音楽性に絶対的自信を持っているからこそ、こんなバンド名にしたんじゃないか、という気さえする。
現在はバンドの形態を取ってはいるが、もとはヴォーカル2人のR&Bユニットとして始まったそうだ。
メインヴォーカルで紅一点のシド。もう一人は彼女と普段から仲の良いマット。
この二人でユニットとしてデビューし、楽器隊のメンバーを加えたり入れ替わったりして現在の編成になった。
他のメンバーは、ギター、ベース、ドラム、キーボードに各1名ずつ。
マットはときにヴォーカルを取りながら、キーボードやミキサー、シーケンサーなどを操作している姿がPVから確認できる。
シドの声質は(その中性的な外見に似合わず)とても女性的で透明感があり、官能的だ。
浮遊感のあるバンド・サウンドによくマッチしている。
本作の#5 Just Sayin' / I Tried のサビで繰り返される「You Fucked Up」というフレーズは、非常に繊細なトーンで、耳に心地よい。
このイディオム自体は「このクソ野郎!」とか「やっちまったなw」というふうに解釈していたのだが、
日本盤ライナーノーツでは「しくじったね」と訳してあり、上手いな、と思った(プロの仕事だから当たり前だが)。
こんなにもセクシーで切ない「You Fucked Up」を、聴いたことが無い。
バンド・サウンドは、ファンクをルーツにもつベースのリフ、ギターのカッティングなどが絶妙だ。
HIP HOP的とも言えるベースの力強いノック、あくまでアクセントというように音数の少ないギター。
クリーントーンもディストーションも使い分け、ギターという楽器の持ち味を十分に活かしている。
そしてこの手の音楽には欠かせない、エレピの呟くようなコードワーク。
まさに「新時代のアシッド・ジャズ」というに相応しいバンドだ。
アフリカン・ミュージックの大御所、Fela Kuti。その息子が、本作の Femi Kuti だ。
分厚いホーンセクション、そこに絡み合うパーカッション。これらの響きが生み出す、力強いファンク。
Sly や Herbie Hancock、James Brown らとは明らかに異なるグルーヴに、アフリカの匂いを感じる。
しかも、今まで民族音楽に馴染みのなかった人にも聴きやすく仕上がっている。
「よく分からないけどなんだか難しそう」というような『難解さ』や『とっつきにくさ』を感じているなら、その心配は無用だ。
Femi自身がヴォーカルとともにサックスも吹いており、アフリカンのグルーヴとポップさを両立させている。
アフリカ音楽というと、ジャズファンはElvin Jonesなどのポリリズムを連想しがちだ。
逆に本作において、そういった複雑なリズムは全面に出てこない。そこは期待外れかも知れないが、
全体にゆったりとグルーヴする曲が多く、中でも#5 '97 はアルバムの中盤で映える良トラックだ。
本作はとくにHIP HOPとの関係を意識しているように思える。
#1 に Mos Def、#12 に Common が参加。
Mos Def は Ronny Jordan『The Brighter Day』にも参加しており、Common は言うに及ばず。
いずれもジャズに親和性の高いミュージシャンだ。
「民族音楽」とカテゴライズしてしまうと見えにくいが、
アフリカン・ミュージックが 実は R&B や HIP HOP と地続きの、「ブラック・ミュージック」のひとつであることを再認識させられる。
【関連アルバム】
『Shoki Shoki』
トーキンラウドのコンピレーションでも紹介されていた作品。
分厚いホーンセクションと熱いパーカッションの響きは、 まさにアフリカン・ジャズ・ファンク。
#1 で聴かれるFemiのバンドを鼓舞する掛け声は、ともすれば吉幾三の「おじさんサンバ」を連想させるが、
そのダサカッコいい感じがファンク熱の高さを十分に伝える。
『Journey to Truth』Steve Williamson
Us3の作品にも参加しているサックス奏者、Steve Williamson がトーキンラウド・レーベルからリリースした作品。
#1 Meditation は無伴奏でメロディもなく、ただサックスを吹いているだけで、オーストラリアのディジュリドゥを思わせる。
関連作品としたのは、サックス奏者によるアフリカを意識したアシッド・ジャズ作品だから、という点による。
数曲にThe Rootsの面々(Black Thought、Hub、?uestlove)やヴォーカルに Jhelisa Anderson、Noel Mckoy が参加している。
企画コンセプトは悪くないのだが・・・アルバムとしての出来はイマイチ。聴きどころはゲストが参加した曲だけと言って良い。
ただ、アシッド・ジャズ資料として、またはサンプリングネタのひとつとして持っておくのはアリかも。
ミシェル・ンデゲオチェロ(Me'shell Ndegeochello)は、作品を重ねるごとにその音楽性を変化させていく。
貪欲に様々な要素を取り込み、一つひとつの作品に「強い意味」を持たせているように感じられる。
それゆえ、新作のレビューを読むと、まるでブラック・ミュージックのコアなファンしか受け付けないような印象を
受けることもある。
たしかに、メッセージ性が色濃い作品もある。グルーヴから離れ、ベースを一切弾かない作品もある。
けれど、あまり構えず先入観なしに聴いてもらうには、本作が適していると思う。
本作は彼女の2作目。ファンクをベースにジャズのテイストを加味した感じで、比較的ストレートなつくりになっている。
この頃の作品は、その後の作品群に比べてもシンプルなジャズ・ファンクをやっている。
このブログで取り上げる音楽性に最も近いのは、この本作だろう。
共演者も豪華だ。
ジャズサイド(という言い方もアレだが)からは才気あふれるサックス奏者Joshah Redman、イッちゃってるギターを弾くDavid Fiuczynski。
彼のディストーションギターはダーティながら肉感的なトーンで、聴く者を惹きつける。
そしてファンクの大御所が二人も参加。絶妙なカッティング・ギターを弾く Wah wah Watson に、
Head Hunters のフリーキーなバス・クラリネットで有名なベテランBennie Maupin !
こんなメンバーをバックに率いながら、決してそれに寄りかかること無く、適所に配して自身のベースと独特の歌い方のヴォーカルとで、
アルバム全体を引っ張ってゆく。
♯8 Who is He and What is He to You は、Bill Withers のカヴァーだ。
この選曲もまた渋い。ブラックミュージックファンの、「分かってる」感を刺激する。
BGM的に流していても意外に重くなく、繰り返し聴きこんでも面白さのある作品。
ミシェル・ンデゲオチェロに興味はあるけれど・・・という人には、この作品がお勧めだ。
あまり知られていないことなのかも知れないが、
the Brand New Heaviesのメンバーは当初、5人ないし6人でデビューした。
コアメンバーであるドラム&キーボードのJan Kincaid、ギターのSimon Barthromew、ベースのAndrew Levyに加え、
男性ヴォーカル&ギターのLascelles Gordon、女性ヴォーカルLinda Muriel、サックス奏者でStay This Wayの作曲者、Jim Wellmanらがいた。
もっとも、彼らはもともとワンポイントでの参加だったのかも知れないが、
初期の楽曲# Dream Come Trueなどは彼らがヴォーカルをとってレコーディングされている。
その後、彼らは抜けてコアメンバーの3人が残った。そこへ、N'dea Davenportがヴォーカルとして加入し、彼らはブレイクした。
したがって、本作がデビューアルバムと目されるが、厳密には正しくない。このアルバムの前にも以下のアルバムがリリースされている。

上記のアルバムのうち、N'deaがヴォーカルをとった楽曲、あるいはN'deaで再録したもので再構成したのが、本作だ。
だから、初期のヒットはあますことなく網羅されている。
#1 Dream Come True、#2 Stay This Way、#4 Never Stopと、ヒットシングルは前半に集中。
バンド名を冠したインスト#7 B.N.H.や、ライブでおなじみの#3 People Get Ready(※Curtis Mayfieldの名作とは同名異曲)など、
ファンク色の強い楽曲ももれなく入っている。
したがって当然といえば当然なのだが、アルバム自体の完成度は高い。
頭から通して、何度も聴けるアシッド・ジャズの名盤だ。
とくに#4 Never StopでのN’deaの伸びやかなヴォーカルは、本当に最高だ。
彼女以外に、このバンドのヴォーカリストはありえない、ということを認識させられる。
このアルバムは、ジャケットが同じのバージョン違いがある。
例によってUS盤とUK盤の違いなのだろうが、詳細は調査不足。
違いの一つは、#6 Don't Let It Go To Your Headが入らない代わりに、# Dream Come Trueのリミックスバージョンが収録されていること。
これは、後述するように、どちらもシングルでも聴けるものだ。
けれど、#6 Don't~が素晴らしいので、そちらを収録したものがおすすめ。
【関連シングル】
Dream Come True
アルバム収録バージョンの他、リミックスを2曲収録(冒頭に述べた理由で、この頃は「featuring N'dea Davenport」という文言がやたら目に付く)。
#1のJoey Negro editは、アルバムのバージョン違いに収録されたreality mixのショートバージョン。
正直、音の使い方に古さを感じるが・・・まあこれはしょうがない。
フルバージョンのreality mixには、曲終盤にバンドがギターカッティングとパーカッションだけになったところに
ヴォーカルが乗っかる所があり(シングル収録のショート版は、そこがカットされている)、そこはまあカッコいいのだが・・・
全体としては・・・うーん、という感じ。
#2のheavies editは別リミックス、Phil Bodgerの手による。
#3のheavies disco 2000 mixは、アルバム収録バージョンのショート版。
さらに、#4にStay This WayのDavid Moralesリミックスが収録されている。
Stay This Way
アルバム収録バージョン(エクステンド)とショートバージョン、それにインスト曲 #3 Bang と #4 O-fa-fu を収録。
アルバムと厳密には同じでなく、装飾音が入ったりと細かな点で違いがあるが、おおむね同じバージョンと見て良い。
インスト2曲はリミックス・アルバム『Excursions』にも収録されている。
↑とは別にEPも出ていて、
こちらはStay This Wayばかり7バージョン(!)を収録。
リミックスとダブバージョン(ヴォーカルトラックを抜いたもの)で構成されており、#3の heavy dubはアルバム収録のトラックと同じものを使用している。
#1のheavy mixはアルバム収録とほぼ同じアレンジだが、エンディングにサックスソロが追加され、長いエンディングとなっている。
#2のMorales mixは、Dream Come Trueのシングルに収められたリミックスとまったく同一のもの。
残り4曲はこのアルバムでしか聴けないリミックス、ということになる。
Don't Let It Go To Your Head
「真夜中のオアシス」と同じく、カバーソング。オリジナルはJean Carne。
「真夜中のオアシス」もそうだが、BNHのカバーは原曲に劣らず、素晴らしい。
奇抜なアレンジをせず、見事にBNHの音になっている。
アシッド・ジャズレーベルを代表するバンド、James Taylor Quartet。通称J.T.Q.。
『Extended Play』のタイトルは、おそらくアナログレコードのEP盤に由来するのだろうが、
その名の通り6曲しか収録されていない(クレジット上は5曲)。
※EP盤は収録曲が少ない、今で言う『マキシシングル』的位置づけ。
本作は、冒頭の#1 Stepping Into My Life をフィーチャーした作品だ。
女性ヴォーカル Alison Limerick はバンドと良く合っている。この組み合わせでもう2,3曲出していればなあ・・・と惜しく思う。
しかし、この作品はこの1曲だけではない。
歌ものはこれだけ(#3 Keep The Dream Alive もいちおう歌ものだが・・・)で、あとは良質なジャズファンクが続く。
#2 Redneckからは、彼らの本領発揮といったところ。
#1を聴いて忘れがちな、J.T.Q.がオルガンバンドであることを、思い出させてくれる。
#5 The Vanishing Point の、淡々としたビートの上でうねるオルガンもたまらない。
しかしなんといっても、#4 Europa のファンクには、興奮を覚えるはずだ。
緊張感のある16ビートに、小気味良いギターカッティング。 ややラフで切れのあるホーン、タイトなエレキベース・・・。
どの楽器も、しっかりと“生楽器の音”を響かせていて、素晴らしいグルーヴを作り出している。
#6 はボーナストラックで、Stepping Into My Life のフルバージョン。
イントロが端折られていないので、個人的にはこちらが好み。#1はヴォーカルの入りがいきなりすぎて、ラジオエディットのような印象がある。
曲数が少ないので見過ごされがちな作品と思うが、むしろJ.T.Q.の魅力がコンパクトな中にぎゅっと詰まって、
一切のムダもない、そんな感じのするアルバムである。
ミュージシャン名もさることながら、このタイトル。そして、このジャケット。
イロモノ好きなら手に取らずにはいられないだろう・・・と思うが、いまや彼女は有名な実力派である。
ミシェル・ンデゲオチェロは、女性ミュージシャン。
はじめはベーシストとして認知されたが、ヴォーカルもとるしキーボードはじめ他の楽器も操る。
ポエトリー・リーディングのごとき彼女の歌は、不思議な存在感があり、リアルな問題を扱う。
「ンデゲオチェロ」とは、スワヒリ語で「Free as a Bird」の意味だという。
小柄ながら、彼女の奏でるベースは太くコシがあり、確固たるグルーヴを送り出している。
本作は彼女の4thアルバム。
ジャケットに反して(?)意外にも聴きやすく、気持ちの良いグルーヴに溢れている。
ラッパーの Talib Kweri が(ボーナストラックでは Missy Elliot も)参加しているなど、ヒップホップ的要素を取り入れた曲もあるが、
それだけではない。
タイトなファンクナンバーや、ソウル~R&B的メロウなトラック。
その随所で彼女のグルーヴィーなベースも堪能できるが、
なんといっても、ここで提示されているテーマが切実だ(輸入盤のみに表示されているADVISORYマークは
彼女のリリックおよびラップの所為だろう)。
アフリカン・アメリカンである彼女は、自らのアイデンティティ、自身の置かれた社会的状況を問うている。
人権問題を扱った詩の朗読や運動家の演説などを引用したり、リリックにそうした文言を刻み付ける。
それは、自分のルーツを見つめ直すという点で彼女にとっては必然だったのだろうと思う。
思えば、ソウルミュージックは過去にも人種差別問題について訴えてきた
(例えば Stevie Wonder の# Living For The City など)。
ここで、聴き手の自分はどうかと考える。
日本に生まれた日本人、特に幼い頃から悲惨な思いをしたこともなく育った自分は、
きっとこの作品を 本質のところでは 理解は出来ないのだろうと思う。
しかし、お固いことは抜きにしても、純粋にこの作品はさまざまな時代のブラックミュージックのかっこ良さが集められた、
タイトル通りの「ミックステープ」として楽しむことができる。
彼女の様々な音楽的要素を見せる本作だが、
このふたつ前の2ndアルバム『Peace Beyond Passion』は、よりアシッドジャズ的だ。
ちょうどこの頃、さきに紹介した『Red Hot + Cool』にも参加している。
本作にギターの鬼才 David Fiuczynski は参加していないのが、若干残念ではある。
もはや、あらためて紹介するまでもない。
Jamiroquaiといえばコレ、というくらいの有名アルバムである。
この3rdアルバムで、彼らはその人気を不動のものにしたと言えるだろう。
このアルバムは、どうしても#1 Virtual Insanity の印象が強すぎる感がある。
イントロのピアノの印象的な響きと、話題性抜群の、あのPV。
当時はテレビでもラジオでもかからない日はないくらい流れていて、この曲に関しては食傷気味な人も多いだろう。
まあ仕方のないことだと思う。
しかし当然ながら、このアルバムの聴きどころは#1 Virtual Insanity だけではない。
基本的には1st~2ndアルバムのコンセプトを継承し、アルバム全体を通してひとつのストーリーとなるような構成をとっている。
#2 Cosmic Girl をはじめとして、シングルカットされた楽曲はどれも素晴らしいが、
ここではそれ以外を少し紹介しよう。
#3 Use The Force は、冒頭のシングルカット2曲に続くアルバムチューンだ。
パーカッションをふんだんに用いて民族音楽的なテイストを入れつつ、タイトなファンク・ビートがテンションを高める。
その次はしっとりしたバラードの#4 Everyday。
スペーシーな雰囲気は、宇宙空間に一人ぼっち残されたような、なんとも言えない寂しさを演出する。
再びシングル曲が続き、ここまでまったくスキがない。
#7 Drifting Along では、Jamiroquai風のレゲエを展開。
宇宙的な楽曲の中にあって、まったく浮いた感じがしないのは、やはりバンドサウンドが確立されている故だろう。
#8~#9はディジリドゥをフィーチャーしたインストゥルメンタル。彼らのアイデンティティを感じさせるが、
民族楽器というよりも、宇宙との交信を行う音かなにかのように聴こえる。
#10はタイトルチューン。これも冒頭部のエンジン音とJayのクルマで話題になった楽曲だ。
アルバム裏面には#12までしか記載されていないが、#13 Funktion がhidden trackとして入っている。
この大ヒットした3rdアルバムは、良くも悪くも彼らにとって大きな転機となったことは間違いない。
このアルバムからギターのサウンドを大きく取り入れ、シンセベースも多用するようになる。
そして彼らは世界中を飛び回る超売れっ子バンドへと成長したのだった。
Jamiroquai は4thアルバムから
急速にディスコサウンドへの傾倒を見せる(Jay-Kay の、Earth,Wind & Fire 他からの
影響は、今までの楽曲からも明らかである)のだが……
バンドメンバーの入れ替わりは激しくなった。
4thリリース前にはベースのStuart Zender がバンドを抜け、5thリリース後にはキーボードのToby Smith も抜けてしまう。
ディジリドゥのWallis Buchanan も脱退し、今ではドラムのDerrick が残るのみとなっている(※2015追記;Derrick McKenzie もその後抜けた)。
その路線は5thまで続き、かつてのようなジャズ~ファンクの影響は次第に薄まっていった感がある。
6thでは2ndを意識したかのようなローファイなサウンドを提示したが、どちらかと言えばロック的なつくりではあった。
どうしても懐古的な意見になってしまうのだが……
やはり、ジャズ~ファンクの影響を感じさせるJamiroquai のサウンドに魅力を感じているのは事実なので、
彼らにはいつまでも70年代のStevie Wonder とHerbie Hancock を足したような音楽をやっていて欲しかった……
と思ってしまうのだが、進化し続ける現役のミュージシャンに、それを求めるのはナンセンスだ。
しかし4th以降のバンドは、カッチリ作りこまれすぎていてスキが無く、生演奏の粗い(荒い)感じがほとんどしない。
音を聴いただけでメンバーの演奏する姿が眼に浮かぶような、生々しい音作りではなくなった。
バンドメンバーの入れ替わりとバンドの方向性の変化は無関係ではない。
ならばあの時点で、いっそのことバンドという形態にこだわらず、打ち込みをふんだんに使って
Daft Punk のようなデジタル・ファンクに突っ走ってみても良かったんじゃないか、あるいはHancockの『SOUND SYSTEM』のような、
スペース・アフリカンとでも形容できそうな独自の音楽世界を切り拓いていたら……などと愚にもつかないことを、妄想せずにはいられない。
(※2015追記;2013グラミー賞授賞式でのDaft Punkのパフォーマンスは、Stevie Wonder や Nile Rodgers との共演で話題を呼んだ。
初期のJAMIROQUAIの路線を引き継いでいるのは、実は彼等かもしれない)
【関連シングル】
Virtual Insanity
エディットバージョンとアルバム収録バージョンの他、
ジャングル・ビートを導入した# Do You Know Where You're Coming From (original mix) 、
それにシングルのみに収録のインストゥルメンタル# Bullet を収録。
# Do You Know Where You're Coming FromはM-BEATとの共同制作で、M-BEAT名義で出されたシングルもある
そのため、Jamiroquai名義の方は(original mix)となっている。
Cosmic Girl

ジャケット色違いで2バージョンあるが、左側が日本盤、右側は輸入盤。
Cosmis Girl の2バージョンのリミックスは、双方どちらにも入っている。
その他、
左側(ピンク色)にはエディットバージョンとインストゥルメンタル# Slipin' N' Slidin' 、
右側の方(青色)にはリミックス2曲とそのダブバージョンをそれぞれ収録。
すべてシングルのみで聴けるもの。
好みで選ぶとよいけれど、ファンなら両方とも持っていたい。
Alright
エディットバージョンとリミックス3バージョン
(うち1つのリミックス曲の、バリエーションをさらに2つ)の計6曲収録。
クラブ向けやしっとり仕上げたもの、原曲が分からないくらいいじったものなどバラエティに富んでいる。
リミキサーは、1stからずっと付き合っているDJ D-Zire。
High Times
エディットとアルバムバージョンのほか、Roger Sanchezによるリミックス違い2曲を収録。
Roger Sanchezは他にも多くのJamiroquaiのリミックスを手がけている。
Deeper Underground
※本来はここで紹介するべきではないのだが、4thアルバムを紹介する予定がないので便宜上ここで紹介
このシングルは、3rdのあと、4thが出る前にリリースされた。
ハリウッド版ゴジラ(GODZILLA)のサウンドトラックに収録されたものだが、
4thアルバム(UK盤)のボーナストラックにも入っている(日本盤のボートラは別の曲)
エディット、アルバムバージョンとリミックス1曲、それに# High Times のアレンジ違い(コーラス入り)を収録。
これにもバージョン違いがある。
↑これはDeeper Underground のセルPVに付属しているCDなのだが、なぜか中古店で単品で売り場に出ているのをしばしば見かける。
エディットバージョンを除く上記3曲に加え、別のリミックスおよびダブを3曲、計6曲収録のお得な1枚。
緑色の#3 JAMIROZILLA MIX と、赤色の#2 METRO MIX は、同じ楽曲。
もしも中古店で両方見かけたら、迷わずこちら(赤いほう)を手に入れたい。
・・・たしかにジャケットデザインは緑色のほうが(GODZILLAのロゴも緑色だし)カッコいいけれど。
James Taylor Quartet、通称 JTQ は、ACID JAZZレーベルの代表格バンドだ。
とはいえ、ACID JAZZレーベルのロゴが入っていないアルバムが多数あり、さらにベスト盤と銘打ったものもいくつかある。
正直言って、どれから聴いたものかわからなくなってしまう。
JTQサウンドを特徴づけるのは、なんといってもハモンドオルガンである。
リーダーの James Taylor (ヴォーカリストのそれとは別人)はキーボード奏者。そこへギター、ドラム、ベースを加えた4人編成(カルテット)。
さらに、必ずと言ってよいほど管楽器を加えている。
その指向は、主に3つに分類できるだろう。
ひとつは、初期の# Blow Upや# Mission Impossible's Themeに代表されるチープなオルガン。
もうひとつは女性ヴォーカルを入れた歌もの。
そして残るひとつが、いわゆるアシッド・ジャズ的ジャズファンクだ。
まだJTQのアルバムをすべてチェックしたわけではないので、途中記事で申し訳ないのだが
初期の頃のサウンドというのは、どちらかというとサーフミュージックにも通じる単純な音楽であったように感じられる。
それはそれでいいのだろうが、そこにジャズを感じる要素は薄いように思える。
したがって、この時期の作品はスルーしている。
歌ものに関しては、どれも楽曲の質が高い。
バンドのアンサンブルが練られているのはもちろん、ゲストのヴォーカルも実力者ぞろいで聴き応え充分だ。
ただ難点を言うと・・・、
歌ものになると、このバンドのアイデンティティとも言うべきオルガンが、あまり目立たなくなる。
バンドサウンドを作ることに徹しているのは好感が持てるのだが、それではBNHやIncognitoとなんら変わらないとも思ってしまうのだ。
バンドサウンドを作るにあたってオルガンでなくエレクトリック・ピアノやアナログシンセなどを弾いている時もあるが、
オルガン好きとしては、JTQにはオルガンサウンドを期待する。楽曲自体は良いので、なんとも言いがたい部分なのだが・・・
そうした観点から紹介したいのが、本作である。
3つ目の彼らの特徴、アシッド・ジャズ的ジャズファンクを全編にわたって展開しているアルバムだ。
4ビートやボッサ・ビートの曲も多く取り上げ、彼らの作品の中では「ジャズ度」が高いものではなかろうか。
#1 Grooving Home は、イントロから「これぞハモンド!」とも言いたくなるようなオルガンサウンド全開の曲だ。
(タイトルはおそらく、ジャズオルガン奏者Richard "Groove" Hormesに捧げたものだろう)
#3 The Stretchや#6 breakout なんかは、トラディショナルなジャズファンクと言えるだろう。
#4 It Doesn't Matter はこのアルバム唯一の歌ものだが、めずらしく男性ヴォーカル。
4ビートでスイングするバンドをバックに、スキャットのアドリブを混ぜるなど多分にジャズを意識した作りである。
(独特の声質には、上手いんだか下手なんだかよく分からない感覚を覚えるが・・・)
#5 Touchdown は管楽器を入れずに、ストイックなグルーヴに乗ってスリリングなキメを見せる。
#8 Bluebird はストレートなバップナンバー。メンバーのソロの応酬は、往年のオルガンジャズを踏襲している感じだ。
#7 Brothers Batucada や#9 Bossa Pilante などはタイトルから分かるとおり、ラテンジャズ的アレンジを施した楽曲。
10曲収録でもトータル50分弱と短く、耳に心地良いので、BGMに流しているとあっという間に終わってしまう。
Jimmy Smithなど60年代のオルガンジャズに馴染んた方には物足りないかも知れないが、
反対に、それらがゴリゴリすぎてちょっと・・・という向きには、是非本作をおすすめしたい。
その物足りなさの原因のひとつには、やはりベースの存在があるように思う。
モダンジャズのオルガンは、オルガン奏者が左手もしくは足鍵盤でベースも弾くので、ベーシストが入らないのが通常だ。
しかし、強力なグルーヴを求めてベーシスト(エレキベースが多いがウッドベースの場合もある)を入れることも多い。
ところがJTQの場合、ベーシストを入れることで逆にグルーヴはマイルドになってしまっているように思える。
オルガンはキーボード化し、ベーシストはオルガンの邪魔にならないよう当り障りのないラインを弾くのみだ。
これならばオルガンがベースも弾いたほうが、よりオルガンジャズらしくなると思うのだが・・・
ベーシストを入れるならば、ベースも自己主張するように太い音色、独自のラインで、グルーヴを推進して欲しい。
まあ、これは好き好きだろう。聴くぶんにはあまり気にならないポイントであるように思う。
もっとファンク色を出したオルガンものをお望みならば Soulive がお勧めだ。
またMaceo Parkerの諸作も、オルガンが(ベーシスト不在で)強力なグルーヴを送り出している。
これらについても頁を改めて紹介する予定だ。
トーキン・ラウドを代表する看板アーティスト、という扱いのわりに、一般には知名度がパッとしない……というのは、往々にしてあることだ。
それはつまり、アシッド・ジャズというジャンルの狭さを現してもいるのだが、言うまでもなく、それとミュージシャン自身の実力は相関しない。
YOUNG DISCIPLES は、そういうユニットである。
UKジャズの歌姫 Carleen Anderson と、パーカッショニストでありながらドラムプログラミングも担当する Femi、
そしてプロデューサー兼トラックメイカー兼ベーシストの Marc.O.Nelson の3人からなる。
生演奏を入れながらもバンド形式ではない。
プログラミングを使いながらも、テクノミュージックのように音を加工することはない。
ラップもスクラッチも入るけれど、ヒップホップとも言いがたく、ハウスのようにダンスビートを前面に出したサウンドでもない……
彼らの音楽を説明しようとすると、実に捉えどころがないのである。
(この記事のカテゴリをどこに分類するべきか、悩んだくらいだ)
YOUNG DISCIPLES の目指したものは、今にして思えば、実験的とも言えたかも知れない。
時代より早すぎたのかも知れないし、シーンの移り変わりの中で、トレンドとトレンドの隙間に
ぽんとこぼれ落ちてしまったスタイルであったかも知れない。
無機質なドラムパターンと生のコンガやギロが上手くマッチして、気持ちの良いグルーヴを作っている。
執拗に同じパターンを繰り返すベースは、ふとした瞬間フレーズをアレンジする“色気”を見せる。
この感覚は生演奏ならではだ。
ファンクの大御所、Maceo Parker 率いる J.B.HORNS の連中をバックに従えながらも、70年代的ファンクを展開するでもなく、
UKジャズ特有の、水の底にいるような、沈んだクールなファンクを展開してみせる。
あるいはメロディを抑え、ほぼドラムとベースだけのダブサウンドを提示する。
ソウル、ファンク、ダブ、アフリカン……様々な要素を取り込みつつも、それらに決して寄らない、独特のサウンドメイク。
こう書くといかにもキワモノな印象だが、そこは流石の貫禄である、Carleen Anderson の歌が入ることで
すっと聴きやすく、耳に馴染みの良い音楽になっているのである。
Carleen の歌声は、低く伸びやかで、例えるなら「大地の祈り」のような暖かさ、力強さだ。
彼女は一時期、N'dea Davenport の後釜としてTBNHのヴォーカルを務めたが、これははっきり言って失敗だったように思える。
バンドのサウンドキャラクターと彼女の歌声は、合っていないと感じた。
やはりTBNHには、N'dea のようなきらびやかな高音の歌い手が似合う。案の定、TBNHはその後もヴォーカリストを替え続けたのだった。
さて、やはり本作にもバージョン違いが存在するのだが・・・
冒頭の写真が比較的よく流通しているもので、#5 All I Have と#8 Step Right On はダブアレンジされたものが収録されている。
ヴォーカルはほぼコーラス部分のループのみ。メロディは極力排され、プログラムされたドラムと、
それに絡む Femi のパーカッションや Marc のベースがフィーチャーされている。
そしてこちら↓がもうひとつのバージョン。
(#1 Get Yourself Together pt1&2 が2曲分としてクレジットされているため、曲番が1つズレている)
#6 All I Have のフルヴォーカルバージョンと、#9 Step Right On のラップが乗ったものが収録されている。
歌ものとして聴きたいなら、こちらがおすすめだ。
ちなみに、日本盤は『Young Ideas』というタイトルになっている。
ジャケットは冒頭の写真のもので、収録曲は別バージョンの方に近いようである。
(しかし、なぜこんなタイトルにしたんだか……)
さらに付け加えると、トーキン・ラウドのコンピレーション『Talkin'Loud two』では、
#2 Apprently Nothin' のアレンジ違いが聴ける。
『Talkin'Loud two』
オリジナルがバンドアレンジなのに対し、よりダブっぽいアレンジになっている。
クールなグルーヴがクラブ向きだ。
このコンピレーションは、他にもこれでしか聴けないバージョン違い曲が入っており、
トーキン・ラウドの主なミュージシャンをほぼ網羅しているので、「なにか一枚」とお探しならばこれを勧める。
YOUNG DISCIPLES は結局、この1枚を出したきりで解散してしまう。
Carleen Andersonはその後、ソロヴォーカリストとして作品を出していくのだが
もしも彼らがまだユニットとして活動を続けていたら、ヒューマン・ビートボックスやポエトリー・リーディング、
フリージャズのミュージシャンらとスリリングな共演をしていたかも知れない……と思うと、
とても惜しい気になる。
JAMIROQUAI がもっとも商業的に成功したアルバムは3rdの『Travelling Without Moving』だろうと思うが、
もっとも内容が優れたアルバムというと、この2nd 『The Return Of The Space Cowboy』ではなかろうか。
前作『Emergency On Planet Earth』よりもぐっとタイトになったグルーヴ、洗練されたバンドアレンジ。
よりスペーシーな感触を前面に出す一方で、環境問題や政治のことなどにも言及する辛辣なリリックは、前作から変わらない。
本作から、ドラムは Derrick McKenzie に替わっている。Nick Van Gelder よりもファンク色が強く、より荒い印象。
ワーウィックのベースを唸らせる Stuart Zender とがっぷり組んで、極上のファンク・ビートを生み出している。
このアルバムは、まず全体の雰囲気が素晴らしい。
シンセサイザーで宇宙的・未来的な演出をしつつ、それらの音源はムーグをはじめとするアナログシンセであったり、
ヴォコーダーを使うなどして、古いラジオから流れてくるようなローファイな音に仕上げている。
女性コーラスやホーンセクションが上手く配されていて、機械的な中にも暖かさを感じるつくりだ。
余談だがこのホーンセクション、聞いた話によると「若干調律を下げてある」ということだ。
ギターやベースなどは440Hz(または442Hz)で合わせるが、それよりも下げた状態(438Hzなど)で調律し、
古い音楽の雰囲気を出す……ということである。
吹奏楽やオーケストラでやられる手法なのだそう。
雰囲気といえば、もう一つ。
#9 Journey To Arnhemland では、Willis Buchanan のディジリドゥがフィーチャーされている。
前作でも# When You Gonna Learn? などでその音を聴かせていたが、今回は Toby Smith のキーボードと絶妙なブレンドで、何とも不思議なヴァイヴレーションを響かせている。
ちなみに「Arnhemland」とは、オーストラリアの先住民アボリジニの住む地域の名前だという。
さて、本作にはバージョン違いがある。
UK盤(および日本盤)は#1 Just Another Story から始まり、#11 Space Cowboy で〆め。
(盤によって、その後ボーナストラックが続く)
これがUS盤では、#1 は Space Cowboy であり、Just Another Story が #11 なのだ。
つまり、冒頭と〆めがそっくり逆になっている(その間の曲順は変わらない)。
曲想としては Just Another Story が1曲目のほうが、合っているように感じる。
何かの始まりを思わせるイントロ、何相にも展開する複雑な曲調は、アルバムの幕開けとして相応しい。
しかし、US盤には #4 Light Years のライブ・バージョンがボーナストラックとして収録されているのだ。
これは、悔しいことに Light Years のシングル盤には入っていない。それどころか、なぜか他のどのアルバム、
シングルにも入っていないのだ(DVDは除く)。
Light Years はスタジオ録音を聴いてもあまりぱっとしない印象だったが、ライブ・バージョンを聴くと
この曲の魅力が分かろうというもの。
割れんばかりの歓声の中、盛り上がるバンドを従え、さらに煽る Jay Kay……。
全体の構成(曲順)をとるか、レアトラック(ライブ・バージョン)をとるか。
これは大いに悩むところだ。
ついでに、JAMIROQUAI のアルバム『Rock Dust Light Star』について。
前作『Dynamite』にも感じたことだが、近年の JAMIROQUAI は、なんとなくこの2ndの雰囲気に近付けているような気がする。
それまでのディスコ路線からはちょっと距離を置き、バンド重視で70年代ファンク的なアプローチと、ローファイな音作り……
しかし、当時のメンバーとは違ってしまっている。
オリジナルメンバーは、Jay Kay のみとなった。
当然のことだが、バンドサウンドとはメンバー各々の要素が集まってつくられるものである、ということを実感する。
『Dynamite』は悪くない内容ではあったけれど、ふとした時に聴きたくなるかというと、そうでもない気がした。
自分の好みがこの2ndのあたりで止まってしまっていて、JAMIROQUAI の変化についていけていないのかも知れない……
【関連シングル】
Space Cowboy
アルバム盤との一番の違いは、ベースのブレイクソロ。
シングル盤は、スラッピングで弾かれていて、これはこれで良い。
ラジオでかかるのもこちらのバージョンが多い。
アルバムバージョンはスラップをせず指弾きで、よりグルーブを押し出した感じになっている。
アルバムの雰囲気を考えると、スラップしないブレイクが曲調に合っている気がする。
これに収録されている#4は、表題曲のデモバージョン。 Jay のスキャットソロが素晴らしい。
この曲のPVでも Jay のダンスが堪能できるので、機会があったらぜひ観てほしい。
Half The Man
国内盤シングルは、なぜかタイトルが『Stillness In Time』になっているのだが
収録曲はどれもアルバムで聴けるものなのでおすすめしない。
UK盤シングルは1stの# Emergency On Planet Earth を Masters At Work がリミックスしたものを収録。
また、#2 Space Clav はシングルのみで聴けるインストゥルメンタル。
Light Years
タイトル曲のスタジオ録音(エディット)の他、
#2 scam、#3 Journey To Arnhemland、#4 We Gettin' Down(アルバム未収録曲)と3曲のライブ音源を収録。
The Kids
1stのあと、2ndが出る前、という時期にリリースされたもの。
ベースの Zender お気に入りの曲とあって、ベースがフィーチャーされていてカッコいい。
# When You Gonna Learn? のライブ音源とインストゥルメンタル・バージョンを収録。
Incognitoの音楽性は、大きくブレることがない。
「偉大なるマンネリ」とは言い過ぎかもしれないが、それは即ち「ハズレがない」とも言える。
非常に質の高いマンネリ、と言おうか。
時代の変化や中心人物の志向の変化、メンバーの入れ替わりなど様々な要素によって、ミュージシャンやバンドというものは
変化していくものだ。
その変化は、ときに往年のファンに受け入れられなかったり、あるいは絶賛されたりする。
Incognitoというバンドには、そうした「変化」はほとんど見られない。
全く変化が無いわけではないが、基本的な振れ幅が決まっていて、その中で右に寄ったり左に寄ったりしている。
本作までの、彼らのディスコグラフィを並べてみる。
(1stアルバムから2ndアルバムまでは10年空いているので、1stの『Jazz Funk』は「0番目のアルバム」とすべきかもしれない)
1st…『Jazz Funk』(1981)
2nd…『Inside Life』(1991)
3rd…『Tribes, Vibes and Scribes』(1992)
4th…『Positivity』(1993)
5th…『100°and Rising』(1995)
6th…『Beneath The Surface』(1996)
7th…『No Time Like The Future』(1999)
アシッド・ジャズがもっとも盛りを見せたのは90年代だ。
ほぼ毎年リリースされるオリジナルアルバムが、そのことを如実に物語っている。
『Tribes, ~』『Positivity』『100°and Rising』の3枚はとくに、彼らを語る上で欠くことの出来ない有名作である。
本作以降の作品は、以下のとおり。
8th…『Life, Stranger Than Fiction』(2001)
9th…『Who Needs Love』(2002)
10th…『Adventures in Black Sunshine』(2004)
11th…『11 -Eleven-』(2005)
12th…『Bees & Things & Flowers』(2006)
13th…『Tales From The Beach』(2008)
アルバム制作ペースは、ほぼ変わらない。
2000年以降のIncognitoはノーチェックだが、ラジオでシングルカットを聴いても、レビューを見ても、どうにもピリっとしない。
いまだに(ファンの方には申し訳ないが)ヴォーカルに Maysa Leak を起用していることを誇ったりしているが、それも新しさを感じない。
さて本作は、彼らの90年代最後のアルバムである。
ハズレがない代わりに、目をひくような出来の曲も無い。
では何故、ここで紹介するのか。
理由は二つある。
ひとつには、この時期が彼らにとってひとつの節目と思われたこと。
同時期にベストアルバムを出している↓

Incognitoはバンドネームのロゴ表記が時期によって変わるので、ロゴ(字体)を見ればどの時期だかだいたい分かる。
このベスト盤と本作は同じロゴを使用している。
そして、同じロゴを使用しているCDがもう1枚。
↓のリミックスアルバムだ。
 『Future Remixed』
『Future Remixed』
正直言って、Incognitoに生演奏のグルーヴを求めてはいない。そういうのはTBNHのほうが生々しく、かつ隙だらけだ。
Incognitoの音作りは隙が無さ過ぎて、逆の意味で聴きどころがない。
では何を求めるのかというと、クラブ・ミュージックとの親和性だ。
これまでにも彼らのリミックスアルバムは有ったが、
 ←輸入盤。『Blue Mood』と同時期のリリース 国内盤、内容同じ→
←輸入盤。『Blue Mood』と同時期のリリース 国内盤、内容同じ→
オリジナルアルバムと同時期に出され、ほぼそのオリジナル収録曲のみを扱ったリミックス、というのは、
この『Future Remix』が最初ではなかったか(本作以降もその企画は幾度か行われている)。タイトルからも、その意識が伺える。
すなわちこの2枚は、対になるような位置づけなのだ。
3rdから本作までひと通り聴いてはきたが、すべてを手元に残したいかというと若干疑問が残った。
どれも同じような作品なら、ひとつだけ選んで持っておけばいいのではないか(あるいはベスト盤で事足りる)。
さきに紹介した『Blue Mood』で、お気に入り曲はある程度確保できている。
となると、それには入らない曲を選んで持っておけば良さそうだ――
そういう経緯で、リミックス盤とともに本作を手に入れた。
リミックスの妙を楽しむために元曲集を購入した、というのに近い。
こう書くと、果たして『No Time Like The Future』は、駄作・凡作なのか? という疑問が出てくる。
くどいようだが、内容は決して悪くはない。
むしろアシッド・ジャズ全盛期の頃のポップさが抜けて、少しミステリアスな雰囲気も醸し出している。
洗練された民族音楽、という趣の#4 Marrakech(マラケシュはアフリカ西岸の国モロッコの観光地。リーダーのブルーイは、アフリカ・マダガスカル沖の小島モーリシャスの出身)や、
(「Ahーーーーー」という声がずっとバックに響いている)ヴォイスの使い方が独特の雰囲気を出している#5 Fareless、
そして本作の目玉カバー曲、#6 Night Over Egypt ・・・と続く。
ラストの#10 Black Rain では、Herbie Hancockの「Maiden Voyage」のオマージュを入れてくるなど、小憎い演出もしてみせる。
楽曲一つひとつの印象は、はっきり言って薄い。
しかし、BGMのように安心して聴けるという一点において、手に入れる価値はあるように思う。
また、これらの楽曲がリミックスによって新たな一面を見せることも忘れるわけにはいかない。
『Future Remix』のリミキサー陣は
Masters At Work、MJ Cole、Jazzanova、United Future Organization……と、なかなかの顔ぶれだ。
#2に I Can See The Future が収録されている(オリジナルアルバムでは#9)。
エレクトリック・ピアノをフィーチャーしたインスト曲だが、この長尺ソロが、はっとさせられるくらい素晴らしい。
これに、リミックスの妙というものを感じ取ることができる。
このソロは、もしかしてリミックスにのみに収録されたものなのか? とオリジナルを聴き直したが、ソロは全く同じだった。
にも関わらず、オリジナルのほうはBGM的単調なソロという印象で、気がついたら終わってたという感じである。
対し、リミックスは鮮烈な印象を残す。
ソロのひと区切り、起承転結に応じてバックのオケの演出に工夫をこらしてあり、聴くものを飽きさせない。
ストリングスやギターのカッティング、ドラムのブレイクなどが実に効果的だ。
ソロが単調に聴こえてしまうか否かは、ソロの内容もさることながら、バッキングのダイナミズムも非常に大きい、と感じた1曲である。
INCOGNITO は、おそらく「アシッドジャズ」という音楽ジャンルでもっとも成功したバンドだろう。
Talkin' Loudレーベルからリリースした作品は数知れない。
アシッドジャズのブームは去ったが、レーベルを替わっても INCOGNITO のバンドサウンドは揺るがず、
作品をリリースし続けている。
同じくもっとも成功したバンド JAMIROQUAI は、「アシッドジャズ」というジャンルの枠を食い破り、
JAMIROQUAI の音を確立させた。
かたや INCOGNITO は、アシッドジャズという枠に留まりつつその存在感を増し(他が消えていった、というのもあるが)、
今では INCOGNITO の音 ≒ アシッドジャズサウンド、という認識すらあるように感じる。

↑本作と同時期にリリースされたオリジナルアルバム『100°and Rising』
前述の通り、INCOGNITO の作品は多い。
その中で今回紹介するのはちょっと変わった作品集である。
個人的には、INCOGNITO というバンドに対して「可もなく不可もなく」という感想を持っている。
ファンの間では、未だに Maysa Leak のヴォーカルを最良とする声が根強くあるようだが、
はっきり言ってこのバンドは、誰が歌ってもバンドサウンドに影響しないように思う。
それは、言い換えればバンドサウンドがしっかりしているということで、バンドプロダクションの、ある意味では理想とも言えるのだが。

↑本作の翌年にリリースされた 『Beneath the Surface』。#12 She Wears Black を収録
さきに紹介した The Brand New Heavies は、N'dea Davenport のあとヴォーカリストが数名代わっている。
このとき、バンドのカラーは大きく違ってしまい、なんとなくしっくり来ない感想を抱いた。
N'dea は再び TBNH に復帰するのだが、やはり TBNH の声は彼女なのだ、という気がした。
ヴォーカリストが代わるということは、バンドにとって一大事なのは言うまでもないが、それを実感した事例である。


↑名曲# Colibri やStevie Wonder の名カバー# Don't You Worry 'bout The Thing を収める『Tribes,vibes + Scribes』
ジャケットは2バージョンあり、収録曲が若干違っている
INCOGNITO の場合、Maysa Leak の前は Jocelyn Brown が、Maysa の後には Pamela Anderson が……など、
歌い手がよく代わっている。
それでも曲を聴けば、INCOGNITO だとすぐに分かる。
けれどそれは、歌が主張しすぎない曲作りとも言えると思うのだ。
INCOGNITOも他のアシッドジャズバンドと同じく、インストゥルメンタル曲をアルバムに収録しているのだが、
ヴォーカル曲との区別があまり無いように感じる。意識して聴かないと、まず気付かない。
歌、というより声(voice)と言ってもよく、バンドサウンドを構成する一要素に過ぎない。
スキャットでもいいと思えるくらい、歌の存在感が、いい意味で、無い。
こうした観点から INCOGNITO をインストゥルメンタル・バンドと捉えたとき、
ほぼインストゥルメンタル曲のみで構成されたこのアルバムは、なかなかに味わい深いものである。
本作は、アルバム『Inside Life』から『100°and Rising』までの中より、
インストゥルメンタル曲だけを(1曲のみヴォーカル曲あり)選び出して構成されている。
渋い選曲ではあるが、裏ベスト盤とも言える好内容だ。
#1 Colibri
ライブでは必ず盛り上がるという人気のインストゥルメンタル曲。
オリジナル盤『Tribes, vibes + Scribes』でも1曲目に配され、オープニングに相応しい。
#4 Deep Waters
この曲のみヴォーカルもの。ただ・・・唯一の歌ものとしてこれを選択した理由が分からない。
佳曲ではあるが、それほど秀逸な一曲とも思えないのだが・・・?
これの代わりにインストバラードの# After The Fall を入れて欲しかった・・・という個人的恨み節。
#5 L'arc en ciel de Miles
『Tribes, vibes + Scribes』収録、邦題は「届けマイルスの彼方に」。
そのタイトル通り、トランペットがフィーチャーされている美しいバラード。
今となっては時代遅れの感がある曲調だが、さらりとアレンジして演奏してみたい曲ではある。
#7 Journey into Sunlight
上記のオリジナルアルバム群には収録されていない曲。70年代のHerbie Hancockを思わせる
ARPシンセサイザーが、壮大な曲調を演出している。
それでいて、どこか懐かしいような感じもする。6/8ビートも心地良い。
なぜかこれを聴いていると、夕陽をいっぱいに浴びている光景が目に浮かぶ。
#3 Magnetic Ocean
#11 Jacob's Ladder
この2曲はエレキベースがメイン。INCOGNITOファンのベーシストは意外に多いそうだ。
Jacob's Ladder は、ベーシストのJulian CramptonがJaco Pastriusの# Kuru をモチーフに書いた曲らしい。
言われてみると、なるほどと思うけれど・・・未確認情報である。
#12 She Wears Black
『Beneath the Surface』収録。軽快で、面白い曲展開を見せる、隠れた名曲。
以前、地方テレビ局の天気予報のBGMで使われていた。
はじめに「可もなく不可もなく」という感想を持っていると書いたが、
それはつまり安心して聴ける内容ということでもある。
さらりとBGMとして聴きたい時などには、歌が主張しないこのアルバムをかけることが多い。
押しも押されぬ、あの JAMIROQUAI のファーストアルバム。
2. Digeridon't
3. J.K mix
4. Canté Hondo mix
5. original demo
6. Canté Hondo instrumental
1. はアルバム収録バージョン、2. はdon't の通りディジリドゥの入らないオケ、
3. は逆にイントロやインタールードのディジリドゥパートを長めに取っている。
6. は4. のインストバージョン。
2. part 1 & 2
3. Hooked Up
4. When You Gonna Learn? J.K mix
1. はヴォーカルパートのみ、2. がアルバム収録バージョン。
3. の Hooked Up が収録されているのが興味深い。
インストゥルメンタルで演奏されていて、彼らのファンクがより楽しめて良い。
2. extended ver.
3. original
4. intrumenal
日本ではしばしば# When You Gonna Learn? との両A面シングルで発売されていることが多い。
3.がアルバム収録バージョン、4. は3. のインストだがフェードアウトが少しだけ長い。
2. extended ver.
3. If I Like It, I Do It
4. Revolution 1993 (demo)
この曲はシングルとアルバムでイントロがまったく異なっている。
アルバムでは、ワウをかけたエレクトリックピアノとギターのカッティングで始まるが、
シングルではストリングスのリフから始まる。
シングルバージョンはアルバムには収録されていない。
ちなみにラジオでかかるのもシングルバージョンが多い(尺の都合だと思う)。
1. がエディットバージョンで、2. がイントロ以外はアルバム収録バージョンと同じもの。
3. If I Like It, I Do It は、アコースティックギターのオケになっていて、アルバム収録バージョンよりも寛いだ、さわやかな演奏。
「アシッドジャズ」と言えば彼ら、TBNH こと The Brand New Heavies が代表格だ。
やはり、彼らもいわゆる「今の音」ではないとは思うが、
このアルバムは、今でも聴くたびに「やっぱりいいなぁ」と思わせる何かがある。
まず、ヴォーカル N'dea Davenport の声のよさ!
のびやかで透明感にあふれ、なおかつ力強さに満ちている。
「生きる歓び」みたいなものを感じずにはいられない。
ドラムの Jan Kincaid はキーボードの他ヴォーカルもとり、# back to love や # keep together などでデュエットしている。
こちらもなかなかのものだ。
そして“バンド”としての音作りにも注目したい。
ギター、ベース、ドラム、キーボードがつくる音の土台に、トランペット、サックス、トロンボーンという3管が
埋もれず目立ちすぎず、良い力加減で乗っかってバンドサウンドを構成している。
ホーン隊はそれぞれ曲中でソロもとっており、単なる音の装飾係ではない。
Simon Bartholomew のギターカッティングはエッジが利いていて、Andrew Levy のベースはシンプルながらもタメが絶妙。
なんというか、それぞれのパートが生々しく、いかにも生演奏しているぞ、というような“楽器が鳴っている”感じがする。
インストゥルメンタル曲(#6 ten ton take、#10 snake hips)を聴くと、それがより実感できる。
このアルバムには別バージョン(↓)があり、

具体的に言うと、こちらには
# Midnight at the oasis
# World keep spinning
の2曲が収録されていない。
# Midnight at the oasis (「真夜中のオアシス」)は、Maria Muldaur のカバー。
ここではオリジナルに近いアレンジのものが収録されているが、
のちに曲の冒頭でシャウトするアレンジのものがリリースされた(後述)。
今では、そちらのほうがよく知られている印象だ。
その2曲の代わりに
# los burritos
というインストゥルメンタルが入っているのだが、これは曲というよりもインタールードのようなもの。
スタジオでメンバーたちがジャムっている様子を録ったような曲だ。
どちらを買ったらよいか、と尋ねられたら、迷わず冒頭の写真のほうをおすすめする。
【関連シングル】
Back To Love

特筆すべきは、Ray Hayden(ここでは Opaz 名義でクレジットされている)の手によるリミックスが収録されていることだ。
クラブで映えるメロウな味付けは、さすが Ray Hayden! と嬉しくなってしまう。
そして、シングルでしか聴けない佳曲 # Baby don't use me 。
なぜアルバムに収録されなかったのか分からないくらい、ファンキーでカッコいい。
フリーキーに吹きまくるサックスがまた、素晴らしい。
Midnight At The Oasis

上で挙げたとおり、 Maria Muldaur の名曲のカバー。
ラジオでよくかかるのは、こちらのバージョンが多い。
Radio Edit(ショートバージョン)とエクステンド(フルバージョン)、それにRay Hayden(Opaz名義)とRoger Sanchezそれぞれの手による
二つのリミックスを収録。
#2 は、フルバージョンとは言いながら、やや冗長な印象。ショートバージョン(#1)でも曲は十分表現されていると思える。
サックスソロがあるのだが、どちらにもきちんと入っている。
ただ、曲のきちんとしたエンディングは、フルバージョンでしか聴けない。
ショートバージョンではフェードアウトで処理されているからだ。
リミックス二つは、どちらも原曲の輪郭を残し、大ナタを振るった感じはない。
Ray Haydenのほうは、ギターやシンセサイザーなどでフレーズを付加して奥行きを出したもの。
対しRoger Sanchezは、クラブを意識したようなハウス的感じに仕上がっている(今の耳で聴くと、古さは否めないが)。
Spend Some Time

ベースのAndrewのペンによる 、アルバムの中盤でひときわ爽やかな印象を残す曲のシングルカット。
アルバム収録バージョンよりも装飾が増え、またN'deaのコーラスも多めに入って豪華な感じになったものが収録されている。
例によって Radio Edit(ショートバージョン)とエクステンド(フルバージョン)、別々のプロデューサーによる二つのリミックスを収録。
Simonのギターソロは、フルバージョンの方にしか入っていない。また、フルバージョンの終盤で聴かれるN’deaのアカペラは、はっとさせられる。
・・・ように思われたが、それは曲の冒頭だけ(このまま行けばいいのに・・・)。
80年代的なチープな電子音を混ぜて、ハウスっぽく仕上げているものの、やはり反復の仕方などに時代を感じさせる(苦笑)。
うーん・・・惜しい。
#4のsweet club mix は、「スイート」とは名ばかりの、冒頭から無骨な機械音満載で、全く違った印象。
中盤からシンセソロやスクラッチなどが入るが、なかなかクール。
このシングルには別バージョンがあり、

↑のものは2枚のCDが入れられるケースになっている。
しかし入っているCDは1枚で、もう一枚はダミー(紙製のディスク)。
Spend Some Timeに限らず、この頃の彼らは、1曲につきシングルを2枚切っている。
1枚はシングル2バージョン+リミックス2バージョン(計4曲)。
もう1枚はタイトルトラック+アルバム曲のライブ音源、という仕組みだ。
↑のものは、 Spend Some Time のRadio Edit(ショートバージョン)を冒頭に、他3曲は
# Stay This Way 、# People Get Ready 、# Midnight At The Oasis のライブ音源だ。
2枚ケースは、2枚とも買った人が両方をひとつに収められるよう配慮(あるいは買わせる戦略?)したものなのだろう。
(いずれにしても、ヴァイナルはもちろんCDも売れない現在では、無用の工夫となってしまったが・・・)